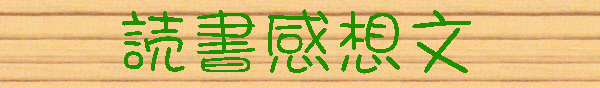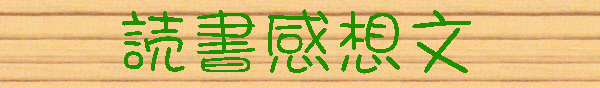| 明石康氏と言えば、元国連事務次長であり、1992年に国連の
|
| カンボジアPKO(カンボジア暫定統治機構=UNTAC)の最高責任者として、 |
| 新生カンボジアの再建に取り組み、見事な成功を収めたことで、世界的に有名な方です。 |
| 実は、明石氏は、我が山形大学の先輩でもあります。 |
| 山形大学の前身である、旧制高校の時代、1年間だけおられたのだそうです。 |
| 僕は、自戒の念を持ちつつ、氏を尊敬申し上げております。 |
| なぜなら、氏は、「行動の人」だからです。 |
| やはり、苦しみながら、批判を受けながら、「行動」をした人が、一番偉いと思います。 |
| 僕にとっては、「結果」より、その「行動」「努力」の方が、数倍重要に感じられるのです。 |
| 自分は何もせず、たかみに座って、批判ばかりしている人間がもしいるとすれば、 |
| 僕はその人間を軽蔑します。 |
| どんなに社会的地位と財産を持っていても、その人は卑しい人間であると思います。 |
| 僕は幸いにも、山形大学の記念式典で、氏のスピーチを聴くことができました。 |
| 決して話はうまい方ではないと思いましたが、にじみ出てくる人格に、 |
| 僕は大変に感銘を覚えました。 |
|
| さて、この本では、氏のカンボジアPKOをはじめとする貴重な体験や、 |
| PKOの機能の変遷、国連の歴史、現在の国連の問題点、これからの国連のあり方の展望、 |
| 人権、開発、環境、歴代の国連事務総長の苦闘などについて、書かれています。 |
|
| 以下に、本書からたくさんの引用をしながら、僕の意見を少し、 |
| 述べさせていただきたいと思います。 |
|
| 「現地で精細に見ると、どちらの側が正しく、どちらの側が悪いということは |
| 決められない場合があり、正邪、白黒というより、限りない灰色に包まれている状況 |
| が多いのが事実なのである。」P.31 |
|
| やはり、現実は単純な「白黒」ではなく、「灰色」のことが多く、それを解決するには、 |
| 大変な知恵と努力が必要なようです。 |
| また、このことに対する理解は、「安易な軍事的・経済的制裁は誤りである」 |
| ということの理解につながるように思います。 |
|
| 「ソマリアの経験が示したものは、複雑な人種的、宗教的、ないしは氏族的な要因に |
| 基づき、まだ烈しい権力欲に駆り立てられる、野心的なリーダーが介在している激しい |
| 内戦のさなかでは、平和や人道援助支援のため外部から助力を行うとしても、現在の |
| 国連の能力では十分に対処しえないことがあるということである。」P.36 |
|
| 「野心的リーダー」の扇動によって、多くの民衆の血が流されている、という事実は、 |
| もっと知られていいように思います。 |
| また、それを防ぐためにも、「教育」が重要なのではないでしょうか。 |
|
| 「全面軍縮が実現した世界で、今までの独立国家の軍隊や、まだ弱体である |
| 国連平和維持部隊に代わって平和を守る軍隊こそ、真に強力かつ理想的な国際平和軍と |
| いえるかもしれない。しかし、それはあくまでも世界政府を前提としており、またそれが |
| 政治制度としてできたとしても、下からの社会経済的な変動や、国と国、地域と地域との |
| 政治的、経済的、文化的な格差の問題が存在しなくなるといったものではないだろう。 |
| そこでは、今の世界には存在しない新しい困難さえ生じてくるかもしれない。 |
| なんといっても、そうした世界政府と超国家的軍隊にいたる道程は、予想外に険しい |
| ものと見るべきであろう。そこにいたる前提として、世界の人々がもっともっと同じような |
| 見方をし、同じような価値観に立つように努力していく必要があると、私は思う。」P.100 |
|
| そのためにも、やはり普遍的「価値」の探求は、欠かすべからざる命題であると思います。 |
| 例えば、「基本的人権」は、その一つなのではないでしょうか。 |
|
| 「他国や国際機関が無制限に加盟国の実状に口をはさみ、世界的な基準を杓子定規に |
| 適用し、各国の政策をやたらと批判するのも考えものだ。批判するにしても、公然と対決的な |
| 態度でしては、逆効果なこともある。それをできるだけアジア的フィネスで |
| やるという配慮が大事なのではなかろうか。 |
| 普遍的な人権基準を、各国や地域の現状に照らしつつ、しだいに拡大していく歴史的な |
| プロセスが存在していることは疑えない。問題はその方向性ではなくて、 |
| 適用のペースであると私は思っている。」P.110 |
|
| たしかに、こういった配慮なしの抗議は、いつも余計な外交的あつれきを |
| 生んでいるように思います。 |
|
| 「少子化や高齢化現象の解決に関して、わが国は将来のモデルケースになりうるという |
| 観点から、その人口政策が世界から注目されている。わが国はまた国連人口基金への |
| 第一の拠出国であるが、世界的拡がりを持つこの問題に関し議論を展開し、活発な |
| 提言を行うことが期待されている。」P.120 |
| 「国連分担金の額ではアメリカに次ぐ2番目のところに達しており、(今年度[98年]は |
| 17.98パーセント)、自発的拠出金に基づく関連機関(国連開発計画やユニセフなど) |
| でもわが国はかなり上位に存在している。しかし職員全体に占める比率でかなり |
| 見劣りする状況にあるのは、国際活動において日本人の顔が見えないという批判に |
| つながっているといえるだろう。」P.132 |
|
| 日本人は、もっともっと「夢」や「理想」を掲げていいのではないでしょうか。 |
| そういったことができないのは、深い人生観や思想、つきつめた思索、などを抜きにして、 |
| 外面だけ繕っていることが多いからなのではないか、と最近僕は思います。 |
| また、自らの小さな個人的幸福のみを、追い求めている国民の多さも、 |
| 原因の一つかもしれません。 |
| ここにいたって、僕はどうしても、「人間教育」の重要性を痛切に感ぜずにはいられません。 |
|
| 「国連分担金の最大拠出国であるアメリカが、連邦議会の反対を理由に、法的義務 |
| である支払いを履行していないことは、明らかに国連の活動基盤を弱めている |
| ものであり、批判されてよい。 |
| 国連の財政的基盤の弱さは、驚くべきものがある。国際平和と開発のために、 |
| 大きな役割を期待されている割りに、その通常予算はニューヨーク市の清掃予算よりも |
| 少ない。それなのに、各加盟国は国連予算の払い込みを渋る傾向がある。」P.142 |
| 「専門知識を持ち経験豊かなNGOの国際的なつながりは、国際政治における |
| 民主的参加や透明性の拡大、さてはマスコミやパソコンの役割増大などの結果、 |
| 強化されてきている。こうして各国民衆の声は国連において各国政府を補完する意味を |
| 持ちはじめており、無視できないものになってきているといえる。」P.144 |
|
| この本を読んで、僕はほんの少しだけ、「外交」というものがかいま見えた |
| ような気がしました。 |
| そして、「大人な思考」「知恵」「本質を見抜く眼」「寛容の心」「個人同士の信頼」 |
| の大切さを感じました。 |
| また、改めて思ったことは、 |
| 「問題を引き起こすのも、解決するのも、人間の力である」 |
| ということでした。 |
| 一人一人の努力によってしか、人類は進歩できないのです。 |
| 「自分は関係ない」と思われる方もおられるかもしれません。 |
| しかし、その方も、やはり「人類」の一員であることに変わりはありません。 |
| 一人一人の一歩は、そのまま、人類にとっての一歩でもあるわけです。 |
| 自らの課題に、果敢に挑戦しながら、「自分に何ができるか」を考えていくことこそ、 |
| 人類の進歩の基盤になっていくものと、固く信じます。 |
|
| そして、僕も、頑張ります。 |