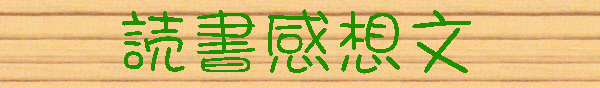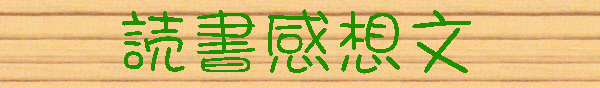| この本は、大学の講義の課題として出された本の中では
|
| 珍しく、「興味深い」本であった。日本の老人医療の
|
| 駆け出しのころから、試行錯誤の中で新しい老人医療を
|
| 切り開いてきた、著者の喜びと気迫が伝わってくる。
|
| この本の中では、「生活」のもつ力の偉大さが
|
| 繰り返し述べられる。そして、「肺炎は治った、
|
| しかし寝たきりになった」という老人の例を示し、
|
| 現在の日本の医療が「生活」から離れ、数々の
|
| 矛盾を生んでいる、と警鐘を鳴らしている。
|
| 医療従事者は、「生活者」としての眼を養っていかねば
|
ならない、と深く感じた。
|
| ※蛇足
|
| この本の著者も、世の多くの医師と同じく、
|
| 悪い癖を持っている。それは、「なんでも
|
| 知っているように見せたがる」あるいは
|
| 「知っているように思ってしまっている」
|
| という癖である。すなわち、この本の中に
|
| 出てくる、経済用語の使い方や、コンピュータ
|
| 関連の文章に、多少の難点が見られる。
|
| また、人間に関する洞察も、少し短絡的な
|
| 感じを受けた。方便としてはいいのだが、
|
| それが人間の全て、と言われると、少々
|
| 抵抗を感じてしまう。
|
| しかし、かくいう私も、あまり人のことは
|
| 言えないのかもしれないので、他山の石と
|
| していきたい。
|