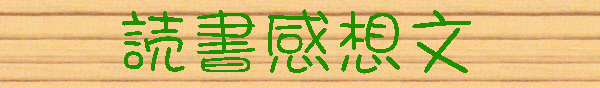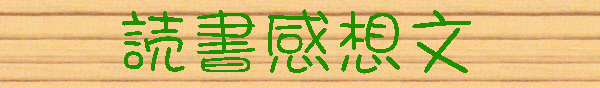| この本は、葉っぱのフレディが生まれて、死ぬまでのストーリーです。 |
| アメリカの哲学者が書いたもので、ずばり、テーマは「生と死」。 |
|
| 文はとても淡々としているのに、ビックリマークとか全然ないのに、 |
| 読みながら、なんだかちょっとドキドキしちゃいました。 |
| やっぱり童話だけに、話が短いんですよね。 |
| 必然的に、生まれてから死ぬまでを読む時間も短い。展開も早い。 |
| それで、ドキドキしちゃったんじゃないかなぁ、と思います。 |
|
| それから、書いている内容が、欧米の話にありがちな |
| 「神様の思し召し」一本槍とは全く違ったから、 |
| というのも、ドキドキした一因だったかもしれません。 |
|
| 今の日本は、「死」というものを、あまり見つめない傾向が |
| あるように思いますが、僕は、もっと日常的に「死」について、 |
| 考えていくことが大事なんじゃないかなぁ、と思う一人です。 |
| いつか来る「死」を考えずに、「生」を本当の意味で |
| 充実させていくことはできないと思うからです。 |
|
| その意味で、この本は「生と死」を身近なものとしてとらえ、 |
| 考えていく上で、とても良いきっかけになると思います。 |
|
|
|
| この本では、「他」のために働き、喜んでもらうことに、喜びを見い |
| だす生き方、そしてその安らかな「死」を描いているように思います。 |
|
| そういうのを「欺瞞」だと思う方もおられるかもしれません。 |
| しかし、僕はやはり、「自分自身のため」だけに生きていては、 |
| 結局、自分の人生に「意味」「価値」「本当の喜び」を見いだすことは |
| 困難なのではないか、と思うんです。 |
| また、死ぬときになって、 |
| 「あぁ、自分は誰にも感謝されることはなかった。 |
| はたして自分の人生に意味はあったのだろうか?」 |
| なんて思うことになったら、なんて恐ろしいことだろうか、 |
| と思います。 |
| そのとき、どんなに地位や財産を持っていても、そんなものが |
| どれだけ役に立つでしょう。 |
| 否、それらはむしろ、その寂寥感を |
| さらに強めてしまうかもしれません。 |
|
| 一つの物語が、喜劇であるか、悲劇であるかを決めるのは、 |
| 物語の課程ではなくて、その結末です。 |
| 僕は、「自分はやるべきことを、自分なりにやりきった」 |
| 「自分は社会のため、人のためにこれだけのことをした」 |
| という、誇りと満足感をもって、死んでいきたいと思います。 |
|
|
| 「自分の犠牲」の上に「他の幸せ」を築くという発想ではなく、 |
| 一見「人のため」のように見えることも、実は結局、 |
| 「自分のため」につながっているという洞察。 |
| この世の全てのものは、常に変化し続ける、しかし、 |
| その変化、そして「生」と「死」の連鎖は、「大自然の設計図」、 |
| 言い換えれば「宇宙を貫く法則」の一つの現れである、 |
| という洞察。 |
| それら、この作品の奥底を流れているものは、 |
| まさに仏法そのものだ、と思いました。 |
| 著者は仏教徒なんじゃないだろうか、 |
| と思ってしまったほどです。(^-^; |
|
| しかし、様々な事象を深く深く洞察していくとき、 |
| その考えが仏法に近づいていくというのは、 |
| きわめて自然なことだと僕は思っています。 |
|
|
|
| おわりに。 |
|
| 童話なのに、とても深い内容でした。 |
| こんなにいろいろ考えさせられる童話も少ないかもしれません。(^-^; |
| もし、機会があったら、ぜひ、読んでみていただきたい一冊です。 |
| (ホント、あっという間に読み終わっちゃいますよ。 |
| そうそう。うちの学部の図書館にも一冊ありました。) |