平塚神社
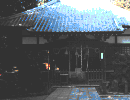 |
本郷台の崖線上にあり、平安時代は豊島郡を治める郡衙のあった場所と推定されています。平安時代末期に豊島近義が平塚城を作った。源義家が後三年の役が終わり凱旋の折り、この地にとどまり城主豊島義近に鎧一領を与えた、元永年間にこの鎧を埋めて、城の鎮守としたのが平塚神社の起こりです。鎌倉・室町時代を通じて豊島氏の居城となり、泰経の時代、文明10年(1478)太田道灌によって落城してしまいました。また、鎧を埋めた塚が平らだったことから平塚となった。 |

旧古河庭園

|
武蔵野台地の高低を巧みに利用した、大正期の名庭園、洋館、洋式庭園はコンドルの設計による。また、心字池を中心に日本庭園もある。陸奥宗光から古河家に引き継がれ、昭和31年都の有料公園となった。
西ヶ原1-27
|

飛鳥山公園
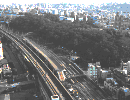
|
江戸時代から桜の名所として知られている飛鳥山を中心とした公園。8代将軍吉宗公がこの地を王子権現に寄進。明治5年(1873)に日本で最初の5公園となった。
王子1-1
|
| 静勝寺 |
太田道灌の死後、雲綱和尚が稲付城の脇に建立した。元禄8年(1695)作のの太田道灌像が有る。
赤羽西1-21
|
| 清光寺 |
豊島清光が一人娘の冥福を祈り、館の一隅に建立した。清光は治承・寿永の内乱で源頼朝の幕下で多くの武勲を建てた。寺宝の寛保2年(1742)作の清光が有る。
豊島7-31
|
王子神社

|
元享年間、この地の領主、豊島氏が熊野権現を勧請した事に始まる。寛永11年(1634)三代将軍家光が権現造りの壮麗な社殿を造営したところから「王子権現」として有名になった。
王子本町1
|
王子稲荷神社
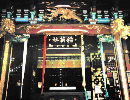
|
治承5年(1181)源頼朝が八幡太郎義家の腹巻き、太刀を寄進した。現在の社殿は文化5年(1808)建立で、この稲荷社が関八州稲荷の統領で毎年大晦日に関八州の狐が集まると言い伝えられている。
岸町1-2
|
音無川親水公園
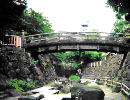
|
建設省の日本の都市公園100選に選ばれている名親水公園
|