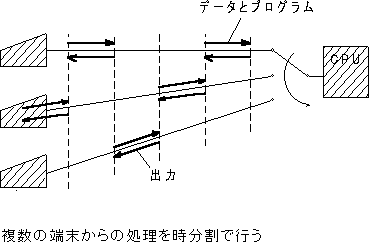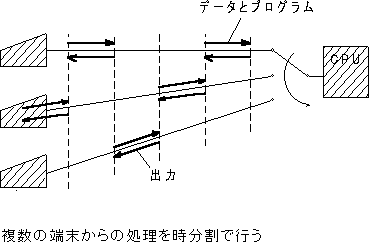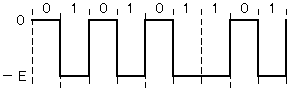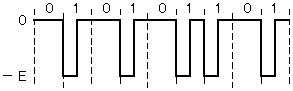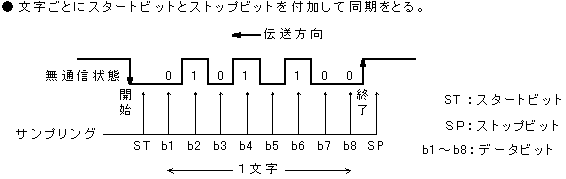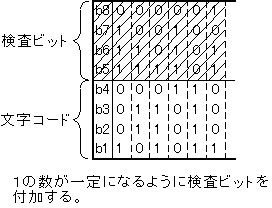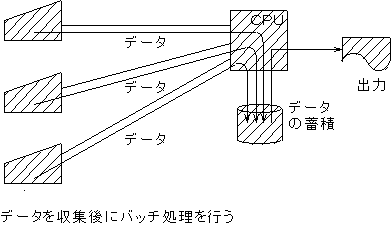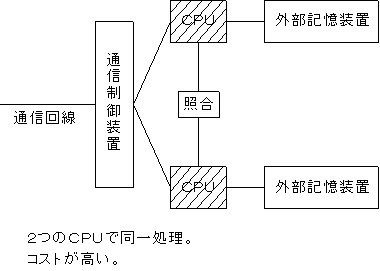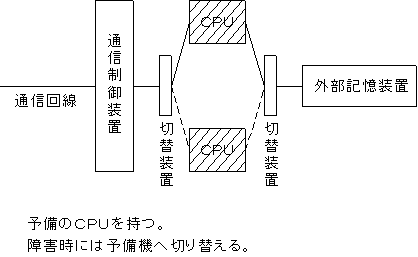タ
ダークファイバ
布設済みの光ファイバケーブルのうち、使用されていない光ファイバ心線。
ターミナルアダプタ
TA参照。
ターンアランドタイム
コンピュータにジョブを投入してから、完全な出力結果を得るまでの経過時間。これは、CPUの処理能力、処理の運用面、管理面も含めたサービスの総合的評価の尺度となっている。
帯域伝送方式
0と1のデジタル信号を別のアナログ信号に変換して伝送する方式。帯域伝送方式には、振幅変調方式、周波数変調方式、位相変調方式がある。
ダイオードブリッジ
ダイオードを4個組み合わせたブリッジ。ダイオードブリッジは、電子式ボタン電話装置の着信検出回路に使用されている。
待時交換方式
ふくそうに遭遇した場合、その呼をいったん待ち合わせの状態にして、回線又は装置が空くまで待たせて、空きができたとき接続する交換方式。
ダイナミックルーティング
ネットワークのルーティング方法の一つ。ルータ間でルーティング情報をやり取りする動的経路選択である。
タイミングアウト方式
データブロック間を一定時間空けることでデータを区切る方法であり、データブロック間のタイミングを規定しておく方式。
タイムシェアリングシステム
中央のコンピュータの処理時間を時分割して、あたかも複数のユーザが同時に利用しているかかのように処理するシステム。
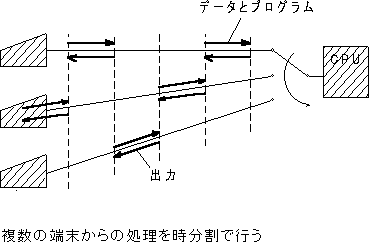
タイムスロット
ハイウェイ上における各チャンネルの時間的位置をタイムスロットという。一つのタイムスロットには8ビットのシリアルデータが伝達される。
ダイヤルインサービス
1本の電話回線に複数の電話番号(追加番号)を設定し、個別に呼びだすことのできるNTTのサービス。
NTTのダイヤルインサービスを利用することによって、中継台を経由しないで直接目的の内線電話機に外線が着信する方式。
ダイヤル送出制御プロセッサ
PBダイヤル送出回路又はDPダイヤル送出回路を制御するプロセッサ。ダイヤル送出制御プロセッサは、PB又はDPの選択信号を外線に送出する。
ダイヤルトーン(DT)
発信音参照。
プッシュホンで局線番号ダイヤル後、1次応答があり、引き続き内線番号をすることで、内線電話を直接着信させる方式。
ダイレクトインライン方式(DIL)
局線からの呼び出しに対してグループ内の特定の電話に直接着信させる方式。
ダイレクトコール/応答モード
ITU−T勧告V.25bisでアドレスコール/応答モードとともに規定されている動作モード。このモードは、DTEからDCEへ電話番号に相当する2進数を送信すると、NCU部で電話番号に読み替えてダイヤルする。
縦電圧
落雷や空雷などで発生する縦方向の電圧。縦電圧は、直接、間接に人身や各種の通信機器に被害を及ぼすことがある。
多点サンプリング
データ信号の各ビットを複数点でサンプリングすること。
短距離受動バス
ケーブルの任意の点に最大8台までの端末を接続することができる形態。短距離受動バスのケーブル長は、100〜200m程度である。
炭素接地棒
酸、アルカリ等の成分を含む土壌で腐食が激しい場所で使われる接地棒。
炭素逃雷器
保安器に使用されている逃雷器。炭素逃雷器は、放電特性の違いにより片方が先に放電するとL1、L2に大きな電位差が生じ、電話機等に使用しているIC部品を破壊する場合がある。
単点サンプリング
データ信号の各ビットに対して、1対1で行われるサンプリング。
端電池方式
電圧補償方式の一つ。整流装置と並列に接続した端電池を負荷電圧の降下に対応して次々に直列に接続する方式である。
単独配線方式
各階(又は区画)の電話需要が明確である場合、各階単独(他とマルチ配線にしない)で配線する方式。各階の電話需要が当初の予測に反して著しく変動した場合、不経済になる欠点がある。
単独・複式併用方式
単独配線方式と複式配線方式を併用する方式。需要変動への対応性と経済性は両者の中間である。
単方向通信
送信側と受信側が決まっていて常に一方向だけの情報を伝送する方式。放送がこの方式であり、データ通信ではあまり使われていない。
端末アダプタ
モデムを用いるコンピュータ端末をネットワークに接続するための装置。VシリーズやXシリーズ有するISDN非標準端末を接続する場合、TAが端末アダプタになる。
端末終端点識別子
レイヤ2のデータリンクを設定するとき、複数の端末を識別するために用いる。基本インタフェースの場合、最大128のTEI値が使用可能である。1次群速度インタフェース
のTEI値は、「0」固定である。
TEI=0〜63 : 非自動割当のユーザ端末
TEI=64〜126: 自動割当のユーザ端末
TEI=127 : 放送形式のデータリンクコネクション
単流NRZ方式
0と1を電圧の「あり」と「なし」で表現し、また符号ビットのスロット長の時間幅でパルスを送出し、ビットスロットごとに電位ゼロに戻らない方式。
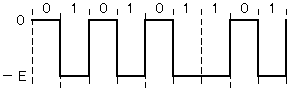
単流RZ方式
0と1を電圧の「あり」と「なし」で表現し、また符号ビットのスロットごとに必ずゼロに戻る方式。
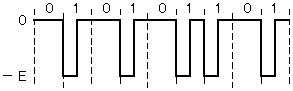
単流方式
0と1を電圧の「あり」と「なし」で表現する方式。
チ
地下き線ケーブル
とう道、管路区間などに収容するケーブル。地下き線ケーブルは、PECケーブルが使用せれている。
蓄積交換方式
データをいったん交換機内で蓄積したあと、交換網中の経路を選んで伝送する方式。蓄積している間に送信先の端末に合わせたデータ変換を行うので、
伝送手順や回線速度の異なる端末間の通信も可能である。
蓄積プログラム制御方式
交換動作の手順のプログラムを記憶装置にインプットしておき、中央処理装置がその手順に従って交換動作をする方式。また交換動作をソフトウェアで行うので機能の追加や変更も容易である。この方式は、PBXやボタン電話装置などで採用されている。
蓄電池
放電、充電を繰り返し使用できる電池。PBXやボタン電話装置の予備電源として、シール鉛畜電池が採用されている。
着信検出回路
外線着信時の極性反転の次のシーケンスである呼出信号(16Hz)を検出し着信を表示する回路。
着信識別機能
外線からの着信に対して主装置のサブCPUにより16Hzの呼出信号の断続パターンを識別する機能。そのパターンに応じてメインCPUで各電話機ごとに着信情報を作成し電話機の着信音を変化させる機能を備えたものがある。
着信自動応答機能
着信時にかかってきた電話の送受器を上げるか、又はスピーカを押下することにより自動的に応答できる機能。
着呼ユーザのアドレス情報フィールドの長さを表現するもの。着呼ユーザアドレス長は、ビット4〜1に2進数表示で挿入する。
中央演算処理装置
セントラルプロセッサユニット参照。
中央処理系
中央制御装置と主記憶装置があり、交換接続動作を実行する中枢的な役割がある。
中央制御プロセッサ
局線系、内線系、通話路系等の各サブプロセッサの制御を行うプロセッサ。また、内線ごとの局線発信規制、着信規制及び発着信内線の番号の識別等の基本的な事項の管理と制御を行う。
中継線交換機
交換機相互を結ぶ中継線を収容する交換機。
中継線信号装置
局間中継線の監視処理、MF信号の送受信等を行う装置。
中継台方式
中継台を設置し、専用のオペレータが着信を取り次ぐ方式。
調歩式Xシリーズ
ITU−T勧告X.20に規定されている接続制御手順。DTEからDCEへは回路T,DCEからDTEへは回路Rを用いて情報のやりとりを行う。
調歩同期方式
8ビットで表される文字符号の前後に、スタートビット「0」とストップビット「1」を付加して同期をとる方式。
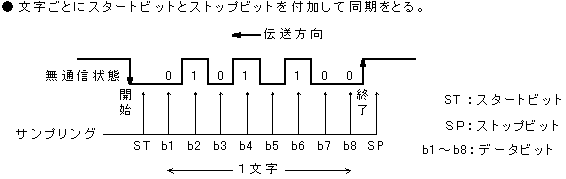
直流ループ監視(S)
ボルシット機能の一つ。内線ループの閉結・開放を監視し、電話機の発呼、ダイヤル・パルスの受信及び終話を検出し、交換制御部の中枢にその情報を伝達する。
直列伝送方式
ビット列を直列に変換して、1本の通信回線で順次伝送する方式。通常、長距離間のデータ伝送に用いられている。
直交振幅変調(QAM:振幅位相変調ともいう)
デジタルデータをアナログ信号に変換する変調方式の一つ。変換された後の波の振幅と位相の両方を使って情報を表現するため、限られた帯域幅で効率よくデータを転送することができる。
ツ
通信用接地
通信機器の電気回路保護、電気変動防止のためにとる接地。
通信用フラットケーブル
カーペットの下に配線するケーブル。偏平・柔軟なケーブルで、対ごとにアルミラミネートの静電遮へいが施してある。また、ミシン目がつけてあるので、対単位に分離することができる。
通話路制御プロセッサ
通話路スイッチ内の該当するクロスポイントのスイッチング素子をONさせる制御を行う。外線とボタン電話機等の接続を行うほか、各ボタン電話機の状態を監視しており、保留音、内線発信音、内線呼出音等の接続制御を行っている。
ボルシット機能の一つ。電話機に対し、2個のトランジスタのベース電流を制御して通話用電流を定電流供給する。
通話メモリ
送信ハイウェイからの信号を一瞬記録するメモリ。通話メモリは、256チャネル分の記録容量がある。記録された信号の内容は制御装置から指示された順番で読み出され、各信号は受信ハイウェイに送出される。
通話路駆動回路(STC)
中央制御回路と情報の授受を行い、外線回路を管理し動作を制御するマイクロプロセサの回路。
ツリー形
1本の幹線から次々に枝分かれして構造。同じ信号を多数のノードに分配する1方向の伝送に適しており、CATV網などに用いられている。
テ
停電検出回路
停電を検出するための回路。停電時に、ホトカプラのコレクタとエミッタ間の電位差が大きくなり、トランジスタが導通してCPUへ停電検出信号を送出する。
停電自動切替装置
停電及び停電復旧を識別するため、外線及び停電用電話機それぞれの通話電流を監視する機能がある。
停電対策試験
信号受信中停電の試験と通話中の停電電話機の試験がある。前者は、トーンリンガの鳴動中に電源をOFFにして、外線着信に停電用電話機で応答できることを確認する試験である。後者は、通話中に電源をOFFにしても異常なく通話できることを確認する試験である。
停電ダイヤル回路
停電時に外線を直接停電用電話機が停電時に外線発信するときの選択信号を送出する回路。
停電用電話機
停電時には外線を停電用電話機に直通にし、外線からの電流供給(局給電)で一般電話機と同様に通話ができる電話機。
定マーク符号チェック方式
キャラクタチェック方式の一つ。伝送する各符号中の1の数が常に一定になるよう、冗長ビットを付加する方式。受信側では符号ごとに1の数をチェックし、一定の数になっているかどうかで誤りを検出する。
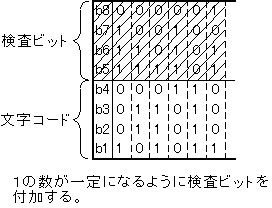
ディレーティング
素子の故障率を少なくする目的で、素子の定格よりも十分低いストレスで意図的に使用すること。
データエントリシステム
遠隔地に発生したデータを通信回線で収集し、いったんセンタのファイルに蓄積するが、データが届いた時点では直ちに処理されず、一定量の情報が集まった時点あるいは決められた時刻に加工処理が行われるシステム。
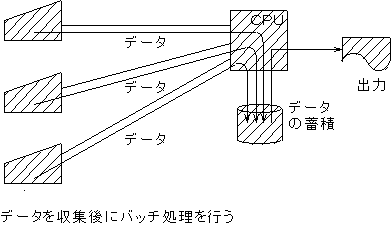
データ端末装置(DTE)とデータ伝送路間で、接続を確立・維持・開放し、コード変換や信号変換などの機能を持つ装置。
データグラム
データの固まり、若しくはデータの単位。
データ信号速度
一般に1回の変調で伝送するビット数をnとすると次式になる。
データ信号速度=n×変調速度
データセットレディ(DR)
V.24の100シリーズ相互接続回路の一つ。また、V.25bisでも用いられている。ON状態で、データ伝送開始のための制御信号受信可能をDTEに示す。
データ線
制御情報を多重化してデジタル信号により行う線。電子式ボタン電話装置の主装置とボタン電話機とのボタン押下情報やランプ点滅情報等の制御のやり取りに用いられる。
データ送受信回路
デジタル多重バスとのインタフェースを受け持ち、バスを通じ主装置と電話機間の音声信号や電話機からの発信、内外線からの着信等のデジタル化、多重化された制御信号の送受信を行う回路。
データ端末装置(DTE)
データ送受信装置として働き、かつリンクプロトコルに従って行われる通信制御機能を備えている装置。
データ端末レディ(ER)
V.24の100シリーズ相互接続回路の一つ。また、V.25bisでも用いられている。ON状態で、DTEの動作準備ができていることをDTEに示す。
データ伝送制御手順
基本形データ伝送制御手順(ベーシック手順)、HDLC手順(ハイレベルデータリンク制御手順)及び無手順の3種類がある。
データ転送速度
単位時間に伝送されるデータ量の平均値。単位は、毎秒、毎分、毎時のビット数、文字数、ブロック数などで表す。
データベース
データの入力・更新・検索などの手順を提供し、情報の集中管理を行うことにより処理の効率化を図るもの。
データリンクコネクション(DLC)
データリンク層から上位のネットワーク層の接続。
OSI参照モデルの第2層(レイヤ2)。隣接するノード間で誤りのないよう通信を実現するための伝送制御手順を規定している。情報を転送する際は、フレームという単位で伝送する。
データリンクの解放(フェーズ4)
情報メッセージの伝送を終了する場合は、主局からEOTを送出する。これに対して従局からEOTを受信し相手側の終結を確認する。
データリンクの確立(フェーズ2)
回線接続後、送信側はENQを送信し、受信側は局指定コードの照会、端末機器の準備状態等の確認を行い、受信可能であればDLE
ACKの応答を返送し、データリンクを確立する。受信不可であればDLE NAKを返送する。
適応差分パルス符号変調方式
ADPCM参照。
適応デルタ変調方式
ADM参照。
デジタルPBX
交換接続を行う通話路を通過する信号がデジタル信号であるPBX。デジタルPBXは、時分割スイッチを用いる交換方式の交換機。
デジタル回線終端装置
DSU参照。
デジタル形ボタン電話装置
主装置から内線ボタン電話電話機まで音声信号を含めすべてデジタル化されたボタン電話装置。デジタル形ボタン電話装置はコーデック等を使用し、音声をアナログ/デジタル変換し、メモリ上でスイッチングを行う時分割交換方式の通話路が用いられている。
デジタル式多機能電話機
デジタル式多機能電話機は、機能ボタンを有し、各種機能を機能ボタンに割り当てることによりワンタッチで機能を利用することができる電話機。デジタル式多機能電話機の仕様は、メーカ独自のものであり、一般に互換性はない。
デジタル信号
アナログ信号を標本化という技術で数値化し、「1」と「0」で表現する2進数に変換して扱う信号。
デジタル多重パス
デジタル多重信号を上り、下りの各1対の計2対でボタン電話へ伝送する。
デジタルデータ交換網
データ伝送を目的とした公衆網で、端末から出力されるデータをデジタル信号のまま伝送して交換できる通信回線。デジタルデータ交換網には、回線交換方式とパケット交換方式がある。
デジタル電話機
ISDN基本インタフェースのDSUに、直接接続して使用できる電話機。
手順クラス
HDLCの手順クラスには、不平衡型手順クラスと平衡型手順クラスがある。
デュアルシステム
稼動する装置を完全に二重化し、2系統のCPUが完全に同一処理をし、それぞれの結果を照合してその正常性を確認しながら処理を進めるシステム。
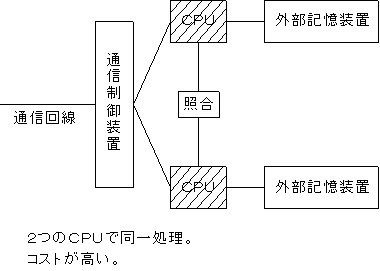
デュプレックスシステム
予備のCPUを持つシステムで、2つのCPUのうち一方が処理を行い、他方が待機して、システムに障害が発生した場合に待機しているCPUに切り替えるシステム。
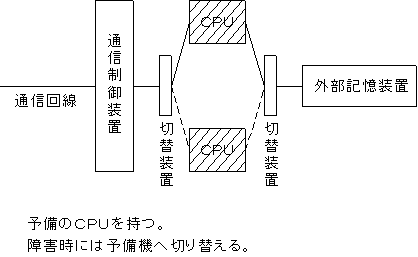
デリミタ符号
データの区切りを示すための符号。一般には復帰改行符号が用いられている。
デリミタ方式
データの区切りを示すデリミタ符号を規定し、データの中からデリミタ符号を検出するとそれまでのデータをパケットに組み立てる方式。
テレサービス
ベアラサービスを利用して、端末相互間で端末機能を含めて情報のやりとりを行うサービス。具体的には、転送モードや情報速度を示す情報伝達属性、アクセスチャネル、やりとりを示すアクセス属性、端末間の通信規約を示す高位レイヤ属性、及び利用可能な付加サービスやサービス品質を表す一般属性を組合せて、その内容を決めている。
テレックス
ITU−T勧告Iシリーズで規定されているテレサービスの一つ。50bit/s以下の伝送が可能なサービスで、電信サービスともいわれている。
テレテックス
ITU−T勧告Iシリーズで規定されているテレサービスの一つ。キャラクタ符号化されたテキストを作成し伝送するサービスで、伝送速度が2400bit/s以上である。
テレビ電話
相手の顔を見ながら電話できるシステム。伝送速度は、ISDNタイプが64Kbps、128Kbps、アナログタイプが14.4Kbps、19.2Kbpsである。
テレライティング
電話機にデータタブレットとディスプレイ装置を付加し、通話と同時に送り手の描画情報を伝送する方式。
電圧補償
電源装置において電源側の送出電圧と負荷側の要求する電圧とに差がある場合、両者の間に電圧を加減する装置を挿入して電圧を調整することをいう。
電圧補償方式
シリコンドロッパ方式、端電池方式、ブースタ方式がある。
電気的条件
信号線のインピーダンスや信号レベルの規格など。
電子写真記録方式
LEDヘッドを用いた現像方式で普通紙に印字する方式。印刷面への鉛筆書き込みや長期の保存に適している。
電子メール
e-mailとも呼ばれている。ネットワークを介して、パソコンなどの端末同士が文字などの情報をメール(手紙)の形で交換するシステム。
伝送制御キャラクタ
基本形データ伝送制御手順(ベーシック手順)で用いられている制御キャラクタで、SOH、STX、ETX、EOT、EQN、ACK、DLE、NAK、SYN、EBTの10種類がある。
伝送制御手順
データ伝送に付帯する制御や手続きを伝送制御といい、また伝送制御を行うための一連の規則を伝送制御手順という。
伝送路での減衰量。通常は、デシベル[dB]で表す。伝送損失のことを線路損失、線路伝送損失ともいう。
伝送路インタフェース(LI)
加入者線の一端における接続条件の規定。伝送路インタフェースは、電気的条件、物理的条件などが規定せれている。
伝達能力
通信網が提供するベアラサービスの属性内の情報伝達属性。情報伝達属性には、転送モード、情報転送能力、情報転送速度等が規定されている。
電話機制御プロセッサ
主装置からデータ伝送された情報に従い、着信時のトーンリンガ音の発生や指定されたランプの点滅等の動作を実行し、また、電話機のオンフックやダイヤル操作等の情報を取り込み、主装置に伝達して発信の動作を依頼するプロセッサ。
ト
同期
送信側のデータ送出のタイミングと受信側の読み出しのタイミングを一致されること。
同期式Xシリーズ
同期式Xシリーズは、ITU−T勧告X.21に規定されている接続制御手順。DTEからDCEへは回路Tと回路C、DCEからDTEへは回路R及び回路Iを用いて情報のやりとりを行われる。
同期転送
送信側と受信側で、タイミングを一致させながらデータ転送を行う方式。
動作モード
HDLC手順クラスの中の動作モードは、正規応答モード、非同期応答モード、非同期平衡モードの3つがある。
同軸ケーブル
中心に太めの銅線があり、それを薄い銅パイプで適当な間隔をあけて取り囲む構造。同軸ケーブルは、中心の銅線と銅パイプで1対である。光ファイバケーブルが普及する前は、市外ケーブルや海底ケーブルで使用されていた。また、テレビのアンテナや10BASE5、10BASE2のLANで使用されている。
トークン
トークンパッシングのLANで管理するアクセス権を端末に渡すためのフレーム。
トークンバス
トークンパッシングのバス型ネットワークで使用するプロトコル。IEEE802.4で規定されている。
トークンパッシング
LANのアクセス制御方法の一つ。LAN上にトークン巡回させ、端末に順次アクセス権を渡す方式である。トークンパッシングには、ネットワークがリング型のトークンリングとバス型のトークンバスがある。
トークンリング
トークンパッシングのリング型ネットワークで使用するプロトコル。IEEE802.5で規定されている。
独立同期
各局に高精度発振器を設置し、各局固有のクロックに同期させる方式。
突入電流防止回路
電源スイッチの接点の溶着や平滑用コンデンサの劣化を防ぐための回路。
飛び越し走査
1回目に走査線を1本おきに走査し、2回目に前回の走査線間を走査する方式。
ドライカッパー
布設済みのメタルケーブルのうち、使用されていないメタル心線。
トラヒック
通信回線を通るデータ量。トラヒックが多くなるとふくそう状態になる。
トラヒック集束
使用率の低い回線をその使用率に応じた割合で絞ること。
トラヒック制御
通信回線にふくそうなどの障害が発生しないように制御すること。トラヒック制御には、フロー制御とふくそう制御がある。
トランザクション
データベース処理で用いられる用語。データベースの接続、レコードの検索、レコード内のデータの更新、接続の切断など。
OSI参照モデルの第4層(レイヤ4)。端末間でのデータ転送を確実に行うための機能で、データの送達確認、パケットの順序制御、フロー制御などの機能を規定している。
トレイラ
送信データの末尾に付ける制御情報。
トレンチダクト
フロアにケーブル等を配線するために設けられた溝状のダクト。
copyright(C) 1998 mori! all rights reserved.