次の各文章の( )内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び番号を記せ。
(1) 図-1に示す回路において、端子a-b間の電位差が20ボルトであるとき、抵抗Rは、( ア )オームである。ただし、電池の内部抵抗は無視するものとする。
① 16 ②18 ③27 ④32 ⑤40
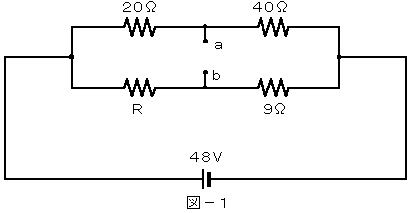
(2) 図-2に示す回路において、端子a-b間の電圧が12ボルト、端子b-c間の電圧が9ボルトであった。このとき、端子a-c間に加えた交流電圧Eは、( イ )ボルトである。
①8 ②15 ③16 ④21 ⑤26 ⑥34
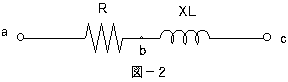
(3) 電気回路において、回路定数や入力が変化すると、回路内の電流や電圧が変化し、ある時間が経過してから一定値に落ち着く。この一定値の状態を( ウ )状態という。
①定在 ②定常 ③不動 ④平衡 ⑤定数
(4) 波形率と同様に、交流波形のひずみの度合いを見る目安の一つである波高率は、( エ )の比で表され、正弦波形の場合1.414となる。
①基本波と高調波 ②最大値と実効値 ③実効値と平均値 ④最大値と平均値
⑤偶数次ひずみと奇数次ひずみ
第2問
次の各文章の( )内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び番号を記せ。
(1) 電気伝導が正孔によって行われる半導体を( ア )形半導体という。
①電流制御 ②電圧制御 ③N ④P ⑤接合
(2) 図-1に示す回路のトランジスタのIb-Vbe特性及びIc-Vce特性がそれぞれ図-2~図-4で示されるとき、この回路のコレクタ-エミッタ間の電圧を6ボルトの点において動作させるためには、ベース-エミッタ間のバイアス電圧を( イ )ボルトにする必要がある。
①0.50 ②0.55 ③0.60 ④0.65 ⑤0.70 ⑥0.75
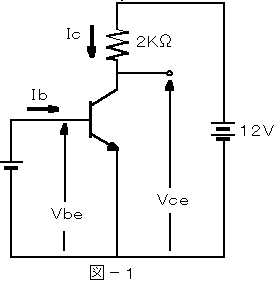
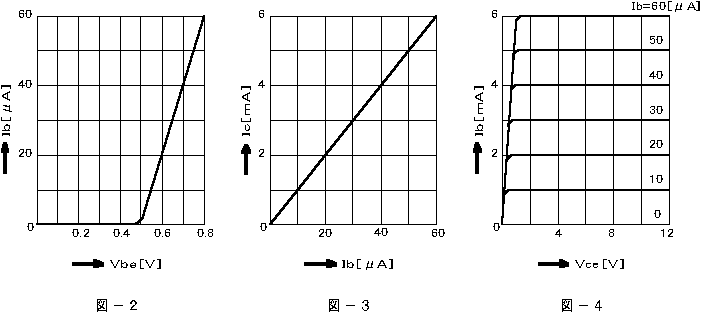
(3) 電界効果トランジスタは、( ウ )及びドレインといわれる電極間を流れる多数キャリアを、ゲートの( エ )で制御する素子である。
①アノード ②ソース ③ドナー ④アクセプタ
⑤カソード ⑥光エネルギー ⑦電流 ⑧電圧
(4) 任意の入力波形の、極めて狭い振幅レベル範囲に入る部分だけを取り出す回路を( オ )という。
①フリップフロップ ②リミッタ ③クランパ
④ゲート回路 ⑤スライサ ⑥遅延回路
第3問
次の各文章の( )内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び番号を記せ。
(1) JIS X 0122(2値論理素子図記号)において、論理和(OR)素子を表す図記号は( ア )であり、否定論理(NOT)を表す図記号は( イ )である。
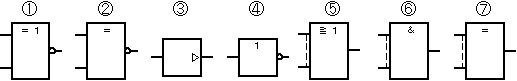
(2) 表は、2入力の論理回路における入力論理レベルA及びBと出力論理レベルCとの関係を示した論理値表である。その論理回路の論理式が
で表されるとき、表中の出力レベルW、X、Y、Zはそれぞれ( ウ )である。
①0,0,0,1 ②0,0,1,1 ③0,1,0,1 ④0,1,1,1
⑤1,0,0,0 ⑥1,0,1,0 ⑦1,1,0,0 ⑧1,1,1,0
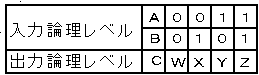
(3) 図の論理回路は、入力a及び入力bの論理レベルと出力cの論理レベルとの関係から( エ )の回路に置き換えることができる。
①否定論理積 ②一致演算(等価演算) ③排他的論理和(EOR演算)
④論理和 ⑤論理積 ⑥否定論理和
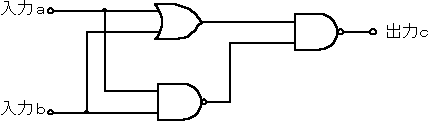
第4問
次の各文章の( )内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び番号を記せ。
(1) 図-1において、電気通信回線への入力電圧が160ミリボルト、その伝送損失が1キロメートル当たり1.2デシベル、増幅器の利得が10デシベルのとき、電圧計の読みは、( ア )ミリボルトである。ただし、変成器は理想的なものとし、入出力各部のインピーダンスは整合しているものとする。
①140 ②80 ③40 ④30 ⑤12 ⑥9
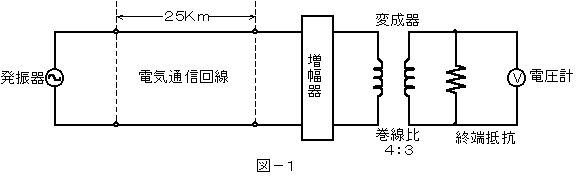
(2) 伝送損失のない一様な線路を( イ )で終端すると、電圧及び電流の大きさは、線路上のどの点においても一様である。
①特性インピーダンス ②純抵抗 ③コンデンサ ④容量性リアクタンス
(3) 図-2のような、一方の伝送ケーブルのインピーダンスをZ1、もう一方の伝送ケーブルのインピーダンスをZ2とすると、その接続点における電圧反射係数は( ウ )で表される。
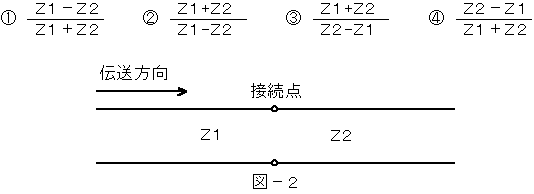
(4) 伝送路は、その減衰量が( エ )に無関係に一定であり、かつ、位相変化が( エ )に比例するとき、信号をひずみなく伝送できる。
①雑音 ②特性インピーダンス ③周波数 ④振幅 ⑤線路長
第5問
次の各文章の( )内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び番号を記せ。
(1) 振幅変調された波形を周波数軸上でみると、搬送波の周波数を中心として上と下の両側に側波滞が現れるが、この両側に現れた側波滞に含まれている情報は全く同じであるから、どちらか一方のみを伝送すれば情報を送ることができる。このような変調方式をSSB変調方式といい、周波数帯域が半分で済む利点があり、電話の( ア )伝送に使用されている。
①デジタル ②スクランブル ③多重 ④ベースバンド
(2) アナログ伝送路における雑音には、熱雑音、変調器や増幅器の非直線性により生じる相互変調雑音、回線相互間の電磁結合又は静電結合により生じる( イ )雑音等がある。
①ジッタ ②干渉 ③量子化 ④漏話 ⑤太陽
(3) 時分割多重化方式においては、多重化する各チャネルのパルス信号を順番に配置し、1周期ごとに、各チャネルの時間位置を識別するための( ウ )同期パルスを挿入する。
①フラグ ②フレーム ③クロック ④スタッフ
(4) アナログ信号のデジタル伝送方式においては、アナログ信号の連続量を( エ )な値に変換するときに生じる量子化雑音を避けることができない。
①定常的 ②ランダム ③周期的 ④離散的
(5) 光ファイバ伝送方式は、一般に、情報伝送の手段として光の( オ )を利用するものである。
①色 ②干渉 ③モード ④回析 ⑤強弱