師偺奺暥復偺乮丂丂丂乯撪偵丄偦傟偧傟偺夝摎孮偺拞偐傜嵟傕揔偟偨傕偺傪慖傃丄偦偺斣崋傪婰偣丅偨偩偟丄乮丂丂丂乯撪偺摨偠婰崋偼丄摨偠夝摎傪偝偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂乮彫寁俀侽揰乯
乮侾乯恾亅侾偵帵偡夞楬偵偍偄偰丄栴報偺傛偆偵揹棳偑棳傟偰偄傞偲偒丄掞峈R2偼丄乮 傾 乯僆乕儉偱偁傞丅偨偩偟丄揹抮偺撪晹掞峈偼柍帇偡傞傕偺偲偡傞丅 乮俆揰乯
丂丂丂嘆俇丂嘇侾俀丂嘊侾係丂嘋侾俉丂嘍俀俉
丂丂丂
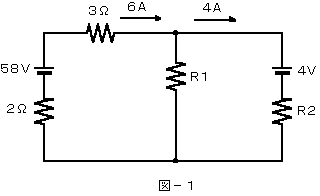
乮俀乯恾亅俀偵帵偡夞楬偵偍偄偰丄抂巕倎亅倐娫偵捈棳揹埑侾侾侽儃儖僩傪壛偊偰偄傞偲偒丄侾侾傾儞儁傾偺揹棳偑棳傟丄惓尫攇偺岎棳揹埑侾俉侽儃儖僩傪壛偊偰偄傞偲偒丄俁侽傾儞儁傾偺揹棳偑棳傟偨丅偙偺偲偒偺梕検儕傾僋僞儞僗倃c偼丄乮 僀 乯僆乕儉偱偁傞丅乮俆揰乯
丂丂丂嘆俇丏侽丂嘇俈丏俆丂嘊俉丏俆丂嘋俋丏侽丂嘍侾侽丏俆
丂丂丂
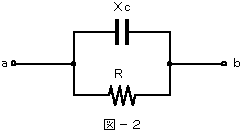
乮俁乯揹帴桿摫偵傛偭偰惗偠傞乮 僂 乯偼丄偦偺乮 僂 乯偵傛偭偰棳傟傞揹棳偑嵔岎帴懇偺曄壔傪朩偘傞曽岦偵桿婲偝傟傞丅 乮俆揰乯
丂丂丂嘆帴壔椡丂嘇揹帴椡丂嘊婲帴椡丂嘋婲揹椡
乮係乯惓尫攇岎棳偺棳傟傞夞楬偵偍偄偰丄桳岠揹椡偼丄乽乮揹埑偺幚岠抣乯亊乮揹棳偺幚岠抣乯亊俠俷俽兤乿偱昞偝傟丄兤偼乮 僄 乯偱偁傞丅乮俆揰乯
丂丂丂嘆揹埑偲揹棳偺埵憡嵎丂嘇揹埑偲揹棳偺廃攇悢嵎丂嘊柍岠棪丂嘋椡棪
戞俀栤
師偺奺暥復偺乮丂丂丂乯撪偵丄偦傟偧傟偺夝摎孮偺拞偐傜嵟傕揔偟偨傕偺傪慖傃丄偦偺斣崋傪婰偣丅丂丂丂 乮彫寁俀侽揰乯
乮侾乯僶僀傾僗夞楬偼丄僩儔儞僕僗僞摍偺摦嶌揰偺愝掕傪峴偆偨傔偵昁梫側乮 傾 乯傪採嫙偡傞夞楬偱偁傞丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆岎棳揹棳丂嘇捈棳揹棳丂嘊僶僀僷僗怣崋丂嘋擖椡怣崋
乮俀乯恾亅侾偵帵偡夞楬偵丄恾亅俀偵帵偡攇宍偺擖椡揹埑嘪俬傪壛偊傞偲丄弌椡揹埑嘪倧偼丄乮 僀 乯偺攇宍偲側傞丅偨偩偟丄僟僀僆乕僪偼棟憐揑側摿惈傪帩偪丄乥嘪乥亜乥E乥偲偡傞丅 乮係揰乯
丂丂丂
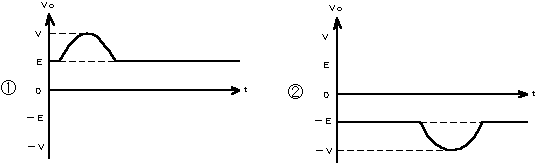
丂丂丂
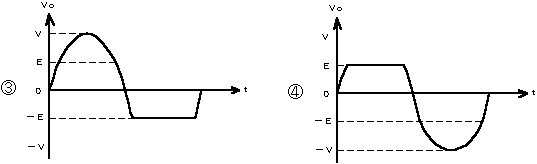
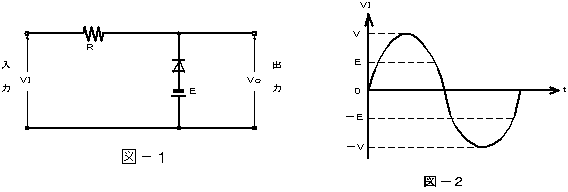
乮俁乯擟堄偺擖椡攇宍偵懳偟丄嬌傔偰嫹偄怳暆儗儀儖娫偵擖傞晹暘偩偗傪偲傝弌偡夞楬傪丄乮 僂 乯偲偄偆丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆僼儕僢僾僼儘僢僾丂嘇儕儈僢僞丂嘊僋儔儞僷丂嘋僎乕僩丂嘍僗儔僀僒
乮係乯僶儕僗僞偼丄乮僄乯偺媧廂丄嶨壒媧廂丄壏搙曗彏摍偵巊梡偝傟傞丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆崅廃攇丂嘇夁揹棳丂嘊帴奅丂嘋夁揹埑
乮俆乯晧壸掞峈偵傛傝惗偠偨弌椡傪僐儞僨儞僒傪夘偟偰師抜傊揱偊傞憹暆夞楬偼丄乮 僆 乯憹暆夞楬偲偄傢傟偰偄傞丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆僐儞僨儞僒寢崌丂嘇俠俼寢崌丂嘊曄埑婍寢崌丂嘋掞峈寢崌
戞俁栤
師偺奺暥復偺乮丂丂丂乯撪偵丄偦傟偧傟偺夝摎孮偺拞偐傜嵟傕揔偟偨傕偺傪慖傃丄偦偺斣崋傪婰偣丅丂丂丂乮彫寁俀侽揰乯
乮侾乯恾亅侾偺榑棟夞楬偼丄擖椡倎媦傃擖椡倐偺榑棟儗儀儖偲弌椡們偺榑棟儗儀儖偲偺娭學偐傜丄乮 傾 乯偺夞楬偵抲偒姺偊傞偙偲偑偱偒傞丅 乮俆揰乯
丂丂丂嘆榑棟榓丂嘇斲掕榑棟榓丂嘊榑棟愊丂嘋斲掕榑棟愊丂嘍斲掕榑棟
丂丂丂
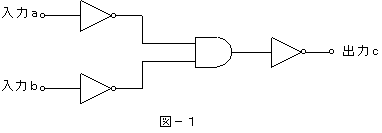
乮俀乯師偺榑棟娭悢倃偼丄僽乕儖戙悢偺岞幃摍傪棙梡偟偰曄宍偟丄娙扨偵偡傞偲丄乮 僀 乯偵側傞丅 乮俆揰乯
丂丂丂
丂丂丂
乮俁乯昞亅侾偼丄恾亅俀乣恾亅俆偺偆偪偺偁傞榑棟夞楬偵偍偗傞擖椡倎媦傃擖椡倐偺榑棟儗儀儖偲弌椡們偺榑棟儗儀儖偲傪帵偟偨恀棟抣昞偱偁傞丅偙偺恀棟抣昞偵奩摉偡傞榑棟夞楬偼丄乮 僂 乯偺榑棟夞楬偱偁傞丅 乮俆揰乯
丂丂丂嘆恾亅俀丂嘇恾亅俁丂嘊恾亅係丂嘋恾亅俆
丂丂丂
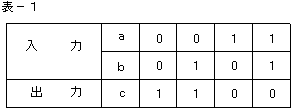
丂丂丂
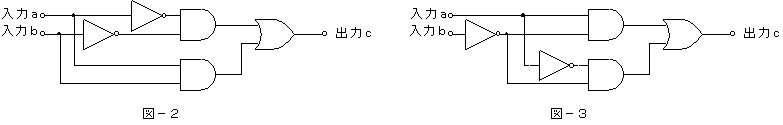
丂丂丂
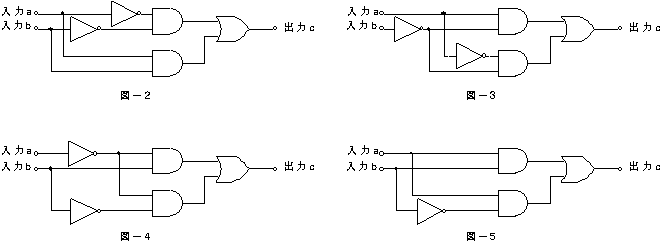
乮係乯昞亅俀偼丄擖椡榑棟儗儀儖A媦傃俛偲弌椡儗儀儖俠偲偺娭學傪帵偟偨恀棟抣昞偱偁傞丅偙偺恀棟抣昞偵憡摉偡傞榑棟幃偼丄乮 僄 乯偱昞偡偙偲偑偱偒傞丅 乮俆揰乯
丂丂丂
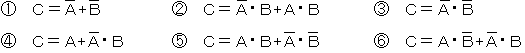
丂丂丂
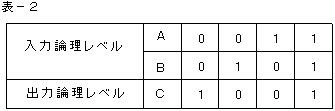
戞係栤
師偺奺暥復偺乮丂丂丂乯撪偵丄偦傟偧傟偺夝摎孮偺拞偐傜嵟傕揔偟偨傕偺傪慖傃丄偦偺斣崋傪婰偣丅丂丂丂丂乮彫寁俀侽揰乯
乮侾乯恾亅侾偵偍偄偰丄揹婥捠怣夞慄傊偺擖椡揹埑偑乮 傾 乯儈儕儃儖僩丄偦偺揱憲懝幐偑侾僉儘儊乕僩儖摉偨傝侽丏俉僨僔儀儖丄憹暆婍偺棙摼偑俁俇僨僔儀儖偺偲偒丄揹埑寁偺撉傒偼丄俇俆侽儈儕儃儖僩偱偁傞丅偨偩偟丄曄惉婍偼棟憐揑側傕偺偲偟丄揹婥捠怣夞慄媦傃憹暆婍偺擖弌椡僀儞僺乕僟儞僗偼偡傋偰摨堦抣偱丄奺晹偼惍崌偟偰偄傞傕偺偲偡傞丅 乮俆揰乯
丂丂丂嘆俀侽丂嘇俀俁丂嘊俁俁丂嘋俁俋丂嘍俇俆丂嘐侾俋侽
丂丂丂
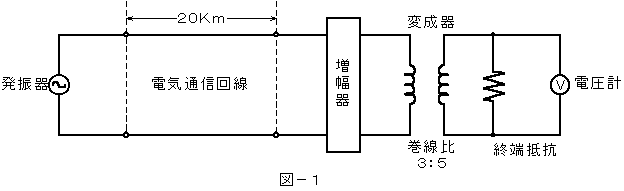
乮俀乯摨幉働乕僽儖偼丄堦斒揑偵巊梡偝傟傞廃攇悢懷偵偍偄偰怣崋偺廃攇悢偑係攞偵側傞偲丄偦偺揱憲懝幐偼丄栺乮 僀 乯攞偵側傞丅乮俆揰乯
丂丂丂嘆侾乛係丂嘇侾乛俀丂嘊俀丂嘋係
乮俁乯恾亅俀偵偍偄偰丄俙曽岦偵偍偗傞楻榖尭悐検偼丄乮 僂 乯僨僔儀儖偱偁傞丅
丂丂丂嘆亅俇侽丂嘇亅係侽丂嘊侾俇丂嘋係侽丂嘍係係丂嘐俇侽
丂丂丂
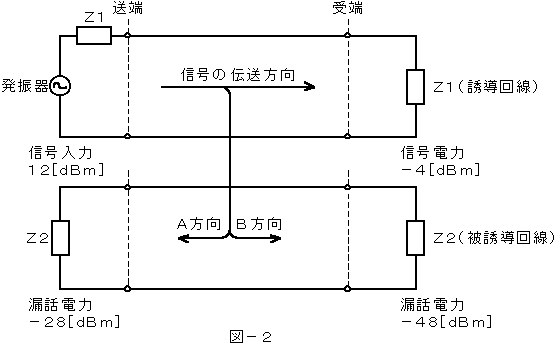
乮係乯愨懳儗儀儖偼丄侾儚僢僩傪侽僨僔儀儖偺婎弨偲偟偨応崌丄偙傟傪婰崋乮 僄 乯偱昞偡丅 乮俆揰乯
丂丂丂嘆倓俛倠丂嘇倓俛倣丂嘊倓俛倂丂嘋倓俛倰丂嘍倓俛値
戞俆栤
師偺奺暥復偺乮丂丂丂乯撪偵丄偦傟偧傟偺夝摎孮偺拞偐傜嵟傕揔偟偨傕偺傪慖傃丄偦偺斣崋傪婰偣丅丂丂乮彫寁俀侽揰乯
乮侾乯揱憲懷堟撪偱擇偮偺堎側傞廃攇悢偺斃憲攇傪梡偄丄偦傟偧傟偺斃憲攇傪晞崋價僢僩乽侾乿丄乽侽乿偵懳墳偝偣偰憲怣偡傞曄挷曽幃偼丄乮 傾 乯偱偁傞丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆埵憡曄挷丂嘇俹倂俵丂嘊俹俠俵丂嘋怳暆曄挷丂嘍俥俽俲
乮俀乯壛嶼丄尭嶼摍偺僨僕僞儖墘嶼偵傛偭偰丄傾僫儘僌怣崋偐傜摿掕偺廃攇悢懷堟偺傾僫儘僌怣崋傪庢傝弌偡僨僕僞儖僼傿儖僞偺惛搙傪忋偘傞偨傔偵偼丄傾僫儘僌怣崋傪僨僕僞儖怣崋偵曄姺偡傞偲偒偵丄乮 僀 乯昁梫偱偁傞丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆儕儞僌曄挷婍傪捠偡丂嘇検巕壔僗僥僢僾偺暆傪彫偝偔偡傞丂嘊僒儞僾儕儞僌廃攇悢傪掅偔偡傞
丂丂丂嘋検巕壔僗僥僢僾偺暆傪戝偒偔偡傞丂嘍崅堟僼傿儖僞傪捠偡
乮俁乯摨幉働乕僽儖偼丄奜晹摲懱偺摥偒偵傛傝丄暯峵懳働乕僽儖偲斾妑偟偰乮 僂 乯偵偍偄偰桿摫摍偺朩奞傪庴偗偵偔偄丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆斾妑揑崅偄廃攇悢丂嘇斾妑揑掅偄廃攇悢丂嘊傾僫儘僌揱憲丂嘋揹椡揱憲
乮係乯俹俠俵曽幃偵偍偄偰丄揱憲偝傟偰偒偨僷儖僗楍傪庴怣懁偱尦偺攇宍偵暅尦偡傞偨傔偵偼検巕壔儗儀儖傑偱嵞惗偟偨怣崋傪丄僒儞僾儕儞僌廃攇悢偺侾乛俀傪幷抐廃攇悢偲偡傞乮 僄 乯僼傿儖僞偵捠偣偽傛偄丅 乮係揰乯
丂丂丂嘆崅堟丂嘇掅堟丂嘊懷堟捠夁丂嘋懷堟慾巭
乮俆乯岝僼傽僀僶揱憲曽幃偱偼丄岝怣崋偑岝僼傽僀僶撪傪恑傒庴岝婍偵摓払偡傞偲丄庴岝婍偼丄偦偺岝偺乮 僆 乯傪尦偺揹婥怣崋偺戝彫偵暅挷偡傞丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮係揰乯
丂丂丂嘆攇挿丂嘇嫮庛丂嘊僗儁僋僩儔儉