| CPU | Core i5-5200U 2.2GHz |
| Memory | DDR3L PC3L-12800 4GB x2 |
| HDD | WD 500GB→Kingston 240GB |
| DRIVE | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| OS | Windows8.1→Windows10 |
| CPU | Core i7-3770 3.4GHz |
| chipset | Intel H77 Express |
| Memory | PC3-12800 DIMM 4GB x2 |
| VIDEO | インテル HD グラフィックス 4000 |
| HDD | SEAGATE ST1000DM003 (1TB)→SanDisk 250GB |
| DRIVE | BD drive |
| OS | Windows8.1→Windows10 |
| CPU | AMD A10-7870K |
| chipset | AMD A78 FCH |
| Memory | 8GB DDR3 SDRAM(PC3-19200 4GB x2) |
| VIDEO | AMD Radeon R7 |
| HDD | Intel 535 240GB SSD + WD40EZRZ(4TB) |
| DRIVE | BD drive |
| OS | Windows7 Professional→Windows10 |
| CPU | Core i5-480M 2.66Ghz |
| Mem/HDD | 4GB/640GB, 5400rpm |
| OS | Windows7 Home Premium |
| CPU | Core i7 930 |
| M/B | ASRock X58 Extreme |
| Memory | 6GB DDR3 SDRAM(PC3-8500 2GB x3) |
| VIDEO | ATI Radeon HD5770 1GB |
| HDD | W.D. 2TB (20EARS) x2 |
| DRIVE | Pioneer BDR-205BK/WS |
| OS | Windows7 Home Premium |
| CPU | Atom Z530 1.6Ghz |
| Mem/HDD | 1GB/100GB? |
| OS | Windows XP Home |
| CPU | Core2Duo T5500, 1.66Ghz |
| chipset | MobileIntel 945GM Express |
| Memory | PC2-5300(DDR2-667) SDRAM 1GBx2 |
| VIDEO | chipset内蔵、13.3inch WXGA |
| HDD | 120GB |
| DRIVE | DVD-R/RW |
| OS | WindowsVista Home Premium |
| CPU | CeleronM 380 1.6Ghz |
| M/B | 910 GML chipset |
| Memory | ? 1GB |
| VIDEO | onboard |
| HDD | 60GB |
| DRIVE | DVD-R/RW |
| OS | WindowsXP Home Edition |
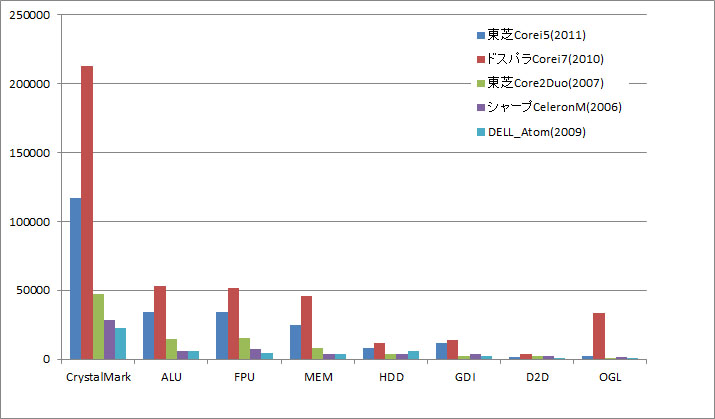
| 時期 | メーカー・機種名 | コメント |
| 1980年前後 | SORD M5 | 初めて触ったパソコン。小学校にあった。プログラムとかはほとんどわかんなかった。ちなみにSORDは潰れた。 |
| 1983年頃 (小学生) | 東芝 パソピアIQ(MSX) | メモリは64kバイトと大容量、しかしスロットは1個しかなかった。当時からソフトをダビング(ラジカセで)したりしていたが、さすがにテープはきつかった。ベーマガ等を読んで、BASICのプログラムを入力して遊ぶのが中心であった。たまにゲームもやった。ディグダグ、ドラゴンスレイヤー(中とかタモリとか出てくるやつ)、ゲームではあまりすごいのはなかった。初めてのパソコンだったが、MSXの限界が見えてきたため5年後くらいに友達に売った。 |
| 1987年頃 (中学生) | NEC PC-8801mk2 FR model 30 | まだ98全盛期ではなく、98はビジネス用途に限られていた。とにかく88さえ買えば何も不自由しない時代。しかし中学生にしては高かった(セットで16万円)。FM7、X1はこの頃既にマイナーになりつつあった。マックスロードで借りて、ファイルメーカーやマジックコピーでコピーしまくるという、市販のゲームで遊ぶ事が中心となった。ザナドゥ、ハイドライド2、ウィザードリィからイース2、ザナドゥシナリオ2、ソーサリアン、大戦略、三国志、信長の野望全国版…カオスエンジェルス。ゲームばっかりしてた時期。メディアは5インチ2DのFD。 |
| 1990年頃 (高校生) | なし | 88から98に移行するかと思いきや、98はやはりまだ高くて買えず。パソコンから離れていた時期。ノーマルに部活に熱中、などはせず、アニメとバイクが中心。 |
| 1992年 | NEC PC-9801RA21 | 大学に入る頃に買った。HDDなし、メモリ640KBのくせにセットで40万円近くした。CPUは386DX 20Mhzで、しばらくは最速気分を味わえた。5インチ2HDのゲーム全盛期でゲームマシンだったが、しばらくしてからパソコン通信も始めた。これが現在の人間関係にも大きな影響を及ぼした。いわゆるエロゲーが台頭してきた時期でもある。それまでエロゲーは、当時からしてもかなり辛い出来の作品ばかりであったが、エルフのドラゴンナイトあたりから明らかにレベルアップしてきた。 |
| 1993年 | SHARP X68030 | Motorolla 68EC030 33Mhz。パソコン通信でCG集めをしてて、この98の16色ではちゃんと見えないCGがあるということがわかり、多色・高解像度マシンが欲しくなる。フォーマットはMAGやその後のPI中心ではあったが、jpegや68picをちゃんと見たい、ゲーセンのようなゲームもしたい、怪しいジョークソフト(Lupinとか)やアングラな香りのするフリーソフト(Panicほか)の世界を満喫したいと思い、とうとう購入。発売前から予約して、21インチディスプレイとセットで40万円以上した。その後買った、240MBの外付けSCSI HDDは7万くらいした。128MBのMOドライブは10万(メディアは3000円前後)した。確かに98では認識することのできない世界があった。同人ハード、高速RS-232Cボードを買ったりした。外付け3.5インチFDDを、Towns用のをちょっと細工して付けたりと、本当に遊べるマシンであった。最終的には2000年に全部で8万で売った。 |
| 1994年 | Apple PowerMacintosh 7100/80AV | PPC601/80Mhz、RAM 16MB(現在64MB)。32万円くらい?モニタと合わせて40万円を超えてたと思うがどうか。初代パワーマックの後期製品。98、68でも飽きたらず、しかし当時流行り始めていたDOS/Vマシンではなくマック。使ってみてやはり納得、洗練されたGUIは思考に馴染みやすく、現在のWindowsみたい(あるいはそれ以上)なシステムが10年以上前からあったというのは驚きである。ワープロや、その後のインターネット、DeskStudio DXという動画ボードを付けて動画の取り込みや再生をした。HDDが故障したがジャンク品に換装し、現在も動く。このマシンから、ゲームはあまりやらなくなった。 |
| 1995年 〜2000年頃 | Apple PowerBook 520 | Motorolla 68EC040 25Mhz, RAM 12MB。640×480で小さなFSTNモノクロ液晶。今見ると、むしろレトロな計算機といった雰囲気で、当時の98ノート等のような事務用品みたいなやつよりずっと上品。マックは安くなったとはいえ、パワーブックはやたら高く、最新機種・68040 33MhzでTFTカラー液晶の540cは定価70万位して、昔のマック的価格というものを思い知らされた。これは既に1年くらい型落ちで、RAM 12MBの後期品で11万円と特価だったので即買いした。モノクロ液晶なれどそれはむしろマックらしい。マックの環境がどこでも移動できるのはすごい、と思った。高いわりにパワーブックの3台に2台は故障すると言われ、これも買って1年以内に2回の故障を経験した。1回は音が出なくなりロジックボード交換、もう1回は蝶番が割れた。渋谷のNCRに直接持ち込み、アップルケアの重要性を知る。しかしワープロと通信中心に、かなり使い込んだ。仕事にノートPCが必要で、相当遅いけどワープロをせっせとやってた。次はDELL。 |
| 1996年頃 | Fujitsu FM-TOWNS 20F, etc. | なんだかパソコンが集まってしまい、98が3台、マック2台、68、Townsと何でもあった時期。しかし前後からディスプレイに照射されるとなんか弱りそうな感じがしたし、またふとすっきりしたくなり、一気に手放したりした。 |
| 1998年 | DOS/V AMD K6-200 M/B:TX-97X | 初めてのDOD/Vマシンはショップブランド。安くて、わりとさくさくWin95が動いて、したい事はだいたいできた。しかしクロックアップしたせいか、電源が入らなくなったり、その他不調によりCD-R焼き専用マシンを経てリタイア。 |
| 1999年 | DOS/V Celeron 300AMhz M/B:BH-6 | クロックアップ遊び用マシン。といってもベースはもらいもののVIPマシン(K林氏に感謝)。450Mhz行けるとか言われてたけど、どうしてもそれでは起動できず370とかそれくらいで使っていた。ABitのBH6は、BIOSで周波数とか倍率とか変えられる、クロックアップには非常に便利なM/Bだった。しかし、使っているうちに電源すら入らない時や、かと思うと夜中にひとりでに起動したりして不気味なことが多発、そのうち電源も入らなくなりリタイア。そんな怪しいCeleronだったが、じゃんぱらに売ってしまった(2000年末 2000円)。 |
| 2000年12月 〜2001年2月 | DOS/V AMD K6-III 3D+ 450Mhz M/B:Freeway FW-TI5VGF(VIA Apollo MVP3) | 上記デスクトップが壊れて、しばらくDOS/Vノート1本でやってたけどパーツを頂いたんで復活したデスクトップ。大した作業はしてないので、快適で問題なかったけどもっと速いCPU+M/Bを頂いたので引退。現役期間は最短。たまたまだけど、毎回およそ1.5倍の速度になっている。(200→300→450→650) |
| 2000年2月 〜2004年3月 | DOS/Vノート DELL Inspiron3700 CeleronA 430MHz | 初代DOS/Vノート。仕事用と思ってそこそこのスペック買ったつもりが、当初は十分速くてカッコ良く、ワープロ中心にはオーバースペックと思われたが、そのうち起動もネットも遅くてやってられなくなった。ただ、ISDNerにはRS-232Cが付いてるのは便利で、意外と長くメール専用マシンとして使ってた。一部のキーが押しても反応なくなってきて困ったが、ノートで4年も使えばそうなるか。Win2000入れて動きは安定してたし、もちろん今でも動く。 |
| 2001年 2月11日〜2007年 | DOS/V PIII 650Mhz M/B:ASUS CUBX(440BX) | ずっと同じVIPマシンのケースとE田氏のCPU等ご協力で出来たマシン。なんとなく家庭用に使っていたが、ノートに慣れると大した事しないユーザーにはデスクトップは邪魔物になるのであった。ケースはでかいので、電源部分が壊れた外付けHDDとか内蔵して、2007年まではDVD書き込み用に使っていたが、日立の出来合いデスクトップを使うことにして引退。確かに、2007年でこのスペックは若干きつい。 |
| 2003年1月 〜2008年頃 | Windowsノート 東芝Dynabook G6/X18PDE Mobile Pentium4 1.8GHz | DOS/Vなんて言葉、まだあったんだ。このノートはでっかくて画面広くてほぼデスクトップ的に使ってあんまり持ち歩かなかった。そういう意味では非常に使いよくて長く使ったけどやはり4年以上過ぎるといろいろ遅くなるので引退。2013.5破棄。 |
| 2008年1月 〜2010年6月 | Windowsデスクトップ 日立Prius Deck 570C5SYA AMD Athlon(TM) XP プロセッサ 1600+ | 実家のお下がり、2002年発売ゆえ十分古いがメモリ1Gにして外付けHDD付けてDVDピーコ専用機として使用。DVD1枚取り込みに1.5時間、書き込みに2時間近くかかるが、それだけにしか使わないからまぁいい、と思ってたら、最新のPCだと取り込み5分とかで終わっちゃうのでこれの存在意義は無くなった。ワープロと軽いネットくらいはできるけど、今時古いデスクトップって”コンピュータ関係でない職場”くらいでしか使われないね。 |