
朝日新聞、2011年12月13日
| 清明 |
| 新暦では、子どもや学生は入学式・新学期をあと数日に控え、社会人は新年度が始まったばかりのころ。 |
| 暦の会 第372回 | |
|---|---|
| 暦と初歩の天文学のおはなし | |
| 2012年2月18日 | 石原幸男 |

| 清明 |
| 新暦では、子どもや学生は入学式・新学期をあと数日に控え、社会人は新年度が始まったばかりのころ。 |
| 節気 | 意味 |
|---|
| 近頃、「中学生みたいな大学生」が増えていると聞く。本来の意味を理解せず、結果だけを覚える、教科書(偉い先生の学説)を鵜呑みにする、そのような教育ばかりを受けてきたためではないか? |

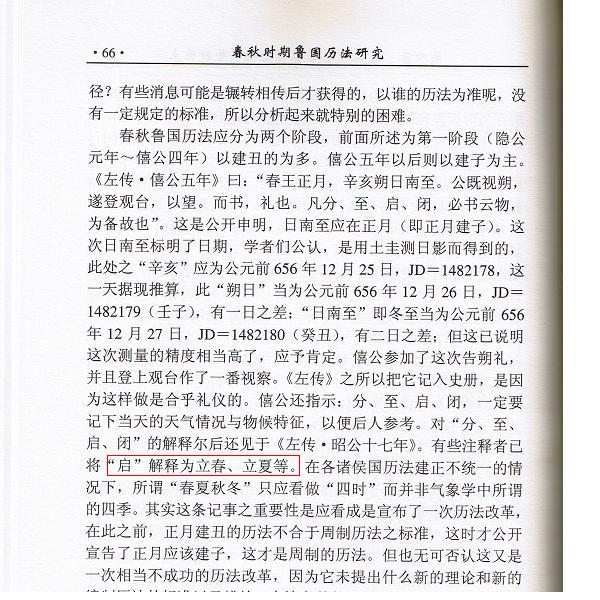
| 上掲書によると、BC660(辛酉)年庚辰朔(日本の「神武天皇即位、辛酉年正月庚辰朔」)は魯国暦では「二月朔」。 魯国は「建丑正月」であったため。 |
| 江戸から小田原までの途中、歩測で「三度もの幅で誤る」 |
| 犬吠埼『三十五度四十二分二十七秒』 |
| 京、梅小路『三十四度九十八分六十七秒』 |
| 一つは、大地だった。授時暦が作られた中国の緯度と、日本の緯度、その差が、術理に根本的な差をもたらしていたことを実証したのである。北極星による緯度の算出、その”里差”の検証、さらには漢訳洋書という新たな視点によって、その誤謬が確実なものとなった。 すなわち授時暦は中国において”明察”である。その数理に矛盾はない。だが日本に持ち込まれた時点で、観測地の緯度が変わり、ひいては授時暦の誤謬となるのである。 |
| 里差 元 創為之○ 申時日食如三日月按宋史當紹聖元年是歳三月壬申朔食未六刻甚此 本朝與異方同日之食而加時差一辰此最為國差之證也○宋史曰 有食按此當 本朝寛元四年是時諸道勘申云申酉之間而蝕不正現獨算道主税頭雅衡云不可食果然乃賞之叙正四位下此則雅衡蓋知里差而言歟○武江與南部南北行程相距一百三十里北極出地差四度置相距里数以差度除之約三十許里而北極出地之差一度也○武江與津軽南北行程相距一百八十里北極出地差六度此亦約三十里為北極出地差度用乗三百六十五奇則知一周凡一萬一千里地厚凡三千五百里○用商尺六尺五寸為間六十間為町三十六町為里也 |
| 建部はなおも九州に渡ることを主張したが、伊藤および随伴の医師の説得により、赤間にて療養することを、無念そうに承知した。代わって伊藤が隊を取り仕切り、春海がそれを補佐しつつ、一行は九州を巡った。さらに各藩と交渉し、琉球、朝鮮半島、北京および南京に観測者たちを派遣している。これらの観測者たちから、 『朝鮮三十八度、琉球二十七度、西土北京四十二度強、南京三十四度』 という観測結果が江戸に報告されたのは、それから半年余も後である。詳細な観測が行えたとは言い難かったが、それでも大まかな値を得ることはできた。 |
| 日延は呉越国の杭州に渡り、そこで公暦として用いられていた”符天暦”を学んで帰国し、ついに賀茂保憲に改暦のすべをもたらしたのだが、 「そのせっかくの暦法を、むざむざ捨ておったのだ」 |
| 地球は、太陽の周囲を公転し続けている。そのこと自体は天文家にとって自明の理である。 だがその動き方が、実は一定ではないということを、春海は、おびただしい天測結果から導き出したのだった。 ・・・・ 後世、”ケプラーの法則”と呼ばれるもので、この近日点通過と、遠日点通過の地点もまた、徐々に移動していく。となると、地球の軌道はどんな形になるか。太陽を巡る楕円である。 ・・・・そして驚くべき誤謬を招いた。なんと授時暦が作られた頃は、近日点と冬至が一致していたのだ。このため授時暦を作った元の才人たちは、それらが常に一致し続けるものとして数理を構築したのである。だが今、四百年もの時間の経過において、この近日点は、冬至から六度も進んでいた。 |