

| 丂巹偼丄帞堢楌傕傛偆傗偔侾擭傪挻偊偨僋儚攏幁弶怱幰偱偁傝傑偡偑丄弶怱幰側傝偺帋峴嶖岆傪孞傝曉偟偰僿儔僋儗僗偺梒拵亅鍖壔亅塇壔亅儁傾儕儞僌亅嶻棏亅泎壔偲偄偆奺僗僥乕僕傪宱尡偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅摬傟偺拵偱偁偭偨僿儔僋儗僗偵帞堢楌俀儢寧偱庤傪弌偟偰偟傑偭偨傢偗偱偡偑丄寢榑偐傜尵偆偲偲偰傕帞堢偟堈偄拵偱偁傞偲偄偊丄弶怱幰偱傕偳傫偳傫挧愴偡傋偒庬椶偱偁傞偲巚偄傑偡丅侾擭慜偲斾妑偟偰丄僿儔僋儗僗傕娙扨偵擖庤偱偒傞庬偲側傝丄帞堢偝傟偰偄傞曽丄偙傟偐傜帞堢偟傛偆偲寁夋偝傟偰偄傞曽傕懡偄偲巚偄傑偡丅杮峞偼丄帞堢弶怱幰偲偟偰乽偙偆偄偆忣曬偑偁傟偽彆偐偭偨乿偲偄偆娤揰偐傜帺暘偺宱尡偵婎偯偄偰丄壜擻側尷傝嬶懱揑偵儗億乕僩偝偣偰偄偨偩偔傕偺偱偁傝丄昁偢偟傕儀僗僩偺帞堢朄偲偼尷傜側偄傕偺偱偁傞偙偲傪偛椆彸婅偄傑偡丅傑偨丄巹偺宱尡偟偨僿儔僋儗僗偺帞堢偼丄埲壓偺傛偆偵暋悢偺宯摑偱偁傝傑偡偺偱丄杮峞偺奺僗僥乕僕偼昁偢偟傕楢懕偟偨傕偺偱側偄偙偲偵偛拲堄壓偝偄丅 亂変偑壠偺僿儔僋儗僗宯摑亃 宯摑嘆丂丂丂儕僢僉乕乮俇摢乯俋俋擭侾侾寧弶椷偵偰峸擖宯摑嘇丂丂丂儕僢僉乕惉拵儁傾傪俋俋擭侾俀寧峸擖 宯摑嘊丂丂丂僿儔僋儗僗乮俁椷梒拵俀摢乯俋俋擭俇寧泎壔暔傪俀侽侽侽擭俀寧偵峸擖 丂 丂梒拵帞堢偱偺嵟戝偺億僀儞僩偼丄亯偺梒拵傪偄偐偵戝偒偔堢偰傞偐丠偵恠偒傑偡丅婎杮揑偵偼丄壏搙娗棟傪峴偄丄揔愗偵塧懼偊傪峴偄丄揔愗側僗儁乕僗傪梌偊偰傗傞偙偲偱杦偳偺梒拵偼偡偔偡偔偲惉挿偟偰偄偒傑偡丅亰偵娭偟偰偼偐側傝僘儃儔偱傕栤戣側偔惉拵偵側傝傑偡丅埲壓偼巹偺帞堢娐嫬媦傃帞堢偺嵺拲堄偟偨帠崁偱偁傝傑偡偑丄偙偺曽朄偱朻摢偺僿儔僿儔亯偑峸擖帪俆俆倗仺侾侽俁倗偱塇壔帪侾俁俆倣倣丄儕僢僉乕乮宯摑嘆乯偺亯偺梒拵懱廳偑尰嵼傑偱偱侾俀俀倗媦傃侾侾俆倗偲丄廫暘戝宆偵惉挿偟偰偄傑偡丅 侾丏帞堢娐嫬
丂宯摑嘊俋俋擭俇寧泎壔亅亰俀侽侽侽擭係寧俀俉擔鍖壔乮栺侾侾儢寧乯丄亯俀侽侽侽擭俇寧俀俋擔鍖壔乮栺侾俁儢寧乯 丂戝掞偺帞堢彂傗帞堢儗億乕僩偱偼丄僆僆僇僽僩偺梒拵帞堢偵偼乽敪峺偑恑傫偩儅僢僩乿偑椙偄偲彂偄偰偁傝傑偡偑丄弶怱幰偺巹偵偼敪峺偺掱搙側偳偑敾抐偱偒偢偵擸傫偩傕偺偱偟偨丅僼僗儅儅僢僩傕帺嶌偟偰偄傑偟偨偑慡偔帺怣偑柍偔丄戝帠側僿儔僋儗僗梒拵側偺偱幚愌偺偁傞儅僢僩傪巊梡偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅 丂偨偩偟丄婽桳僇僽僩偝傫僺乕僐偝傫側偳偺僋儚攏幁戝愭攜払偼丄帺嶌僼僗儅儅僢僩摍偱偝傜偵棫攈側僿儔僋儗僗傪堢偰偰偄傑偡偟丄宯摑嘇偺巕懛払傪俇侽摢傎偳僋儚攏幁払偵攝傝傑偟偨偑丄奆懡條側儅僢僩傪巊梡偟側偑傜侾侽侽倗傾僢僾傑偱惉挿偝偣偰偄傑偡偺偱丄揔墳斖埻偼偐側傝峀偄偲巚偄傑偡丅偙偺応偱偼丄彮側偔偲傕巗斕偺儅僢僩偵傛傝偙偙傑偱堢偭偨偲偄偆帠幚偺傒傪偛嶲峫偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅傑偨丄僪僢僌僼乕僪摍偵傛傞帞堢傪帋傒傜傟偰偄傞曽傕偍傝丄惉岟偟偰偄傑偡偑丄巹偼枹宱尡側偺偱妱垽偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅 丂忋婰偺俹俠僼傽乕僽儖幮偺崟僋僰僊僆乕僈僯僢僋丒儅僢僩偵峴偒拝偔慜偵偄傠偄傠側巗斕儅僢僩傪帋偟偰尒傑偟偨偑丄壛悈偡傞偲嵞敪峺偟偰擬傪敪惗偡傞傕偺傕偁傝傑偡偺偱丄弶怱幰偵偼摿偵拲堄偑昁梫偩偲巚偄傑偡丅 係丏梒拵偺惉挿丂梒拵偺塧姺偊帪偵偼丄昁偢懱廳傪検傞傛偆偵偟偰偄傑偡丅戞堦偺栚揑偼棫攈側亯偵側傞傋偔惉挿偟偰偄傞偐偳偆偐妋擣偡傞偨傔偱偡丅巹偺廃曈偱棫攈側僿儔僋儗僗亯傪偄偪憗偔塇壔偝偣偨僺乕僐偝傫偑岾偄偵傕惉挿婰榐傪嵦偭偰偁傝傑偟偨偺偱巹偼偙偺婰榐傪乽俹嬋慄乿偲屇傫偱儕僼傽儗儞僗偲偟偰妶梡偟偰偄傑偡丅嬶懱揑偵偼壓恾偺傛偆偵僌儔僼壔偟偰斾妑偟偰偄傑偡偑丄寢壥偲偟偰帗梇偺敾暿偵傕妶梡偱偒偰偄傑偡丅僌儔僼壔偡傞嵺偺岺晇偲偟偰偼丄僺乕僐偝傫偺帞堢婰榐偑壓昞偺傛偆偵俀俆倗偐傜僗僞乕僩偟偰偄傞偨傔丄俀俆倗偵払偟偨偱偁傠偆擔傪俀俆倗枹枮偺捈嬤偺擔晅偲俀俆倗傪挻偊偨擔偺擔晅偐傜悇應偟偰偦偺擔傪婲嶼擔偲偟偰偄傞偨傔丄泎壔擔偐傜偺宱夁擔悢偲偼堎側傞偙偲偵偛拲堄壓偝偄丅 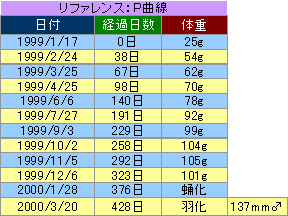 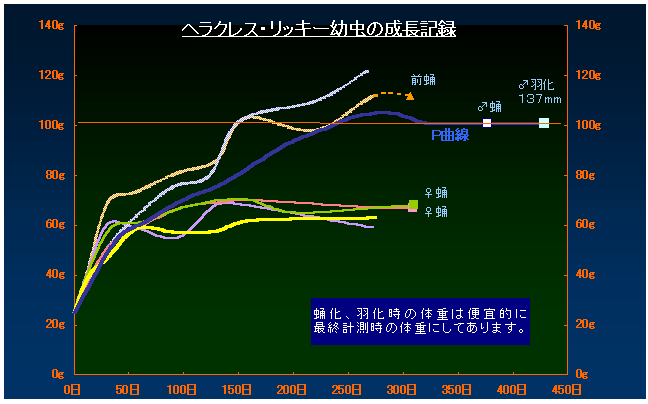 丂僌儔僼傪尒偰敾傞偲偍傝丄俀俆倗乮俁椷弶婜乯偐傜俇侽倗嬤曈傑偱偼亯亰嫟偵侾儢寧偱俀俆倗嬤偄儁乕僗偱栆楏偵惉挿偟傑偡丅偙偺崰偐傜儅僢僩偺怘偄傕栚偵尒偊偰椙偔側傝丄拞僾儔働堦攖偺儅僢僩偑侾儢寧偱敿暘掱搙傑偱尭偭偰偟傑偆掱偱偡丅偦偺屻偼亰偼俈侽倗掱搙傪僺乕僋偵懱廳偱偼掆懾偡傞堦曽丄亯偼俉侽倗偁偨傝傑偱偦偺傑傑惉挿偟懕偗傑偡偺偱丄俇侽倗偐傜偺俁儢寧掱搙偱帗梇偺敾暿偼弌棃傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅俹嬋慄傪尒偰巹偑彑庤偵栚昗偵偟偨偺偼丄偲偵偐偔侾侽侽倗傪挻偊傞偙偲偱偟偨偑丄俇侽倗偐傜俉侽倗傑偱偺娫偵惉挿儁乕僗偑撦傝傑偡偺偱丄婥傪潌傓帪婜偱傕偁傝傑偡偑丄俹嬋慄偑側偩傜偐偵鍖壔傑偱惉挿偟懕偗偰偄傞偲偄偆帠幚傪抦偭偰偄偨偨傔丄俹嬋慄傪忋夞偭偰偄傞偆偪偼椻惷偵帞堢傪懕偗傜傟傑偟偨丅寢壥揑偵偼俉侽倗偐傜侾侽侽倗偵嵞傃惉挿懍搙偑壛懍偟偰堦婥偵侾侽侽倗傪挻偊丄嵟戝偺傕偺偼尰嵼侾俀俀倗傑偱払偟偰偄傑偡丅偙偺掆懾偐傜嵞壛懍偺尨場偵偮偄偰偼晄柧偱偡偑丄俉侽倗偐傜戝僾儔働偵堏偟偨偙偲偑偒偭偐偗偩偭偨壜擻惈偼偁傞偲巚偄傑偡丅傕偟俇侽倗偐傜戝僾儔働偵堏偟偰偨偭傉傝塧傪偁偘偰偄偨傜堎側傞惉挿夁掱偲側偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅 |
