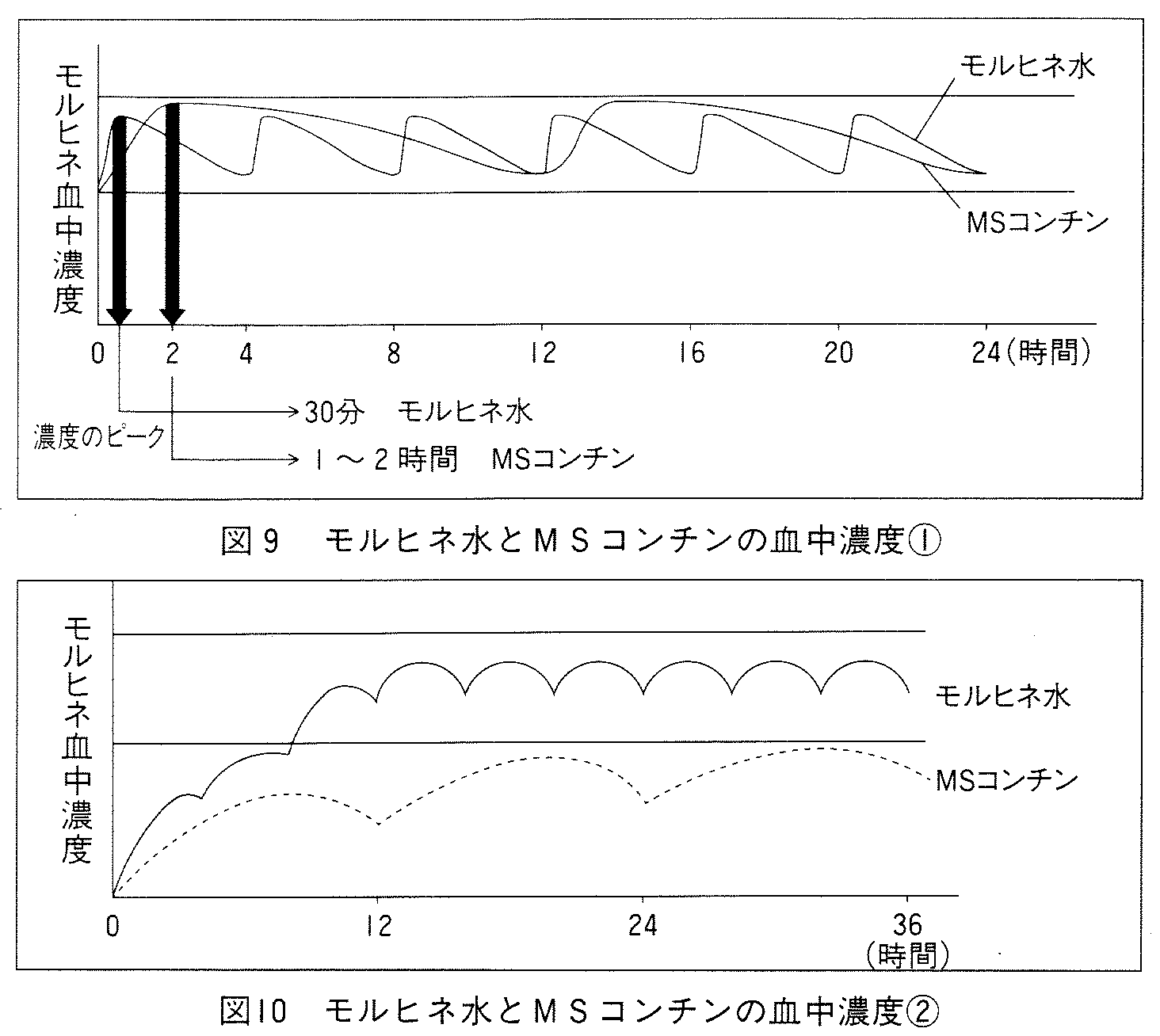�͂��߂�
�@��������Ƃ����A�������ɂ݁A�ꂵ�݂Ƃ�������ۂ���ʂ̕��ɂ͎v�������Ԃ�������Ȃ��B�f�����̋��т��A�x�b�h�̏�ł̂��������B�������ɏ\�N�O�܂ł͂����������Ƃ��������B�������A1987�N�ɐ��E�ی��@��(WHO)���A���{��Łw����̒ɂ݂���̉���x�Ƃ������q�s���A���ȃ����q�l�̎g�������L�߂Ă���́A�����̊��҂��ɂ݂���~����悤�ɂȂ��Ă����B
�@�Ƃ͂����A���҂���̑�����łȂ��A��Î҂̂Ȃ��ɂ��܂������q�l�ɑ������ς�Ό����c���Ă��āA�����q�l�̎g�p�����߂������A�g���͂��߂Ă����ʂ��S�O����ꍇ������悤���B���Ăł́A�����q�l�̐������m�����s���������Ēm���Ă���B���̏͂́A��ʂ̕��ɂ͏��X�����������Ȃ����A�����ƉƑ�����邽�߂ɓǂ݂����߂Ăق����B�����āA����̒ɂ݂����܂�Ƃ�����Î҂ɁA���ɂ݂Ȃ��狳���Ă����Ăق����̂�(�������A�Ƃ��ɖ{�͂̌㔼�����́A���Ȃ���I�ȓ��e�Ȃ̂ŁA��C�ɓǂ݂��Ȃ��Ƃ������A�ނ���ǎ҂̕��̕K�v�ɉ����ēǂ݁A���p���Ă������������Ǝv���Ă���)�B
�@��̎g�����Ƃ����O�ɁA����̒ɂ݂���菜�����߂ɂ́A�܂��ɂ݂��̂��̂𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�������̊ɘa�P�A�`�[���̃}�[�N�́A�K�����Ăԁu�l�t�̃N���[�o�[�v�ł���B����͊��҂���̂��l�̒ɂ݂�a�炰�邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B
�@�l�̒ɂ݂Ƃ́A�g�̓I�Ȓɂ݂̂ق��ɁA���_�I�Ȓɂ݁A�Љ�I�Ȓɂ݁A�X�s���`���A���E�y�C���ł���B�Љ�I�Ȓɂ݂Ƃ́A���҂���̎d���̂��Ƃ�ƒ�̂��ƁA�o�ϓI�Ȃ��Ƃł̔Y�݂�ꂵ�݂ł���B���Ƃ��A��������̒j���̊��҂��ӔC�̂���d���Œ��f���邱�Ƃ�������ꂽ��A�Ⴂ���ꂳ�Ƃɒu���Ă����c���q�ǂ��̂��Ƃ��S�z��������A���ɓ��肽���̂Ɍ��オ�����Ȃ��A�Ȃǂ̂��Ƃ����҂���̒ɂ݂������Ă��܂��B�X�s���`���A���E�y�C���Ƃ́A�@���I�A��I�A�����I�A�N�w�I�Ȓɂ݂ȂǁA���܂��܂ȖȂ���Ă��邪�A�ǂ�����܂肵������Ƃ͂��Ȃ��B���̍l���ɂ��ẮA�ʂ̂Ƃ���Řb���Ă݂����B
�y1�z�ɂ݂�]������
�@���q�ׂĂ����悤�ɁA�ɂ݂����Â��邽�߂ɂ́A�܂��ɂ݂𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��Η��l���m����l�ł����Ƃ��悤�B��������ɔ��������i�Ɋ������邱�Ƃ͉\��������Ȃ��B����ǂ��A���l�������ɂ��ƌ������Ƃ��A���̒ɂ݂��v����邱�Ƃ͂ł��Ă��A��������������ɂ݂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ɂ݂Ƃ����̂́A���̐l�ɂ����킩��Ȃ��A�����܂ł���ϓI�Ȋ��o�Ȃ̂ł���B
�@����Ɠ����ɁA�ɂ݂Ƃ������̂��l�̒ɂ݂ō\������Ă���Ƙb�����悤�ɁA���ꂼ��̗v�f�͊W�������Ă��āA���͂̊��ɍ��E����₷���B1995�N�̈ꌎ�ɂ���������_��k�Ђł͑����̐l���S�g�Ƃ��ɏ������킯�����A��Ў҂̕��̂���Șb������B�n�k����ɁA�Ƒ�����������ו����^�яo�����߂ɁA��ꂽ���K���X��Ƌ�̎U������n�ʂ𗇑��ő������Ă������Ƃ��ɂ݂������Ȃ������B���������ė��������Ă�����A�����炯�̑��ɋC�Â��A�悤�₭�ɂ݂�������悤�ɂȂ����Ƃ����B
�@��Î҂ł����Ă��A�ɂ݂ɂ��Ă悭��������Ă��܂����Ƃ�����BH����͘Z�\�̒j���A�݂���̖����ŕ��ɂƕ������ɋꂵ��ł����B�ނ̒ɂ݂ɑ��Ă̓����q�l�̎����牺�����@���قǂ�����Ă����B���ɂ͂Ȃ����̂́A���Ȃ��̒����������Əd�������͎�肫��Ȃ��B�ނ͕p�ɂɃi�[�X�R�[���������A�Ō�w���Ă�ł����B��Ԃ͂Ƃ��ɋC������邱�Ƃ��Ȃ������������āA�i�[�X�R�[���̉͑�����B����ǂ��A����Ō�w��H����̃x�b�h�T�C�h�ɍ��肱�݁A�b�����Ȃ��炨�Ȃ����������Ă�����ނ͐Â��ɐQ�����Ă��܂����B�܂�����Ȃ��Ƃ��������B���j���Ɉ�̂��������������ɂ���Ă��āA���̖ʉ�Ԃ̂������͈�x���i�[�X�R�[���͖�Ȃ������̂��B�Ō�w�̂Ȃ��ɂ́AH���i���Ă���ɂ݂͂����Ȃ�Ȃ����A�ƌ����l�������B�����������Ă����ł͂Ȃ��B�ɂ݂Ƃ́A�{�������������̂Ȃ̂ł���B
�@����̒ɂ݂Ƃ����ƁA���ɂ̂悤�ɃC���[�W��������������낤���A��ʎ��̂�}���X���A�A�nj��̂悤�ȋ}���ɂƂ͈قȂ�B�������A����̒ɂ݂�������ꏊ�ɂ���ċ�����������������A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�d���A��a���̂悤�Ȓɂ݂���\�l���ԑ������̂������B���̂��߁A���͂̊��Ŋ������������Ԃ�ς���Ă���̂ł���BH����̏ꍇ�̂悤�ɁA���Ɉ�Î҂����Ēɂ��Ƃ�����������Ă�����A�҂��]��ł�����������ɉ���Ă���Ƃ��ɒɂ݂��a�炢�����Ƃ́A�������R�Ȓɂ݂ւ̔����ł���A�悭����p�^�[���Ȃ̂��B��Î҂����łȂ��A�Ƒ��Ƃ��Ă��A�ɂ݂̂����������ʂ𗝉����邱�Ƃ͑�ł���B
�@�܂��A���������ŁA���Ҏ��g�̂Ȃ��ɂ��ɂ݂�a�炰��͂����Ȃ���Ă���(���݁A�����̏�ԂɂȂ�����A�����ی����x�����{�l���g����Ƃ������O���t�^�̕ی������y���͂��߂Ă��邪�A����ɂ���Ĉ�Ô�̐S�z���Ȃ�������A�D���Ȃ��Ƃ����邽�߂ɂ������g�����肷��B���V�����O���Ƃ��čs�������o�Ă��Ă���B��ڂ̗J�����Ȃ��������S�����A�ɂ݂̖����ɂȂ���̂�������Ȃ�)�B
�@�l�\���E����͊C�O�Œ����������ꂽ���������B�ޏ��͓�����ŁA���Ɣx�ւ̓]�ڂ��C�O�ō��m����Ă����B�c���ꂽ���Ԃ̒Z����m����E����́A�Ō�̎��Ԃ������̈�����l�����Ɖ߂��������ƍl���A�l�\�O��ڂ̒a���������Ƀp�[�e�B�[���J�����ƌv�悵���B���łɍ��̓]�ڂ͑S�g�ɍL�����Ă��āA���Âɂ��Ă���Ƃ��̒ɂ݂͂Ȃ�Ƃ������q�l�Řa�炢�ł������A�����Ɣw���ɓd�C������悤�Ȓɂ݂ɏP����B�������A���̔ޏ����p�[�e�B�[�̏������n�߁A���ҏ���o������p�[�e�B�[�̐i�s���l�����肵�Ă��邤���ɁA�ɂ݂͂���ƌy���Ȃ��Ă����̂��B�����ăp�[�e�B�[�̓����A���͂̐S�z���悻�ɁAE����͓��X�Ǝ���߂��B���₩�ȃs���N�̃h���X�Ƀn�C�q�[�����͂��A�w���܂������L���Ċe�e�[�u���̗F�l�����ɂ��������ĉ��B���̊ԁA�ޏ��͒ɂ݂̂��Ƃ͂܂������Y��Ă����Ƃ����B�����ĂȂ�ƁA�����̂Ƃ��̃����q�l�̏��܂܂ň��ݖY��Ă����̂ł���B
�@�����A�ɂ݂Ƃ͕s�v�c�Ȋ��o�ł���B���̊��҂��]�ނ��Ƃ▲���ɂȂ邱�Ƃ��A�܂��̐l�Ԃ��T�|�[�g���邱�Ƃɂ���Ă��A�ɂ݂͘a�炰����B���͂��̂��Ƃ��AE���狳���Ă����������̂��B
�@Not doing but being�|����̓C�M���X�̃z�X�s�X�ł悭�����錾�t�ŁA�u���������邱�Ƃł͂Ȃ��A���ɂ��邱�Ɓv�B�Ƃ�����Î҂́A�ɂ��ƃ����q�l�A���߂Ȃ瑝�ʁA�܂��͐_�o�u���b�N�Ö@�Ƃ����ӂ��ɍl���₷�����A�ĊO���ɍ����āA�ɂ��Ƃ�����������Ă����ق����ɂ݂��a�炮�ꍇ�������̂ł���B
�@�Ƃ͂����A�ɂ݂������܂��Ȃ܂܂ɂ��Ă��ẮA�ɂ݂̎��Â͂�����ł����Ȃ��B���̂��߂ɂ́A������x�̒ɂ݂̕]���͕K�v���B���܂܂ň�Î҂́A���҂���̕\��₵�����Œɂ݂f���Ă����B�������A�ɂ݂͂��̐l�ɂ����킩��Ȃ����o�ł���B�����߂��ʂ����Ă��Ȃ��Ă��A�ɂ��Ƃ��͒ɂ��̂ł���B
�@��ʓI�ɂ́A�ɂ݂̕]���ɂ�VAS(�r�W���A���E�A�i���O�E�X�P�[��)���g���Ă���B����́A��{�̐��̍��[���ɂ݂Ȃ��A�E�[�͍ō��ɒɂ��Ƃ��āA���҂��g���ǂꂭ�炢�ɂ�������Ɉ��������̂��B�������̃`�[���ł́A���҂���ƃ��[���A�̂����b���ł���t�F�C�X�E�X�P�[�����g�p���Ă���(�}3)�B
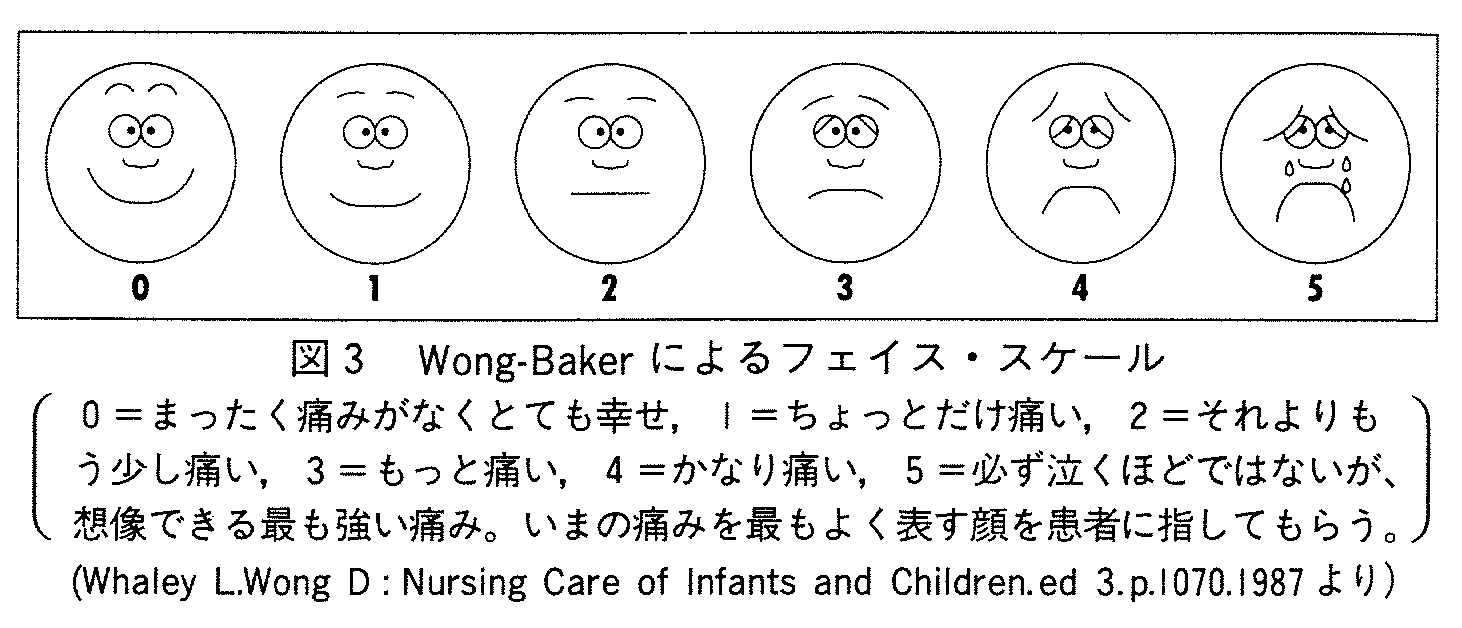
�@�C�M���X�̏����a�@�Ŏq�ǂ��ނ��ɊJ�����ꂽ���̂ŁA�����炪�ō��ɒɂ��A���炪�܂������ɂ݂Ȃ��B�������Î҂���ƌ���ׂĔ��f����̂ł͂Ȃ��A���҂��g�����̂Ƃ��̒ɂ݂�ԍ��Ŏ����B������A���҂��X�P�[���Ɠ���������Ă���K�v�͂Ȃ��B�������́A���Ɏ��Âɂ���āA���҂������X�P�[�����ǂ��ω����邩�ɒ��ڂ���B
�@�ɂ݂ւ̑Ή��ł����Ƃ���Ȃ��Ƃ́A�܂����̒ɂ݂����̂܂܂ɋ������邱�Ƃ��B�ō��ɒɂ��Ƃ����Ƃ�����w���Ă������҂��A�����q�l�̓��^�ŕ\����邭�Ȃ�H�~���o�Ė�Ԃ��n�����Ă���悤�ł����Ă��A�܂��ō��ɒɂ��ƌ����悤�ȏꍇ������B�����Ŋ��҂���̑i����ɂ݂�������������Ȃ��Ǝv���Ă��܂�����A�ɂ݂̎��Â͂����܂����B���҂��ɂ��ƌ�������A���̂܂܂ɋ�������B�����Ď��̒i�K�ŁA���̒ɂ݂���葽���̃����q�l���K�v�Ȓɂ݂Ȃ̂��A����Ƃ��ق��̈��q������ł���̂��f����B���Ƃ��A���m���Ă��Ȃ����߂ɃC���C�����Ēɂ݂Ɗ����Ă��܂��̂��A���̕s�����������������Ă��܂��̂��A�Ƒ��̕����ӂ��߂Ęb�������A�l���Ă����B������ɂ��Ă��A�ɂ݂̕]���́A�܂����҂���̑i���ɂ��̂܂܋������A���ɂ��̒ɂ݂̗��ɂ��錴�����l���A�Ή����Ă������Ƃ��d�v�ł���B
 �y2�z�����q�l���g�����Ȃ�
�y2�z�����q�l���g�����Ȃ�
�@
�@
�����q�l�������Ȃ����R
�@����A�����q�l�Ƃ����ƈ�ʓI�ɂ͒��ŏǏ�A���_�Ǐ���������������낵����Ƃ������C���[�W������Ǝv���B�������A�����q�l�͐��������^���@���s��������A���S�����ʓI�Ȓ��ɖ�ł���B���������q�l�Ȃ̂ɁA�Ȃ����܂܂ŕ���p��������������Ă����̂��낤���B�����炭�ő�̌����́A��x�ɑ�ʂ̐Ö����˂�ؓ����˂Ƃ��Ďg�p����Ă������Ƃ��������邾�낤�B
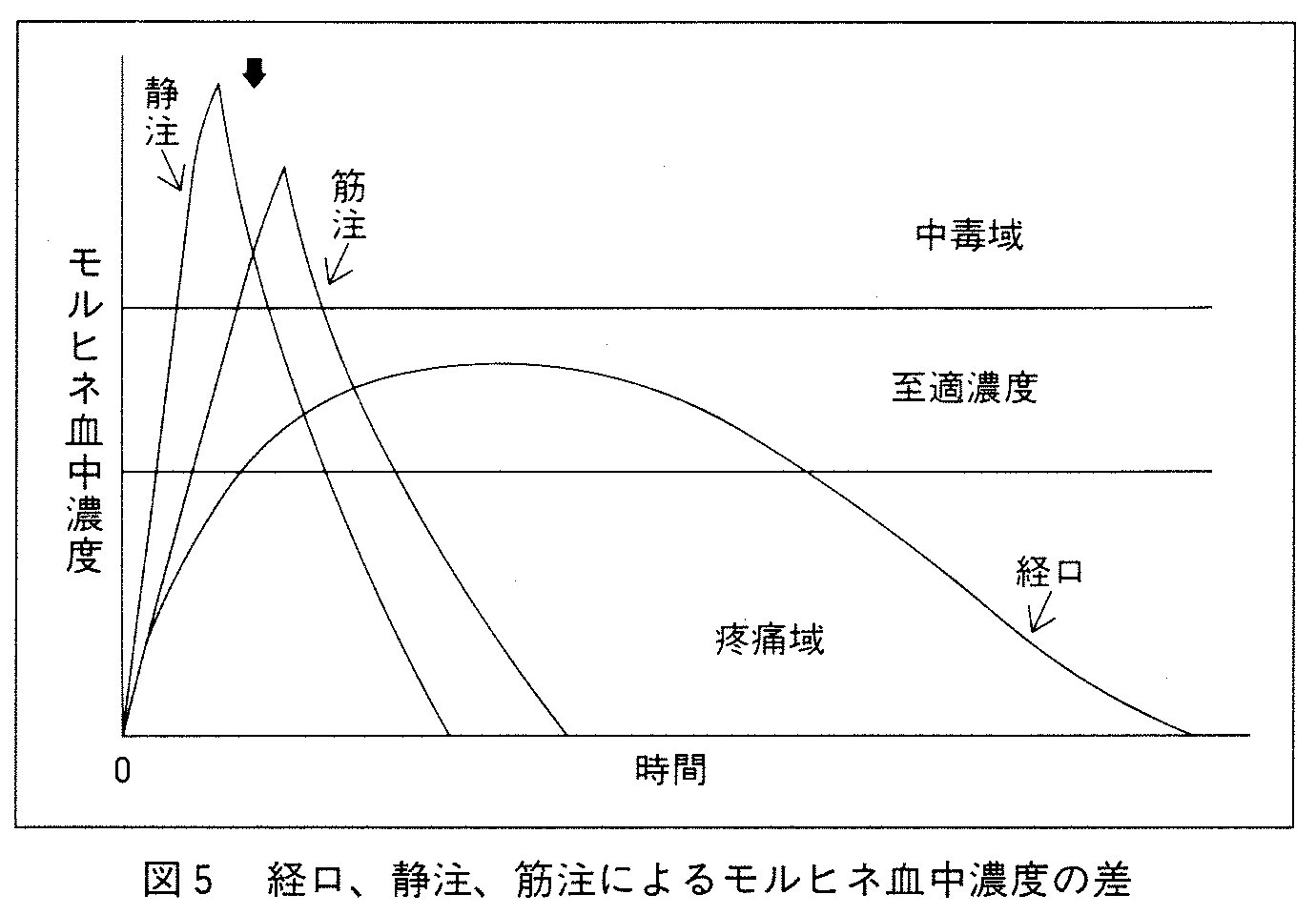
�@WHO�ł͌o�����^�������߂Ă���B�����q�l�̌����Z�x���݂�ƁA�@�u�Ɉ�(����p�͂Ȃ����A�ɂ݂͂���)�A�A���K�Z�x(�ɂ݂��Ƃ�A����p���Ȃ�)�A�B���ň�(�ɂ݂͂Ȃ����A����p���o������)�ɕ�������B���ɑ�ʂɓ��^�����Ö����˂�ؓ����˂ł́A�}5�̖��̂悤�ɁA���K�Z�x��˂������Ē��ň�ɒB���Ă��܂��B���̂��ߋ�������p���o�Ă����̂ł���B�����Č����Z�x�͋}���ɉ�����A�ɂ݂��Ăъ����āA�܂����ˁB����ɂ���č����Ȃǂ̐��_�Ǐ���J��Ԃ��Ă������̂ł���B
�@�o���ł̓��^�Ȃ�A�}5�̂悤�Ɏ��K�Z�x���ɒ�����ۂ��Ƃ��ł���B�������A����̕��p���Ƃ܂��ɂ݂��P���Ă���B�����������p���K�v�ƂȂ��Ă��邪�A�Ԃ������Ɗ��҂���͒ɂ݂������Ă��܂��B����ł́A�\�h�I�ɓ��^�����������Ȃ����A�Ƃ����̂��}7�i�����ځj�ł���B���̗\�h�I�ȓ��^�̊Ԋu���l���Ԃ��ƁA����Z�p����悢�Ƃ������Ƃ��킩�����̂��A�����u�Ɏ��Â̊�b�ɂȂ��Ă���B���ۂɂ́A�����q�l�̐��n�t�ł����Ă��A�N�����A���A�[���A�Q��O�̎l��ŃR���g���[���ł��邵�A�ォ��q�ׂ闰�_�����q�l������(MS�R���`��)�Ȃ�A������O��Œ��߂��ł���Ƃ���܂ł��Ă���B
�@�牺���˂�Ö����˂ł����Ă��A�����I�ȓ��^���@�ł���A�����Z�x��ۂ��Ƃ��ł��A�o�����^�ȏ�ɕ��R�Ȍ����Z�x�ɂȂ�B�����Ƃ��A������̕��p���\�Ȋ��҂���ɂ͊ȕւȕ��@�Ƃ��Čo�����^����ɂ����߂Ă���B
�@�����q�l�͕s�v�c�Ȗ�ł���B�����̖�́A�ʂ������Ă����ƕ���p������ɂ�đ����Ă������A�����q�l�͒ɂ݂ɍ������ʂł���A����p�͒��߉\�ł���B�܂��A�����̕��������q�l�ɑ��Ă������s���ɂ��āAQ&A�����ōl���Ă݂悤�B
Q�F���҂������q�l�̎g�p�����ۂ���悤�ȏꍇ�A�ǂ��Ή����܂���?
A�F���҂������q�l�ƒm��A�ɂ݂�����̂ɖ�����ۂ����悤�ȏꍇ�A���{�l���ɂ݂��������ق����܂����Ɩ��������̂Ȃ�A���͂��̈ӎv�͑��d�����ׂ����낤�Ǝv���܂��B�܂��A�����q�l�͂��₾���ɂ݂͂Ȃ�Ƃ����Ăق����Ƃ����̂ł���A���҂���ƁA�Ƃɂ����悭�b�������悤�ɂ��Ă��܂��B�Ȃ��ɂ͍����̂Ȃ��Ό��ɋÂ�ł܂��Ă��܂��Ă�����������邩��ł��B�Ƒ����ӂ��߂āA�ЂƂ�����������Ă������Ƃ���ł��傤�B
�@����ł͂ǂ������������Ό������邩��̓I�ɏЉ�܂��B
Q�F�����q�l���g���Ɩ����k�߂�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̓��ɓ����Ǝ��Ȏ����͂��݂�̂ł͂Ȃ��ł��傤��?
A�F���炾������Ė����k�߂�Ƃ������Ƃ͂���܂���B�������āA�ɂ݂̂��߂ɐH�~�������Ă�����A�s������������Ă������҂��A�ɂ݂̌y���ƂƂ��ɐH�~���o�Đ��������Ƃ���A�̗͂����邱�Ƃ͂悭����܂��B���l�Ɏ��Ȏ����͂��ɂ݂�����Ƃ��炾�̗͂����ׂĒɂ݂Ɍ����Ă��܂��܂����A�ɂ݂��a�炮�ƁA�����Ă������Ƃ���́A�Ɖu�͂��A�b�v����ƌ����Ă��܂��B
Q�F�������烂���q�l���g���ƌ�Ō����������Ȃ�����A�g���Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł���?
A�F�����q�l�͂���ȏ㑝�₷�ƌ����Ȃ��Ȃ�Ƃ������E���Ȃ��A�ɂ݂ɍ��킹�Ă�����ł����ʂ��邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���҂���ɂ���ẮA�]�����N�ł����Ă��A�ɂ݂��o������ꍇ������A�������烂���q�l���g�p���A�Œ��̕��͎O�N�ԃ����q�l���g���Â����������܂��B
Q�F���_��Q�͂����Ȃ��̂ł��傤��?
A�F�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�����q�l�Ő��_�Ǐo�Ă����̂́A�����q�l�̎g�������܂�����������ł��B�ؓ����˂�Ö����˂ŋ}�ɂ��炾�̂Ȃ��̃����q�l�ʂ������Ȃ��āA����p���o�����Ă����̂ł��B���������s���Ă���悤�ȁA�g�̂̃����q�l�ʂ����ɕۂ���I�Ȉ��ݖ�⎝�������@�ł���A���_�Ǐ�͏o�܂���B
Q�F�ϐ���ˑ������o��̂ł͂Ȃ��ł���?
A�F���҂���̍������s���ޗ��ƂȂ��Ă���_�ł����A���ۏ�͖��ƂȂ邱�Ƃ͂���܂���B�ϐ��Ƃ́A�ɂ݂��p���I�Ɏ��̂ɑ��ʂ��K�v�ƂȂ邱�Ƃł����A�ɂ��Ȃ����ꍇ�͑ϐ��Ƃ������́A�ɂ݂����������ƍl���܂��B���Ƃ��A�ϐ����o���Ƃ��Ă��A�ɂ݂ɍ��킹�đ��ʂ���悢�̂ł��B�ˑ����͐��_�I�ˑ����Ɛg�̓I�ˑ���������܂��B���_�I�ˑ����Ƃ́A�ɂ݂Ƃ͖��W�ɖ��v������s���ł����A�ɂ݂ɍ��킹�K�����������p���邩���肨�����Ă��܂���B�������҂����~������悤�ł�����A����͖�̗ʂ�����Ȃ��ƍl����ׂ��ł��B�g�̓I�ˑ����Ƃ́A�ˑR�̖�̒��f�ɂ���Ă�������̂ł����A�}�ɕ��p�ł��Ȃ��Ȃ����玝���牺�����@�ȂǂɕύX���ă����q�l���p������悢�̂ł��B�܂��A���ː��Ö@��_�o�u���b�N�Ö@�ȂǂŒɂ݂���ꂽ�ꍇ�A�O�T�Ԃ��炢�����ă����q�l��Q���E���~���Ă������Ƃ��\�ł��B��x�n�߂���~�߂��Ȃ��ƍl����̂͊ԈႢ�ł��B
Q�F�����炵���Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł���?
A�F�O�q�̂悤�ɐ��_�Ǐo�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�����q�l�̖��C����q�̂悤�ɓ���̉�b�Ɏx��͂���܂���B
Q�F����p�͔������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł���?
A�F��q�̂悤�ɂ��܂��܂ȕ���p������܂����A�ǂ���Ή��\�ł��B
�@
�@�܂�������ƃj���A���X�͂��������A���̂悤�ȕΌ��̂��߂Ƀ����q�l���g�p�ł��Ȃ��ꍇ������B
�@�@�u�����q�l�v�C�R�[���u�����߂��v�C���[�W�B���҂��g�������ӎ����Ȃ�����A�����F�߂����Ȃ����߂Ƀ����q�l�����ۂ��邱�Ƃ�����B
�@�A�_�l�͎������ς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ɂ݂͂��^���ɂȂ�Ȃ��A�܂�ς����Ȃ��Ɗ�����͔̂E�ϗ͂�����Ȃ��A�ƃ����q�l�̎g�p�����ފ��҂��������B�����������q�l�̒m�����`����Ă��A�ɂ݂������邱�ƂɈӋ`�����������Ă�����ł���A���̋C�����͑��d�����ׂ��ł��낤�B
�@
�ɘa�P�A�`�[���̂����u�ɑ�}�j���A��
�@���E�ی��@�ւ������߂Ă���WHO���������f���ɁA�������́w���u�ɑ�}�j���A���x���쐬�����p���Ă���B�}8�ɊT�����������B���Ƃ�����̒ɂ݂ł����Ă��A�����Ƀ����q�l���g�p����K�v�͂Ȃ��B���҂���̒ɂ݂ɍ����������̖�����X�ɒi�K�I�Ɏg���Ă����B���́A�傫���͎O�̒i�K���l���Ă���B
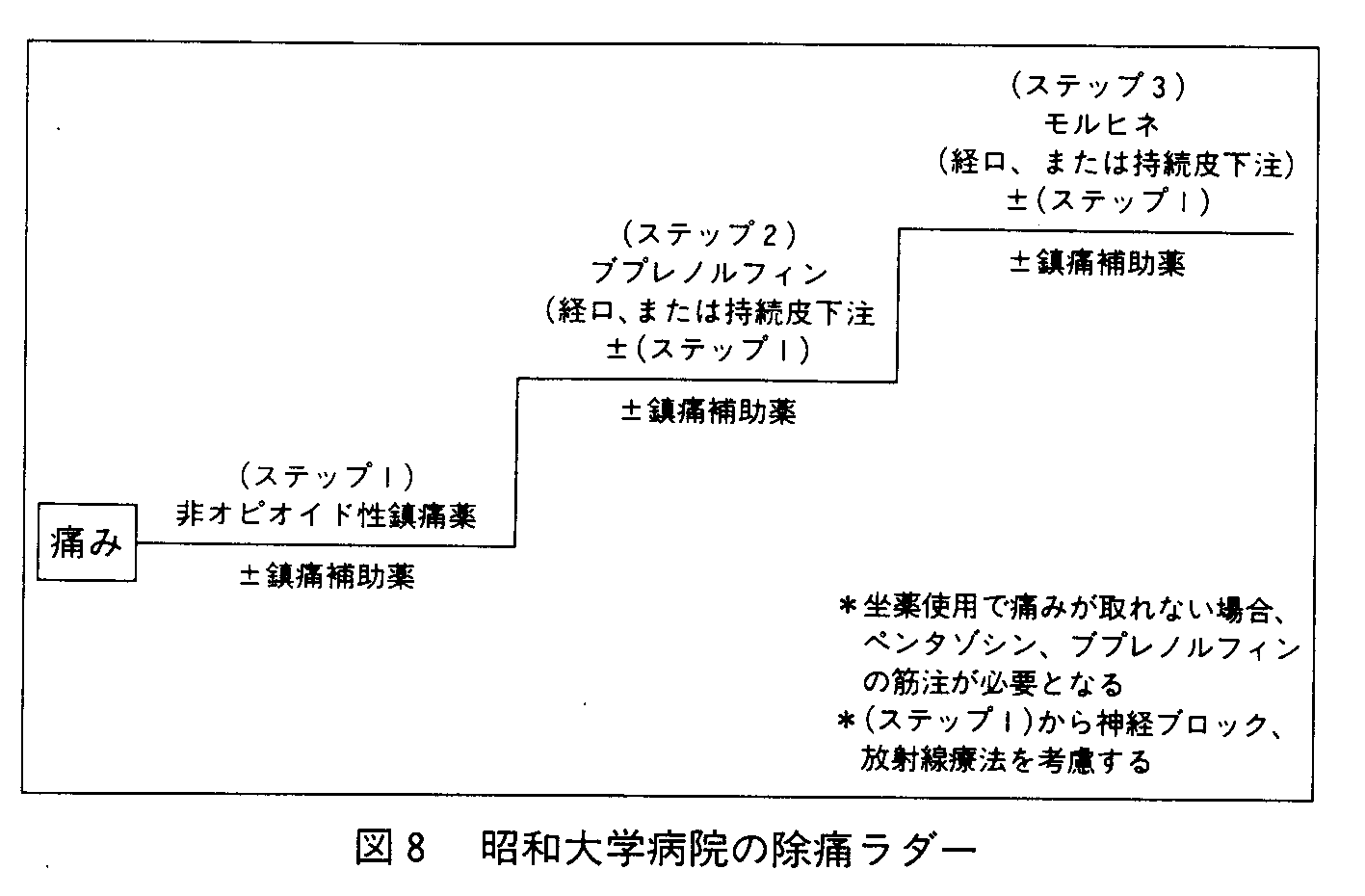
[�X�e�b�v1]��X�e���C�h���������ɍ�(NSAIDS)
�@�X�e�b�v1�́A��I�s�I�C�h�A�܂�A��ʓI�ȉ�M�������ɍ܂ł���B�������͈ݒ��ւ̕���p�����Ȃ��i�v���L�Z��(�i�C�L�T��)���g�p���Ă���B����Ƃ��ẮA�W�N���t�F�i�N�i�g���E��(�{���^����)���A�C���h���^�V��(�C���_�V��)���g�p���Ă���B���ւ̓]�ڂɂ��ɂ݂ɂ́A�v���X�^�O�����f�B�������}����p�̂���X�e�b�v1�ƃ����q�l�p����ƗL���ł���B�܂��A��ᇂɂ��M�ɑ��ẮA�i�v���L�Z�����ƂĂ����ʂ�����B
[�X�e�b�v2]�u�v���m���t�B��
�@�X�e�c�v2�Ƃ��āAWHO�͖���w��̃R�f�C���������߂Ă��邪�A�������́A����h�R�����ɖ�̃u�v���m���t�B��(���y�^��)��p���Ă���B�u�v���m���t�B���̒����͖���Ɏw�肳��Ă��Ȃ����ƂƁA�����q�l�ɔ�ׂĕ֔�̕���p�����Ȃ����Ƃł���B�킪���ɂ́A���˖�ƍ�����B���a��w�ł͉@�����܂Ƃ��āA�㉺�����쐻���g�p���Ă���B
�@�u�v���m���t�B���̕���p�Ƃ��āA�D�����̂悤�ȓf���C�E�߂܂�������A�����p�x�ŏo������̂ŁA�\�h�I�ɓf���C�~�߂̃v���N�����y���W��(�m�o�~��)������ł�����Ă���B
[�X�e�b�v3]�����q�l
�@�X�e�b�v2�̃u�v���m���t�B���ŗL���l�̌��E�ɒB�����ꍇ(�o�����^��4�~���O�����A�����牺�����@�܂��͐㉺���^�ł�2�~���O����)�A�����q�l�w�ڍs����B�܂��A���������̕�������A�x�����x�]�ڂ̌ċz��������銳�҂ł́A�u�v���m���t�B�����ނ��냂���q�l�̂ق������ʂ����҂ł���̂ŁA�X�e�b�v3�̃����q�l����g�p���Ă���B
�@�����q�l�̂��߂ɑ��K���A�܂�n�b�s�[�Ɋ����銴�o�����҂��ă����q�l�����������t�����邪�A�����q�l�ɂ���Ēɂ݂������ꂽ���҂���͖��邭�Ȃ����悤�Ɋ����邾���ŁA�����q�l���̂ɑ��K���̍�p�͂Ȃ��B
(1)�����q�l�̌o�����^
�@�����Ƃ��ẮA�܂��ɂ��Ȃ�O�ɁA�K�����������p���邱�Ƃ��B�����q�l�̌o�����^�@�ɂ́A���̓������̂ŁA���ꂼ��̓�����m���āA�I�����Ă����K�v������B
�@����MS�R���`��(���_�����q�l�������j������ɓ���Ȃ��悤�ȏꍇ�́A���̒Z�����������Ďg�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(A)���_�����q�l���n�t
�@���_�����q�l���n�t�͑�����������B��{�͎l���Ԃ��ƁA�܂�6���A10���A14���A18���A22��(��{��)�̌܉�̕��p�����A����l��(�N�����A���A�[���A�A�Q��)�ł��قƂ�ǂ̊��҂���̓R���g���[���\�ł���B���p�̎�Ԃ��l���A�������͈���l��̕��@��I�����Ă���B�������A�����1000�~���O�����ȏ�̑�ʓ��^�̕��̏ꍇ�͈���܉�̂ق������܂����߂��ł���B���҂���̍D�݂ɂ���āA�������A���C���ȂǂŖ�������B���_�����q�l���p��ɁA�D���Ȉ��ݕ�������ł��������낤�B
�@���҂���ւ̓��^�ʂ͂����܂Œɂ݂ɍ������ʂł���A�ȑO�Ɍ��߂��Ă������60�~���O�����Ƃ����ɗʂɂ������K�v�͂Ȃ��B�������́A�����5000�~���O�����̃����q�l�p���Ȃ���A�ӎ��������ɊO���ɒʉ@�ł������҂�����o�����Ă���B�������A�ɂ݂̌����ɂ���ẮA�����q�l�̌����ɂ��������u�ɂ�����̂ŁA���̑�͌�ŏq�ׂ����B
�ɂ��Ƃ��ɂ͈�܂��͂��̔��ʂ�Վ��ŕ��p����B���ʂ�����Ă��鎞�Ԃ́A��\�ܕ��Ȃ̂ŁA�O�\��������Ύ��̗Վ����g�p�ł���B�܂��A����̉����߂�Ƃ��̎w���ɔ����Ă��܂��̂ŁA�������ł��g�p���\�ł��邱�Ƃ��w�����Ă���B�����Ƃ��A����ɕp��Ɏg�p����悤�ȏꍇ�́A�g�p���̃����q�l���̂̈���ʂ�����Ȃ����A�����q�l�̌����ɂ����ɂ݂̏ꍇ���l������̂ŁA���҂���̂悤�����݂Ȃ��烂���q�l�̑��ʂ��A��܂̕ύX�̕K�v���������Ă���B
(B)���_�����q�l������(MS�R���`��10�A30�A60�~���O������)
�@���_�����q�l�������́A�����Ǔ��ŏ������n������A8�`12���ԂƁA�����ԍ�p����������(�}9)���A�������͂Ȃ��B���ݍӂ��ėp����ƒ����Ԃ̎������ʂ͂Ȃ��Ȃ�B���܂̐F�ɂ���ėe�ʂ��������A10�~���O�����͉����F�A30�~���O�����͎��F�A60�~���O�����̓I�����W�F�ł���B�ɗʂ͂Ȃ����A���҂���̕��p�̎�Ԃ��ɂ��l����ƁA�����10�������E���B�l���͂��邪�A�����600�~���O�����ȏ�̊��҂���ɂ͉��_�����q�l���n�t�̂ق����������Ă���B
�@MS�R���`���͔��Ɏg���₷�����A���̓_�Œ��ӂ��K�v���B
�@�@���p���J�n���Ă���\���Ɍ��ʂ��o��܂łɓ�`�O���K�v�ł���(�}10)�B�������͂܂��A���_�����q�l���n�t���u�ɂ╛��p���R���g���[�����Ă���AMS�R���`���w�ύX����悤�ɂ��Ă���B���̍ۂɂ́A���_�����q�l�̍ŏI���^��MS�R���`���̍ŏ��̓��^���ɂ���B����́AMS�R���`���̌����Z�x���㏸����܂łɎ��Ԃ������邽�߂ł���B
�@�A�ɂ��Ƃ��ɕ��p���Ă��A���ʂ��o��̂�1�`2���ԕK�v�ł���B�Վ��͉��_�����q�l���n�t�ɂ��邩�A���p�S�̂����_�����q�l���n�t�ɕς���B�������AMS�R���`���͊��ݍӂ��ƌ��ʂ͑����Ȃ�B�ݑ�Ȃǂً̋}���ɂ́A�Ԃ��Ďg���Ƒ��������ڂ������B�����ꂢ�̂ŁA�I�u���[�g�ɕ��ŕ��p����Ƃ悢�B�܂��A�}�Ɍ�������߂Ȃ��Ȃ����Ƃ��͍���Ƃ��Ă��g�p�ł���B
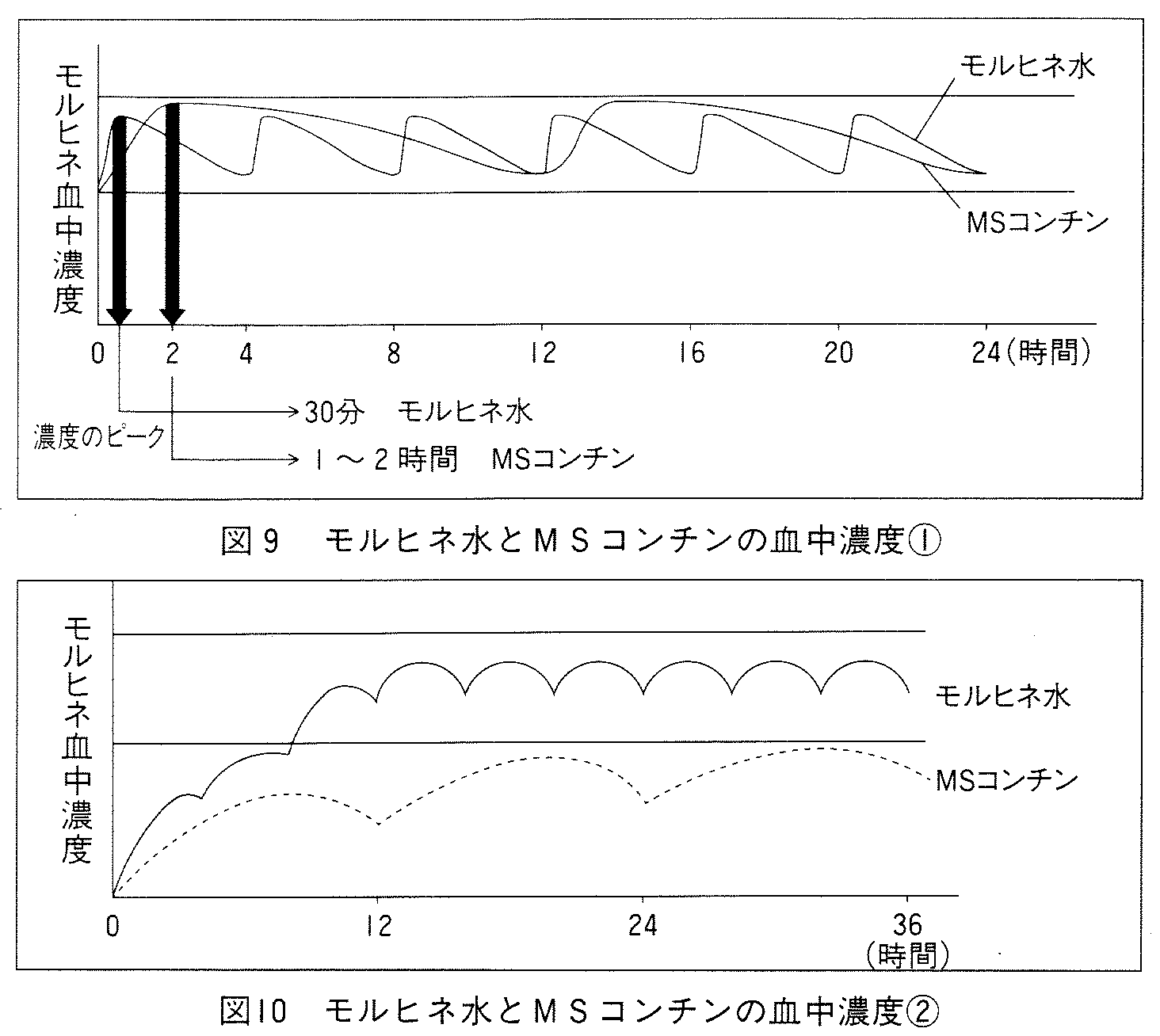 (2)�����q�l����
(2)�����q�l����(�A���y�b�N����10�A20�~���O����)
�@���҂���ւ̌o�����^���ł��Ȃ��Ȃ�A�����牺����������p�ł��Ȃ��ꍇ�ɕ֗��ł���B����O��̓��^�ł悢�B�o���ɔ�ׂāA�̑��ł̑�ӂ����ɒ��ڑ̏z�ɓ���̂ŁA�����Z�x���オ��₷���A���ʂ������B�o�����獿��ɕύX����Ƃ��́A�����Z�x���}���ɏ㏸����ꍇ������A���ӂ��K�v�ł���B
�@���o��z���^�i�\�t�܁j�������u�Ɏ��Í܁@�f�����e�b�v�p�b�`�F�畆�ɓ\��^�C�v�Ŏg�p���e�ՂȂ��߁A�嗬�ɂȂ����܂��B�i�Ǘ��҉��M�j
(3)�����牺�����@�A�����Ò��@
�@�o���ł̓��^���ł��Ȃ��ꍇ�A�܂��A�o�����\�ȏꍇ�ł��}���Ȓɂ݂��������Ă�����A�ɂ݂̃R���g���[�������ɂ����ꍇ�Ɏg�p����B�o�����\�ŁA�u�ɂ╛��p�̃R���g���[�����ł���A�������͌o�����^�ɖ߂��悤�ɂ��Ă���B�o���ł̓��^���ł��Ȃ��ꍇ�Ƃ́A�C���E�X(����)���ӂ��߂Ċ��҂ɓf���C��q�f������ꍇ�A����A�ċz����A��p�⌟�����Ȃǂł���B�Ƃ��ɓf���C�́A�����牺�����@�ɕύX���Čy������ꍇ������B�����牺�����@�Ǝ����Ò��@�͌��ʁA����p�Ƃ��ɓ����ł���B�������A�����牺�����@�ł͑S�g�̔牺���b������Ƃ���Ȃ�ǂ��ł����܂�Ȃ��B�ƂĂ��ׂ��j�Ŏh���̂ŁA�h���Ƃ����A�܂��j�������Ɣ牺�Ɏh�����܂܂ł��ɂ��͂Ȃ��B�����̊댯�͂Ȃ����A�Ö��̂悤�ɘR���S�z���Ȃ��B�ݑ�ł́A���҂���A���Ƒ��Ɏh�����蔲�����肵�Ă��������ꍇ�����邭�炢�ł���B�����牺�����@�͈��20�~�����b�g�������E�ł���A����ȏ�̑�ʓ��^�ɂȂ�ꍇ�͒��������ɂ��邩�A�����̐Ò��ɂ���B���łɁA���S�Ö��h�{�Ȃǂ̐Ö��̌o�H������ꍇ�́A�����Ò��@��p���Ă���B
����F����̃P�[�X�ꃂ���q�l��ʓ��^��
�@F����͎O�\�܍̏����������B�c�t���̑��q�Ə��w��N���̖����ƂɎc���A��딯���������v���œ��@���Ă����B��ᇂƂ������t�͖{�l�͒m���Ă������̂́A�����s�\�ł��鎖���͒m��Ȃ������B�咰�����p��̍Ĕ��ŁA���Ղ̂Ȃ�����ᇂłЂƂ����܂�ɂȂ��Ă����B�]���͒������̂́A�t�����瑾�����ɂ����Ă̒ɂ݂͌���ł������B���ː��Ö@��_�o�u���b�N�Ö@���{�s���ꂽ���A���ǃ����q�l�̑��ʂ���������ʂ�����A������̈��ݖ�ň��5000�~���O�������K�v�������B���N�O�܂ň��60�~���O���������x���Ƃ���Ă������Ƃ���l����ƃ����q�l�̏펯���ʂł���B��e�ƍȂ̖����͏\���ɂ͂ł��Ȃ��������A���̑�ʂ̃����q�l�����݂Ȃ���Ƃʼn߂������Ƃ͂ł����B
�@�����āAF����͌�������ނ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă���A�����I�ȐÖ����˂ň��12000�~���O�������K�v�ɂȂ����B�������A���̑�ʒ��˂ł��ӎ��͂͂����肵�Ă��āA����l�ƃI�Z���Q�[����g�����v���y���ނ��Ƃ��ł����B����l���{�C�ł��̂ŁA�u�����͕����Ă����悢�̂Ɂv�Ƌ�s�����ڂ��قǂł������B
 �y3�z����p����������
�y3�z����p����������
�@�����q�l�̎g�p�ɂƂ��Ȃ��āA�������̕���p������Ă���ꍇ������B�Ǐ�̋����́A���̂Ƃ��̊��҂���̕a���a�C�̐i�s�̓x�����ɂ���Ă��������A�l���̑傫�Ȃ��̂ł���B������ɂ��Ă��A�����q�l�g�p�̐��ۂ́A���̕���p�̃R���g���[���ɂ������Ă���A�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
�@�����ł́A�����q�l�̕���p��̖�͂�����x�m������Ă��Ă���B�����ł́A��������Ă��镛��p�ƁA���̑Ή��ɂ��ďq�ׂĂ݂����B
����M����̃P�[�X�|�����q�l�̕���p
�@M����́A58�̒j���������B�A������Ő��т��������Ă���A��b�͕M�k�ł������B�������A���Ƀ{�[���y���ŗ����悤�ɕ����������A�˂Ă����B�u�{�N�͔����Ŏd�������Ă��܂����B��Ђ��|�Y�����Ƃ��̘J���g���̈ψ����ł����B�Ō�܂ʼn�ЂɎc���Ďc�����������܂����v�B���̂Ƃ��̐M���W���A��\�N�ȏ���O�̂��ƂȂ̂ɁA�����╔������������K�˂Ă����B�u�{�N�͎��ʂ̂͋����Ȃ��B�������A�����炵���Ȃ��Ȃ�̂�����Ȃ̂ł��B������A������g���Ė����Ȃ�����A���������Ȃ��Ă��܂��̂͂���ł��v�B���́A�����q�l���K���I�Ɏ��Ԃ����߂ĕ��p����A���������Ȃ����肵�Ȃ����ƁB���C���͂��߂͏o�邪�A�������Ɋ���Ė����Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�ƁB�����āA�ǂ����Ă����C�������āA�{��ǂ�A���L��������A�d���������肷��̂Ɏx�Ⴊ����ꍇ�́A���C�~�߂��p�ӂ��Ă��邱�Ƃ�`�����B
�@��̒��߂�����悤�Ȓɂ݂��o�Ă����̂́A���ꂩ�炷���ł������B�ȑO��蕛��p�̘b�͂��Ă������̂ŁA�����q�l�̐��n�t�̕��p���n�߂�ꂽ�B�����q�l���g�͋ꂢ�̂ŁA�Â��V���b�v��C���A�������G�b�Z���X�Ŗ��������Ă���BM����́A�V���b�v�ƃ��C����I�B���̖�̂��Ƃ�ނ́u�ɂ݂̃J�N�e���v�ƌĂB
�܂��A�قƂ�ǂ��ׂĂ̐l�ɏo�Ă��镛��p�ɂ��ĕt���������B����́A�֔�ł���B�����q�l�����ǂ̓������������Ă��܂��̂ł���B�������A��������܂����܂��������Ă����A���ƂȂ镛��p�ł͂Ȃ��B�����Ƃ��A��Î҂̂Ȃ��ɂ��֔�Ƃ�������p�͒m���Ă��ĉ��܂͎n�߂Ă��Ă��A���܂̗ʂ߂����A�֔�����������Ă��܂��ꍇ������B�֔�̒��x�ɍ��킹�āA���܂̗ʂ��v���ɑ�������K�v������BM����ɂ͏o�Ȃ��������A�l�ɂ���Ă͓f���C���o��ꍇ������B������f���C�~�߂őΏ��\�ł��邪�A��x�f���Ă��܂��Ɛ��_�I�ɂ�����p�����邱�Ƃ͓���ƍl����B��t�ɂ���ẮA�f���C�~�߂�\�h�I�ɏ�������ꍇ������B�܂��A�t����̑��̋@�\���ቺ���Ă��Ă��A����p�͏o�Ă��₷���B
�@���ǁAM����͉��܂Ɩ��C�~�߂����ނ��ƂɂȂ����B
(1)�֔�
�@���ׂĂ̊��҂���ɂ������Ă���Ǐ�Ȃ̂ŁA�\�h�I�ɑΏ�����K�v������B�ږ�̂悤�ȓ��ꕨ�ɓ���������̃s�R�X���t�@�[�g�i�g���E��(���L�\�x����)�����p���₷���֗��ł���B�ւ��d���ꍇ�́A�_���}�O�l�V�E��(�J�})�p����B�������R�Ɗɉ��܂ł悤�����݂�̂łȂ��A�����q�l�̕��p�J�n�����`�O���̂����ɕւ��o��悤�ɁA�ɉ��܂��}���ɑ��ʂ��邱�Ƃ��d�v���B��̗ʂ͒ʏ�֔̕�����ʂɂȂ邱�Ƃ������B��`����Ɉ��ւ��o��悤�ɃR���g���[�����A�ꍇ�ɂ���Ă͍���⟯�������p����B�����q�l���p���́A�p�����ĉ��܂��g�p����K�v������B
(2)�f���C�E�q�f
�@��30�p�[�Z���g�̊��҂���ɂ݂���Ǐ�ł���B���݂͂��߂Ă����ɏo�Ă��邪�A�܁`�\���ŏ�������ꍇ�������̂ŁA�O�����Ċ��҂���ɐ�������悤�ɂ��Ă���B�����f���C�����Ȃ炪�܂�ł��邩������Ȃ����A���ۂɓf���Ă��܂��Ɗ��҂���̓����q�l�̕��p�����߂���Ă��܂��������B�������́A��q����悤�ɕ���p���\�z�ł��銳�҂���ɂ́A�\�h�I�ɐ��f�܂����������胂���q�l�����ʂ���n�߂�悤�ɂ��Ă���B
�@�����q�l�̓f���C�ɂ́A�v���N�����y���W��(�m�o�~��)���悢�B�܂��A�f���C����肫��Ȃ��Ƃ��̓n���y���h�[��(�Z���l�[�X)�≖�_�N�����v���}�W��(�R���g�~��)�̂ق����f���C�ւ̍�p�������̂ŗp���邱�Ƃ����邪�A���Í�p�����邽�߁A���҂���̏��]�ɍ��킹�đI������悤�ɂ��Ă���B
�@�p�x�͏��Ȃ����A�f���C�~�߂̖�ɂ͂ǂ�����̊O�H�Ǐ�Ƃ�������p������A�Ƃ��Ɍ����Ƃ��ꂪ���Ȃ̂��A�J�V�W�A���B����́A�����Ƃ��Ă����Ȃ������ŕ����̂Ȃ������낤�낵����A�x�b�h�̏�ł��������������藎�������Ȃ��Ȃ�B�悭���_�I�ɃC���C�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƌ������Ă��܂��B�A�J�V�W�A�̎��Âɂ͓f���C�~�߂̌��ʂ⒆�~�A�܂����_�r�y���f��(�A�L�l�g��)�𓊗^����B
(3)���C
�@�O�`�܊��̊��҂ɂ݂���Ǐ�ł���B�ʏ�͎O�`�ܓ��őϐ����ł��A���C�͏�������ꍇ�������B���̊����ł́A���{�ł͖��C���������҂������悤���B����͍��m�Ƃ̊W������Ǝv���B�����q�l�̖��C�͂ЂƂ�ł���Ƃ������Q�����Ă��܂����A�N�������Ęb�����������ɂ͂͂����蓚�����邱�ƁA�ړI�������čs������Ίo��������Ԃł����邱�ƁA�Ȃǂ����҂���ɓ`���Ă����悤�ɂ��Ă���B
�@���C���s���ȂƂ��́A�o���^�R���܂̃��`���t�F�j�f�[�g(���^����)�������߂Ă���B�[���ȍ~�ɕ��p����Ɣ��ɕs���ƂȂ�̂ŁA�\�l���ȍ~�̕��p�͔�����B����p�Ƃ��Ă͕p���A�ő����Ȃǂ�����B
(4)����
�@�̑���t���̋@�\��Q�⌌�t�̓d�����ُ�Ȃǂ̗v���ɂ���ẮA�܂�ɍ������������Ă���B�ɂ݂��Ȃ��ꍇ�̓����q�l�����ʂ���B�����⌶�o������A�n���y���h�[��(�Z���l�[�X)���A�Q�O�ɕ��p����Ƃ悢�B�Ƃ��ɖ�Ԃ���ςœ_�H���Ă��܂�����A�吺�������Ă��܂��悤�ȏꍇ�́A���Í܂Ő������m�ۂ���K�v������B
�@�������́A���҂���Ɂu�ŋ߁A�Y����ۂ�������A�b���Ƃ�ł��܂�����A�܂����܂̍���Ȃ����Ƃ͂���܂��v�Ƃ����˂Ă݂āA���{�l�������ɂ��ĔY��ł�����A�C���ςɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă�����A�����܂Ŗ�̍�p�ɂ����̂ŁA�C���ςɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��A������Ɠ`����悤�ɂ��Ă���B
�@�܂��A�Ƒ����Ή��ɍ����Ă�����A�������Șb�̓��e��ӂ߂���A���̂��тɒ�������̂ł͂Ȃ��A���̂܂܂Ɏ���Ă����悤���b������B���҂���{�l��Ƒ��ɂƂ��āA�\���ȗ�����������炾�B
(5)�ċz�}��
�@�ʏ�̊��҂���Ƀ����q�l���g�p����ꍇ���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�܂�ł��邪�t�@�\��Q���}���ɏo�������ꍇ��A�x����A�x�]�ڂ̗\���T�Ԃ��炢�̏d�ǎ��̎g�p�ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B�����q�l�̉e���Ƃ��Čċz���̌��������邪�A���̓�_�ɋC�����āA�o�߂��݂邱�Ƃ��ł���B
�@�@���̌ċz���[���A���C�ʂ���ӂ���Ă��邩�B
�@�A���O���ĂׂΗe�ՂɊo�����A�͂����肵����b���ł��邩�B
�@�����q�l�ɂ͂��̂悤�Ɍċz�}����p�����邪�A���ɔx�]�ڂȂǂ̌ċz����̃R���g���[���ɗL���ł�����B
(6)���p(
�O�fQ&A�Q��)
(7)�~�I�N���[�k�X
�@�葫�̃s�N�b�Ƃ���^���̂��ƂŁA�����q�l�̑�ʓ��^�ł����₷���Ƃ���Ă��邪�A���ʂł��o�����銳�҂���͂���B�������́A�N���i�[�p��(���{�g���[��)��O�Ɏg���Ă��邪�A�قƂ�ǂ̊��҂̃~�I�N���[�k�X����͌y�����Ă���B
(8�j�A��
�@�p�x�͏��Ȃ����A���҂ɂƂ��Ă͂炢�ǏB��܂̕ύX���K�v�ȏꍇ������B
(9)�����y��(�����)
�@�����ɑ����݂��邪�A�R�q�X�^�~���܂őΉ��ł���B
(10)��������(����)
�@�����p�x�͖�܊��Ƃ���Ă���B�Ǐ��I�ɑΏǗÖ@���s���B������X�̂�����A�������A�O���Z�����A�l�H���t�̎g�p�Ȃǂł���B
(11)�����q�l�s�Ϗ�
�@�����̊��҂���ɂ݂��錻�ۂŁA�����q�l�𓊗^����ƈ݂̂Ȃ��̂��̂�����邱�ƂŚq�f�������B���������̊��҂ł͉ߓx�̒��Â��A�܂�ɐ��_�Ǐ�A�q�X�^�~�����o�Ɋ�Â��Ǐ�(����݁A�C�ǎx�������)�Ȃǂ������邽�߁A��܂̕ύX���K�v�ł���B
 �y4�z�����q�l�̕���p���ߏ�ɏo�����銳�҂���ւ̑Ή�
�y4�z�����q�l�̕���p���ߏ�ɏo�����銳�҂���ւ̑Ή�
����܂ŏq�ׂĂ��������q�l�̕���p���A�ƂĂ���������銳�҂�����B�����ł́A�ߏ�ȕ���p�̌����ƁA����ւ̑Ή��ɂ��ĊȒP�ɂӂ�Ă݂����B
(1)�t�@�\��Q
�@�����q�l���^���A�܂��J�n���ɂ����Ƃ����ӂ��ׂ��_���t�@�\��Q�ł���B�����q�l�͐t���Ŕr������邽�߁A�����ɏ�Q������Ƒ̓��̃����q�l�̔Z�x���オ���Ă��܂��B�Ǐ�Ƃ��ẮA�f���C�A���C�A�����Ȃǂ����������B
�@�����A�t�@�\��Q�̌�������ᇂ̔A�Lj����ɂ�鐅�t�ǂł���A�t�(�t���ɃJ�e�[�e����}�����ĔA�H��ύX���邱��)�����҂����Ƒ��ɁA�����Z�����\���������������ŁA���ӂ����ΑI�����Ă��悢�Ǝv���B
(2)�̋@�\��Q
�@�̑������̓]�ڂȂǂɂ��̋@�\��Q���A�����q�l�̕���p���������Ă��܂��B����́A�̑��ł̃����q�l�̑�ӏ�Q�ɂ��B�Ǐ�Ƃ��ẮA�f���C�A���C�A�����A����݂�����B�܂��A���A�����j�A���ǂ̏�ԂŊ̐������Ɉڍs������Ƃ��́A�����������ɏo������B�����q�l�̌��ʂ��n���y���h�[���̕��p�Ȃǂ��K�v�ƂȂ�B
(3)������
�@�����q�l�̕���p���o�₷���a�ԂƂ��ẮA��������₷�����d�v�ł���B�x����A�H�����ǁA���傭ጊ����Ȃǂ���A���S�Ö��h�{�̃J�e�[�e����d���O�J�e�[�e���Ȃǂ̈㌴�I�Ȋ����܂ŁA��Ԃ̈������҂���̊����̋@��͑����B����l�ł����M����{�[�b�Ƃ��Ă��܂����A�����q�l�g�p���̊��҂͖��C�⍬�����o�₷���B�Ή��͊����ǂւ̎��Â���̂ƂȂ�B
(4)���J���V�E������
�@�x����₻�̑��̂���̍��]�ڂ̊��҂���ɑ����݂���Ǐ�ł���B���ÂƂ��ẮA�_�H�Ȃǂ̐����⋋�A�X�e���C�h�܂̓��^�A�J���V�g�j���̒��˂Ȃǂ�����B�ŋߔ������ꂽ�p�~�h�����_��i�g���E��(�A���f�B�A)�Ƃ����Ö����˗p�̍��z���}���܂́A�p��̋ؓ����˂��K�v�Ȃ��A���҂����QOL(�N�H���e�B�E�I�u�E���C�t=�����̎��A�����̎�)�����コ����ƌ����悤�B
(5)�d�����ُ�
�@�i�g���E����N���[���Ȃǂ̓d�����ُ̈�ɂ���Ă��A�����▰�C���������Ă���B�Ƃ��ɁA��i�g���E�����ǂɂ͒��ӂ�����B���̂ق��A���w�Ö@�̎{�s����{�s��A���ː��Ö@�̎{�s����{�s��ɂ�����p���o�₷���B�܂��A�]��ᇂ�]�ւ̓]�ڂɂ���ē��W�������i�Ǐ�̂��ߓ��ɂ�f���C������Ƃ��Ƀ����q�l���g�p����A���̏Ǐ���������邾�낤�B�C���E�X(����)�̏�Ԃł̃����q�l�̎g�p���Y�ނƂ���ł���B��ɏq�ׂ������q�l�s�Ϗǂ���q�l�̑�Ӎy�f���������Ă�����ɂ��A��܂̕ύX�ȂǏ\���ȑΉ����K�v���B
�@
�ߏ�ȕ���p�ւ̑Ή�
�@�������́A�܂��A�G�v�^�]�V��(�Z�_�y�C��)�A�t�F���^�j�[��(�t�F���^�l�X�g)��p���Ă���B�G�v�^�]�V���̓y���^�]�V���Ɠ����̒��Ɍ��ʂ����B�����q�l�ɔ�ׂĖ��C�A�f���C�A�����A�֔�Ȃǂ̕���p�����������Ȃ��B�����������ɂ́A���˖��Ȃ��B�܂��A�����q�l�̏��ʓ��^�ŕ���p�̑ϐ����l��������ɁA���ɍ�p�̂���ʂ܂ő��ʂ���A�Ƃ������@���Ƃ��Ă���B
�@���ꂩ��A�d���O�u���b�N�Ö@�╠�o�_�o�p�u���b�N�A���������t�F�m�[���u���b�N�Ȃǂ̐_�o�u���b�N�Ö@���A�����Ȃ̋��͂čs���A���ʂ������Ă���B
 �y5�z�����q�l�Ŏ�肫��Ȃ��ɂ݂ւ̑Ή�
�y5�z�����q�l�Ŏ�肫��Ȃ��ɂ݂ւ̑Ή�
�@���݁A�����q�l�ɂ���āA����̊��҂���̖�90�p�[�Z���g�̕��̒ɂ݂��A���S�Ɏ�菜�����Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B�c���10�p�[�Z���g�̕��ɂ��ẮA�ɂ݂��y���ł��Ă����S�ȏ��ɂ͂ł��Ȃ��B�������A�����̊��҂���ɑ��Ă��A���ɕ⏕����X�̖�܂̑g�ݍ��킹�A�_�o�u���b�N�Ö@�A���ː��Ö@�A���w�Ö@�A���M�Ö@�ȂǁA�����̎��Ö@�����̕��̏Ǐ�ɍ��킹�đI�����邱�ƂŁA�\���ɑΉ��ł���̂ł���B���܂⎄�����́A����̒ɂ݂�a�炰�鑽���̎�i����ɂ��Ă���̂��B
�@
�j���[���p�X�B�b�N�E�y�C��
�@�����q�l�������ɂ����ɂ݂̑�\�̓j���[���p�X�B�b�N�E�y�C���ł���B�j���[���p�X�B�b�N�E�y�C���Ƃ����̂́A�����_�o���邢�͒����_�o���������菝�Q���邱�Ƃɂ���āA�����炳���ɂ݂ł���B�����_�o���`���ꂽ�ꍇ�́A�������ꂽ�_�o���x�z����̈�̊��o���ቺ������A���тꊴ���݂���ɂ�������炸�A�������ɂ�A�A���f�B�j�A(Allodynia�F�y���G�ꂽ��A�y���@�����肷�邱�Ƃɂ���Ēɂ݂��������ԁj���o�������肷��B�ɂ݂̐����Ƃ��ẮA�ܔM�ɁA�Y�L�Y�L�����s�����̂���ɂ݁A�������̎h���悤�Ȓɂ݁A���邢�͕��U����ɂ݂̂��Ƃ�����B
�@����́A�����_�o(�r�_�o�p�A��ڐ_�o�Ȃǁj��Ґ��_�o�ւ̐Z���∳���̌��ʁA���̒ɂ݂��������Ă��₷���B��\�I���u�ɂƂ��āAPancoast�^�x����̘r�_�o�p�Z���Ⓖ������p��Ĕ��̐卜�_�o�p�Z��������(�����u�ɈȊO�ł́A�����ɁA�я��v�]��_�o�ɁA�Ґ��������u�ɁA�����ɁA�r�_�o�p���������nj�Q�Ȃǂ�����)�B�������A�j���[���p�X�B�b�N�E�y�C���ł����Ă��A���ɕ⏕���_�o�u���b�N�Ö@�A���ː��Ö@�Ȃǂ�g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA�ɂ݂�a�炰�Ă������Ƃ͉\�Ȃ̂ł���B
�@
�Z�f�[�V�����̌���
�@�ܕ��炫�̍��̎}���a���ɂ͒u���Ă������B�u�������A���N�͉Ԍ��ɍs���Ȃ������ˁB�ł��A���͂����ɂ����v�B������ʏf��̖ڂ���A���F���܂��X�[�Ɨ��ꂽ�B�f��́A�̑�����̖����������B���t�őS�g����������A�̐������ƒ��Í܂ňӎ����ቺ���Ă����B�f��́A��̎o�ł��邪�A���ۂɂ͎��̐Ԃ�V�̂��납�珬�w���܂ł̈�Ă̐e�ł���B
�@���̊O�ɂ́A���C�傪�L�����Ă����B�u���̕l�Ɏq�ǂ��̂���A�����A��Ă��Ă�������ˁv�B�܊K�̌�����́A�ŋ߂ł��������h�[���ƃz�e�������n�����B�܂�Ń��]�[�g�z�e���̈ꎺ�̂悤�ł���B�����s���̂��̕a�@�ŏf��́A�I�������}���Ă����B�����̓z�X�s�X�ł͂Ȃ��������A�ƂĂ������ȏ�Ԃɏf��͕ۂ���Ă����B
�@�ɘa�P�A����Ƃ����t�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�ЂƂ�̉Ƒ��Ƃ��āA�������̂��Ƃ��Ō�w����Ƙb���������B�f��́A�̕s�S�̏�ԂŁu�g�̒u���ǂ���̂Ȃ���Ɂv��i���Ă����B���̋�ɂ�a�炰��ɂ̓����q�l����Í܂ŏ����ӎ��𗎂Ƃ��A��������K�v���������B���Í܂ƃ����q�l�̍���ŗǂ��R���g���[�������Ă����B�������A���̓��͌ċz�̏�Ԃ������A�}�ς�\�z�����Ō�w����́A�����q�l�̓��^�������킹���B�f��͈ӎ����߂��Ă������A��ɂ�i�����B����̊Ō�w����ɓ`�����B�u�Ƒ��Ƃ��ẮA�����Ō�w���������ꂽ����ɁA�ċz���~�܂��Ă����܂��܂���B���܂̋�ɂ��y�����Ă��������v�B1995�N3��12���A���j���B�f���81��ڂ̒a�����ł������B�Ō�w����ƉƑ��ƂŁA�n�b�s�[�o�[�X�f�C���̂��A�a�������j�����B���Ȃ����Ō�w������܂𗬂��Ă��ꂽ�B�f��̌����猾�t�͏o�Ȃ��������A�͓̂͂��Ă����Ǝv���B
�@�Z�f�[�V�����B���҂���ɒ��Ì��ʂ̂����𓊗^���A�ӎ��������鏈�u�������B������t�ɂȂ肽�Ă̂���́A�]����`�����炢�ɂȂ�ƁA���҂���̈ӎv�Ƃ͊W�Ȃ����Í܂�������ˑR�_�H�̂Ȃ��ɓ����Ă����B����́A�I�����ɂ����銳�҂���̐��_�I�ȋ�ɂ�a�炰��Ƃ������ڂ��������A���ۂ͊��҂�������ɌJ��o����鎿��Ɉ�t�̗ǐS���ς����Ȃ������Ƃ����̂�����ł������C������B�����̊��҂��瓦���Ȃ��ŁA�^���ʂ�����������ɘa�P�A�^�����n�܂��Ă���́A�Z�f�[�V�����͗ǂ��Ȃ��s�ׂƂ��āA�ɘa�P�A�W�҂���h������Ă����B�������A�ŋ߂ɂȂ�A�Z�f�[�V��������������Ă����B
�@����́A�I�����ɂ�����u�g�̒u���ǂ���̂Ȃ��v��x����Ȃǂ́u���ꂵ���v�A�����āA�ǂ����Ă���肫��Ȃ��u�ɂ݁v�ɑ��Ăł���B�c���ꂽ���Ԃ̒��Z�A���҂���{�l��Ƒ��̓��ӂȂǁA�K���͐T�d�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���{�̃z�X�s�X�̒��S�Ƃ������闄��L���X�g���a�@��l������O�����a�@�̃z�X�s�X�̈�t�������A�K���ƂȂ銳�҂���ɂ��S�O�����A�Z�f�[�V�������s���ׂ��Ƃ̌������o���Ă���B
�@�������z�X�s�X�a���ł���ȏ�̎�͂Ȃ��Ƃ����ƁA��ʕa�@�ł���ȏ�̎�i�͂Ȃ��Ƃ������x���́A�����Ԃ�����Ǝv���̂ŁA�����������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ��ƁA�\�N�O�ɍs���Ă�����Î҂̓s���̃Z�f�[�V�����ɂȂ��Ă��܂�����ł���B���Ȃ��Ƃ��A���҂������Ȃ邱�Ƃ������Ă���������A���ׂĂ̋�ɂ���������邱�Ƃɂ͂Ȃ邾�낤�B
�@
�@�Ȃ��A��������̒ɂ݂̍����ɂ������Â��邩�Ƃ�������A�ɂ݂̂���Ȃ����A���̂܂܊��҂���̐����̎��A�N�H���e�B�E�I�u�E���C�t(QOL)�ɒ������邩�炾�B�����āA����̒ɂ݂͂܂��������키�K�v�̂Ȃ����̂��ƐM���邩��ł���B�܂��A�����g�ƂĂ��ɂ���ł��邱�Ƃ��A���҂���ւ̋����ɗǂ��e����^���Ă���̂�������Ȃ��B
�@Not doing but being(���������邱�Ƃł͂Ȃ��A���ɂ��邱��)�[�Ō�ɍĂт��̌��t�ɂ��ǂ肽���B��w�͂��ꂩ������B���A�ɂ݂̎��Â����i�����Ă������낤�B�����A�ЂƂ�̈�҂Ƃ��āA�������҂̖T��Ɋ��Y���Ƃ����v�����A�l�Ԃ̐S�����͂ւ̌��������A���킸�ɂ������Ǝv���B
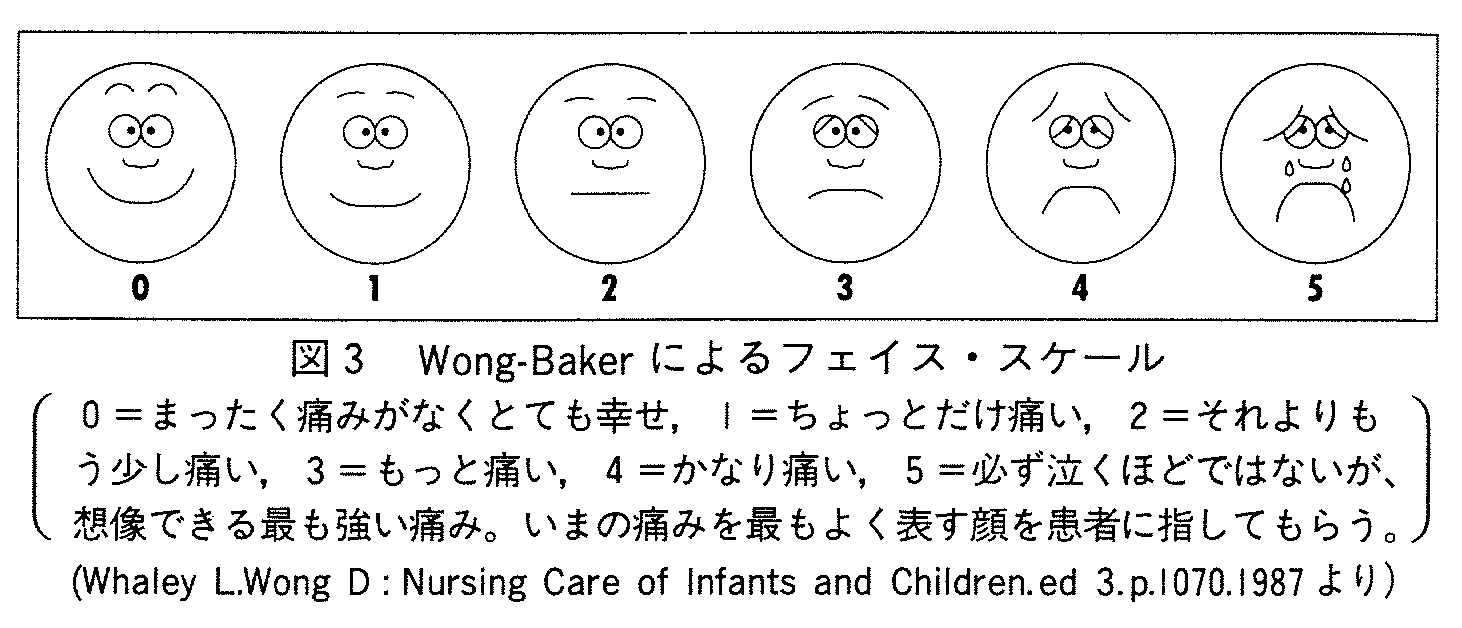
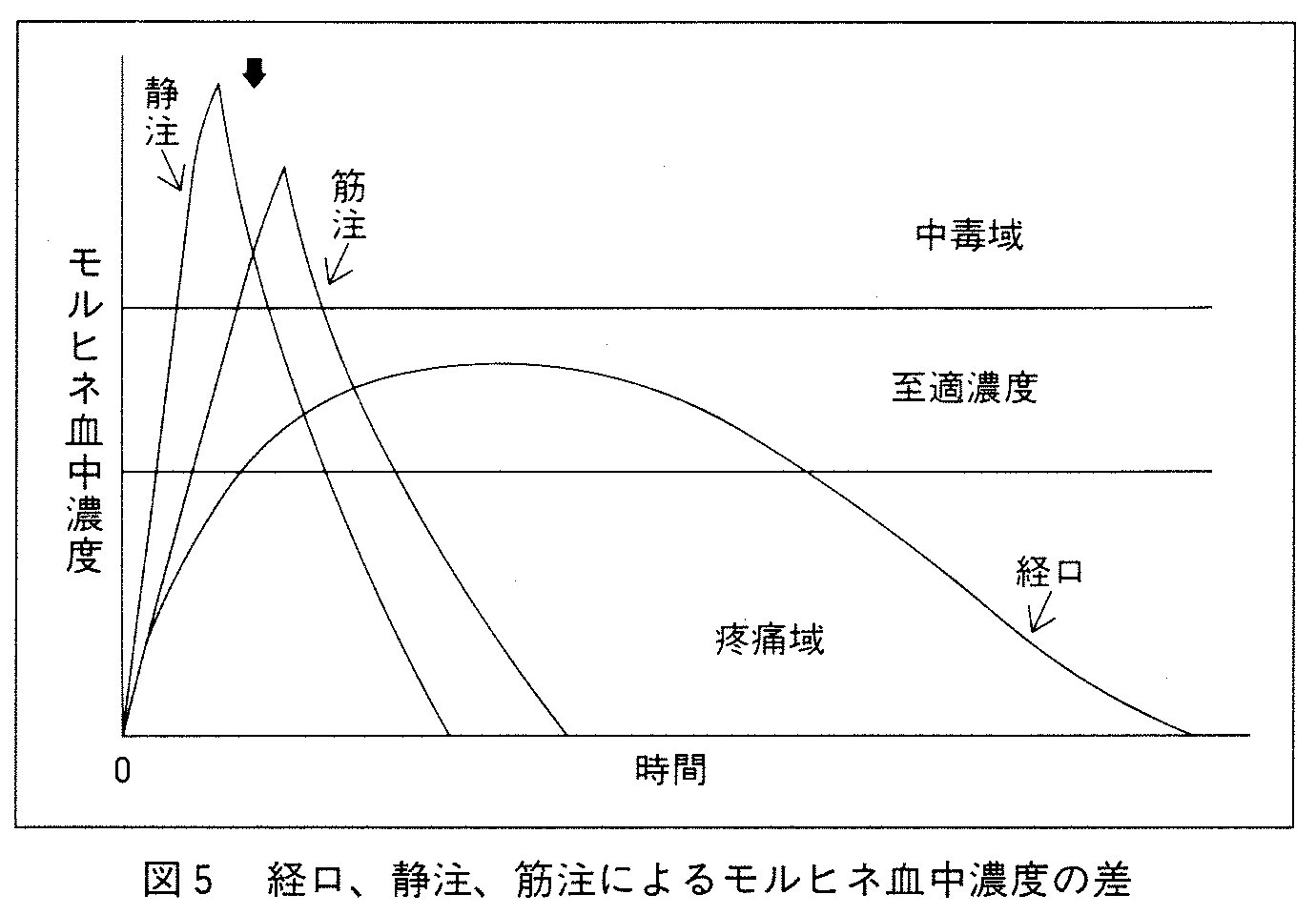 �@WHO�ł͌o�����^�������߂Ă���B�����q�l�̌����Z�x���݂�ƁA�@�u�Ɉ�(����p�͂Ȃ����A�ɂ݂͂���)�A�A���K�Z�x(�ɂ݂��Ƃ�A����p���Ȃ�)�A�B���ň�(�ɂ݂͂Ȃ����A����p���o������)�ɕ�������B���ɑ�ʂɓ��^�����Ö����˂�ؓ����˂ł́A�}5�̖��̂悤�ɁA���K�Z�x��˂������Ē��ň�ɒB���Ă��܂��B���̂��ߋ�������p���o�Ă����̂ł���B�����Č����Z�x�͋}���ɉ�����A�ɂ݂��Ăъ����āA�܂����ˁB����ɂ���č����Ȃǂ̐��_�Ǐ���J��Ԃ��Ă������̂ł���B
�@WHO�ł͌o�����^�������߂Ă���B�����q�l�̌����Z�x���݂�ƁA�@�u�Ɉ�(����p�͂Ȃ����A�ɂ݂͂���)�A�A���K�Z�x(�ɂ݂��Ƃ�A����p���Ȃ�)�A�B���ň�(�ɂ݂͂Ȃ����A����p���o������)�ɕ�������B���ɑ�ʂɓ��^�����Ö����˂�ؓ����˂ł́A�}5�̖��̂悤�ɁA���K�Z�x��˂������Ē��ň�ɒB���Ă��܂��B���̂��ߋ�������p���o�Ă����̂ł���B�����Č����Z�x�͋}���ɉ�����A�ɂ݂��Ăъ����āA�܂����ˁB����ɂ���č����Ȃǂ̐��_�Ǐ���J��Ԃ��Ă������̂ł���B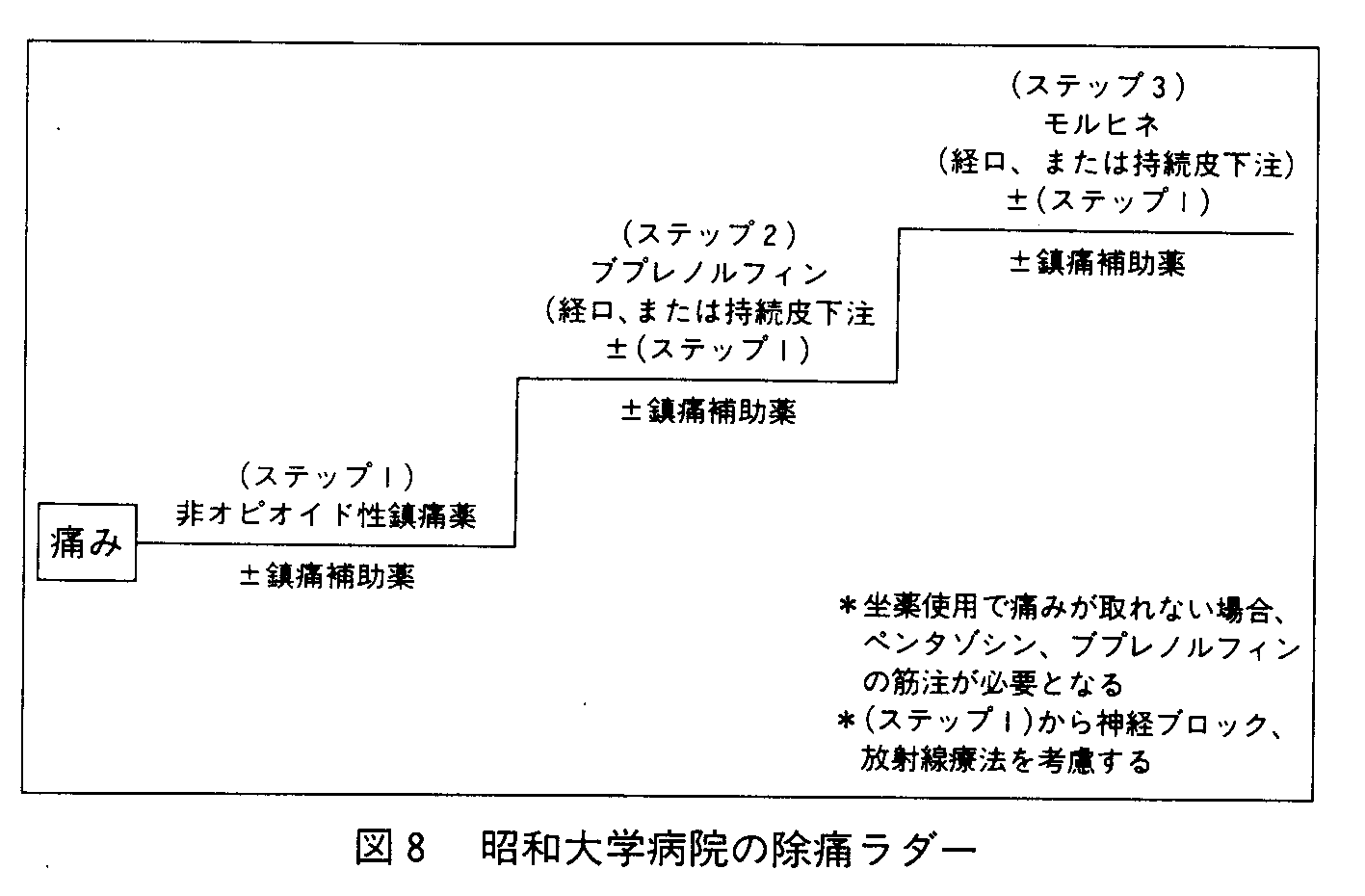 [�X�e�b�v1]��X�e���C�h���������ɍ�(NSAIDS)
[�X�e�b�v1]��X�e���C�h���������ɍ�(NSAIDS)