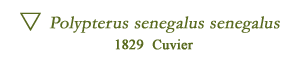

DATA
セネガル川、ガンビア川、ボルタ川、ベヌエー川
白ナイル、アルバート湖(モブツ・セセセコ湖)
トゥルカナ湖、オモ川、チャド湖、ニジェール川
シャリ川など広範囲に分布
側線鱗数 53〜61 周辺鱗数 34〜40 背中線鱗数 15〜21
体長 50cm
販売名 セネガル、セネガルス
セネガルスといえば、各雑誌などで入門種の代名詞になっているが入手も安易で安価に購入でき、
水槽内飼育(60cm水槽など)では大型になりにくく、
成長も穏やかなのが入門種として言われているのだろう。
だが、意外と噛み癖のある個体やブリードによる弊害など購入時気をつけたい。

東南アジアでのブリードが盛んで、数年前からアルビノ個体も固定化されコンスタントに流通し
その他に、プラチナ、ロングフィン、アルビノショートなども入荷している。
アルビノ個体であるが、過去に1例だけワイルドでの入荷が確認されている。
現在流通している東南アジアブリードのアルビノ個体は、ブリードによっての出現個体を固定化したもの。
現在流通している個体は、90%以上が東南アジアのブリード個体であり、
ワイルド個体は年間数便しか来ず、またその数も少ない。
ワイルド個体に関しては、入荷便がコンゴ便などであることからその流域の河川より採取された個体と、
推測されるがはっきりした詳細は不明。
トップを飾っている画像だが、恐らく日本では初めての紹介となるであろう
ナイル川産の現地採取個体である。
特筆すべきは各鰭が大きく、また背鰭が通常透明であるが2/3程薄黒く色が入っている。

歴史として、キュヴィエCuvierによって1829年に記載され独立種とされてきたが、
1941年にポールPollによって基亜種にされた。
体色は、灰褐色が知られるが底砂によって大きく体色が影響変化し、明るい底にすれば体色も明るくなる。
また、赤みを帯びる事もある。
幼魚期には、幼魚班としてバンドのような模様が出るが、成長に伴い消滅する。
各鰭には模様はない。
いろいろな意見もあるだろうが、私的には大磯砂が一番似合うのではないかと思う。

生息場所は、水草やアシなどが茂る比較的浅い場所に生息している。
食性は、雑食ともいえるほどで魚、エビ、水生昆虫や昆虫までも食べるようである。
また、飼育下でも人工飼料、生餌、ハツ、ワームなど殆どの物を食べ、食欲も旺盛。
繁殖に関しては、繁殖例が多く生後1年前後で繁殖可能となり繁殖に挑戦するには良いだろう。
天然下では、雨季に繁殖期を迎えると広く知られているが現地での情報によると、
乾季にも稚魚が多く採れる事が去年現地調査した人間が確認しており、
確認した河川のセネガルスに関しては、雨季、乾季に関係なく繁殖をしていると考えられる。

水槽内飼育では、大型に育てるには大型の水槽が必要と思われ、それでも大型化させるには、
ある程度の年数、餌の管理が重要と思われる。
私的意見だが、ブリード個体に関しては大型化はしないと考える。
現地では、40cmを越える個体が多く捕獲されているようで、
最大長50cmは十分にありうるサイズでそれを越える個体もきっと・・・

現地採取の恐らく日本初公開セネガルス
汚い画像で申し訳ないです。

ナイル川産個体

オモ川産個体

オモ川産個体上記同個体38cm
D's room Graphic collection
撮り溜めていた画像を公開します。
今後も良い画像があれば掲載していく予定です。
また、このサイトを閲覧している方で、自慢の個体を載せて頂ける方がおりましたら
polypterus@pc.117.cx までDM頂ければ幸いです。




|

|