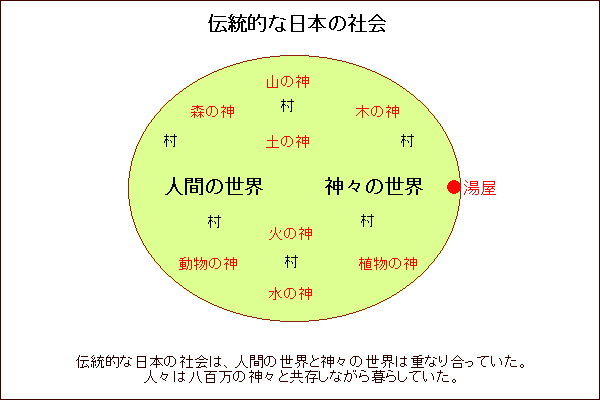
このコーナーでは、「千尋」の世界観をテーマごとに読み解いていきます。
●「千尋」制作のねらいはどのようなものか? 2001/07/07
●「不思議の町」に迷い込んだ理由一つとして何が考えられるだろうか? 2001/07/02
●「不思議の町」は、どのようにして生まれ、発展してきたのだろうか? 2001/07/07
●「千尋」制作のねらいはどのようなものか?
宮崎駿監督によると、「千と千尋の神隠し」は冒険物語と呼ぶべき映画であるという。冒険物語といえば、武器を振り回したり超能力の力比べをしたりするイメージが強いが、「千尋」にはそのようなシーンは登場しない。また、正邪の対決が主題という訳でもないから、誰かが絶対的な善人として描かれることがなければ誰かが絶対的な悪人として描かれることもない。まして、正義の味方が武器や超能力を使って悪者を倒すような物語ではないという。
舞台は、日本に棲んでいる様々な神様がやってくる不思議な町。主人公の千尋は10歳の普通の女の子で、特別な能力がある訳もなければ才能に恵まれている訳でもない。千尋は、ある日突然不思議な町に投げ込まれ、湯屋という神様のためのお風呂屋さんで働き始める。そこで修業し、友愛と献身を学び、積み重なっていく経験の全てが、千尋にとって冒険そのものであり、その中から「生きる力」が引き出されていく。この「生きる力」というものは、人間なら誰でも潜在的に持っている力であり、普通の女の子である千尋が自ら「生きる力」を引き出していくからこそ、普通の10歳の女の子のための冒険物語になり得るのであるという。
世の中というものは善人も悪人もみな混じり合って存在しており、これを峻別することは出来ない、と宮崎氏は指摘する。善人だけの社会とか、悪人だけの社会というのは存在しない。もちろん、一人の人間の中にも善人的なるものと悪人的なるものが共存しており、完全な善人とか完全な悪人というふうな割り切り方は出来ない。その代表ともいうべき存在が湯婆婆という湯屋を支配する魔女であり、一見悪人のように見えるが悪人と言い切れる訳ではなく、厳格なように見えて甘い一面も垣間見せる。同じように、湯屋で働く者たちの誰が善人であり誰が悪人であるというふうな分け方もしない。
「今日、あいまいになってしまった世の中というもの、あいまいなくせに浸食し喰い尽くそうとする世の中を、ファンタジーの形を借りて、くっきりと描き出すこと」がこの映画の主題であるという。すなわち、湯屋はある意味において「社会の縮図」であり、湯婆婆は「人間というものの見本」なのである。
さて、現代日本の子ども達は「生きる力」が衰えているのではないか、と宮崎監督は考えている。子供だけで自由に振る舞える空間が小さくなり、大人達によって囲われ、安全に守られ、危険から遠ざけられていると、生きることがうすぼんやりにしか感じられなくなって、「生きる力」そのものが弱くなってしまうと言うのである。千尋は、まさにそのような子供の象徴として登場する。
だが、子供というものは、本来「生きる力」の固まりである。一家で外国に引っ越したときに現地の言葉を最も早く習得するのは常に子供であることが示すように、子供はどんな環境にでも速やかに適応できる柔軟さを持っている。もちろん、千尋もそういう能力を持っているはずなのだが、今の日本の豊かすぎる環境の中では「生きる力」を発揮する機会もなく、退化するに任されている。
けれども、もし千尋のような子供が、突然働かなければ生きていけないような環境に放り込まれたらどうなるだろうか、と宮崎監督は考えた。退化した「生きる力」は再び甦ることはないのだろうか?
千尋は、突然突然不思議な街に放り出され、両親がブタにされてしまったので自分ひとりの力で生きていくしかなくなる。この世界で生きていくことは、すなわち働くことである。千尋は湯屋で働き場所を得て懸命に働いていく。ある時は感性を研ぎ澄ませ、ある時は全身を動員して働く。五感を駆使し、知恵をひねり出す。そして目覚しい判断力と行動力が発揮され問題を解決していく。このように、多くの苦労や困難を盛り越えていくうちに、本人も気づかなかった忍耐力が湧き出して、千尋の中で眠っていた「生きる力」が呼び覚まされていく。宮崎監督は、その過程を余すことなく描ききることで、子どもが本来持っている「生きる力」の可能性を表現しようとしたのかもしれない。
さて、「言葉」というのもこの作品における重要なキーワードの一つである。千尋の迷い込んだ世界では、「言葉」を発することはとり返しのつかない重さを持っているという。それは、あたかも言葉の重みがどんどん失われていく現実の世界の裏返しのようである。力のない空虚な言葉が無意味にあふれているだけの世の中は、子どもの未来に良い影響を与えない。だから、宮崎監督は「言葉は力であることは今も真実である」と考え、作品を通じて「言葉」の持つ重みについても深く訴えかけようとする。
「千尋」は日本が舞台となっているが、これは日本の伝統的な世界、すなわち民俗的空間―物語、伝承、行事、意匠、神ごとから呪術に至る様々な伝統―を作品中に織り込ませたかったからだという。「千尋」に登場する神様は宮崎監督の創作ではあるが、それらは日本の伝統的文化が色濃く反映されている。
国際化時代が叫ばれて久しく、外国の文化や伝統を学ぶ必要性が叫ばれている。だが、本当に大事なことは、まず日本の文化や伝統を学ぶことである。自国の文化や伝統を理解せずして、外国の文化や伝統を理解することなど出来ない。このことを、宮崎監督は「ボーダーレスの時代、よって立つ場所を持たない人間は、もっとも軽んぜられるだろう」と表現する。よって立つ場所を持たなければ、現在の自分自身はもちろん、将来像も描けないからだ。
まず自分の足元を固めること。それなくして自分が将来に何をしたいかという希望も見えてこないのだ。10歳の女の子の「生きる力」を信じ、10歳の女の子が「本当の自分の願いに出会っていく」ことを信じる。宮崎監督は、そのサポートが出来るような作品を作ろうとしたのかもしれない。
●「不思議の町」に迷い込んだ理由の一つとして何が考えられるだろうか?
引っ越しのために車を走らせていた千尋一家は、いつの間にか「不思議の町(霊々の世界)」へ迷い込んでしまう。そこは、人間社会のすぐ隣にありながら地図に載っている訳でもなく、亜空間というべき別世界である。その世界へ行く方法は全くのナゾであり、自由に往来することもままならない。そもそも、その世界の存在を知っている人もほとんどいない。
千尋一家は、なぜ「不思議の町」に迷い込んでしまったのだろうか?
その理由について、設定資料等で詳しく説明されているのでなければ推定するほかない。ここでは、説明がないのを逆手にとって大胆な仮説を考えてみよう。結論を先に書けば、千尋一家全員の投げやりな態度が「不思議の町」への扉を開いてしまったのではないかと想像される。「投げやりな態度」というキーワードは、なぜ千尋の両親がお店の食事を無断で食べ始めたかについて考えていくことから浮かび上がらせることが出来る。
不思議の街に迷い込んだ千尋の両親は、もの珍しさにつられて足を踏み入れていった。嫌がる千尋が「ねえ、戻ろうよ!」と叫んでも、全くお構いなしであった。そして、無人の街を探検した挙げ句、店頭に置かれていた食事に手をつけ、街の掟を破ったかどでブタの姿にさせられてしまう。
千尋の両親が街へ入り込んでいった理由については、「両親は高度成長期に育ったから好奇心が旺盛であり、何事に対しても貪欲だから。」というふうな説明がされている。まあ、その説明は分からないでもない。しかし、お店に置かれている食事を断りなく勝手に食べ始めた行動まで「好奇心が旺盛」という言葉で説明するには、いくら何でも無理がある。もし、そのような説明で片づけられてしまったとしたら、「高度成長期に育った世代は人様の食べ物でも平気で手をつける非常識な世代である」ということになってしまい、世の中の30代はたちまち怒り出すだろう。
では、なぜ千尋の両親は無断でお店の食事に手をつけてしまったのだろうか? 想像の域は出ないが、両親はリストラによる引っ越しで投げやりに近い状態になっていたから、後先考えずに食事をむさぼり始めたのではないだろうか。別に投げやりの原因がリストラでなくても良いのだが、とにかく何らかの理由で投げやり状態になっていなければ、お店の食べ物を勝手にむさぼる非常識な行動に出る理由を合理的に説明することは難しい。もし、あとで店員に見つかって怒られたとしても、自分はサイフもカードも持っているんだから怖いものなどないぞ、という訳である。(実際には、そこはルールの違う世界であって、勝手に神様の食べ物を食べた罰としてブタにさせられてしまうのだが・・・。)
父・明夫の顔つきは見るからに体育会系で、典型的な上昇志向・中央志向の相が出ており、どこからどう見ても田舎で気楽な生活を楽しみたいというような顔つきではない。おそらく、大学ではラグビー部あたりにいたのだろう。そして、体育会系の人脈を頼りに一流企業へ就職し、バリバリの営業マンとして働いていたのかもしれない。一方、母・悠子は知的でクールな女性であり、一方で打算づくで計算高い相が出ている。結婚相手を選ぶ時も、体格が良く、羽振りも良くて、なおかつ将来出世しそうな勢いのある明夫を選んだのものと思われる。悠子の結婚年齢は平均初婚年齢よりも若いが、これは早くから明夫に目を付けてキープしていたからであろう。当然、将来は重役夫人あたりに収まって、リッチなアーバンライフをエンジョイしようと目論んでいたのかもしれない。
だとすれば、田舎に引っ越して都落ちしてしまうことは、夫婦にとって面白かろうはずはない。まして、リストラに遭った挙げ句の都落ちならなおさらである。
悠子は知的でクールということになっているので、好奇心から「不思議の町」に入り込むことはあったとしても、明夫が勝手に食事に手を着けようとすれば「勝手に食べたりしたらダメよ」と言って制止する分別くらいはあるはずだ。ところが、制止するどころか明夫と一緒になってむさぼり始めた。やはり、悠子も投げやり状態であり、二人とも後先も何も考えず、もうどうなってのいいという位にまで投げやり状態になっていたのではないだろうか。
引っ越しの日、明夫は楽天的な性格ゆえに表情こそ明るくハンドルを握っていたが、心の中では深い挫折感に苛まれていたのかもしれない。「俺はもう出世街道を外れてしまったよ。トホホ。」などと。悠子の方も「まさか、この人がリストラされてしまうなんて思いもよらなかったわ。本当にこの人を選んで良かったのかしら。おかげで私の人生もメチャメチャだわ。」などと考えながら外の景色を眺めていたのかもしれない。千尋は千尋で、引っ越しそのものがかったるい。これまで苦労して作り上げてきた友達関係がチャラになってしまったので、また一から友達を作らねばならない気苦労を想像してか、鬱な様子が表情にまで出ていた。このように、あくまでも想像ではあるが、一家全員が一致して人生を投げやりに感じた瞬間、その「気」が空間を歪ませ、「不思議の町」へ迷い込む扉が開かれてしまったのかもしれない。
「不思議の町」への扉が開かれるのは、投げやりになってしまった人の「気」によるものなのかどうかは分からない。だが、「不思議の町」は、投げやりになってしまった人々に「生きる力」を呼び覚ますためのチャンスを与えてくれる場所という見方も出来る。千尋は「不思議の町」で仕事を得て懸命に働き、「生きる力」を回復していった。しかし、そこで投げやりになったままでは仕事を得ることもないから消滅させられてしまうか動物の姿に変えさせられてしまうしかない。このような見方が成り立つとすれば、「不思議の町」とは、人間の「生きる力」を吸い取りもすれば呼び覚ましもする、「もののけ姫」のシシ神のような存在であるかもしれない。
※この文章について、千尋一家はいつから「不思議の町」へ入っていったのかという質問が届いたが、上記の説に基づいて考えた場合、舗装道路が終わった時点で既に「不思議の町」への道へ入っていたと考えられる。もっとも、ここで記した説はあくまでも一つの見方を提示しただけに過ぎず、どのような原因・タイミングで「不思議の町」に入っていったかのかのパターンは、数多く考えられると思われる。(2001/07/15補足)
●「不思議の町」は、どのようにして生まれ、発展してきたのだろうか?
「不思議の町」は、人間が立ち入ってはいけない世界ということになっている。なぜなら、そこは日本の各地に棲んでいる八百万の神様の世界であり、特に湯屋は神様の疲れをいやす世界であるからだ。
だが、もしそこが本当に人間の立ち入ってはいけない世界であれば、人間は入った瞬間に消されるか動物にされてしまうはずである。だが、人間もそこで仕事を持てば生きていくことが出来る。湯婆婆の下においては、名前を奪われること=人間界の者ではなくなることも条件に入っているようであるが、だからといって心の中まで支配されてしまう訳でもない。つまり、「不思議の町」にあっても、人間が人間として存在することが許されているのだ。
このことから、「不思議の町」は少なくとも人間や人間の世界と全く無縁の世界ではないであろうことが分かる。そればかりか、湯婆婆が人間のある部分を代表しているように、「不思議の町」は人間の世界の鏡のような存在であるといえると考えられなくもない。
結局のところ、「不思議の町」とはどのような意味をもった存在なのであろうか?
この部分についても、設定資料等で詳しく説明されている訳ではないので推定するほかない。またしても仮説の提示にとどまるのであるが、ひとことで言えば「不思議の町」は人間の世界と神々の世界とのズレによって生み出され、発展してきたのではないだろうか。
人間の世界と神々の世界のズレがどのように発生し拡大していったかを考えると、下の図のような模式図を描くことが出来ると思う。
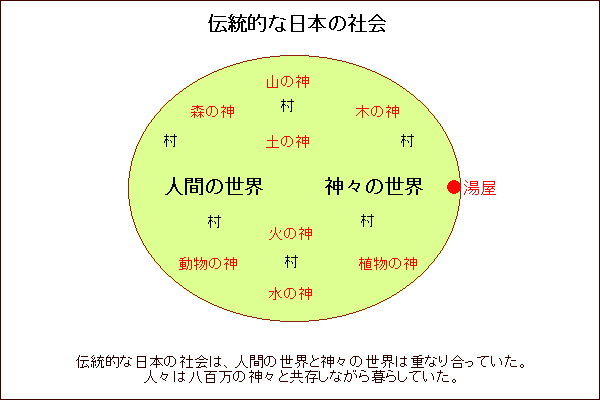
古来より、日本に住む人々は自然界に存在するありとあらゆるものには神が宿ると考え、八百万の神の存在を信じていた。自然の要素は、すなわち神の分身であるとも考えてきた。日本人なら、あの山の中に山の神が鎮っているのだと言われれば、ほとんど抵抗なく同意することが出来る。この森の中には森の神が鎮っているのだと言われても、あるいはこの樹木の中には樹の神が鎮っているのだと言われても同様である。日本人は、自然の恵みを神の恵みと考え、八百万の神々と共存しながら暮らしていた。私達にとって、神とはかくも身近な存在であった。(1)
つまり、日本とは人間が住む世界と神々が棲む世界が共有されている国であったと言うことが出来る。伝統的な日本の社会において、人間の世界と神々の世界は対立するものでなければ並列するものでもなく、そのまま重なり合って渾然一体となっていた。山には山の神、森には森の神が宿り、人々は神々の恵みに感謝しながら生活していた。神々は、人々の信仰によって支えられていたと言うことも出来る。(2)
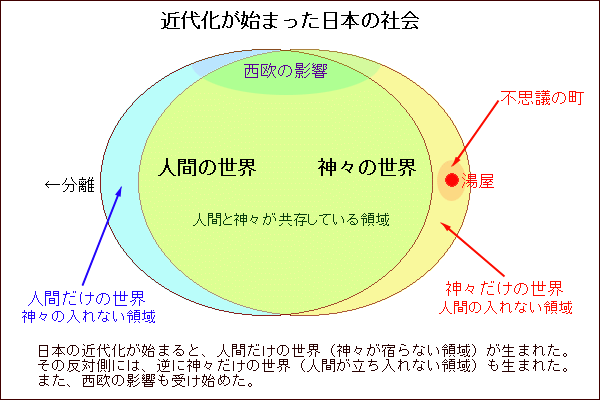
さて、日本の近代化が始まると、人間の世界と神々の世界との重なりにズレが生じ始めた。すなわち、人間だけの世界の出現である。それは、神様の入れない領域の誕生を意味するものであった。近代文明は、あらゆるものに神々が宿るという信仰を衰えさせ、したがって神々の宿らないモノを生み出していったからである。神々の宿れない世界は、神々にとって仕事がないことである。だから、仮に神様が立ち入ったとしても、仕事がないために消滅するしかないであろう。
同時に、ズレの反対側には人間が立ち入れない神々だけの世界というものも出現することになった。一方に神々を必要としない領域が生まれたのであるから、もう一方に人間を必要としない領域が生まれるのは当然の帰結である。不思議な町や湯屋は、このようにして人間の立ち入れない世界となっていった。仮に人間が立ち入ったとしても、そこで仕事を得ることがなければ消滅するかブタの姿に変えられてしまうしかないであろう。
近代化の進行は、同時に西欧の文化や技術を輸入することでもあり、人間の世界にも神々の世界にも影響を及ぼすことになった。西欧の神様や魔術・魔法も伝えられ、日本の神々と同居するようになっていった。
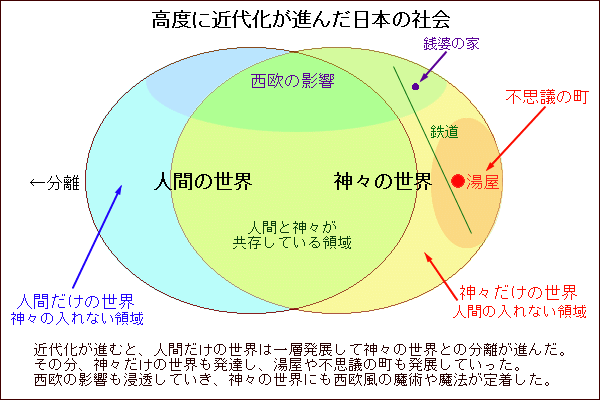
近代化がさらに進んでズレが拡大すると、人間だけの世界=神様の入る余地のない領域がますます発達することとなった。昔の人々は、かまどには神様が宿っていると考えたものだが、現在、マイコン内蔵の電子炊飯器に神様が宿っていると考える人はいない。同じように、パソコンに神様が宿っていると信じる人はほとんどいなし、携帯電話に神様が宿っていると信じる人もほとんどいない。第一、いまどきのパソコンや携帯電話は使い捨ての消耗品同然であり、神様を宿らせる余裕さえない。
人間だけの世界の拡大と同時に、バランスをとるために神々だけの世界も発達することになった。「不思議の町」も軒先を連ねて市街地が発達し、湯屋も要塞のごとく大規模化していたが、人間世界の発達と表裏一体をなすものだったのであろう。
物語の後半に出てきた銭婆(ぜにーば)の家は、日本古来というよりも西欧の魔女の家という造りであったが、これは西欧の影響を受けた結果であろうと思われる。日本はもともと多神教の国であり、西欧の神様を受け入れるのは容易であったし、魔術や魔法も抵抗なく受け入れられている。よて、神々の世界における西欧文化の同居も問題ないのであろう。もしかしたら、湯婆婆や銭婆は西欧の出身で、日本に居着いているのかもしれない。そして、日本的な領域と西欧的な領域の間は、鉄道で結ばれているという訳である。
さて、千尋が迷い込んだ「不思議の町」は、本来は人間の入れない領域にあった。だが、そこで仕事を得ることが出来れば人間として存在することが出来た。ということは、これと全く逆のことも起きているだろう。本来神様の立ち入れない領域にあっても、例えば「パソコンの神様」「携帯電話の神様」を信じる人がいれば、すなわち"仕事"を得ることが出来た神様は、そこで神様として存在することが出来るに違いない。
----------
IT革命が進行し、高度情報化社会が進展していけばズレがさらに拡大し、「不思議の町」も発展を続けていくかもしれない。だが、このまま永久に発展し続けていくのだろうか?究極的には、人間の世界と神々の世界は完全に分離してしまうのだろうか?
しかし、どんなに近代化が進んでも、日本に住む人々の心の中から神々が完全にいなくなってしまうことはないだろうと思われる。人間の世界と神々の世界が完全に分離してしまうこともないだろう。なにしろ、この国では原子力発電所やロケットの発射場など、およそ神様とは縁のない施設を作る時でさえ、必ず地鎮祭を催してその土地に棲んでおられる神様を祀る習慣を大切に守っているからだ。インターネット上でもおみくじや占いが大人気を博しているのも、新たなる神様の"働き場所"が生まれつつあることを予感させる。将来は、パソコンや携帯電話にだって神様が宿っていると考える人が増えていくかもしれない。
このように考えてみると、日本は依然として人間と神々が共存しており、将来もそうあり続けるのではないだろうか。やはり、日本は八百万の神々とともにある国なのだ。
(1)例えば、その年に収穫されたコメを神に捧げることいよって自然の恵みを感謝する新嘗祭は、人間が神とともにコメを親しく食する祭儀でもある。これは、私達が神と共に暮らしていることを確認する祭儀でもあった。
(2)神々は人々の信仰によって支えられているのであるから、人が信仰しなくなった神は死に絶える。「もののけ姫」におけるシシ神も、人々がそれを信じていればこそ生きることの出来た神であった。人々がシシ神を信仰しなくなれば、わざわざ神殺しに行かなくてもシシ神はその時点で実質的に死んだであろう。同じように、人々が信仰しなくなったイロリの神、カマドの神、井戸の神も現在では絶滅同然になっている。
参考文献
高橋勝『子どもの自己形成空間』川島書店,1992
厚生省大臣官房統計情報部編『人口動態統計』厚生省,1992
深谷昌志『無気力化する子どもたち』日本放送出版協会,1990
恩賜財団母子愛育会編『日本子ども資料年鑑』中央出版,1998
朝日新聞連載コラム「10年ほど生きてます:2000年のコドモたち」朝日新聞,2000