|
巨大オオクワガタ(♂78mmUP)作出のために −2年1化で育てる超大型個体− |
|
私がオオクワガタの飼育を始めた数年前は、良質な材を使って2年1化で飼育すると太くて かっこいい大型個体が育てられると言われていました。実際、野生のオオクワガタも、大型 のものはカワラタケ等で腐朽したエノキやクヌギなどの良質な成育環境のもと2年1化で育 つと言われています。つまり、いい餌を時間をかけて摂取吸収し、じっくりと成熟することで 大型になれるのだと考えられています。しかし、最近は菌床ビンの普及と質の向上によって、 誰もが1年1化で大型個体(〜♂78mm)を育てられるようになりました。ただ、80mm前後 の超大型個体を育てることは未だ難しく、そのためには飼育技術以外に血統がかなり重要 であると考えています(大統領の血統論)。 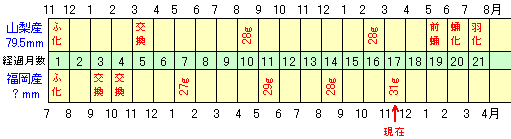 我が家には1998年7月に孵化した幼虫が未だ蛹化せず成長しているものがいます。そう、 2年1化の経過をたどっているようです。今後どうなるのか楽しみですが、不安もあります。 そこで1つ参考になるデータがありますので比べてみたいと思います(上図参照)。 上段は山梨産オオクワガタ専門の清水くわがたさんが羽化させた♂79.5mmの飼育報告 を参照させてもらってます。1997年11月後半に孵化、その後3回餌交換をし、21ヶ月目 に無事羽化を確認という経過です。下段は私が飼育している幼虫の経過です。清水くわが たさんの幼虫と同じように経過してくれるのなら、そろそろ蛹化してくれるかもしれませんね。   1999年8月21日(28g) 1999年11月14日(31g) しかし、30gオーバーまで育った幼虫は全国でも数多く報告されていますが、蛹化不全や 羽化不全で死亡するケースが多いようです。特に1年1化で30g前後になった幼虫は蛹化・ 羽化不全が起こる率が高いようです。これは恐らく、急速に成長したものの十分成熟する ことができず、何らかの無理が生じたためだと考えられます。もし十分に成熟することがで き、より自然の経過に近い2年1化型で育った幼虫であれば蛹化・羽化不全の率も少なく なり、超大型個体の育成が可能となるかもしれません。 |
 |