脚本は山田洋次と森崎東、監督は山田洋次。撮影は高羽哲夫、音楽は木下忠司。
厚生省の民生局防疫課の課長補佐でツツガムシと揶揄される早乙女良吉(有島一郎)はある日、湘南電車のなかで土方で働く労務者バン・ゲンゴロウ(ハナ肇)に出会う。痔の一種、脱肛で苦しんでいた彼は長年の知己でサナダムシと揶揄されていた友人(市村俊幸)の博多転勤の会に出席した帰りで、いささかふさいでいたのだが、傍若無人な源さんのふるまいはそんな落ち込んだ彼の気持を払拭させてくれるものであった。
源さんは良吉の家族のものにこわがられながらも、戸を修理したり、犬小屋を作ったりと、きさくに仕事をしてくれるので、隣りの家の奥さん(ク里千春)も大助かりだった。山田洋次は『自作を語る』で久里千春を“中産階級の僭越な女”を演じさせたら天下一品と評価。
息子に持って来た犬を散歩させたとき、源さんは海辺で自殺しかかった娘・愛子(倍賞千恵子)を助けた。
トカラ列島出身の愛子は男に裏切られ、家族からも見放されて、死のうとしたのだった。源さんは愛子の心身がよくなっていくにつれ、好意を示すようになっていた。
源さんが愛子を映画に誘った日の夕方、暴行されかかったような様子で愛子が帰宅する。ショックで彼女は口も聞けない。良吉は警察に連絡すると共に、翌日警察からの知らせで、暴行犯に会うとなんとそれは源さんであり、愛子の誤解から生じたものだった。良吉は告訴を取り下げると言ったにもかかわらず、源さんは自分がやったという主張を変えようとしない。
良吉が出社中に愛子も家を出てしまった。やがて一年がたち、彼も青森勤務を命ぜられる。妻(中北千枝子)や娘(真山知子)は湘南のマイホームを空家にしてまで付いていく気持ちは無かった。この時代、助監督の鈴木敏夫はマイホーム主義という言葉が流行したと言うが、山田洋次は「マイホーム主義は一種の家庭崩壊で、偏狭なエゴイズムだということが、この映画の基調である。狭い価値観で人を差別する人間が、映画を見て笑う。笑っている自分の価値観に気付いて反省することがある。それが喜劇の意義だ」と言う。
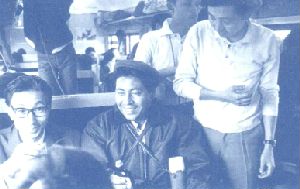 単身赴任で青森に向う列車のなかで、良吉はふと前の座席に来た赤ん坊連れの女の顔を見た彼は驚いてしまった。愛子だったのだ。結婚したのだ。結婚相手はと見回すと、源さんだった。二人との再会を喜ぶ彼。
単身赴任で青森に向う列車のなかで、良吉はふと前の座席に来た赤ん坊連れの女の顔を見た彼は驚いてしまった。愛子だったのだ。結婚したのだ。結婚相手はと見回すと、源さんだった。二人との再会を喜ぶ彼。DVDの『自作を語る』によれば、東宝から有島一郎をわざわざ借りたのは、「背が高くてヒョロヒョロしているコメディアンが、サラリーマンにはぴったりだと思ったから。斎藤寅次郎の映画に出ていた渡辺篤のような、どう見ても失業者といったギクシャクした体の動きができる、存在そのものがコメディアンといった人が最近はいなくなった。・・・ラストは甘いね。けれども、小沢重雄という評論家が、ハッピーな終わり方をする、だから映画はいいのだと書いてくれたことが、忘れられない」と証言。
予告篇の冒頭はハナ肇が仁義を切るところで始まる。この場面は映画本編には無い。森崎さんのシナリオにはあって撮ったのかもしれませんね。当時は予告篇用の撮影は別撮りだったので独自の遊びかも。
土田 啓三 山田喜劇の過去と現在
山田洋次監督が一連の喜劇の中で描いてきたものと
今日の山田喜劇の危機 (キネマ旬報1970年8月下旬530号)
忘れがたい初期の作品
「男はつらいよ」シリーズ二作が、昨年度キネマ旬報,ベスト・テンに入った事で、ようやく山田洋次作品の良さが評価されるようになった。しかし、これはむしろ遅すぎたというべきで、山田は過去に、馬鹿シリーズや「なつかしい風来坊」「愛の讃歌」等の秀作を何本も作っているのである。少なくとも「男はつらいよ」が、ベストテン六位にランクされるくらいなら、「なつかしい風来坊」はもっと上位に入るべき傑作であった。もっとも「男はつらいよ」が過去の山田作品に比べ、劣っているというわけでは決してない。演出はますますうま味を増し、小憎らしいばかりの演出テンポは快調である。しかし、僕はむしろ、荒っぽく、破綻はあったが、何か惹かれる物があった初期の作品の方に愛着を感じる。
例えていえば、最近の作品はふっくらと丸味をおびてはいるが、電気釜で炊いたご飯の如く、すんなりとまとまっていて、過去の、ハンゴウで炊いたような、ところどころ焦げついた出来具合の方が、今ではなつかしく感じられるのである。
山田洋次の第三作目に当る「馬鹿まるだし」は、山田にとって初めての喜劇であり、これによって作品的にも興行的にも認められただけでなく、以後の「男はつらいよ」に至る、一連の山田喜劇のパィロット・フィルムをつとめた記念すべき作品である。徹底的にお人好しで、単純で、ヤクザ的世界にあこがれる主人公は、周囲におだてられ、利用されて、結局自らをだめにしてしまう。他人から見れば何と馬鹿だろうと思える。が、この彼の姿こそ、我々がともすれば忘れがちな魂のふるさとなのだ。当時すでに全盛となっていたヤクザ映画のパロディになっていたが、単にパロディとして終わらず、ヤクザ映画に共通する、古い型の日本人の姿を描き出す事ができたのである。(脚本に加藤泰が加わっている事に注目)この作品や「男はつらいよ」がヒットしたのも、ヤクザ映画がいつまでも人気を保っているのも、これらの浪花節的義理人情の世界が、・永遠に日本人の心情を代弁しているからであろう。
「馬鹿まるだし」が興行的に成功したために、馬鹿シリーズと称する作品がこの後二本続いたが、いずれも一作目の二番煎じと見られ、作品的にはそれほど評価されなかった。しかし僕は、この後の二本をこそ注目すべきだと言いたい。
古き日本の魂の叫びを
その一つ、「いいかげん馬鹿」は主人公の性格こそ前作のシタイルを借りているが、シチュエーションは全く異なり、ひなびた漁村を舞台に、ふるさとに永遠に帰れない男の悲劇を通して、ふるさとを喪失しつつある現代人への警鐘をこめた佳作である。捨て子だった主人公安吉は、戸籍を持たないため、ふるさとにも居られず、外国へ移住する事もできない故郷を喪失した人間である。そして、村のため、人のためになろうとする努力がすべて裏目に出、心がやさしいために、都合の悪い事はすべて彼の責任にされてしまう。そして、とうとう故郷に居られなくなり、わびしいテキ屋に転落している所を、ただ一人彼をかばってくれた岩下志麻のお嬢さんとバッタリ出会うのだが、それもつかの間、ここでもヤクザに追われ、逃げ去ってゆく所で終わっている。これは彼が一生、安住の地を得る事がないであろう事を暗示しているのだが、これほど、生きる事の悲しさと、政治から見捨てられた人間の、救いようのない悲劇を冷たく見すえた作品を僕は知らない。
また一方、さびれてゆく漁村の生活を守るために村人たちは、自分たちの島を観光地にしようともくろむ。島はどんどん切り拓かれ、自然が破壊され、人工の観光地ができ上がってゆく。その過程を通じて、生きてゆくために、また文明の発達のために、人々は自らのふるさとと共に、心のふるさとをも失いかけているのではないかという、素朴な、しかし力強い訴えが見られるのである。映画の中でハナ肇が繰り返し歌う、 “うさぎ追いしかの山…”の歌も、もはや遠い過去のものとなってしまった。
「馬鹿まるだし」が、浪花節的心情から日本人の心にせまっているのなら、「いいかげん馬鹿」は、失われゆくふるさとへのノスタルジーを、日本人の心に訴えかけているのである。単調な現代生活の中で、ともすれば見失いがちな、古い日本人の作りあげてきた魂の叫びが、二つのジャンルに集約されてこの二作に表現されているのだ。
そして「馬鹿が戦車でやって来る」では、同じく疎外された主人公の怒りが、ついにはゲバルトにまで到達する。「汚れの一家」と村中からのけものにされ、農地解放で得た土地までも巻き上げられた主人公が、最後に戦車を持ち出して大暴れをする話だが、差別され、抑圧された者の怒りがゲバルトに転化しうる可能性を示した点で、これは今日の学生運動や、三里塚の農民の尖鋭化を予見したような作品でもあるのだ。
山田作品の中でも、主人公を徹底的に被害者として描いたものは、恐らくこの二本の罵鹿シリーズだけであろう。もちろん、どちらもそれほど出来のいい方ではないが、それでも山田が被疎外者の悲しみにひたり切って、怒りをストレートにぶつける、そのナマの真情吐露に、僕はうたれた。「馬鹿まるだし」が最近再公開されたが、僕は是非とも、特に「いいかげん馬鹿」の再公開を望む。 「イージー・ライダー」や「真夜中のカーボーイ」の如く、頽廃してゆく都会への幻滅や、人問のふれ合いを描いた作品が登場してきた現在、もう一度「いいかげん馬鹿」の良さを、見直すべきだ、と思うのだが。
失敗を恐れず 新しい喜劇を
以後の作品についてはスベースが少なくなって来たのでここでは割愛するが、最近の作品について一言。
白井佳夫氏は、「男はつらいよ」シリーズを評して、寅さんが、周囲の人間の善意に包まれ、過保護であり過ぎると書いていたが、僕もまさしくそう思う。人間の心の暖かさを描き続ける山田洋次の姿勢には大いに敬意を表するが、どうも最近主人公を甘やかし過ぎ、それが作品自体を小さな殻に閉じ込めてしまっているのではないか。少くとも過去の作品には、運命にふり回される主人公を見つめる厳しい目があったように思う。
そしてその過保護性は、山田洋次自身についてもいえる事なのだ。山田は今や企業内で自分の好きな作品を自由に作らせてもらえる数少ない、あるいは唯一人の作家であろう。松竹という、人情喜劇の伝統にはぐくまれた会社に在籍し、さらによきスタッフ、よき演技者に恵まれ、支持観客も増え、今や順風満帆である。
だが、そこ仁危険なおとし穴がある。過保護に浸りきる事が、作家の精進を停滞させる事だってあるのだ。会社や批評家にほめられているうち、知らず知らずのうちに、作品的に失敗しても新らしいジャンルに挑む冒険を避け、無難な過去のスタイルを保持するだけの“名匠”になってしまわないかと恐れる。困難な条件と、少ない日数の中で、ねばりにねばって、しゃにむに作品を自己の物に仕上げてゆく中でこそ、作家としての成長があると思う。
馬鹿シリーズの頃がなつかしくなってくるのも、実はその辺にあるのだ。山田としては、 「九ちゃんのでっかい夢」で失敗し、批評家にもさんざんコキおろされた事にこりているのかも知れないが、失敗を恐れる事はない。寅さんの如く、失敗を繰り返しながら、新しい喜劇の創造に取り組んでもらいたいものだ。
山田は今、半年ぶりの新作「家族」の撮影に入っている。山田にとっても、久しぶりにシリアスな題材になりそうだ。日本中を旅する一家の話といえぱ、大島渚の最高作「少年」を思い出す。何かと同期の大島と比較されるが、この新作も山田の代表作となる可能性は充分だ。これまで蓄積してきた成果がどれだけ現われるか、今から楽しみである。
(西宮市・22 歳)
平田泰祥 森崎東が描こうとする連帯とは
観客と森崎東と主人公を結ぶもの!
(キネマ旬報1971年11月上旬564号)
森崎東監督が、さかんに"連帯"ということを言っている。ここで、その"連帯"の意味を考えてみようと思う。
深作欣二監督は、こんなことを言っている。「私は、田舎から東京にやって来て、映画を作り始めた。田舎から都会にやって来た人が、都会で生ぎて行くのに、二つの型がある。一つは、都会に必死で同化しようとして、その体制内の一部になってしまう人。もう一つは、どうしても都会に同化しきれず、或は同化しようとせず、たえず都会に対してのコンプレックスを持ち、反撥し、居直って生ぎて行く人。この二つである。私は、正に後者の揚合で、私の作る映画の主人公たち、チンピラやギャングたちは、私の分身であり、彼らをこの上もなく愛していた。」
これを読むと、深作監督の傑作「狼と豚と人間」が思い出される。しかし、ここで問題にしたいのは、私や、森崎東は、前者なのだろうか、後者なのだろうか、ということである。
言うまでもなく森崎東は後者であり、私も後者であろう (自己満足かも知れない)。では、なぜ森崎東は、同化しようとしないのか。現代では、同化しなげればオエライ人にも、なれないし、出世コースにも乗れないのである。森崎東は、おそらくこの問いに対してこう答えるだろう。"同化して、オエライ人になり、出世コースに乗ることによって、みじめな、安易な、安定生活、プチブル生活(小さな家に、小さな庭、妻と子と、幸福な家庭)を得るぐらいなら、不安定で、徹底的にキタナイ頽廃生活をする"。そして私は、まさにそんな森崎東の映画を愛すのだ。
同化されない森崎東は、孤立するのだろうか。孤立はしない。ここで森崎東は、言うのだ。 "同化されない劣等人間たちよ! 一緒になろうではないか!”と。
五六一号において周磨要さんは「今の世の中、ドロップ・アウトして人の生産物にたかるか、生産体系に組み込まれて無気力になるかの二者択一に走りすぎる。」と言っている。まさにその通りである。しかし、生産休系に、反撥しながら組み込まれるのと、素直に組み込まれるのとでは、大きな差がある。少なくとも、多少の反撥は感じつつ生産し、孤立しながらも、手をさし延べて、連帯を求めているのが、普通の人々ではないか? いやそうに違いない!
サラリーマンとドロップ・アウトの連帯を描いた傑作に、森崎+山田の「なつかしい風来坊」があり、また先生とチンピラの連帯を描いた作品に、森崎+山田の「吹けば飛ぶよな男だが」がある。この二作に森崎東の名があることは、重要なことである。ここでこの二作の"連帯"の意味について考えてみよう。
「なつかしい風来坊」の最初のシーンは、満員電車の中で早乙女(有島一郎)が、しかめっ顔をして、立っている所へ伴源五郎(ハナ肇)が来て、こんな会話をする。 「気分悪そうだな!どうした?」「はあ、私は痔なんです」「そうかい痔かい/」と大声で言う。 「それでイボ痔かい。キレ痔かい。」こんな会話で、囲りの人々は、必死で笑いをガマンしている。このシーンで囲りの人々は「早乙女は、運の悪いやつだ。酔っぱらいにからまれて」と思うだろう。それに早乙女にしたって、気分のいいことではない。だが私は、電車の中で大声で痔の話ができる源さんをうらやましいと思った。囲りの人々や早乙女も、感じたはずだ。みんな、ほんとうは源さんになりたいのだが、なれないのだ。これがこの作品の限界であり、森崎が「女生きてます」を作り、山田が「男はつらいよ」を作る分れ目である。このことは後でふれる。
この早乙女一家は典型的なプチブル一家であり、早乙女は典型的な弱いサラリーマンである。会社では局長に頭は上らず、不平不満を堂々と家もしない。前述でわかるように彼の不平=痔だ。彼は体制内にいながらも、すべて同化してないのだ。そしてその同化してない部分が、まさに源さんの心と一致したのである。ここで重要なのほ、生産体系に組み込まれた人(体制内で、反撥を感じつつ生きている人)と、ドロップ・アウトしている人(体制外の人)との連帯が生まれる。ということである。この結びつきは、この作品のラストに至って、一そう明確になる。
つまり、早乙女との結びつきを断ってしまったかのように去った源さんと愛子は、夫婦になっていて、汽車の中で彼と出逢うのだ。その時、早乙女は彼らを暖かく迎え、二人は彼をすぐに受け入れる。ここで断っていた連帯は、すぐ復活し、早乙女と源は結ばれるのである。この結びつきこそこの作品のすべてであった。少なくとも森崎東にとっては、そぅだったに違いない。
「吹けば飛ぶよな男だが」で同じく有島一郎扮する先生と、なべおさみ扮する三郎と、緑魔子扮する花子の結びつきにも、同じようなことが言える。チンピラの三郎が、花子をねたに強請りをやる。 その相手が先生である。しかし、先生の神妙な態度に、すっかり白げた三郎は、そこで酒を飲み合って、二人は意気投合するわけである。体制内での人、つまり先生は、気が弱く、今もって独身である。そして、そんな不平不満をエロ映画にしか持って行くことがでぎないのである。彼はやはり休制内の人でありながら、全てを同化できないのだ。まさに、早乙女のイメ一ジと同じである。森崎は、同一の俳優を使って、同一のイメ一ジを出させ、ドロップ・アウト(体制外)の人との連帯、結びつきを、この作品でも強く言っているのである。
森崎東と山田洋次の協同脚本の中では、かならずと言っていいほど、体制内の人と体制外の人(主人公)との連帯が、描かれている。 「愛の讃歌」(末見)も、やはり有島一郎を使っている所から見ると、やはり同じイメージで作られていると思う。また「男はつらいよ」の第一作においても、寅(外)と博(内)の友情が描かれている。後の作品には、見られない特徴である。脚本段階において森崎東は、常に体制内で、反撥を感じつつ生きている人と体制外の人との連帯を描き続けた。これを土台として傑作「女生きてます」は生まれたのである。
「女生きてます」を見る時、常に森崎東は過去において、体制内の人と外の人の連帯を抽いて来たということを忘れてはいけない。そして、森崎東は、ここで徹底して、体制外、ドロッブ・アウトした人間たちを抽く。一見、ドロップ・アウトした人々の連帯だけを描いているようだが、ここでも、やはり森崎東は、体制内と外との連帯を彼の目標としているのだ。つまり、私と森崎東とこの作品の中のドロップ・アうトした人々との連帯である。森崎東の"連帯"とは、観客と森崎東と映画の主人公たちとの連帯である。これが彼の目標だと思う。連帯が安易にできるとは言えない。そして現実は、もっときびしいのである。しかし少くとも森崎東の目は、ドロップ・アウトしている人に近いと言えよう。そして彼は映画の主人公たちに、常に手をさし延べているのは、確かである。
山田洋次が「男はつらいよ・奮闘篇」において、頭の弱い予は、ストリッバーになる。なんて言っておきながら、過保護につぐ過保護で、頭の弱い花子は、暖かい人々に囲まれて一生くらすことになる。森崎東の描いたポチは、花子の分身である。だからこのごろ山田洋次は、上品ぶっている。また物語も鼻にかかるようになって来た。森崎東こそ、今からの私たちの期待を受けて、真の連帯を作るために、一心同体とならなければならない監督なのである。山田洋次の弱点は、体制外の人々を描くことができないことである。常に自分は、体制外になりたいと思いつつ、やはり体制内での保護が忘れきれないのである。これが、山田洋次と森崎東の決定的な違いである。だから森崎+山田で、森崎の監督した「女は男のふるさとョ」の笠子のエピソードが実に白々しかったのは当然である。
森崎東は、声を大にして言う。 「かつて日本映画の誇りと良心であった木下恵介は"日木映画は、かつてのものと、全然別物になってしまった。日本映画は、 もう上品な一般人の見るものではなくなってしまった”と断言した。その適り、だと思ぅ。そして、それでいいのだと思う。いや、そうでなくてはならぬ、とさえ思う。日本映画は、やっと上品ぶったプチブルのものではなく、下品なプロレタリア一トのものになろうとしている。エッチでド助平なプロレタリアートだけが"一体何が誰が、人間を下品にしているのか?"について、"一休何が人間にとって上品なのか?"について、今日語りうる数少ない人々ではないだろうか。日本映画は、未だかつてない程、優秀な観客を獲得しようとしている。深夜映画でべスト・テンに入る映画を作れたら、死んでもいい、とさえ思う。」
東宝の森谷司郎の作品に、常に反撥を感じるのは、正に上品ぶっているからだ。出る主人公、男と女も、すべて上品ぶっている。そして監督まで、それが当然だみたいな形で同じ傾向の作品を作り続けている。東宝は上品ぶっている限り、破滅するだろう! 今の観客は、下品なのだ。下品でキタナイからこそ「男はつらいよ」を見、「儀式」をも見るのだ。
森崎東は、私たちに手をさし延べている。それに、私たちは答えてやろう。私たちは、その手を結ぼう。そしてて"映画を、下品で、労働者的節操という奴さえ持ち合わぜないルンペン的プロレタリアートのものに!"
(広島県・学生・十八蔵)