「原画の描き方」ということに関しては、私程度の技量のものが書いた駄文をいくら読んでみたところで読者の得るものは少ないと思う。
故にここでは私のお薦め参考書の簡単な紹介と、私が原画を描く時の手順を紹介しておくのに留めておく。
参考書であるが、お薦め順に並べると「快描教室」(*1)「やさしい人物画」(*2)「やさしい美術解剖図」(*3)の三つ、そして番外として「動物の描き方」(*4)となる。
「やさしい人物画」「やさしい美術解剖図」の二冊はタイトルからも想像がつく通り、いわゆる美術書である。この二冊を用いて美術デッサンを学んでおくと、理屈でもって人間の様々なポーズを様々な角度から見た絵が描けるようになるので、学んでおいて損はない。というか、学べ(オイ
しかし、美術デッサンだけを学ぶことにはいくつかの問題がある。
第一の問題は「柔らかい」キャラが描きづらくなるということだ。
これは、美術書に掲載されている図版の大半が、人体の構造を理解させるための骨格と筋肉とが強調された「理想的な」人体の図で占められていることから来ている。男性を描くのならともかく、女性を描く時に筋肉質な女性しか描けないようではうまくない。
第二の問題はキャラのポーズがかたくなることだ。
これは人体を理詰めで描く以上は仕方のないことであるが、やはりうまくない。
第三の問題は難しい構図のポーズを描くのに不適だということだ。
骨格と筋肉の繋がりの法則から理詰めで未経験のポーズを描くことは非常に難しい。本当の意味で美術デッサンを習得していればそうでもないのかもしれないが、中途半端に美術デッサンを学んだ人間にはこれほど難しいことはない。
これらの問題を解決する方法は唯一つ。うまい人間の絵を模写していくことだ。
模写に模写を重ねることで絵描きとしての経験値が増し、骨格や筋肉の構造を知っただけでは描けない、肉の柔らかさや質感を持った絵が描けるようになる。
それならば最初から模写だけをすれば良いではないかと思う人もいるかと思う。
だが、私が考えるに美術デッサンと模写とは対の関係にあるものである。
家の建築を例とするならば、美術デッサンは家の基礎設計と骨組みの部分、模写は家の外面を飾る壁塗りやデザインの部分である。骨組みだけでは殺風景な家しかできないし、壁塗りだけでは家そのものがまともに建たない。それ故、本当に良い家を建てるには双方の技術が必要になるわけだ。
話を戻そう。
私が一番のお薦めとしている「快描教室」は、その双方を解説した本である。但し、かなり実践的な知識の書かれた本であるため、完全な素人が読むにはあまり適さない。ある程度、デッサンの知識を持った経験者が読むべき本である。(*5)
模写の参考とする絵描きであるが、基本的には個人の好みで良い。ただ、敢えて私のお薦めの絵描きを挙げるとすれば、「快描教室」の著者である菅野博士、花とゆめ系の作家である山口美由紀の名が出てくる。
両人とも、デッサンのしっかりとした、色気のある絵を描く人であるため、模写の参考とすると得るところが大きいと思われる。
*1:
快描教室 きもちよ〜く絵を描こう! 菅野博士著 定価(税込): \ 1,470 ISBN 4568501938 美術出版社刊
*2:
やさしい人物画:アンドリュー・ルーミス著 定価(税込):\ 1,890 ISBN 4837301037 マール社刊
*3:
やさしい美術解剖図:ジョーゼフ・シェパード著 定価(税込):\ 1,523 ISBN 4837302025 マール社刊
*4:
動物の描き方:J・ハム著 定価(税込):\ 2,100 ISBN 4767985056 建帛社刊
*5:
本当の初心者が絵を学びたいのであれば、「やさしい人物画」「快描教室」「やさしい美術解剖図」の順で読むと良い。
3.2:原画作成の手順
3.2.1:ラフ描き
オリカの原画を作成する時に、私が最初にするのは小サイズでのラフ描きである。
気軽に描けるラフ描きでポーズの全体のバランスを見るのだ。
使用する画材(?)はシャープペンと大学ノート。
一見、安っぽい印象を受けるが、大学ノートには罫がついているため、水平線が確認しやすく、絵のバランスが取りやすいというメリットがある。
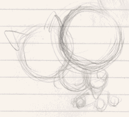
|
画材の用意ができたら早速がしがし描いていく。バランス取りが目的であるのだから細部を描き込んでいく必要はない。頭、首、胸、腹、腰、肩、肘、手首、膝、足首の位置を示すマーカーを用いて全体の構成を組んでみる。 |
ラフ画を描いてみると、当初考えていた猫系キャラとの絡みは頭身的に難しいことが分かる。ここで無理に二キャラの絡みを描いても良いものはできそうもないので、当初の予定は放棄して普通の猫を抱いている形に変えることにする。

|
ぱっと見、うまく行きそうな感じがするので、これを元に細部を詰めることにする。 なお、左図の色のついたマーカーは、それぞれ首(赤)、肩(黄)、肘(緑)、手首(水色)、腰(マゼンダ)、ひざ(青)、足首(紺)の位置を示している。 このように、関節の節目の位置を意識しておくと、原画がデッサン的に破綻することは少ないものである。なお、見やすさの関係からこの絵の中での左腕のマーカーの表示は省略した。 |
3.2.2:ラフ画の拡大
続いて行うのはラフ画の拡大である。
ラフ画は全体のバランスを取るために描かれたものであるため、一般に原画の元絵とするにはサイズが小さく、拡大する必要があるのだ。
ラフ画を拡大するためには、まずラフ画の各部の比率をチェックしていくことが必要となる。
頭と胸、頭と腕といったように、基準となるパーツを元に各部の比率を導き出し、それを元として拡大していくのだ。
この際にも大学ノートの罫が目安として役に立つ。下手にスケッチブックなどを使うよりもずっと便利である。
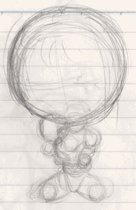 |
このように元のイメージにかなり近い状態で拡大できる。 若干、頭と身体のバランスが変わっているが、これは拡大する時に意識してバランスを修正したためである。 |
3.2.3:下書き
拡大したラフ画を元に、下書きを仕上げていく。
下準備で集めた資料をじっくりと見て、衣服やアクセサリ類の概要を理解したら大まかな部分から細かい部分へと描き込みを続ける。
私自身は顔の輪郭を描いてから、目(斜め顔の場合、奥の目から)、髪、口、身体と描いてくとバランス良く描けるのだが、ここら辺は人によって全く異なるので、自分の描きやすい様に描けば良い。
 |
これで下書きは完成。 この段階で描いた絵に満足がいかない場合は何度でも描き直すことが必要である。 人間の目には、左図のような線の整理されていない絵を見る場合、自然に最も良い線を選び出すという習性がある。 そのため、ペン入れの前後の絵を見比べると、一般にペン入れ前の方が綺麗に見えることが多い。逆を言えば、この段階で良く見えない絵にペン入れをしてもより満足のいかない結果が出るだけだということである。 |
3.2.4:ペン入れ
主線のまるで整理されていない下書きは、そのままでは彩色用の原画とはなり得ない。
彩色作業をやりやすくするために、下書きの線を整理して原画とする作業、これをこの講座では便宜的にペン入れと呼ぶこととする。
ペン入れには幾つかの方法がある。
下書きに直接ペンを入れる方法、ライトボックス(*1)を使って、下書きの線をトレースする方法、一旦、PC上に取り込んでからタブレットで修正していく方法、etc……。どの方法を選ぶかは、その人の技量と手持ちの機材によって異なることになる。
私の場合、以前は下書きに直接ペンを入れる形でペン入れをしていたが、ペンの扱いが苦手なこともあり、現在では一風変わった方法でペン入れをしている。
ここではその方法について説明していくことにする。
私のペン入れはコンビニエンスストア(*2)に出掛けることから始まる。
目的はカラーコピー機。下書きに直接ペン入れをして失敗し、下書きを失うことのないように単色カラーコピーを用いてコピーしておくためだ。
単色カラーコピーの際に使用する色は、シアン、マゼンダ、イエローなどCMYKの色成分に含まれるものを選ぶ。
無事にコピーが取れたら、そのコピーしてきた紙にペン入れをする。
ペン入れの際に使用するペンは、私の場合、顔料インクを用いた0.1〜0.3ミリサイズのミリペンである。メーカーは特に問わず、店頭で使ってみて使いやすいと思ったものを使うことにしている。
ペン入れはできるだけ丁寧に行うようにする。
大きな弧を描く時には雲型定規を使い、線が乱れたり、はみ出したりした部分は白のミリペンを利用して修正する。
ここで丁寧に作業をしておくと、原画を取り込んだ後の修正作業が大分楽になる。紙の上で5分かかる修正作業は、PC上でマウスオンリーで行うと10分以上かかるものだと考えておくと良い。
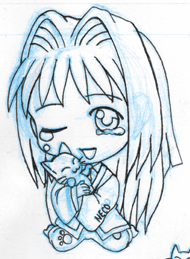
|
ペン入れの終了した画像はこのような感じになる。 ブラウザ上では縮小された画像になっているため、主線などが一見綺麗に見えるが、実際の絵を見てみるとそれほど綺麗ではない。 とはいえ、私の腕ではこれ以上線を綺麗にすることもできないので、後の処理はPC上ですることにしてこれで良しとする。 |
ペン入れが終了したらスキャナを用いて原画を取り込むことにする。
取り込みの設定は、私の場合、CMYKのフルカラーで、解像度は600dpiにしている。
取り込みが済んだら下書きの線を消していく作業に入る。
使用するツールは、Adobe Photoshop4.01。
これ以降の操作説明は基本的にこのツールの操作を例にとって書いていくので、他のツールを使用している人間は、使用しているツールに合わせて創意工夫すること。
|
取り込んだペン入れ画像をロードし終えたら、チャンネルパレットを表示させ、黒以外のチャンネルをすべて白で塗り潰す。 こうすることによって原画から簡単にペン入れの線だけを取り出すことができるのだ。単色カラーコピーを取った時に、CMYK成分の色を利用したわけはここにある。 |
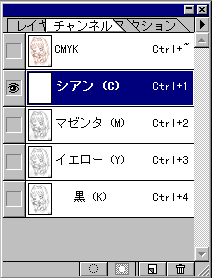 |
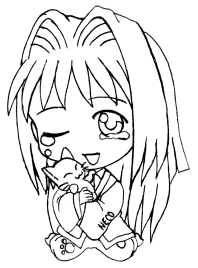 |
不必要なチャンネルをすべて消してから、編集モードをRGBモードに変更し、色調補正>レベル調整、で黒と白とのコントラストを明快にした画像。 |
奇妙なことであるが、紙上で原画を描いていた時には気づかなかった絵の欠点が、PC上に取り込んで見て初めて明快になるということが非常に多い。
そのため、本当の意味での彩色用の原画というものは、PC上での線修正が終わった段階のものを指すと言っても良い。
次の項目では、その線修正の方法について書いていくこととする。
*1:
アニメーターが、原画をトレスしたり、動画を描いたりする時に使う、照明の内蔵された箱のこと。昔は馬鹿でかいものばかりであったが、最近は技術の進歩からかタブレットサイズのものも見受けられるようになった。値段的にはゲームソフト一本分するかしないかくらいなので、利用することが多いと考える人なら買ってしまっても良いかも。
*2:
単色カラーコピーの使える店であれば何処でも良いのだが、単色カラーコピーの料金は店によって違うことが多いので、できるだけ安い店を探すと良い。ミニストップあたりだと1枚10円のことが多いのでお得である。