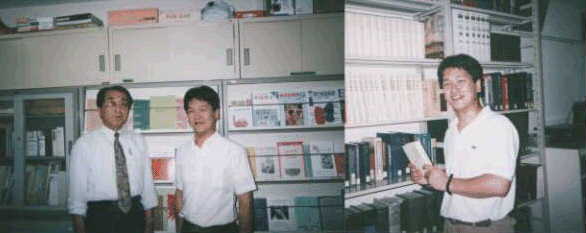
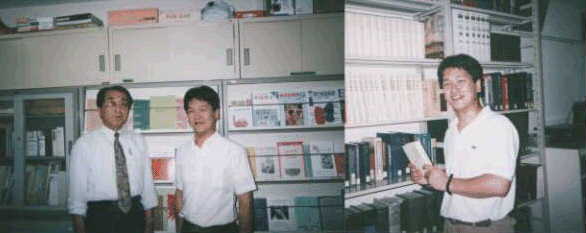
渡辺先生の講義では主に文献を読みながら過去から現在に至るまでの「歴史的 背景」に基づく英語教育理論全般が学習できる。特に「ELEC」に関しては第 一人者である。
渡辺先生は埼玉大学附属中学校の学校長を兼任されているため、本当に多忙で
ある。火曜日と金曜日位しか大学にはおられない。後3年は学校長をお勤めにな
られる関係上、埼玉大での教鞭もまだまだ健在なはず!とにかく歴史的な教授法
を叩き込まれるため講義ははっきりいって苦痛だ!しかし、内容は濃い!「時代
のニーズ」にのっとった教授法が存在していることを改めて知った。以下に渡辺
先生の講義の一部を紹介する。
<戦後の花形「Oral
Approach」について......>
The word "approach" rather than
"method"(comparing with Palmer's theory)has been chosen
deliberately. It has been chosen in order to stress the fact that
we are concerned with a path to a goal---a path or a road that
includes everything necessary to reach that goal. We are
concerned with such
a path rather than with a method of teaching. a method of
teaching often im-
plies the limitation of what the teacher does---the limitation to
a parti-
cular set of classroom procedures. The final goal toward which
the "oral
approach" is the path or road or way, is the full mastery of
English for any of the purposes for which one seeks to learn a
foreign language.
---------C.C.Fries, On the Oral Approach.
オーラル・アプローチは教師がオーラルで教授することを求め、そのことで教 授法に制限を加えるものではなく、最終的な目的が学習者のオーラルな言語運用 能力であり、そのゴールのためにはあらゆる手段を使って教授してゆく。
In the "Oral approach" although the language of the
pupil is avoided as much as possible it is used when necessary to
make sure that explanations are thoroughly understood.
文法的な説明等が確実に学習者に分かっているのであれば、母国語の使用はな るべく避けなければいけない。(逆に)説明不十分で理解不十分な場合は母国語 (日本語)で説明しても良いのである。
現代英語は社会的なニーズから「OUTPUT」に重点が置かれているが、本
質においては中学校英語(14歳言語習得臨界期)では「理解から運用へ」とい
う形が存在している。
 左から、長研・竹本先生、院生・岡安君
左から、長研・竹本先生、院生・岡安君
院生・林さん、真尾 先生。
(院生2年の鈴木さん、教職経験ありの金子さん もいます!!)私を含め、 計7人!!!
真尾研究室にはエアコンがある数少ない研究室です。
「いやー、今のは授業じゃなかったねー!」「あんたもよくシャベルねー!」
「顔真っ赤にしてまー」「どうせ聞いてやしないんだから!」「そこまでうちの
○○は落ちてねーよ」......新任初めての研究授業で「授業じゃない!」
などと言われたら嫌になります!!
私はそう言われて悔しくて埼玉大学に研修に来ました!!!!!!!!!!!
しかし、褒められてそれで良いと思って勘違いするより本音で勝負の先生の授
業後のコメントを聞く方が大変貴重です!しかもすべてが理論に裏付けられてい
ます。県内でも人気のある指導者、ディスカッサントである理由はそこにありま
す?!
真尾先生は「教材開発」の第一人者です。”SUNSHINE”などの編集を
手がけています!とにかく課題がたくさん出されます!多いです!文献より出典
がない経験談をもっとも嫌います。要するに一般化されていない、客観視されて
いないものはだめということです!課題一つにつきほぼ何らかの書物1冊という
ことになります。金銭面で苦しい私は図書館通いや先生に借り物通いで右往左往
しています!
以下に真尾先生の研修会に必ず言われる「Teacher's Roll」を載 せます
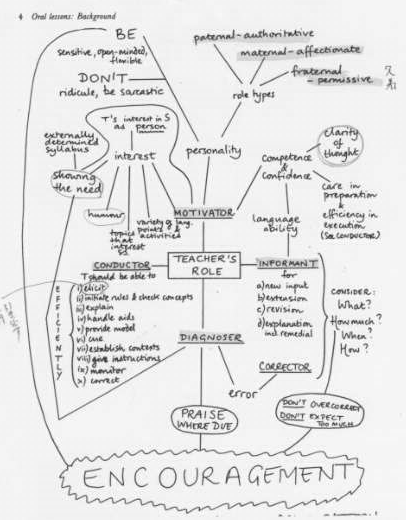
「どんなにすばらしい教授法であっても人間性が問われるときも大きい、逆も 真。」
渡邊先生の過去から現在に至るまでの英語教育理論変遷は大変今後の示唆に富むものでした。特にErecの創設以来のご経験から、今では知る人も少なくなった、CC.Friesとも実際にお会いされている先生です。Audio lingual method に関しては第一人者と言っても過言ではありません。その内容たるや、現在の英語教育への大きな指針を与えて頂きました。
真尾先生は教授になられ、埼玉大学教育学部の看板的存在になられました。相変わらずその毒舌と真髄をつくご講義は健在で県内でも信望がますます高くなっております。現場のご経験のある先生なので現場と理論とをうまく織り交ぜた講義をされるところに、現職教員から多大な支持を受ける原因があります。
1年間の講義も終わり、各先生方はそれぞれのご研究、お仕事に従事されています。
尚、埼玉大学、英語科練、美術科練、音楽練等改築工事のため、ここ数ケ月はどたばたしております。
春には美しい新校舎で、freshman が講義をうけることでしょう。