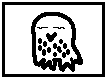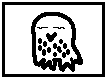
Lecture Note
ここではさまざまな機会に話をした内容あるいはそれに触発されて考えたことについて、
できるだけ簡潔に、各回完結でノートします。
Piaget,J.について
この学者について語ることは、私の心理学履歴について語ることになるので大変長いものになってしまうことが考えられます。それゆえに、簡潔に述べなければなりませんが、最近手に入れた、小田亮さんという方の大変面白い本である「サルのことば」(京都大学学術出版会)にならって「著者自身の学問人生」に沿って述べるのも面白いのではないかと思いますので、ちょっと自分史的にはじめてみます。
Piagetに最初に出合ったのは、心理学からというよりも、大学に入学してすぐに、今はなき青土社の「現代思想」などという雑誌を読み始めていた私としては、「構造主義」というものに対する関心からでした。なぜ構造主義に関心があったのかについては、私の大学にジュリア・クリステヴァの著作を日本に紹介し始めていた枝川先生が総合雑誌「展望」に書かれた論文や、社会思想史の陸井先生の講義も影響したように思いますが、その前に自分でレヴィ・ストロースの「悲しき熱帯」や月刊「言語」を読んでいたからであったように思います。それらを読むうちに、彼らの思想界にPiagetという「心理学者」が異色な存在としていることを知ったわけです。すなわち、構造は「静的なものではない」と主張する学者としてです。
Piagetのいう構造
「構造は機能する中にあらわれる。」私はPiagetがこのようないいまわしを使ったのかは知らないが、少なくとも私の理解する限りでは、彼の構造に関する理解にはこの命題が含意されているはずである。彼にとっての構造は、たとえば人体の構造とか車体の構造とか、建築物の構造ではなく、知能の構造である。構造そのもののみを取り出して確認できるものではないのである。人が物をつかむことから初めて実際に身体を媒体にして外界に関与するプロセスの中に、ある種の整然としたパターンをもった行動傾向が現象してくる、そこにかれは着目し、具体的にものにかかわるという行為の中で機能している身体のなかに、いいかえれば人間が世界と交流し合うその様式の中に、知的な構造を見出したわけである。ここには本有観念など存在しない。「感覚運動」に「心理プロセス」の具体的な展開の萌芽のイメージを当てはめることができたのも、このような彼の根本的なアイデアが反映していることは間違いあるまい。私はある科学者が、素粒子の説明に関して述べた文で、素粒子が素粒子たる性質をあらわすことができるのは素粒子がある運動を展開する場においてであって、決して素粒子そのものにその運動を説明しうる諸要素が備わっているのではないという見方を説明している場面に出合って、Piagetの言おうとした機能するとは、このような要素と全体の力動的な関係を言わんとしたのだなと、独り合点した記憶がある。
彼は模倣する「傾向」を持って人間は生まれてくるが、その「テクニック」を備えているわけではないといった。なぜならそのテクニックは、模倣する相手(=世界)が教えてくれることになるのだからであろう。
いないいないばあ
この遊びをじっくり考えて行くと、人間のこころというものが、いかに不思議なものであるかが、理解できます。この遊びが乳児にとって楽しいものになるには、或る条件が必要です。
物を自分の行為の中に取込んで扱うことができるようになる時期の行動の特徴を「第2次循環反応」と呼びます。自分の身体しか制御対象とできず、手を握ったり開いたりすることしかなかった「第1次循環反応」の時期と異なり、この物を扱うことができる時期になると、ものの一部をみて全体を理解できるようになるといわれています。有名なのは、ほ乳瓶の底をみてそれがほ乳瓶だとわかって欲しがるという行動が見られます。身体運動感覚と触覚、そして視覚が協応関係を形作り、見たものをつかめるとともに見えないものもつかむ態勢に入ることで、見えるものの延長線上に位置付けられるようになると考えればよいと思います。物の世界を扱うという行為のシステムの全体構造のなかに、物の一部の知覚が位置付けられることで、物が独立した刺激物(見えている部位だけとしての)としてでなく、乳児の行為のシステムが機能するための機会原因的位置を占めるようになると見てもよいと思います。すなわちわかりやすく言えば、見えている部分に触発されて見えない部分が感覚運動的に再現される、と言いかえればよいと思います。「心」、「想像力」の芽生えです。
大人からすると不思議なのですが、このように一部が見えていれば全体が行為として予測できるにもかかわらず、第2次循環反応初期の乳児にとっては、物が完全に視界から消えてしまうと、物そのものがあたかもなかったかのように、突然探索的な行為が姿勢や表情の領域も含めて、消失してしまうことです。隣の部屋に行ってしまった養育者は、この世からいなくなったも同然なわけです。最初のころ養育者が視界から消えると泣き止むというのは訴える対象がなくなったということを端的に示しています。
いないいないばあは、なくなってしまったのかという不安と、いやある筈だという期待の入り混じった非常に不安定な状態から、やっぱりあったという確認を通じた緊張の低減をその内容にもっていると考えることが出きるのですが、このような物の永続的な存在というものに対する確信の始まりの時期であるからこそ、それが興味深い、面白い遊びになるものと思われます。
でも、大人同士でこの遊びがおこなわれることはありません。それは、相手が消えてしまったほうがよい場合が多いからかもしれません。大人は対象物であるところの相手の存在の永続たらんことを決して望んでいるわけではないのでしょうか。
「保存」課題
Piaget心理学では「保存」の概念の発達は、前操作期における重要な側面をなします。
ある容器からある容器へと水をうつしても、その量に変化はないという、大人としては常識に思えることも、幼児にとっては必ずしもそうはいかないという有名な「液量保存の実験」を、既にその段階をクリアしているはずの小学生に課してみたところ、数%の子ども達が「間違え」てしまいました。彼らは、最初に二つの容器を比較して二つの容器の水が同じ量であることを確認した後、容器をうつした水のほうが、移さずにそのままにしてあったほうより少ないと判断したのです。
大人と言う存在は、このような「課題事態」の意味をよく理解していて、質問が出されると、「これは、あるひとつの概念の水準を自分が達成しているものかどうかを確認している課題である」とその事態を受け入れ、その「課題」に答えることになってしまいます。わかりやすくいえば、彼らはいくら目の前で容器から容器に水が移されていても、それを目で見て確認しているのではなく、「水とは、形が変わっても量は変化しないものである」という命題でその事態を把握していることが多いのです。彼らにとって現実は命題の集まりでできています。
それでは、小学生の「間違った」子ども達はなぜ間違ったのでしょうか。実は、彼らは実験のプロセスを穴のあくほど見つめ、そしてその当然の結果として、移された方の水が少ないと判断したのです。
あなたも空っぽになった容器に指を入れてみればわかるでしょう。それが濡れているのが。大人はいつのまにか、現実ではなく仮想現実の世界で生きていたのです。それもモニターの中ではなく、目の前の生の世界をそのようなものとしてです。
子どもは「直感的思考段階」という言葉が示すように、目の前の現実に惑わされます。大人は、観念形態に惑わされるのです。
三角形
4歳ぐらいの幼児に白い紙を渡して、三角形を描いたカードを見せ、「この三角形を描いてごらん。」と鉛筆を渡してみましょう。そうすると、幼児はその見本を見ながら、白紙の上に自分が引いた線となんども見比べながら、時には不満足げな表情で、絵を完成させるでしょう。
彼らの多くは三角形の描画に失敗します。たてから横に直角に2本の辺を引くところまでは、何とかできるのですが、3本目が引けないのです。引いたとしても、開いた2つの頂点の間を、一方からもう一方へまっすぐに線をひくことができません。
大人の目からするとどう考えても不思議なこの描画の行動も、この時期の子どもからすると、こうならざるを得ないのです。おとなにとって直線を引く際には、描画しつつある直線の周囲になんら支えは必要ではありません。物差しがないと不安だと言う人もいますが、それはきれいにひこうとするからのことです。大人は心の中にひとつのしっかりしたものさしをもっているので、ある地点に視点を定めると、その視点から一本の直線を生み出すことができるのです。この時期の幼児は、まだ心の中にしっかりとしたものさしができていません。ですから線を引くにも自分の外に支えが必要となります。つまり彼らは、四角形の机の上で、四角形の紙の上で直線を引くことで、最初の2本目までは枠組に支えられているのですが、3本目の線に支えとなるものが存在しないのです。(ちなみに直感的思考段階はこのものさしがひとつできてしまうがゆえに直感的に判断してしまうのです。)
講義をしていますと、この現象にたいして、「それでは三角形の机の上で三角形の紙に三角形を描かせたら、うまく書けるのですか」と質問を受けました。私はこの実験に関する論文にあたったことはないのですが、おそらくそういうことになるのだろうと思います。
今、これを書きながらラジオを聞いていると、国際宇宙ステーションで8時間の宇宙遊泳というニュースが耳に入ってきました。思いますに、支えというのは視覚的な支えもそうですが、重力による上と下という枠組みの身体の姿勢維持を介した支えという側面にも今後注意を向ける必要があると思います。それは心のものさしということの内実を深める上でも必要となるでしょう。無重力の宇宙で育った幼児は、どこを支えに空間の軸をみいだしてゆくのでしょうか。これは今後の課題です。
操作の操作
Piagetが心理学者であるというよりも、発生的認識論の研究者であるということは、彼の理論の視角とそこからくる「限界」を明らかにする上で押さえておくべき事項であるように思います。アインシュタインは「もし、自分が光の速さで運動したならば」と仮定して理論構築を開始しました。物の世界に自己投入しながら、私の関与を極力排してゆくという方向をとったPiagetの思考展開は、ベルグソンの「物質と記憶」からの影響を深く感じさせますが、行き着くところは、一見、私のいない物そのものの世界であり、私の意識からは独立した、他なるものの世界なのです。しかし、このように結果として出来上がった、私から独立した存在のもつ体系的な法則性は、私というものの関与、すなわち特定の時間軸上の特定の空間に、特定の質量を占める存在として、中心化する場をもつことなく存在することが不可能な、私の関与からはじめることを通じてしか、到達することは不可能なのです。先人から学びながら、彼は自己の外界への操作的な関与を通じた、外界のもつ論理数学的な構造の構築、すなわち「操作を操作」してゆくことを通じた人間の認識構造の成立を「構成主義的構造主義」として語ろうとしたのです。アインシュタインと同じくPiagetにとっても、「エーテル」に満たされた「絶対空間」は存在しなかったのです。
でも、その構造を構成する主体は果たして「私」なのでしょうか。Piagetは、私という構造体が私であるところの大事な側面を忘れていました。私は、「あなた」との関係においてはじめて「私」たりえるのだということです。
「どうしようもない」存在
波多野完治という心理学者がいます。戦時中でも防空壕の中でフランス語の文献を読みふけっていたという方ですが、この学者がかなり以前にPiagetの「認識と感情」に関する理論を新書版の本にまとめています。岩波新書で「子どもの認識と感情」というタイトルで出版されています。これを読めばわかるように、Piagetにとって感情とは認識の裏打ちをするような位置付けで研究されるべきものであると考えられていました。自動車のガソリンのような、認識の活動にエネルギーを注入するような、役割をになったものと考えていたようです。
でもWallon,H.という精神医学者は、Piagetのように健常の子ども達を対象にするのではなく、障害児と呼ばれる、発達が必ずしもすんなりと進まない子ども達を対象にしていましたので、情動が一筋縄でいかないものであることに気づいていました。情動は、単に世界にかかわる適応的な行動を支持するのみならず、場合によっては阻害する場合が多いことに注目したのです。われわれはあまりに情動が高まりすぎて、行動がいびつになり、思考が鈍ることがあることを知っていますし、情動の高まりの最たるものである「泣く」という行為に明白なように、その高まりは、外界との関係を遮断してしまいます。泣くと涙がこぼれおち、視界が不透明になります、そもそも目をつぶってしまいます。とにかく泣くことにより、人は「お手上げ」の状態になります。
Piagetにとっての「循環反応」は発達を進めるための繰り返し行動という位置付けが付与されていました。けれどもWallon的解釈では、これは「常同行動」や「強迫的な反復行動」という位置付けを与えられることになります。場合によっては自傷的な状態、自閉的な状態へと悪循環を重ねる場合があります。
このような自己制御の利かない状態に転がり落ちる結果へと導いてしまう情動であるにもかかわらず、Wallonはこの側面を人間にとって不可欠な、人間の本質をなす行動の側面であるという結論に達しました。赤ん坊がいくら泣いても、数センチ目前にあるものさえ、自分で自分の手中にすることはできません。それにもかかわらず、その泣き声を聞きつけた他者は、彼が何について泣いているのかを推測し始めてくれます。「おしめが濡れたのが気持ち悪いのか」、「おなかが空いたのか」、「眠いのか」、「怒っているのか」。他者は単なる「表出」に過ぎない泣き声を「表現」と受け止めて意味づけ、赤ん坊の世界との交渉の橋渡しをしてくれることになるのです。情動はこのような「私」と「あなた」、そして「もの」という三項の要素を、ひとつの意味の場で結びつけることになります。意識や言語の発生から始まる長い人間の知能の歴史にも、この情動が大きく関与しているというのは、意外ながらも事実なのです。
「泣いてなんとかなると思うな」という科白は、「泣いたらなんとかなる」人間社会の真理をはしなくも物語っています。
身体がかかわりあう中にあらわれる心
さてこのへんでPiagetから観点を少し移動して、Erikson,E.H.の視角で人間の精神発達を考えてみようと思います。
Eriksonはいわゆるフロイト派です。フロイト派の特徴は、人間を意識課程のみで行動する存在と捉えるのではなく、前意識や、無意識の世界を含めた精神活動に射程を広げるとともに、生物学的な存在として、その身体でかかわり会う存在として人間を捉えようとします。心理的な活動を、身体的なレベルでの活動から分離させることなく、身体を持ってかかわりあう関係に現われてくる心理的な活動として、心理的現象を捉えようとします。
残念ながら「心」は「心」と直接かかわり合うことができません。もちろんそういう実体があったとしてのことですが、精神的な活動は物質的な形態をとるなんらかの手がかりに媒介されることなくお互いに交信し合うことができないのです。
生まれたての赤ん坊から、お年寄りにいたるまで、人間という生物はそれぞれの年齢に応じて、それぞれの身体をもちます。それゆえ、対人関係のありかたも、そのような身体に規定されて、その時期、あるいはその各々の世代のずれに応じて、さまざまに固有な形態をとることとなります。
心というものが、当初から完成されたものでなく、発生してくるものであるということは、Piagetにおいて一貫して主張されていたことです。それゆえ、そのように発生してくる人間の心の形は、このように年齢に応じてことなる身体とそれによって規定される人間関係、そしてそれによって規定される対物関係のありかたによって規定される、というのがさらにそれを深めた科学的な見方であるといえます。心を前提にしてその交信を云々する古典的な「情報理論」的コミュニケーションの観点では人間の精神活動を捉えることはできないのです。Piagetの考える外界には、他者が存在し、その存在が物とのかかわりをも媒介するというのが前述したWallonの観点だとするならば、Eriksonはその媒介し媒介される関係のあり方が、各々の年齢で、各々の身体的な条件に応じて変わってくる、更に付け加えればそれを性的な「精神エネルギー」が方向付けるという観点を持ち込んで、対人関係一般という抽象的な観点から1歩踏み込んだ精神発達の理論を展開した、というのが順当な位置付けであると思われます。人間の心はそのような具体的な現実の諸関係の総体として、具体的な姿をあらわすことになるのです。
二つの器官が担う異なる関係
人間には消化器官の両端に外界に向けて開かれた器官が2ヶ所あります。一方の一般に「入口」とみなされている側は、主に食物が外部から内部に向かって移動して行きます。他方の一般に「出口」とみなされている側は、主に消化された糟ともいえるものが、内部から外部に向かって移動して行きます。
抽象化すれば、これはよく似た機能として済まされてしまうのですが、こと人間社会でこの両機能が実行に移されることを考えると、見方はまた異なってきます。
人間は身体を持っており、生後1年を通じて、寝かされている存在から、自分で掴み、立ち上がり、移動する存在として、その運動の様相も急激な変化を経験します。それに伴い、これまで「受け入れる」ことにおいていかに他者と渡り合うかが問題だった対人関係が、「自分からやろうとする」ことにおいて、他者と渡り合う対人関係へと移行してゆきます。今まで「吸い込む」ことに使われていた口が、「噛み切る」ことに使用されるとともに、ことばを「紡ぎ出す」という新しい機能を担い始めます。
寝かされた状態で、垂れ流しを許容されていた乳児も、養育者の意図を裏切って、意外な動きを見せ始め、厄介な存在としての側面が肥大してゆきます。「自分がやりたい」という欲求の表われは、同時に「自分でやりなさい」という外部からの要求を招来します。人間の文化では、生活習慣というものがあります。食物は調理され、食器に並べられ、定時に提供されます。排泄物も、適当な量を、定められた容器に、定期的に提供することが、その清潔な生活空間を保持するために、要求されます。定期的に食物を供給するのは養育者の側ですが、定期的に排泄するかどうかは、本人が調節しなければなりません。
入口を通じては「吸い込む」ことをめぐる関係であったものが、出口を通じては「保持する」ことと「手放す」ことめぐる関係として、自分とは異なる他者の要求を考慮に入れながら、かつ自分の主導のもとにおいてそれを実行してゆかねばなりません。
フロイトが目をつけた二つの器官を通じた精神エネルギー充当の関係を、エリクソンはこのように、社会的な関係一般にわたる普遍的な側面の考察を通じて捉えなおしました。
このようにして、いままで無私の奉仕を受けることで、融即の世界に漬かり込んでいた乳児も、養育者が「私には私の生活がある」と本音をちらつかせ始めるころになると、同時に「私にも私というものがある」と自覚し始めます。「自我領域」というものが生まれるのです。
幻想の中で役割を担う
「私がしたい」という気持ちには、「私が」という気持ちが前面に出ています。「第1次反抗期」といわれる時期の幼児の「反抗」は、「あなた」がやるのではなくて「私」がやりたいのだ、というイニシアティブの問題が葛藤の前面に登場しています。「ごはんたべなさい」。「いや」。「もうほしくないの?」。「いや」。「それじゃかってにしなさい」。「いや」。どこまでいってもいやなのです。なぜなら、行為の内容ではなく、行為の主体が誰かということが問題になっているからです。
しかし、その「私」の担うのが、どのような役割関係のなかでのどのような行為なのか、ということに次第に関心が向けられてゆきます。生後1年目の(相互に対称的な)ボールのやり取り関係のなかで、私がボールを持っているのが楽しいのではなしに、ボールをやり取りすること自体が楽しくなっていったように、人間活動における相互関係の中においても、個々の行為に自分も関与するという次元ではなくて、各々が相補的な関係にある役割というもののひとつを自分が担い始めることに関心が向けられるということです。関係を取りしきる規範は養育者など、権威のある他者から絶対的なものとして幼児に降りかかります。Piagetの直感的思考期が示していたように、心の中に何らかのものさしができ始め、それが行為を規制する規範として機能し始めるわけです。
ここでの出すぎた真似は、それゆえ「恥ずかしい」というさらし者にされた感覚ではなく「悪いことをした」という、規範に照らした罪の感覚です。
ただ、おとなの世界に介入しようとするといっても、実質的にそれが可能になっているわけではありません。大人には大人の世界があり、自分はせいぜいそれを外側から羨望のまなざしを向けるにとどまる、という位置関係をとることを余儀なくされます。大人達の果たしている関係は理想の対象に置きかえられることになり、それにかわって幻想の中で満足すること、すなわち「ごっこ遊び」に甘んじることになるのです。エディプス王のように実の父親を殺して、自分がそれにとって代わることは、現実にはできないのです。
物の世界の無機的な法則
「あなたたち」と「私」との関係において葛藤を覚える時期は、「勤勉性」と「劣等感」が葛藤の主題となる次の時期には、一見、潜伏してしまったようになります(それゆえフロイトは「潜伏期」と名づけました)。子どもは親の手から離れて、次第に同朋との活動を重要なものとして位置付けるようになります。「わたしたち」の世界の誕生です。ここでは「父権」的な規範が上からあるいは前から立ちふさがるように行動を規制するというよりは、集団活動を通じて規範を手の内にすることで規範が実現されることが積極的に追求されることになります。彼らは特定の他者との葛藤というよりは、物の世界の無機的な法則性を自分のものとすることを、わたしたちの中で確認し合うとでもいえるような、規範をめぐる葛藤関係が展開します。
あなたが実現したことを、私も実現することで、その場にいる存在感を確認しているとでも表現すればよいでしょうか。特定のキャラクターグッズをAさんが持っていれば、私も持っていたいし、Bさんが興味を持つ世界には私も興味を持っていたいという、自分を図るものさしを、自分の独自性に求めるのではなく、集団内で価値をもつ一定の基準に求めることにおいては、まだまだ「近代的自我」というところには至っていないのかもしれませんが、遊びの中では、他者の特殊な条件に応じて、規範を融通を利かせて変更するということも可能になります。ハンディのある年少児たちには、ゲームのルールを変えてでも参加しやすいようにするという、ルールへの態度に関する柔軟性が示されるようになります。
ただ、今日の日本の社会を考えてみますと、そのような集団の活動は、地域社会では崩壊しつつあり、「学校」という世界のみが唯一集団活動を組織的に維持する場として機能しているのが現状です。それに「塾」という場が付随的かつ補完的に機能しています。このような状況の中では、自分や他人の「勤勉性」を評価する基準に一元的な尺度があてがわれてしまうことが必然的に加速化し、いわゆる「学歴」や「偏差値」という人間の特性の一側面のみが過大に評価尺度として機能することになり、そこから「落ちこぼれる」者は、社会の脱落者的な位置にいるという感覚を味わうことになります。
今日、イリイチ,I.の主張した「学校化」された社会が、その後の青年・成人期にわたるまで、われわれの生活に染み込んでしまっているという現状は、子どもの心理的な次元での構造特性の分析を進めるよりも、「生産性」を唯一の原動力として機能してきた現代社会という組織の構造を分析してみることで、より真相が明らかになるのかもしれません。もちろんそれを乗り越える条件も同時に醸成されているには違いないのでしょうが。
アヴェロンの野生児
フランソワ・トリュフォー監督の「野生の少年」には、人間になるということが決して人為的に行われれば可能になるというものではなく、ごく普通の人間の家庭でごく普通の人間関係のなかに自然に過ごすことを通じて可能になるのであるという主張が込められているような気がしてなりません。
この映画に登場する3人の人物、イタール先生、ゲラン婦人、ヴィクトール少年、はそれぞれが父親、母親、子どもを代表していますが、イタール先生はどちらかといえば、父親というより純粋な教育者であり、ゲラン婦人は、母親というより、母親以上に少年に愛情を注ぐ保母さん的な位置を演じているように思います。
私が気になったのは、ヴィクトール少年が庭でのこぎりを挽いている時に、帰宅したイタール先生が、彼の仕事を中断させて、お勉強の時間にはいったというところです。イタール先生にとっては、お勉強の時間が唯一、人間の世界に入るための唯一の経路とみなされているような気がするのですが、この映画で監督は、ヴィクトール少年は、どちらかといえば、ゲラン夫人との、食事や仕事の手伝いなどを通じて、また、同年齢の子ども達と遊ぶことをつうじて何かを学んでいることを、それとなく描こうとしたような気がしてなりません。少年が、一度はイタール先生に、もう一度はゲラン婦人に示す、相手の手をとって自分の顔を撫でさせる「クレーン動作」のシーンは、彼が決して知識を仕付けられたからでなく、イタール先生やゲラン婦人との情動的な交流を通じて、ともに家族的な関係のなかでお互いが必要な存在として生活を共有することを通じて、人間になっていったのだということを示しているような気がしました。
BACK to Owl's Report HOME PAGE