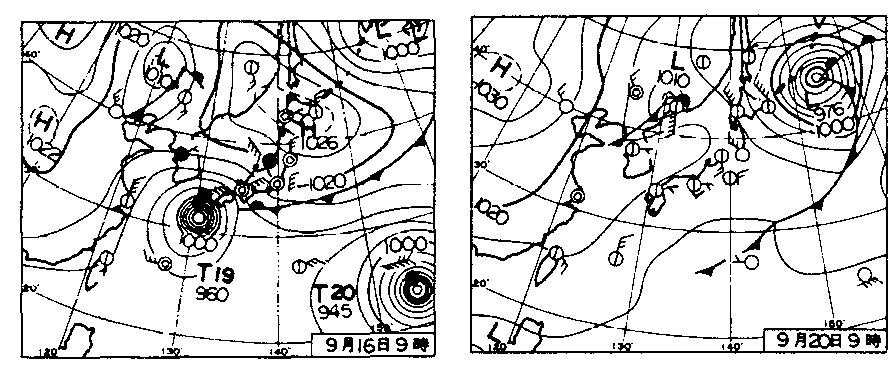
Yoshio MIYAWAKI・Hiroshi Abe:Record of Chinese Goshawk at Takeyama,Yokosuaka City, Kanagawa Prefecture
アカハラダカAccipiter soloensisはハイタカ属の小型のタカ類である。朝鮮などで繁殖し、フィリピンなどで越冬するが、日本では主に渡りのコース上である九州地方で、春と秋の渡りの時期に観察される(森岡ほか、1995)。東日本では稀であるが、愛知県伊良湖岬では毎年数羽から数十羽、年によっては100羽以上が秋の渡りの時期に観察されている(川田・藤岡、1995)。 神奈川県内では1991年9月23日に横須賀市峯山での記録があるが(稲森、1991)、写真などによる記録がないこと、単独の観察者による観察であることから、日本野鳥の会・神奈川支部からは正式な記録として認められていない。 筆者らは、横須賀市武山において1997年と1998年に合計4例のアカハラダカを観察し、鮮明な写真による記録はできなかったものの、複数人による詳細な観察と、不鮮明ながらホームビデオによる撮影に成功したので報告する。また、過去の天気図から4例中3例が、アカハラダカを観察したほぼ4日前に、九州地方の渡りルート付近を台風が通過していることから、この関連の可能性について述べた。
観察地は三浦半島の中央よりやや南に位置する、横須賀市武山(標高200.4m 北緯35°13' 0" 東経139°39' 30")で、山頂展望台からの視界は、北西方向を除く270°以上の広範囲を望むことができ、眺望は良好である。 筆者らは、当該展望台で毎年秋期にサシバを中心とするタカ類の渡りの調査を実施しているが、今回の観察例はいずれもこの場所から観察したものである。 観察には10倍の双眼鏡と、20倍程度の望遠鏡を使用した。なお、1991年に観察された峯山は、武山の西北西約7kmの地点である。
4例の記録を表1に示した。表1.アカハラダカの観察記録
(付表)アカハラダカの観察記録 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山頂の西側の高度210m(目の高さ)くらいをパタパタはばたく感じで北東へ通過。 |
外側初列風切の先半部が黒い。下面は白っぽく、胸の辺りが淡い赤色。上面は青灰色でハイタカなどと比べて青味が強く感じた。 |
宮脇・川島清氏 |
|
|
|
|
|
|
|
展望台の真上、高度220m(観察者の10m上)くらいを翼をややすぼめてゆっくり滑翔し、西へ降下。 |
下面は白っぽく、下雨覆は殆ど黒斑がない。ただし、不規則に小さい黒斑が見えた。翼先は成鳥ほどではないが外側初列風切が影のように黒っぽい。 |
阿部・宮脇・ほか |
|
|
|
|
|
|
|
山頂の西側斜面より、旋回しながら上昇。高度500mくらいまで上昇し北西へ滑翔。(2)の個体と同一と思われる。 |
(2)の特長のほかに、シルエットはツミやハイタカと比べ、翼の先が尖り、後縁が直線的に見えた。ほかの観察者によると、尾羽に黒い横帯が4本見えたという。 |
阿部・宮脇・ほか |
|
|
|
|
|
|
|
山頂の西側斜面より、旋回しながら上昇、高度300mくらいをゆっくり西南西へ滑翔。 |
(2)(3)の特長のほかに、初列風切の外側4枚が突出して分裂していた(撮影したビデオより解析)。 |
宮脇・小林正史氏 |
記録された4例はいずれも飛翔中の個体を観察したものである。飛翔中のハイタカ属の識別には慎重を要するが、付表の形態記録から以下のとおりアカハラダカの特徴を備えており、観察個体はアカハラダカとして間違いない。 観察例(1)では、外側初列風切の先端部が黒かったが、これは本種成鳥の特徴である。観察例(2)(3)(3)では、下雨覆がほとんど無斑であったが、これは本種幼鳥の特徴である。観察例(4)では、初列風切の外側4枚が分裂しているのが確認されたが、この分裂はハイタカでは6枚、ツミでは5枚であり、本種と同定する根拠となる。
過去の天気図をもとに、アカハラダカの渡りと台風の関係について考察した。(1)の場合(1997.9.20)1997年9月15日に九州の南の海上で停滞していた台風19号は、翌16日九州枕崎に上陸、日本海を北上して低気圧に変わった。一方台風20号は、18日、八丈島の東の海上を北上、19日には、関東の東沖を足早に北上し、20日には北海道の東で低気圧に変わった。二つの台風が相次いで接近し、19号が九州を通過して日本海に抜けた4日後に観察されている。(図1)(2)(3)の場合(1998.10.4) 観察された4日前の9月30日に、台風9号が玄界灘を通過、翌日に日本海で低気圧に変わっている。(図2)(4)の場合(1998.10.9) 観察された4日前の10月5日前後の九州地方の天候は安定しており、この場合の台風との関係は認められない。(図3)また、文献3の場合、アカハラダカの見られた1991年9月23日の4日前の9月19日に、台風18号が四国沖から房総半島に近づき、渡りルートを直撃したわけではないが、福岡では風力5の強い北の風が吹いていた。(図4) この様に武山付近でのアカハラダカの出現記録の4例中3例は、その4日前に九州の渡りルート付近を台風が通過、あるいは台風による強風が吹いており、台風との関連が考えられる。筆者等には気象学の知識が乏しいため、詳しい天気図の解析は困難であるので、今後専門家の協力による詳しい解析を期待するとともに、データの蓄積を図っていきたい。
天気図の転載を快く許可していただいた、日本気象協会管理本部 与五沢「気象」編集担当、小学館編集部 野上「10年天気図」編集担当の両氏に感謝いたします。
稲森但,1991.フィールドノート アカハラダカ.はばたき,235.日本野鳥の会神奈川支部.川田隆・藤岡エリ子,1995.1994年伊良湖岬の渡り鳥調査報告書.7pp.伊良湖岬の渡り鳥を記録する会,森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男,1995.日本のワシタカ類.98-107pp.文一総合出版.森田正光・森 朗,10年天気図.小学館.日本気象協会編.気象年鑑 1998,1999年版 .
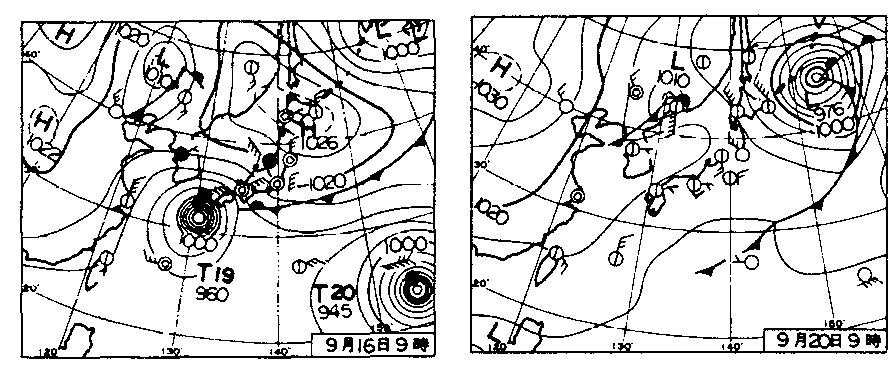
図1.1997年9月16日(左)および9月20日(右:観察日)の天気図(気象年鑑による)
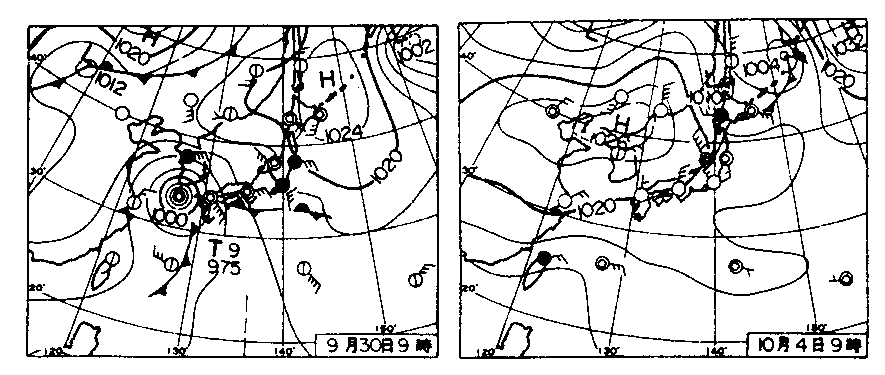
図2.1998年9月30日(左)および10月4日(右:観察日)の天気図(気象年鑑による)
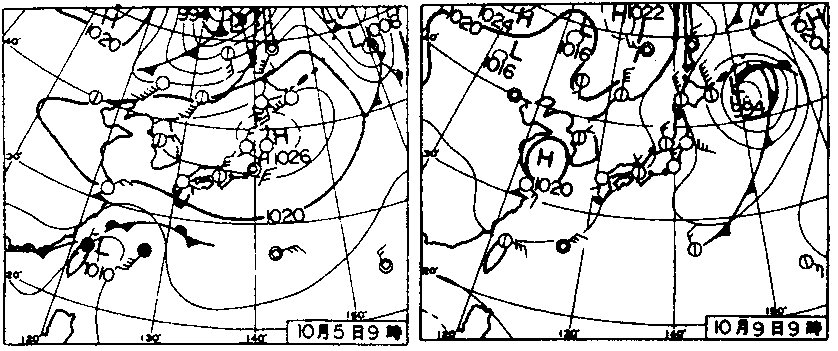
図3.1998年10月5日(左)および10月9日(右:観察日)の天気図(気象年鑑による)
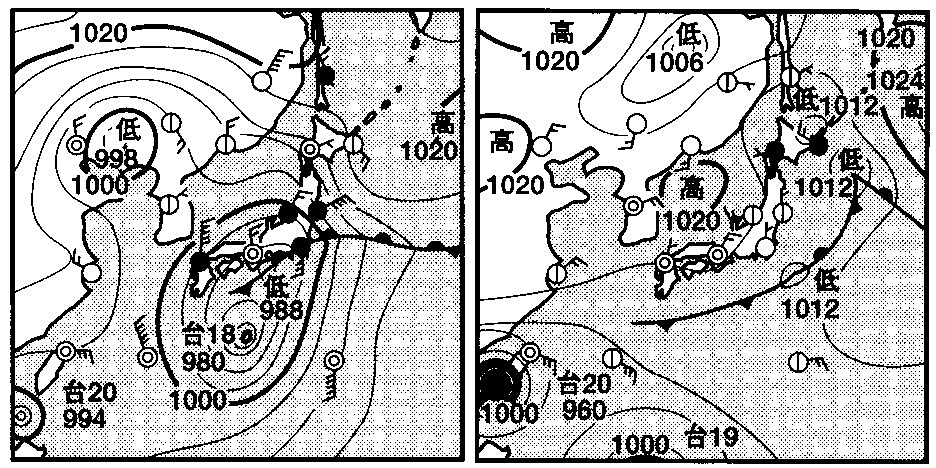
図4.1991年9月19日 (左)および9月23日(右:観察日)の天気図(森田ほか1996による)