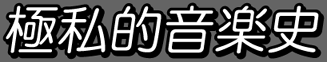
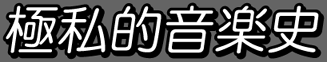
|
僕の音楽形成に最も大きな影響を与えたのは多分The Beatlesであることは間違いが無いと思う。しかし、自覚して聴き始める以前、フォーククルセーダーズ(以下フォークルと略す)という「あんぐらふぉーく」グループが無視できない存在だった。僕の音楽体験としてたぶん、最も古い記憶はフォークルのシングル「こぶのないラクダ」という曲だったと思う。たしか「帰ってきたヨッパライ」(もともとアンダーグラウンド−今で言う "インディーズ" )
が意表をついた大ヒットになり、あわててでっちあげた第2段シングルなんだと思う。 曲の作りは完全にヨッパライを踏襲したコミックソングで中近東風のアレンジがおかしくて、幼稚園に入るか入らないかの僕は一日に何十回となくレコードをかけて聴き狂っていた。(当時5歳くらい?)ちなみにB面はいまだに歌い継がれている名曲「悲しくてやりきれない」だった。5歳のガキにはこういった叙情性などわかるわけがなく、B面はきれいなもんだった。もちろんA面は幾度となく針を落としたため、擦り切れてキズだらけ。 僕が物心ついたころの世相は(1968年前後)ちょうどベトナム反戦運動と全共闘がもりあがり、同時にアメリカ産のPOPカルチャーが大挙して押し寄せる最中だった。しかし、この時代を語るときに必ず出てくる決まり文句
フォークゲリラ・EXPO70・浅間山荘事件・東大安田講堂陥落・アポロ月着陸・太陽の塔と過激派による占拠・三波春夫の笑顔と「♪こんにちはぁ〜♪こんにちはぁ〜♪世界の国からぁ〜♪」の歌声・♪ブルーブルーブルーシャトー♪・小川ローザのふともも・そして「あんぐらふぉーく」・戦争を知らない子供たち…
等々がほぼ同時期に発生し、また相互に密接に関連していたなんていうことはその後10年ほどして高校生になったころにやっと理解できたことだ。
ということで僕の音楽体験は北山修&加藤和彦の二人に強く影響されていた訳だ。ものの見方としても、角川文庫ででていた北山修のエッセイ集にけっこう影響されていたように思う。当時反戦とか反体制といえばとにかく「ハンタイ!」と叫んでデモ行進かゲリラという時代に、いくぶん気弱だけれどものすごく醒めた目が貫かれた文章が新鮮に思えた。
|
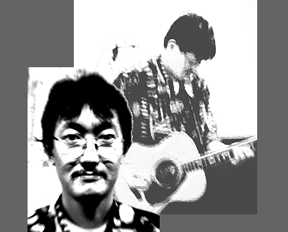
|
|
古川(AG・ハープ)
|
|
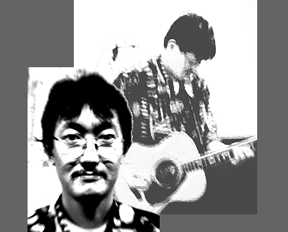 |