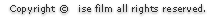まるで蒸気機関車のように白い息を吐き出しながら、坂道を登り切る。
汽笛を鳴らしたい思いで空を仰ぐ……。
ガキの頃も今も、冬の朝の気分はほとんど変わらない。
年末から年始にかけて、
新作『妻の病−レビー小体型認知症−』の東京での劇場公開があり、
予想を遥かに越えるお客さんが足を運んでくれた。ありがたい。
いつも以上にアンケートの反応がよく、私信のような内容が多いのに気づいた。
「実は私の母が認知症で……」
「もしも妻が(夫が)認知症になったらと思って……」
「私自身、心の病を抱えていて……」
私のいつもの映画に増して、『妻の病』は観る人一人ひとりを写す鏡になっているようだ。
闇の中でおよそ一時間半、それぞれが自分の記憶をたぐり寄せ、自分自身の物語を紡いでいる。
“自分だけの物語を語りたい、聞いてほしい”という思いで、
映画を見終えてすぐに筆を取ってくれたようだ。
どんなビックリするような事件、物語より、誰にとっても切実なのは、
自分の身のまわりに起こる些細な出来事なのだ。
マス社会になって、テレビや新聞、雑誌、さらにはインターネットの中に、人々は物語を探したがるけど、
本当は、自分自身のことが最大の関心事なのだ。
良し悪しの問題ではなく、きわめて自然に普通に……。
それでいいとも思う。
切実な「物語」は、そこから始まる、と私は思う。
映画『妻の病』のプロローグで、
主人公・石本浩市医師が私に(カメラに)数年来悩まされている妻・弥生さんの認知症の症状を語りかけているその時、
携帯電話に知人から「東日本大震災」で混乱する状況のメールが入る。
象徴的だと思う。
その時、日本中、世界中を揺るがした未曾有の災害以上に、
石本医師にとって妻の認知症の日々の方が切実で重いのだ。
そのように人は生きていると思う。
私にとってドキュメンタリーとは、
そんな一人ひとりの「物語」に触れることだ。
知ったかぶりをせず、聞いた風なことを言わないで、
ただただ映像の記憶を信じて、そのことだけを「物語」ることだ。
今回もまた厳しい批評もあった。
「説明が足りない……」
「ドキュメンタリーとして甘い……」
「こんなことで認知症問題は前へ進まない……」
これまでのどの作品も、同じようなことを言われ続けてきた。
でも、映画が観た人一人ひとりの「物語」として起ち上がれば何よりだと思う。
たった一人の人にでも届けば、それで充分ではないか。
「あなたに誉められたくて」という急逝した高倉健さんの名エッセイがある。
健さんがオフクロさんに誉められたくて映画を創り続けてきたという想いを綴ったものだ。
私も「あなたに誉められたい」と思う。
誉められたい「あなた」に向かって創り続けているようにも思う。
健さんは、オフクロさんに心配され通しだったけど、誉められたことはなかったらしい。
そんなものかもしれない。
浅い春、
二月から、自作『妻の病』と前作『シバ 縄文犬のゆめ』が、
広島、横浜、静岡、金沢、浜松、京都などのミニシアターで連続上映される。
春には全国各地での自主上映を拡げていきたい。
私にとって上映に取り組んでくださることは、自作の映画を「誉めてくれる」ことなのだ。
応援よろしくお願いします。