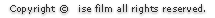ようやくと作品が一本仕上った。
作品を子供に例えたら、もう何人兄弟になったのだろう…。
産みの親であり、育ての親でもある、
自主製作・自主上映に取り組み続けてきたカントクは思う。
大家族になってきたなぁ…と。
創るたびに身を削ってきたというよりも、
創るたびに、撮らせてもらった人や自然や物たち、手がけた作品(子供達)から、
大切な何がしかをもらい、逞しくなってきたように思う。思いたい。
作品を創ることこそが、ヤワな自分を鍛えることになるのだ。
時々、「伊勢さんが自分自身で気に入ってるのは、どの映画ですか?」と聞かれ、
とまどうことがある。
私は、どんなに酷評され無視された作品でも、
ごく一部にしか観られることのないPR映画のようなものでも、どれも気に入ってるから、
子供達の中で、どの子が一番可愛い?と聞かれたって、答えようがない。
出来の悪い子の方が可愛い、ということだってあるもんね。
社会的には、何の評価を受けることがなくても、
ひとつひとつが創らないわけにはいかなかった「いのち」ある作品達だ。
産まれ出たばかりの作品は、
『妻の病 –レビー小体型認知症—』
可愛い子供です。
映画『風のかたち』で出逢った15年来の友人、
四国・南国市に暮らす小児科医の石本浩市さんと、
若年性認知症を患う奥様の10年間に及ぶ、病との日々を記録したドキュメンタリーだ。
こんな風に紹介すると、重く暗い映画のように感じるかもしれないが、
まったくそんな作品ではありません。
「ラブロマンス、だね…」と試写で観た友人が言ってたけど、
たしかに認知症の映画というよりも、石本夫妻の愛情物語と言っていいかもしれない。
もちろん、ただ甘いだけではなく、充分にホロ苦いラブロマンスだけど。
社会的な「問題」を描くのが当然だと思っているジャーナリスト、
ドキュメンタリスト諸氏からみたら核心から目をそらしていると思うかもしれないが、
愛や孤独を描くことこそ映画の重要な役割だと思うのだ。
「問題」を観るのがドキュメンタリー映画だと思っている人達には、
映画の中に何も「答え」が見当たらないから、物足りないと思うかもしれないが、
映画はお勉強じゃないんだからさ!と言いたい。
いつものように「ひとりでも多くの人に観てもらいたい…」と思って、
これから上映活動に取り組むのですが、「誰にも観せたくない…」と思ったりもする。
創ることと観てもらうことの不思議を、ずっと生きてきてキャリアを積めば、
きっと割り切れるもんだと思ってたけど、ますます、その矛盾は深まっていく。
どおいうことなんだろう?
何が何だか、ワカラナイ。
完成した、とは言っても、越えねばならない重要なハードルがまだいくつかある。
プロデューサーも兼ねているから、出来上がってからの方が、
ストレスのたまるハードルが多いかもしれない。
ようやく頂上まで登り切ったと思ったのに、まだまだ続きがあるのだ。
山登りと一緒だ、下山するまでが山登り。
むしろ下りの方が危険なんだと、友人の山男は言っていた。
その山男に教えてもらったように、小さな歩幅で、慌てずにリズミカルに、
一歩一歩着実に歩くべし。生きるべし。
簡単なようで、これがなかなか難しい。
まわりのスタッフの力を借りながら、もうヒト踏ん張り。
「悠々として 急げ」好きな言葉だ。