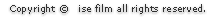細谷亮太医師の郷里、
山形・河北町での『大丈夫。-小児科医・細谷亮太のコトバ-』上映会場は
超満員800人を超える観客で埋まっていた。
画面に、もう今は無い築百年の木造住宅、細谷医院の外景が登場すると、
会場がザワめいた。
更に、もう今は居ない細谷先生のお父さんの診察風景が紹介され、
その表情のクローズアップが映ると、
会場全体が大きなドヨメキに包まれた…
とても感動的な反応だった。
長い長い時間、街の多くの人々を見守って来た小さな医院と医師。
細谷先生のお父さんは、90才を過ぎるまで、開業医として活躍された町医者だ。
70年に及ぶ地域医療の実践で、郷里の人々の絶大な信頼を受けていたにちがいない。
その反応に、細谷先生もとても嬉しそうだった。
自分の場所で黙々と仕事をする人の存在こそが、信頼に値する…
小児医療をめぐってねばり強いかかわりを続ける
細谷亮太医師の血筋に触れさせてもらったような体験だった。
細谷先生同様に、私も又、父親が同業、記録映画の仕事をしていた。
伊勢長之助という編集者だった…
もう40年近く前に逝ってしまったけれど。
父、長之助も細谷先生の父上同様に、黙々と仕事をする職人気質の映画人だったと思う。
私が3才のときに家を出てしまい、その後離婚してしまったので、
私には、ほとんど父と暮らした記憶がない。
そのせいもあって、私は父のことをよくわかっていないと思う。
でも、まわりの友人達の様子を見ても、父親のことをよくわかっている
という奴はあまり居なそうだから、
父親とは、そんなものなのかもしれない。
それでも、同業なので、父の仕事ぶりを先輩の映画人に聞いたり、
何本かの作品を観たりして、想像することは出来た。
記録映画の中でも、文化映画・PR映画という地味な分野での仕事が
ほとんどだったので、一般の人にはほとんど知られていないはずだ。
ともかくよく仕事をした人、少なくとも、
普通の映画人の三倍は仕事をしたと思う。
借金に追われて、ということもあったけど…
その辺りは私も似てなくもないか。
編集の仕事に関しては、絶対の自信を持っていた。
構成力があり、リズムがある。
映像をよく知っていたのだと思う。
その父が、戦時中インドネシアで報道班員として国策映画を創っていた時代がある。
もうずいぶん前から、戦争の時代の父のこと、
その時代に創った作品を少しずつ調べていた。
オランダのフィルムセンターにある父が手がけた作品を観に行ったりもした。
今月末一週間ほどインドネシアに行き、新たに見つかった父が編集したと思われる作品を
観せてもらいに行こうと思う。
今頃になって、父のこと母のこと、とっくの昔に居なくなってしまった親のことを
もっと知りたいと思うようになった。
妙なもんだ。
親というのは、子どもたちの思いの中ではじめて親になるのかもしれない。
映画は観る人がいて、はじめて映画になるように…
大切なモノゴトは、そのコトに思いを深める人がいて、はじめてくっきりと輪郭をあらわすのだ。
撮影して、編集して、音を入れて、上映して…
相変わらずドキュメンタリーな日々が続く。
私も又、父と同様に他の人の三倍くらいは働かなければ。
やりたいことが、やらねばならないと思っていることが、たんとあるから。