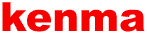
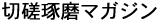
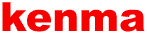
|
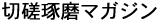
|
(当初、『ミックを憐れむ歌』という作品を掲載させて戴く予定でありましたが、都合 により変更させて頂きます。ご了承ください。)
話は今から20年も前にさかのぼる、僕がまだ小学校三年生の頃の事だった。
ある日おやじがまたいつもの様に唐突におみやげを持って帰ってきた。
おやじのおみやげは大概の場合、怪しい物が多かった。
回しているうちにバラバラになってしまうルービックキューブや、「なめんなよ」の パッチ物「なめるなよ」、また全然コンパクトじゃない持運びに困るような「ウオーク
マン」などなど・・・。
そんなおみやげを持って帰る度におかんは冷たく突っ込んでいた。
「そんなん どこで拾ってきたんや・・・」
しかしこの時は違っていた。
そのおみやげは新品の、まだ皮の匂いがプンプンするキャッチャーミットだった。
僕は本当にうれしかった。
「おとうさん。どうしたん。このキャッチャーミット!」
「どうしたんってお前、キャッチャーミット言うたらドカベンやないかい!」
なんだか今改めて文章にしたら全然辻褄が合っていない会話だったが、その時僕はお やじの気持ちが痛い程よくわかった。
当時「ドカベン」は僕らのヒーローだった。
ちょうど水曜日の7時からのテレビのオンエアが始まったばかりの頃で、学校に行け ば「岩鬼がどうした」「あの時の里中がどうだ」「この前の不知火のボールはキャッチ ャーミットに入るまで10分くらいかかってたぞ(冷めた奴もいたんです)」などなど 「ドカベン」の話題でもちきりだった。
放課後ソフトボールをやろうものなら、皆の希望ポジションは「山田太郎」のキャッ チャーに集中していた。
そんな時代だったのでそのキャッチャーミットのおみやげは涙が出る程嬉しかった。
「おとうさん ありがとう。」僕はめずらしく素直におやじに対して感謝の意を表明 した。
おやじもうれしそうだった。そしてちょっぴり得意気にこう言った。
「な。ええやろ それ。 でもなそのままやったら硬うて使われへんど。」
「ほんまや。僕の力やったら締まれへんわ。どうしよう。ボール掴まれへんわ。」
僕は困惑した。せっかくのキャッチャーミットもボールを掴めなければ意味がない。
おやじはまるで僕のそのセリフを待っていたかの様に、さらに得意気に鼻の穴を膨ら ませて、ドラえもんが「タケコプター」をポケットから出す様な感じである物を取り出 した。
「そんな時にはな。な。ドロースや。これをビャーっと塗ってやなあ、ボールをはさ んでミットごとぐるぐる巻きにする訳や。ほんならな。な。明日になったら柔らこうに なってるわ。」
「ほんまに?良かった。明日僕、放課後試合あるんや。それやったらその時使えるわ 。やったあ!」
(僕のおとうさんはなんて素敵なおとうさんなのだろう!)
当時僕は不覚にも本気でそう思ってしまった。
(これで明日の試合はバッチリや! これで僕もドカベンや!)
その後は親子二人がかりで「ああでもない こうでもない」と言いながら、その新品 ミットにドロースを塗りたくった。
当時の僕には全く理解はできなかったが、おやじは「南海の鶴岡監督はなあ・・・」 とか「東映フライヤーズはやなあ・・・」とかいった話を嬉しそうに僕に聞かせながら だんだん柔らかくなっていくキャッチャーミットをパンパン叩いていた。
翌日僕はそのキャッチャーミットを大事そうにかかえて、しかしちょっぴり皆に見せ びらかしながら登校した。
「雁金、それキャッチャーミットやん!」「かっこええなあ!」道すがら出会う友達 はそう言って声をかけてきた。
僕は有頂天だった。
もう授業が終わった後のソフトボールの試合の事しか頭の中にはなかった。
普段でも先生の話をまじめに聞いているタイプの子供ではなかったが、その日は特に うわの空でただただ終業のチャイムが鳴るのだけを待ち焦がれていた。
そしてやがて、待ちに待った終業のチャイムは鳴った。
僕らは一斉に運動場へ駆け出した。
(さあ、ソフトや! 試合や! ドカベンや!!)
僕は普段なら試合が始まる寸前まで何をするでもなくボーっとしているのだが、この 日ばかりは居てもたっても居られず、自ら率先してベースやバッターボックスを地面に 書いたりして、一刻も早く試合が始められるように全面的に協力した。
(さあさあ!早く早く!)
僕は、はやる気持ちを押さえるのに必死だった。
僕らの試合は、試合といってもまあクラスの中の言わば紅白戦の様な物でクラスの中 で二つのチームを作って行なうといった形式をとっていた。
堺の というより恐らく僕が通ってた小学校だけのシステムかもしれないが、僕達の間では一つの集団の中で二つのチームを作って何かゲームをする場合、そのゲームに秀でた二人が皆の間からまず選出され、その二人がジャンケンを行ない、そのジャンケンに勝った方が自分の必要とするメンバーを指名するという、まるで小さなドラフトの様なシステムをとっていた。
このシステムは、僕らの間では二人がメンバーを取り合う事から、「とーりー」と呼 ばれていた。
(とーりーとーりーじゃっしんやー の掛け声でじゃんけんを行なう・・・誰が考 えた掛け声やろう? 今だにナゾである)
その日も通例にしたがって、運動神経のいい二人がまず皆の間で選出された。
そして「とーりー」が始まった。
僕はワクワクして新品のミットを拳でパンパン鳴らしながらその「とーりー」を眺め ていた。
当たり前の事だがこの「とーりー」では上手な者から順に指名されていき、後になれ ばなる程下手な者しか残らないシステムになっていた。
僕は最初はニコニコしながらその様子を見ていたのだが、笑いがだんだん凍りついて いくのが自分でもわかった。
理由は言うまでもなく、自分がなかなか指名されないからである。
僕は言いようもない不安に襲われた。そしてその不安は的中してしまった。
しかも最悪の形で・・・。
その日、その試合の為に集まったクラスのメンバーは全部で19人であった。
言うまでもなく、野球の試合は18人で行なわれる(9人×2チーム)訳でその日の 状況から言えば、どうしても一人余ってしまうのである。
僕はまんまとその一人になってしまった。誰からも指名されなかったのである。
僕は遅まきながら、そこで「自分が下手くそである」という避けようもない現実に直 面して、呆然と立ち尽くしてしまった。
(ちょっと待ってくれよ・・・。それはあんまりやろう?)
しかし悲劇はそれだけでは終わらなかった。
僕らのシステムでは、この時の僕のように最後まで誰にも指名されずに残ってしまっ た人間は「いるか いらんか」に回されるのである。
「いるか いらんか」とはつまり「その人間が必要か?必要ではないか?」という意 味で「とーりー」と同じように前述の二人がジャンケンを行い、そのジャンケンに勝っ た方が「残った人間が いちおう補欠として必要か必要でないか」を宣言するのである。(いつの世も子供の世界は残酷なのである)
僕はそれに回されてしまったのである。
僕はもうその時点で試合には出られない事が確定していたので、うつろな目でその様 子を眺めていた。
数回の「あいこ」の後でやがて片方の奴がジャンケンに勝った。
そして宣言した。「いらん」と・・・。
僕はその瞬間にすべてを理解した。
僕は試合に出られないばかりか、補欠としても必要とされていないのである。
「いるか いらんか」で「いらん」といわれた人間は自動的にジャンケンに負けた奴 が渋々引き取る形になっていた。
だけど、僕は「もう たくさんだ」と思った。
「俺、今日は帰るわ。」僕は力なくそうクラスのメンバーに告げた。
「何でやねん。そんなんいうなや!最後の方で代打で出したるやんけ!」
「いらん」と宣告された僕にとって『身元引受人』にあたる「いるか いらんか」 ジャンケンに負けた奴が居丈高に僕を引き止めたが、僕は聞く耳を持っていなかった。 せっかくのデビューの機会を失われた哀れな新品のキャッチャーミットを、それでも 大事そうに抱えて僕はトボトボ帰路についた。
その間、前の晩我が家にキャッチャーミットがやってきてからの出来事が走馬灯の様 に甦ってきた。
このキャッチャーミットでプレイする事をワクワクしながら待ち焦がれていた自分が 情けなくて情けなくてどうしようもなかった。
そしてせっかくこのキャッチャーミットを買ってきてくれ、今日の日の僕の活躍を心 待ちにして一緒に夜遅くまでミットを手入れしてくれたおやじに対して、何だか重大な 裏切りを犯してしまった様な、そんな罪悪感に駆られて僕は涙を堪えるのに必死だった。
するとその時、間の悪い事に当時クラスが一緒だったある女子にバッタリ出会ってし まった。
「あれー。雁金君。もう帰るのん? みんなソフトの試合やってんちゃーん?」
能天気なかんじでヘラヘラとその女の子は僕に声をかけた。
僕は今まで堪えてきた物が、その一言をきっかけにガラガラと音をたてて崩れ去って いくのを感じた。
情けなかった。究極に情けなかった。涙でメガネの向こうの、その憎たらしい女子の 顔がかすんで見えなかった。
「うるさいわーっ。」その一言を言うのがやっとだった。
僕は誰はばかることなく大泣きに泣いた。
「なによー。雁金君。私なんにも悪い事ゆうてないのにー。泣かんでもええやんかー。」
その女子がそう言うか言わないかのうちに僕は脱兎のごとく駆け出していた。
一体今日おやじが仕事から帰ってきて今日の僕の活躍について聞いてきたら、どんな 顔をして答えればいいんだろう?
こんな情けない思いをするくらいだったらもう野球なんかするもんか!
僕は本気でそう思った。
結局、そのキャッチャーミットはそれ以降もずっと陽の目を見る事はなかった。
だけどあの時あんな悔しい思いをして「もう野球なんかするもんか!」と硬く決意し た僕だったが、それがガキの特権なのか2〜3日もすればケロっと忘れてしまって、野 球はやっぱりやめられなかった。
そしてやがて、何を間違えたか知らないが小学5年の頃にはひょんな事からピッチャ ーをやる事になり、その時たまたまいいピッチングをした事がきっかけとなって地区の エースになり、いつのまにか野田小学校を代表するエースにのしあがっていた。
(嘘だと思うでしょうが本当なのです!!何せ他のチームは僕のボールを打ち砕く為 にソフトボールであるにもかかわらず、フリーバッティングのピッチャーにオーバース ローで投げさせて練習していたくらいなのですから・・・でもあんまり力説したらまる で作り話みたいに聞こえるので、サラッとこれくらいにしておきます)
何はともあれあの時僕を「とーりー」で指名しなかった奴や「いるか いらんか」で 「いらん」と言った連中に対しては溜飲を下げる事ができた。
しかし何より可哀相なのは、キャッチャーミットである。
持ち主の僕が結局ピッチャーになってしまった事によって、本当に誰にも使われなく なってしまったのである。
そんな状況を察知したのか、おやじはそのキャッチャーミットは自分で面倒をみてや るしかない事にやがて気がつき、たまに父兄のソフトボール大会があるとなんだか無理 やりみたいにキャッチャーを引受け、ミットを慰めてやっていた。
僕もそんな機会にはおやじの試合を必ず観戦したものだったが、ポロポロ パスボー ルはするわ、挙げ句の果てにはファールチップを急所に当てて悶絶するわ散々だった。 それに懲りたのか、やがておやじもキャッチャーはその時以来しなくなってしまった・・・。
哀れなキャッチャーミットよ。
お前も雁金家に引き取られる事がなかったら、もっといい思いができただろうに・・・・。
ミットは今も堺の実家で活躍の機会を待っている。