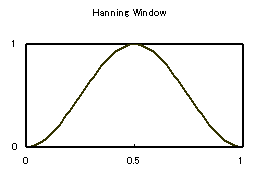FFTにより周波数領域に変換すると実数値、虚数値の二つの値が各周波数にでてくる。この二つの値はX軸に実数、Y軸に虚数を割り当てると、原点からの距離が絶対値、X軸からの角度が位相ということになる。
絶対値は周波数の大きさ、位相は遅れを表す。
位相が180度ずれていると、±が逆の振動をあらわす。
特にモーダル解析の際は絶対値だけでなく位相が大きな役割をして、180度ずれると逆方向に振動していることになる。
通常加速度センサーをはじめとするセンサーには外部にアンプが必要となる。そのためセンサーとレコーダー等の間にアンプを接続すると、配線が面倒な上に、電荷出力となるため、ノイズに弱くなり、配線が高価になったり、難しい問題が多い。
それに対応するため、センサーにアンプを内蔵させ、さらにレコーダー側から一定の電圧を与えることで電源を供給する仕組みが開発された。これがICPと呼ばれているものである。
これにより、電圧出力となり、比較的ノイズに強くなり、おまけにアンプを間に入れる必要がなくなるため、配線は楽になった。
問題としては、電源を供給するために電圧が与えられているため、カップリングにコンデンサーが使われているため、直流成分あるいは非常に低い周波数の信号を伝えられない。
ちなみに、ICPはPCB社のIntegrated Circuit Piezoelectricの略の登録商標であり、他のメーカーも同様の機能を別の登録商標で販売している。
インパルス波
振動解析を行う際に加振を行う方法として、サイン波、チャープ波、ランダム波等を用いた場合には、加振器が必要であるが、それなりに高価な上に、設置等に知識が必要なため、初心者には難しく、エキスパートも準備に時間がかかる。
この問題に対処できるのがインパルス波である。インパルスハンマー(impulse hammer)あるいはインパクトハンマーと呼ばれるいわゆるハンマーを用いて対象物を瞬間的に(impulse)加振する。
特徴としては加振器を用いないため設置に頭を悩ませない、一回の測定がすぐに終わる、加振器よりは安い、人間がたたくのでばらつきが大きい、加振スペクトルを制御できない、周波数ごとに最適なハンマーが異なる、特定の周波数を加振するエネルギーが小さいというものがある。
音響解析では加振器が必要ないため、チャープ波等が簡単に行えるため、インパルス波を用いることはほとんどない。
FFTを使うと振動や音声には基本周波数以外にもいろいろな周波数に信号が測定されます。大きく分けると
1.ノイズ
2.漏れ
3.高調波
4.別のモードの振動
などでしょうか。その中で高調波といわれているものは、実は音声でいえば音色のようなものであり、同じ音程の音でもピアノとバイオリンではっきり異なる原因ともなっています。
簡単にいうと、例えば440Hzの音は1秒間に440回振動するわけで、そうすると極端にいうと440回同じ波形が観測されます。(強引ですが)その一つ一つの波形が完全なサインカーブになっていれば高調波は存在しません。しかし、サインカーブではなくねったり、その中で振動していたりすると、別の周波数の振動ということになりますが、同じ波形が繰り返されるとすると、440回同じことが繰り返されるので、440の整数倍の周波数ということになります。したがって高調波は基本周波数の整数倍の周波数が検出されます。
逆にこの高調波の割合等を比較すれば、信号の歪みなどを定量的にひかくすることもできます。
コヒーレンス関数
コヒーレンス関数は、平均化と密接な関係にあり、測定の入力と出力の関係がどの程度あるかを表すものです。
周波数領域において、0と1の間をとり、完全に相関があるばあいは1、相関がない場合は0をとり、1に近いほど、相関が大きいということになります。
この関数は入力側(加振器あるいはインパルスハンマー)と出力側(加速度センサー、マイク)のそれぞれのデータを必要とするため、現状マイク入力しかないRH1FFTでは実装できていませんが、今後方法を検討してみたいと考えています。
サイン波
時間領域で特定の周波数が連続するデータのこと。
音響や振動解析において用いると特定の周波数について分析でき、エネルギーが集中できるため、特定の周波数を分析するのに適する。しかしながら、ガタ等の非線形の影響がでやすいという短所もある。(逆にこれにより非線形性をあぶりだすことに用いることもできる)
例えば440Hz、880Hz、1760Hz、、、で同じ振幅のWAVデータのCDを用いて
CD->CDプレーヤー->アンプ->スピーカー->マイク->PC
と録音すると、周波数ごとのこの系全体の伝達関数がわかり、さらに、FFTすることで、2倍、3倍、4倍といった高調波(harmonics)を測定でき、どのくらい歪んでいるかを定量化できる。
サンプリング定理
アナログ信号をデジタル化する(A/D変換)際に重要になるのが、サンプリング周波数fs(サンプリング周期の逆数)の半分以上の周波数は正しく再現されないというのがサンプリング定理。
図に描いてみるとわかりやすい。
これによると、1000Hzの音を録音したい場合には2000Hz以上でサンプリングする必要がある。これはFFT解析でも同様でサンプリング周波数の半分以下のみが周波数領域に解析される。ただし、原理的には1/2倍までできるが、一般的なFFTアナライザ等は1/2.56倍以下を表示することになっている。これは解析の誤差を避けるためのようである。RH1FFTではこれを採用せず1/2倍までを表示するので、もしも誤差にシビアな場合にはサンプリング周波数は、対象周波数よりも余裕を持つ必要がある。
音声の場合44.1KHzでサンプリングするのが一般的であるが、人間の可聴域が20Hz〜20KHzであり十分との判断がされている。
ただし、安価なマイクやスピーカーでは20KHz付近では既に対応できないため、十分な配慮が必要
自己相関関数
時間領域の信号がどれくらい周期性を持っているかをあらわす関数です。
これをFFTをかけ、特定の周波数にピークがあると、波形の周期性=音程を調べることができる。
http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/04/05/317192
も参考にしてください
周波数領域の微積分
振動測定の場合、加速度、速度、変位を測定することになります。しかしこれら全てを同時に測定するのは困難なため、状況に応じて、一つ測定することになります。
しかしながら、加速度を測定して、変位という形で出力したいということはよくあります。この場合には積分する必要があります。
測定した時間データをそのまま数値積分すると、様々な要因による低周波の誤差が蓄積することで、たいていの場合、おかしな結果になります。
そこで、一度周波数領域に変換(FFT)し各周波数ごとに積分するという方法が一般的です。x''=sin(wt)としたときにはx=-sin(wt)/w^2になりますから、当然計算は可能です。また、計算結果は周波数領域ですから、低周波の誤差についても高周波のみを表示する分には大きな誤差が発生しません。
また、時間波形にする場合には低周波の誤差の大きな部分をフィルターでカットしてから時間領域に変換(IFFT)すれば、そこそこ納得できるデータがでます。
ただし、当然のことながらカットした周波数のデータが消えているため、絶対的な振動の様子を知りたい場合には使えません。
周波数分解能
FFTの原理から
一回のFFTを行う音声データの長さ(ブロックサイズ)がD(sec)の場合には得られる周波数領域のデータの周波数はf=1/D(Hz)ピッチとなる。これを周波数分解能(frequency
resolution )といいます。
相互相関関数
2つの異なる信号がどのくらい関係があるかをあらわす関数。
横軸は時間であり、もっとも大きな値を取っている時間分だけ信号をずらすともっとも近い信号となることをあらわす。
例えばオリジナルの信号Aをアンプからスピーカーを通してマイクから録音した信号Bの相互相関関数をとった場合の最大値がtだった場合、Bの時間軸をtだけずらした状態が最も近い信号となり、そこで、同じ時間位置でのデータを比較するとどのくらい信号が変化しているかを調べることができる。
http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/04/05/317192
も参考にしてください。
チャープ波
特定の周波数であるサイン波では全体的な傾向をつかんだり、どの周波数が対象か特定していない場合には時間がかかるという問題点がある。
その欠点を補うため、サイン波の周波数を時間とともに変化させる(掃引、sweep)したものがチャープ波(chirpあるいはスェプトサインswept
sign)です。
特徴としては、時間が比較的短く、かつインパルス応答と比較して、ノイズの影響が少ない(S/Nがよい)、振動解析の場合には加振器が必要ということがあげられる。
周波数の増え方が時間に線形に増加、指数関数的に増加の二種類があり、線形の場合には各周波数ごとのエネルギーが一定になり、指数関数的な場合にはオクターブ毎のエネルギーが一定になる。後者は特に音響解析時に用いる。これは人間の耳が指数関数的に音を認識するためであり、1オクターブ上の音は周波数が2倍であり、したがって、ピアノやハープの弦の長さは1オクターブ違うと長さが半分になり、弦の長さが指数関数的に変化している。