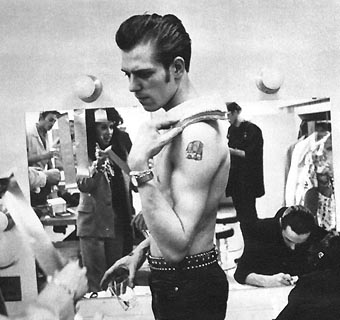
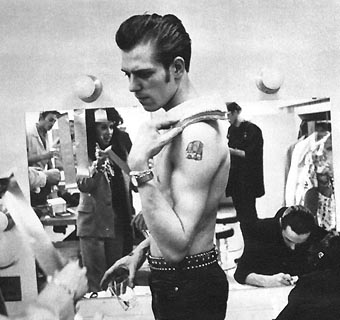
経験から言えることだが、クラッシュのレゲエやダブを評価しないパンクスは多い。逆の言い方をすればレゲエやダブなどやらずにトミーガンみたいな曲ばかりだったら好きなのに、ということである。世に語られるパンクという音楽にあてはまるのは、やはり1枚目と2枚目がまさにそれであって、森脇美貴夫みたいに「3枚目以降は知ったことではない」と乱暴に切り捨てられることもある。
ジョー・ストラマーはかつてこう言った。「パンクはスタイルではない。姿勢だ。」白人の若者たちが日ごろ思っている不満をそのまま表現したのがパンクであれば、ジョーの言っているパンクとは姿勢である、ということはそのような怒りや不満、正義への疑問というのもが表現の基本にならなくてはならない。「白い暴動」の歌詞には黒人たちの暴動のことが折り込まれているが、この黒人たちは西インドからやってきた人達がその怒りや不満を歌にした場合レゲエやダブになる。ジョーから見ればパンクをやるにもレゲエをやるにもなんら変わりがなかったろう。いやむしろ融合により音楽的センスがより磨かれたと思う。
パンクが発したエネルギーは現代の都市の中で起こる内部的な衝突であると言えるが、レゲエは都市に入り込んだ異質な土着的パワーとの衝突とすることができるであろう。社会制度の中で虐げれれる存在としての黒人は、労働者階級よりもより過酷な状況におかれるが、その生命力と団結力で生き延びようとする。時として81年のブリクストン暴動のような事件を起こすが、日常的な反発力はレゲエとともにある。彼らは都市のテクノロジーを健康のまま謳歌し、あらたな表現としてダブさえ作り出す。しかし拭い切れない翳はつきまとい、皮肉にもこれこそが表現を深化させ白人からも共感を得ることになっている。この両者が都市に生きるものとしてシンクロするのは自然なことのように見える。
アメリカでいえばロックンロールとゴスペルやブルーズの関係に似ている。しかしかなり違う。「スタイルではない、姿勢である」アメリカにはスタイルとしての交換が大きかったのでソウルが生まれたと思う。姿勢はおのずから相容れなかった。
イギリスにおいて、パンクにシンパシーを感じるならレゲエを理解することはたやすいことだろう。どちらかを理解しどちらかを遠ざけるということはありえないように思える。これ以上は趣味の問題だからどうでもいいのだが、すくなくともクラッシュにとってレゲエで歌える世界があって、当時の世界において彼らが見たり感じたりしたことを純粋に表現しようとしたのだ。
「俺達とピストルズはよくレゲエの曲をやるべきかどうか議論した。(ジョニー)ロットンは大変なレゲエ狂だったが、自分なりのルールをもっていて、レゲエに手をだすべきでないと考えていた。ともかく、俺達はそれをパンクスタイルでやったんだ。」とジョーは語っている。パンクバンドとしてラスタとの連帯を初めて表明するがごとくファーストアルバムのなかでジュニア・マーヴィンの「ポリスとコソ泥」をとりあげ、シングル「コンプリート・コントロール」としてプロデューサーをジャマイカの大御所リー・ペリーを迎え、そして78年には「ハマースミス宮殿の白人」を発表しNMEでその年の代表曲に選出された。
レゲエとの親密な関係はさらに80年の「ロンドン・コーリング」を経てますます深まっていった。「サンディニスタ」にはマイキー・ドレッドの参加し、3枚組みの大作の中で曲の半数以上がレゲエやダブであった。結果からいえばこの大いなる「実験」は失敗だった。セールスも芳しくなく、シングルカットした「THIS IS REDIO CLASH」もチャートを低迷し、初期からファンの離反をも招く結果となった。しかしこれをレゲエやダブをやったからという図式で理解するよりは、単純であった感情の吐露が表現的に深化し複雑になるという真面目に取り組めばさけて通れない道をたどったからであると考えるのが正しいと思う。ジョーの詩が描く世界はより混沌としヘヴィになり、街にあるよりももっと遠くのことを歌いはじめた。そういうことだったのだ。