石川代官屋敷門
| ||||||||

|
代官屋敷 元町商店街から山手に抜け る坂の途中にあります。手前 の道が代官坂で、この屋敷に ちなんで名付けられたそうで す。主屋は建替えられていま すが、手前の建物は昔のまま のようです。 |

|
旧屋敷門? 屋敷入り口の左手にある建 物で、木肌の古さから幕末頃 の建物のようにも見えます。 横浜も中心地区は震災や戦災 で壊滅しましたが、山手の方 は古くからの建物が多く残さ れているので、この建物も焼 け残った物と思います。 |
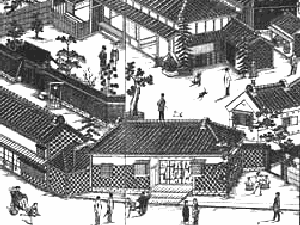
|
明治初期の石川家 この絵図は明治のものです が石川家の長屋門が描かれて いて、その位置も形も大きさ も上記の建物と一致します。 名主屋敷ですから長屋門も珍 しくないのですが、ペリーの 来訪時は当然この門を通った のではないでしょうか。 |
|
注・・・ 横浜は開港と共に神奈川奉行の支配するところとなり、石川家は総年寄りとして名主の上に 位置付けられました。ただ神奈川奉行の支配体制は期間が短かった所為か資料が少なく、同じ 幕府直轄の港町だった長崎奉行所の支配体制が参考になると思います。 それを見ると奉行が直接支配したのは地租免除となる長崎の港湾と市街地で、その周囲の地 租の対象となる農村は、名主出身の町年寄(名主の代表)が長崎代官として支配していたそう です。つまり年貢米の徴収集積は町年寄が代官職を兼務して行っていたようで、他の旗本領で 名主が郷代官を務めるのと同様の支配体制だったようです。 横浜も幕府直轄の港町なので、神奈川奉行の支配体制も長崎奉行所に倣っていたと思われ、 石川家を総年寄りとして代官職を兼務させていたと思われます。ウィキペディアで調べたので (長崎代官で検索)確信には至りませんが、横浜代官屋敷という呼称の方が相応しいかも知れ ません。 | |