シティの裏通りにある大衆向きイタリア料理の店で、大介氏はロンドン支店
の若い連中と昼の食事をしていた。当地では昼食の時にも軽く一杯飲むの
が慣習である。
「昼にも飲むのか」と目くじらを立てることはない。ほんの一杯のグラス・ワ
インとかハーフ・パイント・ビア(コップ一杯程度)の食前酒なんだ。
クラーク(事務行員)は大体パブでサンドイッチ片手に立ち飲みし、昼を済
ませるお国柄である。
「次長また載りましたね」
「ありがとう、この飲み代は俺が持つよ」
「ごちそうさまです。でも次長の歌のレベルは必ずしも高いとは思いません
がね」
「そうだよな、何か子供をダシにしているよな。次長は子煩悩だからな」
「それにロンドンからというのが同情をひくよね」
アルコールの入った行員たちが、好き勝手に揶揄する。
「まあ言ってみれば、山上憶良ならぬロンドン憶良ですね」
最も若い亜麻野君が総括する。
「そうか、なかなかセンスのよいニックネームじゃないか。その綽名は戴き
だな、早速一首浮かんだよ」
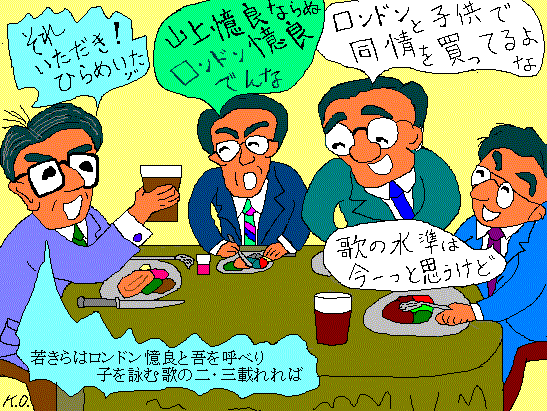
若きらはロンドン憶良と吾(あ)を呼べり子を詠む歌の二、三載れれば
嬉しいことに、この歌が宮柊二先生からトップに選ばれた。
「第一作・・・作者に与えられた『ロンドン憶良』の綽名が親しく、面白い・・・」
との選者評を戴いた。1位になると、20年に一度編集される歌壇秀歌選に
採録される。
「いゃあ、参りました。尊敬尊敬」
「これからは憶良次長と呼ぶことに一同で決めました。よろしくお受けくださ
い」
鼻っ柱の強い若手行員たちも、ついにシャッポを脱いだ。
かくして、異郷の地に「ロンドン憶良」の綽名が誕生し、読者諸氏に駄文を
呈することとなった次第である。
ご参考
万葉歌人山上憶良(660−733)は奈良初期の官吏。702年遣唐小録と
して渡唐、帰国後は天平開化に貢献。東宮侍講。721年ごろ筑前守。
太宰師(だざいのそち)大伴旅人(おおとものたびと)とともに中央歌壇に対
し筑紫歌壇を形成。
家族愛、老病、貧困をうたい、旅人が世の虚しさを嘆いたのに対し、世の術
のなさを追い求め、我執と迷妄の文学を達成した。「恋」の氾濫する万葉集
でただひとり「愛」を歌った点でも独自性は高い。
(小学館 大日本百科事典より抜粋)
憶良等は今は罷(まか)らむ子なくらむその彼の母も吾をまつらむぞ
長歌
瓜食めば、子等思ほゆ、栗食めば、況してしぬばゆ、何処より、来たりしも
のぞ、眼交に、もとな懸りて、安寝(やすい)し為さぬ
反歌
銀(しろがね)も金(こがね)も玉も何せむに勝れる宝子に及(し)かめやも
「ロンドン憶良見聞録」の目次へ戻る
ホームページへ戻る