1665年のロンドンにはペストが大流行した。
翌1666年の9月2日午前2時、パン屋からでた火事は、4日間燃え続
ける大火となった。世界の富を集めていたかのような商都ロンドンは灰
燼に帰してしまった。
当時は木造の建物が多かったからである。10万人以上が焼け出され
ホームレスになったというが、死者はたったの8名だったという。
大発生していたネズミが焼け死に、さしも猖獗(しょうけつ)をきわめた
ペストが収まったのは、「ケガならぬ火事の功名」であった。
(ネズミとペスト菌を焼き殺すため、当局の作為的な放火だという説もあ
るようだ)
時の政府は、今後この都市が二度と大火によって灰にならぬように、
「以後建てる建物は全て石作りかレンガ造りとすべし」とのお触れを出
した。
政府が偉かったのは、この時焼けてしまった数多くの教会の再建に、
天才建築家クリストファー・レン卿をあてたことである。現存するセント・
ポール寺院を始め、53以上の教会がレン卿によって見事に建築され、
我々の前にある。
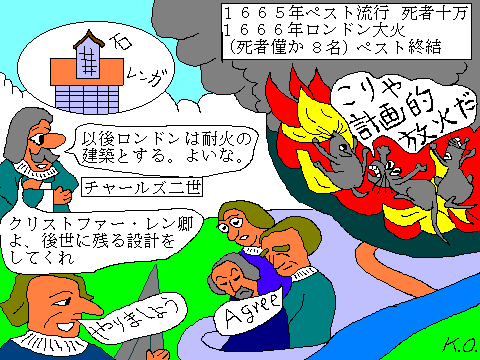
レン卿はシティの道を広く直線にしたかったが、こればかりは承認され
ずに、焼ける前のくねくねした通りが残った。(これも歴史的資産か)
ロンドン市民は3百年間このお触れを忠実に守り、木造建築の安普請で
再建しなかった。石とレンガの建物は火災から富を守った。二つの大戦
ではドイツ軍の攻撃にあったが、局部的被害で済んでいる。
日本ではどうだろうか。これほど徹底されないのではなかろうか。
例外とか抜け穴とかで、木造建築を続けたのではあるまいか。
東京は、関東大震災と第二次大戦の戦災で、二度灰燼となった。しかし、
都市計画のチャンスを逸した。パリのような都市美をつくり損なった。公
益よりも私権を認め過ぎたからであろう。その結果、社会資本の充実の
ために今何億もの巨額な金が必要となり、それは最終的に国民の負担
となっている。
目先のことより百年先を見据えた政治の出来る為政者の養成と、私権を
犠牲にしても公益を優先する政治を支持する国民に脱皮することが必要
であろう。
21世紀を語るといっても、せいぜい2020年ぐらいまでしか論じられてい
ないことが気になる。それも若い労働人口が激減するという経済的観点で。
読者諸君、とりわけ若い諸君に切望したい。自分の孫や曾孫に、どのよう
な社会、どのような環境を残すか、たまには友人と国家百年の計を語ろう
ではないか。
『學ぶ』は親鳥が巣から飛び立つ姿を下から子が眺め、『真似る』ところか
らきた象形文字という。環境問題の処理については、英国に『学ぶ』か『真
似る』ことがまだあるようだ。(もちろんドイツにもアメリカにも)
「ロンドン憶良見聞録」の目次へ戻る
ホームページへ戻る