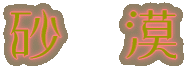 |
|---|
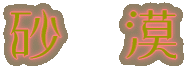 |
|---|
| あぁ 暑い熱い・・・ あつぅい そこは・・・見渡す限り一面の砂。砂漠。 砂が幾層にも積み重なったその姿にはえもいわれぬ迫力があり、まるで無限に広がっ ているかのよう。 それを構成している熱い砂に触れれば、火傷ではすまされないだろう。 絶対に人を、生き物を受け入れない・・・孤高の地。 空は透き通るようにどこまでも青く、果てしなく広い。 そこに、ぎらぎらと輝く空の主が1つ。 砂漠すべてを照らし出す傲慢な主は今も健在。 高い位置から何もかもを見ている。 ・・・もしかしたら、笑っているかもしれない。 “なんと小さく愚かな者達もいたものか” なんて。 さて、1つ・・・そんな小さく愚かな者の末路をお見せしよう。 ここは、砂漠の上。空の主の下。 そうとしか表現できない場所での、ある青年のお話。 青年は、延々とただ歩いていた。 強い主の光から見を守るために分厚い服をかっちりと隙間なく着込み、手にはズタボ ロの袋を持っている。 長い間その光にさらしっぱなしだったのだろう。 それらはすべて主の光に焼け、砂をかぶり、黒ずんでいた。 深々とかぶったローブから時折ちらちらと覗く青年の頬は意外に白く、青年はほとん ど白と茶、汚れた薄い黒で構成されていたが、ただ1つそれ以外の色を持つものが あった。 それが“赤” 鮮やかにきらめく紅。 それは袋を伝い、ぽたぽたと零れ落ちる、深紅の液体。 青年はそれに気付いてはいたが、止める術を知らなかった。 時々押さえてみては手についた液体に眉を顰めていたようだが、今ではもう袋を見る ことさえしない。無駄だと悟ったのだろう。 赤い・・・紅い液体は砂の上に落ちてはすぐに吸収され、痕も残らない。 しかし青年はただ歩きつづける・・・足を動かしつづけるだけでそんなことには気を 配る様子も・・・いや、気付く様子もない。 赤い主は容赦なく彼を焼く。じりじりと、じっくり。まるでおいしく料理するよう に。 それに耐え切れなくなったのだろうか、ふいに青年がふらりとよろめき、かろうじて 踏みとどまる。・・・倒れればいくら服を着込んでいても、火傷は免れない。 そんな時だ。 「おい」 涼しく、甘い・・・その声が耳を打ったのは。 青年はその声に即座に反応した。肩をビクリと弾ませて。 しかし振り向きはしない。 どうしてかって? 体力の無駄だと思ったわけではない。もとから・・・気付いていたからだ。 自分の後ろにぴったりと、けれどある一定の距離を保ったままで、ソレが着いてきて いたことに。 足取り、呼吸、袋から液体がたれるその1滴1滴まで舐めるように見ているその存在 に、青年が気付かないはずもなく・・・いつの間にか、青年はソレを意識していたの だから。 しかし今まで、ソレが青年に声を掛けたことはなかった。 ただ視線を寄越すのみで。 だから青年自身、ソレを警戒しながらも、何もしようとはしなかった。 声を掛けることは愚か、振り向いてソレを確認することさえ。 青年がソレを知らなかったのは道理だ・・・が、青年にはそれがその存在の声である ことが、何故だかすぐにわかった。・・・いや、本当はもっと前から知っていたのか もしれない。 青年は疲れ果てていた。・・・それは例えようもなく。 「こちらを向け」 だからかもしれない。その声に振り向いてしまったのは。 そこには男がいた。 青年にとって、男はひどく魅力的にうつった。 何が?と聞かれれば、きっと青年は答えにつまるだろう。 けれども、その存在は青年の視線を熱く、そして磔にするのに、充分・・・いや、そ れ以上の力を、確かに持っていた。 男はこの砂漠に相応しいとは嘘でも言えない、どこか派手で特徴的な格好をしてい た。 青年の後ろを歩いていたはずなのに・・・主の光で焼けてはいない、真っ黒でゆった りとしたアラビア風のズボンを履き、上半身には同じ黒の細長い透けた羽衣のような 薄布を左肩から腰の右にかけて斜めに垂らすといった格好。 その布は男の足元にはらりと落ち、砂についているのに今まで引きずっていた様子は なく、いたって綺麗なものだ。 それしか身につけていないその身体はほとんど強い光の下に向き出しと言っていい状 態。 そのせいで男の浅黒い肌、脂肪のなさそうな筋肉質の身体が一目で見てとれる。 顔はどちらかと言うと西洋人的な感じで、髪は豪奢な金色、睫毛は長そうで唇は薄 かった。 そして・・・もっとも印象的なのがその瞳。 袋から垂れるあの液体と同じ・・・紅。 何もかも自分とは正反対だと、青年は呆然と思う。 なんせ・・・青年は汗だくで疲れきってふらふらしているのに、男は口元に笑みすら 浮かべて涼しそうにこちらを見つめているのだから。・・・汗さえもかかず。 それに・・・どうしてだろう? 男はこの灼熱の太陽の下に肌をさらしているのに、火傷している様子も、熱がってい る様子もない。 明らかにおかしい。 しかし青年は頭がぼんやりとして、そこまで頭が回らない。 ただ漠然と男に違和感を持っただけだった。 そんな青年を見つめて男は話し掛ける。 「・・・こんな砂漠をただずっと歩いてるだけで・・・お前、つまらないと思わない のか?」 思う・・・思うさ。でも、これが普通なんだ。こうしないと駄目なんだ。 男はいかにもおもしろいと言いたげにクスリと笑う。 「それはどうして? 何故しなくてはならないんだ?」 どうして・・・って・・・。それは・・・皆がやっていることで…。 それに、父さんも母さんも・・・自分達も通った道だからって・・・。 「おもしろいことを言う・・・。 何故皆がしているからといって自分もしなければいけない? 父親が母親が言うから・・・どうだというのだ?」 それは・・・。 「虚しいとは思わないのか? こんなところをただ歩くだけで・・・。楽しみも何もないじゃないか。 それにお前がこんなふうに歩いていたって、たどり着くのはどこだ?」 ・・・そういえば・・・、父さんも母さんも・・・ 「そう、結局は砂漠に住んでいたろう? ここに終わりなんてないんだからなぁ」 終わりが、ない・・・? 「そう。ここには、あってもオアシスだけ。 ようはどれだけ大きなオアシスに住むことができるか、だ。 お前らはそれを探してるんだろう?」 俺は・・・いつかはここを抜けることができる・・・って・・・ 「クククッ、そんなことを考えていたのか? そんなわけないだろう。この砂漠を抜けることができるのは死んだ時だけだぞ」 そんな・・・。 青年は絶望したように、熱い砂に膝をつく。 確かに足にも分厚いズボンを履いているが・・・熱いだろうに。 本当に熱さにやられているのだろう。 見知らぬ男の言葉を・・・やすやすと信じてしまうぐらいに。 そんな青年を見て男は口元を吊り上げてほくそ笑む。 そして 「なぁ・・・」 男はそんな青年に甘い声をかけた。 「俺と同じ所へ来ないか・・・?」 あなたと・・・同じところ? 「そう・・・涼しくてイイ所・・・」 “涼しくて” 青年はその言葉に惹かれたように顔を上げた。 そしてまじまじと男を見つめる。 「本当に・・・?」 男は笑みを深める。 「本当に。俺を見てみろ・・・涼しそうだろう?」 それはそうだ。 男は汗などかいていないし、空の主に照らされても火傷さえしていない。 青年はコクコクと頷く。 「じゃあ・・・来いよ・・・」 男は青年に手を伸ばす。 けれど、けして自分から歩み寄ろうとはしない。 否・・・それはできないのだ。 そして青年はよろよろと立ち上がり・・・その手を取った。 途端に男は痛いほど青年の手を握り締める。 「な、何!」 『もう・・・逃がさない』 男が青年を強い力で引き寄せると、その身体は砂の中へと沈み始める。 もちろん、青年も一緒に。 そして青年は、男と供に沈んでいった。 砂漠の下へ。絶対に空の主の・・・、日の光が届くことのない世界へと。 “・・・・・愚かな・・・” 「ん・・・」 青年は闇の中で目を覚ました。 当たり前と思っていた空の主の光がなくて面食らったが、そこは確かに涼しかった。 ・・・寒いくらいに。 辺りを見回しても、あの男の姿はない。 名前を呼ぼうとして、自分があの男の名前さえも聞いていないことを思い出す。 「・・・?」 ・・・じゅるじゅるという音が聞こえる。 何かを啜るような、音。 そして青年は気付いた。 すぐ近く。今まで闇だと思っていたそこが、ごそごそと蠢いているのを。 おそるおそる近づくと、それはあの男で。 その姿を視界に認めた瞬間、青年は愕然とした。 空の主の下で、男の肌は確かに黒かった。 しかし・・・ 強い日の光の下ではあんなに魅力的に見えた肌や服が、この闇の中ではなんと色あせ て見えることか。 服も肌も闇に溶けて一体化し、ただ男の啜る紅い液体とその瞳だけが、らんらんと光 を放つ。ぎらぎらと紅い瞳を輝かせた男は恍惚としたような表情をしていたが、それ は・・・なんとも恐ろしいものにしか見えず。 男はもうまったく、あの魅力を持っているようには見えなかった。 しかし、青年が見て衝撃を受けたのはそのことではなかった。 その・・・男が啜っているモノだ。 それは・・・自分が持っていたあの、袋の中身なのだから。 青年は思い出す。 母や父が毎日のように言っていたことを。 『何があっても・・・あの袋だけは大切にしなければいけない。』 『あれだけはなくしてはいけないよ』 それは、呪文のように繰り返された。 もう頭に刻み込まれて・・・消えはしないと思っていたのに。 どうして忘れていたのか・・・。 あの砂漠で、あれが重くて重くて・・・あれを捨ててしまおうかと考えたことさえ あった。 家から出てきたときは、大事に大事に運んでいたのに。 だんだんと扱いが乱暴になってきて・・・ここへ来る前にはもうボロボロだった。 中身も漏れてくるほど・・・。 そしてその漏れた液体が、男を引き寄せた。 紅く滴る液体が・・・男の何よりの好物だったから。 あれがなければもう、青年は砂漠へは戻れない。 ずずぅっ・・・ 最後の1滴を、男が啜る。 「はぁ」 甘いため息。 まだかすかに、恍惚の色が残っているような・・・。 男はようやく気付く。 自分の後ろに誰がいて、どういう目で自分のことを見ているか、ということに。 口の端が自然と上がった。 男はゆっくりと振り向いた。 「さぁて・・・どうしようか?」 男は笑う。 主の光の下では綺麗だったその笑みは、この闇の中では恐怖の象徴。 青年は震え上がった・・・が、もう遅い。 もう二度と・・・青年が日の光に当たることはないだろう。 |
|---|
感想を投稿者へ送ってあげてください。
もしかしたら、続きが読める・・・かも!