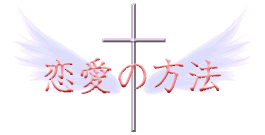 |
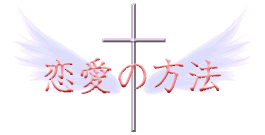 |
![]()
7 「緑、お疲れ。俺が送って行ってあげるよ」 バイトを終えた緑が店を出ると、案の定、中谷が待っていた。 ここ最近、ずっとこんな調子で、中谷は夕方五時になると店に来て、緑に話しかけていた。もちろん緑は見向きもせず通りすぎる。しかし中谷は諦めなかった。 「また明日も来るよ」 隆史がいるからなのか、特に何をするわけでもないが、緑にとっては会いたくない人物だ。本当は顔を見るのも嫌だった。 「いい加減にしてくれよ…」 中谷の車を見送ってから、緑は頭を抱え込んで、しゃがみ込んだ。 「警察に行ったらどうだ?」 「いや、それは…」 緑にとって警察は、どうしても行きたくないところだった。 昔、『club Trip』で働いていた頃、客とトラぶり、警察沙汰になったことがあった。その時の警察の態度は冷たかった。ただ一方的に緑を詰った。 結局注意だけで終わったが、それ以来、緑は警察を信用していなかった。 「もう暫らく放っておくよ。今のところ、何もされてないからな…」 仕方なく立ち上がり、家路を急いだ。 「緑、悪いが今日、少しだけ夜の部にも入ってくれないか?」 ある日、バイトが終わる一時間前に、緑は店長にそう言われた。夜の部には高校生が入っていたのだが、少し遅れてしまうという連絡が入ったのだ。隆史はもう一つバイトをしており、入る事が出来なかった。 「いいですけど…。連絡だけさせてもらえませんか?」 「いいぞ。中の電話を使ってくれていいから」 緑は鉄朗の会社に電話をし、遅くなると伝えた。鉄朗は夕食を作って、待っていてくれると言って電話を切った。(少しだけだから、いいか…) 淡々と仕事をこなしながら、バイトが終わるのを待った。 結局緑がバイトを終えたのは、午後七時だった。 いつもは隆史と店を出るが、今日は一人だ。中谷がいるんじゃないかと警戒したが、車がなかったので安心して道路に出た。ここからマンションまで歩いて十分。走れば五・六分で着く。緑は鉄朗の顔を早く見たくて、走った。 そしてマンションが見えてきたその時―― 「今日は遅かったんだね」 と、後ろから声がしたと思ったら、突然口と鼻をハンカチで押さえつけられ、何か薬を嗅がされた。 緑はそのまま意識を失った。 緑がふっと目を覚ますと、近くに中谷の顔があった。慌てて顔を逸らし、自分の状態を見た。両腕はベッドに括り付けてあり、足も縛られていた。おまけに服は剥ぎ取られ、華奢な身体が曝け出されていた。 「紐を解けよ!」 「ダメだよ。緑はこれから俺に抱かれるんだ」 「あんた、頭おかしくなったんじゃないのか?」 「俺はまともだよ。今までは大人しくしていたんだけど、ちょっと我慢の限界がきたみたいなんだ」 中谷はベッドに座り、緑の頬を撫でながら、何でもないように話す。緑は中谷の手を振り解きたかったが、両手が塞がれていて、抵抗しようもなかった。 「こういうのも、たまにはいいだろう?」 中谷は怪しく微笑むと、緑の上に覆い被さった。 首筋に舌を這わせ、緑の身体を手で探る。 「やめろ!俺に触るな!」 中谷に触られていると、緑は自分がどんどん汚れていく気がした。今まで散々いろいろな男と寝ていたのに…、と緑自身も思うが、鉄朗に抱かれるようになって、少しずつ浄化されているように感じていた。 汚いと思っていた、自分の身体。 一生、この汚れは取れないと思っていた。 しかし今はこの身体が好きだった。鉄朗に愛される身体。だから好きだった。 そんな緑を他所に、中谷は自分の思いを緑に訴えた。 「好きだよ、緑。初めて緑を見たときから、ずっと好きだった。いつも緑の事ばかり考えてた。愛してるんだ。だから俺のものになってくれ!好きなんだ!緑だけなんだよ!」 自分の身体の上で語られる、熱い思い。少なくとも緑は、そういう思いだけは理解する事が出来た。緑が感じる、鉄朗への思いと同じなのだ。 緑はそっと息を吐き出し、瞼を閉じた。 「そんなに俺を抱きたいのか?だったら抱けよ。好きなだけやればいい。でも俺は一生、お前を愛する事はないよ。俺にはもう、すべて捧げた人がいるから。俺のすべて、その人のものだから。心も身体も、求めているのはその人だけだ」 緑の瞳が開かれた。その瞳から鋭い光が放たれ、中谷を威圧した。 「緑…」 「どうした?やらないのか?」 冷ややかな笑みの中に、明らかに軽蔑と諦めが含まれていた。緑の顔は、この世のものとは思えないほど艶やかで、中谷の下肢を刺激した。中谷はゴクッと唾を飲み込み、緑を抱きしめようとした。 ――コンコン―― 突然扉をノックする音が部屋に響き、二人の動きが止まった。 「お客さま、フロントでございます。他の部屋で少々問題が発生致しまして、中を確認させて頂きたいのですが、宜しいでしょうか?」 扉の向こうから、男の声がした。中谷は訝しく思いながらも、緑に布団をかけ、ベッドルームから出ていった。 緑はホッと、息を吐き出した。 (テツ…) 目を閉じて、マンションで待ってくれているはずの鉄朗を思い出す。 今日、中谷に抱かれたりしたら、もう鉄朗に合わす顔がないと思った。しかしここを逃げ出す手段がない。諦めたような顔で、天井を見つめた。 そしてそっと耳を澄まし、扉の向こうの様子を窺った。ガチャッと入り口の扉が開いた音がしたと思ったら、すぐに中谷の叫び声が聞こえてきた。 「うわっ…!!」 ――ドサッ!!―― 緑には何が起こったのかわからず、ただ扉をじっと眺めていた。 「緑!どこだ!?」 それは緑がずっと会いたかった、鉄朗の声だった。 「テツ…?」 「緑!」 勢いよくベッドルームの扉が開き、そこからスーツ姿のままの鉄朗が入ってきた。髪は乱れ、ネクタイは歪んで、曲がっている。 「テツ…」 「緑!大丈夫か!?怪我は?痛いところはないか!?」 紐を解いてやり、きつく抱きしめる。白く細い身体が、鉄朗の身体にしがみ付き、小刻みに震えていた。 「テツ…」 鉄朗は緑の背中を撫でてやり、優しく口づけた。 「もう大丈夫だよ。とりあえずここから出よう」 しっかり抱きついて離れない緑の服を全部着せてやり、もう一度口づけ、手を引いて部屋を出た。 隣の部屋では、中谷が床に倒れて、じっと天上を見ていた。 「どうしてだ?どうして、俺じゃダメなんだ?俺は緑を愛してるのに…。こんなに愛しているのに…」 中谷は天井に向かって呟いた。鉄朗はそれを一瞥して部屋を出ていことしたが、緑は立ち止まり、口を開いた。 ギュッと繋いだ手に力を込める。 「俺のことは諦めな。俺はこの人しか好きにならない。この人しか愛さない。死ぬまでずっと、好きだから、何したって無駄だ」 緑はそう言うと、逆に鉄朗の手を引き、部屋を出た。 8 ホテルでタクシーを拾い、マンションへ向かった。タクシーの中で緑は、ずっと鉄朗を見ていた。訊きたい事はたくさんあった。 しかし今は、繋いだ手の暖かさと、鉄朗の存在を感じていたかった。マンションの鍵を開けて、中に入るとすぐ、鉄朗がバスルームに消えた。 緑はまだ玄関に突っ立って、鉄朗の行動を見ていた。 「緑。おいで」 バスルームから顔を覗かせた鉄朗に呼ばれ、緑は素直に傍へパタパタと走っていった。 鉄朗は先程自分で着せた緑の服を脱がし、一緒に浴室に入った。そして緑を椅子に座らせ、身体を洗い始めた。 白く、艶やかな肌を、丁寧にタオルで擦る。鉄朗は魅惑的な項を眺めていると、中谷に対しふつふつと怒りが沸いてきた。順に洗っていき、手に達したとき、白く細い手首に赤い痣が出来ているのが見えた。鉄朗はそっと手首に口づけ、後ろから緑を抱きしめた。 「ごめんな…、緑。守ってやれなくて。俺、口では守ってやるとか、触れさせないとか言っといて、結局何もしてやれなかった…。ごめん…」 緑は振り返り、鉄朗の頬に手を伸ばした。 「何言ってるの?テツは俺を助けてくれたじゃん。ホテルまで来てくれたじゃん。だから今、ここに居るんだよ?」 「でもお前に、傷がついた」 「こんな傷、どうってことないよ。ただ赤くなてるだけだし…」 「ごめんな…」 頻りに謝る鉄朗を抱きしめ、緑から口づけた。 「テツ、謝らないで。テツは何も悪くないよ。いいんだ、こんな事はどうだって。俺はテツの傍にいられれば、それだけでいい…」 ぽてっ、と鉄朗の胸に頭を凭れさせ、目を閉じた。 静かな鼓動を聞いていると、不思議とすべて忘れられる気がしてくる。 「緑…」 緑にはいつだって、鉄朗がすべてだった。出会ってから現在に至るまで、緑が鉄朗に感謝した事は数知れない。中谷のように、よく知りもしない男と散々セックスして、金を貰っていた自分を愛してくれる。 その事実だけで十分過ぎると思っていた。 「俺は、あの男を許せない。俺の大事な緑を傷つけたんだ。許せるわけない」 縋り付いている緑の目を見つめ、嫉妬している自分の心を覗かせた。中谷が緑を抱いていないのは、知っていた。それでも触れた事がどうしても許せなかった。 「テツ、俺ね。身体は少し傷ついたけど、心はまったく傷ついてないよ。だってテツが助けてくれたんだし、心配してくれた。ほら、俺って家族いないじゃん?今まで心配してくれる人間さえいなかったんだよ?でも今はこうしてテツが心配してくれるでしょ?なんか嬉しかったりもしたんだ…」 緑は鉄朗が自分を責めてしまわないように、懸命に自分の思いを話した。 嘘なんか言っていない――これが緑の本心だった。 「緑…、俺はいつも緑のことしか考えてないよ。どこにいても、いつも心配してる。家族はいないって言ったよな?でも今は、お前には俺がいるから。もう家族だろ?俺と暮らして、いろんな事話して、一緒にご飯食って、抱きしめあって。それって家族だろ?」 「テツ…」 見上げてくる緑が愛しくて、鉄朗は目の前の身体をきつく抱きしめた。 「愛してる…」 何度も何度も緑の耳元に囁き、抱きしめて放さなかった。 バスルームから出て、二人はすべてを忘れるように、夢中でお互いを求め合った。 キスして、お互いを愛撫しあい、緑は鉄朗に貫かれ、快感に溺れた。 行為が終わってから、緑は鉄朗の膝の上の寝転がり、眠気と戦った。鉄朗はベッドボードに凭れて、緑の身体を抱いている。梳かれる髪が心地良くて、こっくりこっくりと舟をこいでいた。 (気持ちいい…) 半分夢の中にいながらも、今日の事を思い出していた。 (テツ、カッコよかったな…。いきなり現れてさ…。あれ?でもどうして俺があのホテルにいるって、わかったんだろう…?) 目を閉じて考えたが、どうしてもわからない。 「あのさ、テツ…」 「ん?」 髪を梳いていた手を止め、上から優しく口付ける。 「どうして俺があのホテルに連れて行かれたってわかったの?」 「え?」 「だってすごく不思議なんだもん」 下から見上げられ、その瞳に惹き付けられた。今日はいつにも増して緑は妖艶で、鉄朗は背筋がゾクッとした。 整いすぎた美貌は、時には危険を生じさせる原因にもなる。 「緑を迎えに行ったんだ」 「え、コンビニまで?」 「そう。で、途中で緑があいつの車に、乗せられているところを見たんだ。慌てて追いかけたんだけど間に合わなくて、タクシー拾ってホテルまで付けてった」 「そうだったんだ…」 緑はその情景を思い浮かべてみる。きっと鉄朗は必死に追いかけてくれていたに違いない。そう思うと嬉しくて、涙が零れてきそうになる。 「でも…」 「え?」 「ホテルでちょっと、手間取っちゃって…。部屋番号、聞き出すのに時間がかかったんだ」 また鉄朗がごめん、と誤ろうとしたのを察し、緑は起き上がってその唇を自分の唇で塞いだ。 「もう、謝るのはナシだよ」 「……了解」 苦笑しながら、今度は鉄朗から口づけた。 軽いキスは次第に深くなっていき、鉄朗は緑の身体を抱きしめ、ベッドに組み敷いた。 緑。俺もずっと愛してる。死ぬまでずっと愛してる。もし信用出来ないなら、確かめればいい。一生傍にいて、俺を見てろよ。嘘じゃないから…」 「うん…。うん…」 大好きな胸に縋り付き、幸せをかみ締める。 緑はこんなに幸せでいいのだろうかと思う。 幸せである事に慣れて入ない緑は、まだ幸せである事に不安を感じる。幸せであればある程、それが壊れてしまった時のショックは大きい。それは経験した者にしかわからない不安だ。 「幸せ過ぎて、怖いよ…」 緑の不安な呟きは、鉄朗の口の中に消えていった。 |