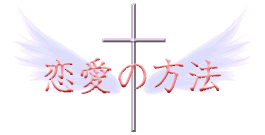 |
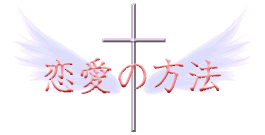 |
![]()
4 中谷はあれから店には来ていない。緑に気付いたのかそうでないのか、よくわからない。しかし、警戒はしていた。最後に会ったとき、緑のことを好きだといっていた。そのことを緑自身から鉄朗は訊いていた。 ――油断は出来ない。―― 鉄朗は最近緑が少しずつ心を開いて、いろんなものに溶け込もうとしているのを感じていた。今まですべてを拒絶して、たった独りで生きてきた緑に、心を開いて他人と接すれば独りじゃなくなる。それに自分がいるということを教えたかった。緑は十六歳だが、孤独感が強すぎて何も知らないままここまで来てしまった。少しずつでいいからいろんな事を教えてやりたい。 傷ついた心を癒してやりたい、と思っていた。それが鉄朗が考えた緑との恋愛方法で、多少変わっていてもお互いが幸せであればそれでいいと思っている。 緑を幸せにしてやりたい。 「テツ、急いでよ。遅刻しちゃうじゃん」 相変わらず鉄朗を起こして、朝ご飯を作って一緒に仕事に出る毎日が続いていた。 あの日、不安で一杯になり鉄朗に縋った。鉄朗は優しく抱きしめ、緑を慰め、安心させた。そんな事が出来るのは、この世で鉄朗しかいなかった。今の緑の心の支えは、鉄朗だった。 「元気だね。朝から」 寝惚けたまま身支度をし、緑と一緒に家を出るため、急かされていた。 「まだ若いからね。テツとは違うんだよ」 「何だってえ!?」 テツは緑の頭を抱き込み、拳でグリグリと突付いた。 「痛いって、テツ」 楽しそうに笑いながら、緑も反撃する。テツの脇腹を擽って解放してもらう。 「時間がないんだから、こんなことしてる場合じゃないだろ!」 口ではそう言っても、テツの首に腕を回して、縋り付いている。 「甘えん坊だなあ、緑は」 テツも緑の腰に腕を回し、優しく口付けた。あまり濃厚なキスをすると、緑を手放したく無くなるので、触れるだけの軽いものにした。 「テツ…」 「帰ったら一緒に風呂入ろうな」 「うん…」 「好きだよ」 「うん…。俺も…。好きだよ、テツ」 「よく知ってるよ」 見上げて来る緑に、もう一度キスをした。 「行こうか」 まだ縋り付いている緑をそっと離し、玄関を開け、一緒に仕事に向かった。 「なあ、最近元気ないな、お前」 バイト先のコンビニに着くなり、隆史が緑にそう言った。 「そうか?」 「そうだよ。このあいだ会いたくないっていう男が来てから、お前ずっと元気ない」 緑は驚いた。中谷の事で落ち込んでいる事を、誰にも気付かれないように元気に振舞っていた。 「気のせいだよ」 苦笑して、カウンターに向かった。 鉄朗以外の誰にも、弱いところなんて見せたくない。 これが今の緑のプライドだった。 あれから緑は裏の仕事を多くしていた。カウンターに立つのではなく、荷物を片付けたり、冷蔵庫の補充をしたり、商品の注文をしたりしていた。 しかし昼の時間帯だけはそうもいかない。 「お待たせしました」 レンジで温めた弁当を客に渡し、必死に接客していた。 一時近くなり、やっと客が減ってきたその時、店の自動ドアが開き、一人の客が入ってきた。 「いらっしゃ…!!」 入ってきた客は、緑が一番会いたくなかった中谷だった。 「探したよ、緑。いきなりいなくなるなんて酷いじゃないか」 中谷は嬉しそうに笑って、レジにいる緑に近づいた。緑は恐怖のため動けなかった。逃げなくては、と思うのだが、身体か動いてくれなかった。 「変わってないね、君は」 手を伸ばして緑に触れようとする中谷を、ただただじっと見ているしかなかった。 「鷺宮、先に休憩入れよ」 異様な雰囲気を察した隆史が、固まってる緑に休憩を勧めた。 「あ、そうだね。そうするよ」 何とか中谷の手をかわし、奥に引き込んだ。しかし中谷はずっと緑を見ていた。その視線を背中に感じながらも、怖くて振り返る事は出来なかった。 緑は昼ご飯が、喉を通らなかった。襲ってくる不安や、中谷の顔の残像が目の前から離れなかった。 「テツ…」 頼れるのは鉄朗だけだった。 今、鉄朗の声が聴きたくて堪らない。 顔を見たい。 抱き締めてもらいたかった。 「鷺宮、大丈夫か?」 静か過ぎる部屋を不審に思い、隆史が声をかけてきた。 「大丈夫だよ。俺のことは気にしなくててもいいから」 「気にしなくてもいいって…。お前、顔色悪いぞ。帰ったほうがいいんじゃないか?」 確かに鉄朗を感じる事が出来る、あのマンションに帰りたいとは思った。でもここで帰ったら、何だか中谷に負けるような気がして悔しかった。 (あいつなんかに、やっと手に入れたこの生活を壊されて堪るか!) 自分には鉄朗がいると思うだけで、強くなれた。 「さっきの男はもう帰った?」 「帰ったよ。でもいろいろ訊かれた」 「何を!?」 「今どこに住んでるのかって訊かれたし、何時にバイトが終わるのかも訊かれた。もちろん嘘ついといたけど」 「ごめん。ありがとう。でも大丈夫から」 隆史はそれ以上、追及しなかった。緑から、訊いて欲しくないという雰囲気が漂っていたからだ。 人には訊いて欲しくない事がある。 それを訊かないのも優しさだった。 「休憩、代わるよ」 椅子を立ち、カウンターに向かった。 バイトが終わるまであと四時間。 (今日は急いで帰って、テツの好きな天ぷらを作ろう。それから一緒にお風呂入って、鉄の腕の中で寝よう) 頭の中から中谷を消し、仕事に集中した。 5 午後五時。ようやくバイトが終わり、緑は隆史と一緒に店を出た。今日は陽射しが強く、かなり暑い。すでに日は傾いているが、熱が残っており、店を出るとドッと汗が吹き出た。 「地獄だ…」 外の気温にそう感想を漏らした。 店に入ったすぐ、緑は隆史とあまり話さなかった。誰に対しても警戒心が強く、自分から話しかける事は滅多になかった。しかし時間が経ち、隆史がどういう人間かわかるようになり、警戒心がなくなっていった。 今ではもう、仕事中や帰り道でもよく話す。今まで年上の人間ばかり相手にしていて、同じような年の人間との接し方がわからず苦労はしたが、何を話しても返事が返ってきて、笑ってくれる。だから深く考えず話せば上手くいうという事を学んだ。 「家に着くまでの辛抱だよ」 隆史に慰められるが、暑さはなくならない。 「バイトは嫌だけど、涼しいから店に居たいよな」 「そうだな…」 永遠に続くような家までの道のりは、遠くに感じられた。二人が黒い車の脇を通りすぎようとしたとき、車の窓が開き、男が顔を出した。 「緑、待ってたよ」 それは帰ったとばかり思っていた中谷だった。 「なっ…!!」 それまで笑顔で隆史と話していた緑の顔が、恐怖に歪んだ。 「お前!まだ居たのか!」 そんな緑を見て、隆史が中谷に怒鳴りつけた。緑はただ隆史と中谷を交互に見ているしか出来なかった。 「君には関係ない事だろう」 中谷は隆史を見ずにそう言うと、緑に手を伸ばした。 「これから一緒に食事でもしないか。美味しいレストランがあるんだ」 「この野郎!いい加減にしろ!」 隆史は中谷の手を払って、突っ立っている緑の腕を掴み、歩き出した。 「待ちなさい!緑!」 「走るぞ!」 後ろに中谷の影を感じ、二人は走り出した。家の方向に向かうわけにいかず、反対の方向へひたすら走った。三十分近く走っていると、中谷は力尽きたのか、姿が見えなくなった。 「も…もう…この…へ…んで…、いいじゃ…ないか…?」 この暑い中、ずっと走っていれば汗が流れ、話すのも途切れ途切れになる。 「ごめん…」 木陰に座り込みながら、緑は謝る事しか出来なかった。何も関係ない隆史を巻き込んでしまった事が申し訳なくて仕方ない。 「気にするな。それにしても暑いな、今日は」 「訊かないのか?あいつが誰なのか」 「訊いて欲しくないんだろう?」 「どうして?」 「そんな顔してるよ」 隆史はそう言ったが、本当に話さなくていいんだろうか。不自然に感じているだろうという事はわかっていた。しかし話すとなると、昔やっていた仕事の事も話さなくてはならなくなる。 緑は隆史に過去を知られてしまうのが怖かった。知られたら折角友達になれたのに、嫌われるんじゃないかと思うと言えなかった。 こんなふうに思ったのは鉄朗以外では、初めてだった。それだけ緑は隆史に心を開いていた。 「ごめん…」 今はただ、それしか言えなかった。 「謝らなくてもいいよ。それより家まで送ろうか?またあいつに会ったら困るんだろ?」 「大丈夫だよ。女じゃないし、送ってもらうのも変だろ?それに買い物もあるし」 「そっか。じゃあ気をつけて帰れよ」 「ああ。ありがと。ごめんな」 息が整ってきたので、家に帰ることにした。 緑の足は自然と駆け足になる。まだ鉄朗が帰ってきていない事は知っていたが、あのマンションだけが緑が落ち着ける場所だった。 鉄朗の仕事は接待が多く、帰りが遅くなる事がしばしばあった。今日も例外ではなく、接待が入った。 「明智。今日の接待も大丈夫だろ?」 そう上司から言われては、断れない。仕方なく承諾し、緑に知らせるため、電話をした。 「ごめん。今日少し遅くなるから、先にご飯食べててくれるか?」 『そう…』 「緑?どうした?」 声に元気がないのを不審に思った鉄朗は、心配になった。 『何でもない。それで、何時ごろになるの?』 「十時までには帰れると思う」 『うん…。わかった。でもできるだけ早く帰ってきて』 「ああ。終わったらすっ飛んで帰るから」 『待ってる』 電話を切った後も鉄朗は緑のことが心配で、仕事がなかなか手につかなかった。声だけで緑の状態がわかる今、先ほどの声は心配に値するものだった。 (何かあったんだろうか…?) 不安要素はあり過ぎて、困るほどだ。 鉄朗は仕事をしているうちに、心配し過ぎて気分が悪くなってしまった。顔は青ざめて、酷く辛そうな感じだった。 「ちょっと、明智さん!顔色悪いわよ!大丈夫なの?」 心配そうに声をかけてきたのは、以前告白してきた恵里だった。 「えっ!?あ、大丈夫だから」 あれから恵里は家にも電話をしてくるようになった。今はまだ、緑が受けた事はないのでいいが、万が一そんな事があれば緑を傷つけてしまう。 「でも顔色悪いわよ?今日、接待もあるんでしょう?」 「ああ、まあ…」 言葉を濁し、曖昧に返事をするしかない。 「接待。代わってあげましょうか?」 「本当に!?」 「ええ。その代わりお願いがあるの」 「何…?」 一体何を言い出すのか、少し怖かった。とんでもない要求をされたら困ってしまう。 「一緒に暮らしてる子、居るでしょ?その子に会ってみたいの」 「え…?どうして?」 「どうしても。ダメ?」 緑に会わせる事は簡単だが、変に誤解されては困る。折角心を開きかけているのに、また元に戻ってしまったら、きっと二度と心を開く事はないだろう。それが怖かった。 「だた会うだけなのよ?」 鉄朗にとってそれは究極の選択に近かった。 早く帰って緑と話し、抱きしめたかったが、恵里の要求を訊くには怖いものがある。 (どうしたらいいんだ…?帰りたいけど、緑には会わせたくない…。でも今日は緑が心配だ。説明すればわかってくれる。きっと) 「わかった。今度時間作るよ」 「ほんとに!?ありがとう。じゃあもう帰ったら?あとは私がやっておくから」 「それじゃお言葉に甘えて」 鉄朗は恵里に仕事を託し、会社を出た。 心はすでに緑の待つマンションに飛んで行っていた。 6 「ただいま!」 鉄朗は勢いよく玄関を開け、部屋の中の緑を探した。 「テツ!?」 まだ帰ってこないと思っていた緑は、いきなり鉄朗の声がしたのに驚き、慌てて玄関に走っていった。 「ただいま、緑」 まだ驚いている緑をきつく抱きしめ、荒々しく口付けた。 「どうして?遅いんじゃなかったの?」 「緑が心配で帰ってきちゃったんだ。何かあったんだろ?」 「嘘…」 「何が嘘なんだ?」 「俺、何も話してないよ?どうしてわかったの?」 見上げてくる緑がかわいくて仕方なく、押し倒したい気持ちを堪え、笑顔で質問に答えた。 「もう緑の事は声を訊くだけでわかるんだよ」 「テツ…」 胸に顔を埋めて、抱きついた。この胸の中だけが、ただ一つの居場所。安心してすべてを任せられる所。中谷の事で不安でどう仕様もなかった心が、鉄朗の鼓動を訊いていると落ち着いてきた。 「また中谷が来た。今度ははっきり俺だってわかったみたい。バイト先で待ち伏せされて、連れて行かれるところだった」 「何だって!?」 「でも隆史が助けてくれた」 鉄朗は隆史のことを緑からいろいろ話を聞き、知っていた。緑から初めて他人の名前を聞き、楽しそうに隆史のことを語る姿は微笑ましかった。やっと緑にも友達が出来た事を嬉しく思う一方、緑の口から自分以外の男の名前が出ることに少し嫉妬した。 「そうか。大丈夫だ。絶対に俺が守ってやる。誰にも緑には触れさせない」 この台詞を訊く度、緑の心は幸せでいっぱいになる。 「ご飯食べたら一緒に風呂入ろうな。約束だから」 「うん」 緑は背伸びをして、鉄朗に口付けた。 (テツと一緒にいたいから、あいつに好きなようにはさせない) そう固く心に誓った。 緑は丁寧に丁寧に鉄朗に身体を洗ってもらった。最初は少し抵抗があった洗髪も、優しくしてもらう。湯の温かさよりも、鉄朗の体温の方が緑には温かかった。大好きな鉄朗の腕に抱きしめられ、嫌な事をすべて忘れる。この世にたった二人だけなような錯覚さえした。 「テツ、俺も洗ってあげるよ」 バサッと湯を頭からかけられ、泡と落としてから鉄朗の方に振り返った。 「そうか?じゃあ頼もうかな」 鉄朗からタオルを渡され、緑は嬉しそうだった。何度も一緒に風呂に入っていたが、いつも緑が洗ってもらうばかりで、洗ってやった事はなかった。 「目、瞑っててね」 緑はシャンプーを手に取り、濡れている鉄朗の髪に手を差し入れた。何だか美容師になってみたいで楽しかった。 「お客さん、かゆいところはありますか?」 笑いながら鉄朗に問い掛ける。 「特にありません」 鉄朗もすっかり客になり切り、緑に付き合った。 「お客さん。好きだよ」 泡のついた手で、広い背中に抱きつく。まだ目を瞑ったままの鉄朗の顔を覗き込み、キスした。突然の事で多少驚いた鉄朗は、片目を開け、緑を見つめた。 「もう美容師は終わり?」 「まだ」 クスッと笑って、再び髪を洗い始めた。湯で泡を流して、次は身体を洗った。鉄朗は緑に触れられているうち、欲情してきてしまった。それは素直に身体に現れた。 「テツ…」 「ごめん。気にしなくていいよ」 鉄朗は何となく照れてしまい、顔を背けた。そんな鉄朗をかわいいと思う。いつだって自分の事より、緑を優先する。それが嬉しかった。 「テツ、無理しちゃダメだよ」 一言そう言って鉄朗の前に回り込むと、顔を下肢に近づけた。 「緑!そんな事しなくていい!」 慌てて緑を引き上げようとするがすでに遅く、硬くなったものを握られ、動きが一瞬止まった。 「ちょ…!!」 温かい感触に包まれ、抵抗も疎かになる。 緑は熱心に奉仕した。舌を巧みに使い、息づく鉄朗のものを愛撫する。先端を舐め上げ、舌を這わす。そうしているうちに先端から透明な体液が流れてきて、それを舐め取る。 「んん…っ…はあ…」 鉄朗は身体から力が抜け、ただ緑の髪に手を置き、快感に堪える事しか出来なかった。緑はそっと視線を上げ、鉄朗の顔を盗み見た。鉄朗が感じている事を確かめ、更に舌を使い追い上げる。 「緑…、もう、いいから…」 ヤバイと思い、緑を引き上げようとしたが、更に深く咥え込まれうまくいかなかった。 「りょ…く、ヤバイから…」 幾らなんでも口の中に放つわけにはいかない。しかし緑は口を離さなかった。咥え込んで、弾ける寸前の鉄朗のものを吸い上げる。 「くっ!」 吸われて、ずっと我慢していたがそれも限界に達し、ついに緑の口に放った。勢いよく入り込んできた生暖かい液を、緑はすべて飲み干した。 「緑。無理してこんな事しなくていい」 口の端から流れていた白い体液を指で拭ってやりながら、罪悪感に苛まれ、きつく緑を抱きしめた。 「無理なんかしてないよ」 「でもしなくていいよ、こんな事。俺は緑が大切なんだ。だからお前にこんな事させたくない」 「違うよ、テツ。好きだからしてあげたいことってあるでしょ?俺はテツが好きだから、テツが感じてくれるのを見るのが好きだし、嬉しいよ」 自分の気持ちを鉄朗に告げ、罪悪感なんて感じる必要ないことを必死に伝える。 「負けたな…」 緑の言葉に驚き、微笑んで緑を膝の上に抱き上げた。 「緑、賢くなったね」 「テツがいるからだよ」 首に腕を回し、支えてくれる鉄朗を見下ろした。 「軽いな、緑。もっと食わないとだめだぞ」 細い身体を掌でなぞり、首筋に口付ける。 「ねえ、テツ。ここでしよ?俺、もっとテツを感じたいよ」 「ここじゃ危ないからダメだよ」 「支えてくれてるじゃない。それに…。抱かれてるとテツが俺のだって事、実感出来るから嬉しいもん。もっとテツに触ってたいもん。こんな俺…、嫌いになる?」 不安そうに見つめてくる緑が綺麗で、抱き寄せ口付けた。 「嫌いになんてならないよ。絶対に」 「うん…」 頬が紅色し、目が潤んで来た緑をしっかり支え、唇を白い身体に押し付けた。舌をずらし、耳朶を軽く噛むと、緑からくぐもった声が洩れた。 「んっ…あぁ…」 そのまま唇を移し、口付ける。舌を差し込み、緑の口内をくまなく侵す。緑も積極的に舌を絡め、鉄朗を感じた。鉄朗は片手で緑の腰を支え、もう片方で胸の尖りを弄った。 「ああっん…ああっ…やっ…」 鉄朗にされる刺激に、体のすべてが熱を持ち、腰の辺りがムズムズと蠢く。 「はぁ…っ…あぁ…っあ…」 緑の喘ぎがバスルームに響く。身体が反り返り、鉄朗の上から落ちそうになり、慌てて両手で腰を抱いた。 「緑、しっかり首に掴まってて」 急に愛撫が止まったのに、顔を戻して鉄朗を見つめた。 「え…?何…?」 「しっかり掴まってて。危ないから」 「ん…」 曖昧に頷くと、顔を鉄朗の肩に埋め、身体を密着させた。二人の身体の間に挟まれている緑のものは、すでに先端から蜜が溢れ、鉄朗の下腹を濡らしていた。 「好きだよ、緑。ずっと愛してる…」 耳元に囁いて、自分の唾液に濡れた指を後ろに持っていき、そっと挿入した。緑の内は熱く、鉄朗の指を締め付ける。 「あぁあっ…て…つ…ふっ…あぁ…」 指で内を探り、緑の感じるポイントを何度も擦り上げる。指を抜く度きつい締め付けにあい、鉄朗も我慢できなくなる。 「緑、いい?」 顔を覗いて、頷いたのを確かめ、再び勃ち上がっていた自分のものを、潤っている蕾に押し当てる。 「んっ…」 先端が触れたのを感じ、緑から声が洩れた。ゆっくりと侵入し、緑を繋ぎ止める。 「はぁ…!!ああぁ…」 挿入と同時に緑の身体が反り返った。鉄朗は緑の腰を引き寄せ、一気にすべてを押し入れた。 「あっ…あっ…ふっ…ああ…」 緑は自分から腰を動かし、鉄朗から快感を受け取る。鉄朗は緑のものを扱き、更に快感を与えた。 「ああ…はあ…ああん…」 上下に体を揺すり、身悶える。もう意識は吹き飛び、体だけが鉄朗を感じるものになっていた。 「テ…ツ…テ…ツ…あぁ…は…」 何度も名前を呼び、その度に突き上げられ、もう我慢できなかった。 「あぁっ…もう…イ…きそう…」 緑から最後の頼みの声が聞こえ、扱く手を速めた。 「ああ…っは…あぁあっ…ああっ!」 鉄朗の手の中に白い快感の印を放ち、きゅっと鉄朗を締め付けた。 「くっ!緑…」 鉄朗も締め付けに堪えられず、緑の中に二度目の欲望を解き放った。 緑はぐったりと鉄朗に身を預け、荒く息を吐いている。 「緑…。好きだ。誰にも渡さない。俺だけのものだ」 自分の方によりいっそう体を抱き寄せ、腕の中に抱き込む。緑はそっと顔を上げ、自分の首筋をさ迷っていた鉄朗の唇を指先でなぞった。 「俺…、テツのもの?ずっと?」 「そう。ずっと俺のもの。だからどこにも行くなよ?」 「行かないよ」 指でなぞった場所を舌で辿った。 明日のことを考えると怖くなる。また中谷が居るかもしれない。何か言われるかもしれない。それでも今だけは何も考えず、鉄朗の体温だけを肌で感じていた。 |