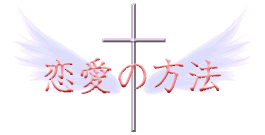 |
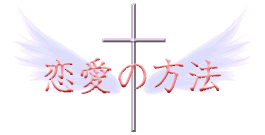 |
![]()
1 緑と鉄朗は暖かな温もりの中にいた。それは布団の温もりだけではなく、隣からお互いの確かな熱が伝わってくる。 二人が一緒に暮らし始めて三ヶ月が経ち、恋人同士になって一ヶ月が過ぎた。 緑はそれまでやっていたレストランのウェイターを辞めて、新しいバイトを見つけ充実した毎日を過ごしていた。 それでもまだ孤独感からは抜け出せない。 鉄朗が出張などでいないとき、無性に寂しくてテレビや音楽を必要以上にかけて気を紛らわす。鉄朗が帰ってきたらべったりとくっついて、甘えるというのが緑のパターンだ。 言葉だけでは心が満たされない。 鉄朗に抱きしめられて、口付けされて、貫かれる痛みを感じて心が満たされるのだ。 しかし初めて鉄朗に抱かれてから一ヶ月経つが、まだ抱かれたのはたったのはたったの五回で、他はただ一緒に寝るだけなのだ。 鉄朗は緑に負担をかけたくなくて何もしないもだが、欲求不満にはなる。それでも緑が愛しくて自分を押さえつけていた。 緑はもともと精力が強い方ではなかった。 それは過去に身体を売っていたからセックスに飽きて興味がないというより、緑にとってセックスは商売でしかなかった。 愛する二人が言葉では足りないのもを埋めるために、身体を重ねるなどという事を知らなかった。 それが鉄朗に抱かれるようになってから変わってきた。 抱かれる事に喜びを感じる。 相手が男でも鉄朗なら嬉しく思うのだ。 それまではセックスをする事に感情は伴っていなかった。 今は何も不満はない。 緑の望みはたった一つ、鉄朗の傍にいること。 ただそれだけなのだ。 「緑、もう朝だぞ。起きろよ」 腕の中で気持ちよさそうに眠っている緑にそっと声をかけて起こした。 昨夜鉄朗は久ぶりに緑を抱いた。 出張から帰ってきた途端、緑は鉄朗に抱きついた。たった三日間鉄朗が傍にいなかっただけで、寂しくて変になりそうだった。 だから緑から誘ったのだ。 「あと少しだけ…」 いつもは鉄朗が起こしてもらうのだが、今日は昨日の行為のせいで緑が疲れているだろうから自分が起きなくてはと思い、何とか起きる事が出来た。 「バイトに遅れるぞ」 「ん、わかった…」 もそもそと布団から起き上がり、鉄朗に笑いかけた。 ずっと寝不足で身体が辛かったが、昨日の夜、やっと満足に眠る事が出来た。鉄朗がいないあいだ寂しくて、落ち着かなくて、よく眠れなかったのだ。 「どうしたの?テツが俺より早く起きるなんて珍しいじゃん」 「緑のためならなんだって出来るんだよ。早く起きることなんてあさめしまえ」 「テツ…」 裸のままの身体を鉄朗に摺り寄せて、また甘えた。 緑は鉄朗に出会ってから人に甘える事を覚えた。誰かに頼って、弱い自分を見られるのが嫌だった。 一人で生きていける、その思いが強かった緑は自分以外は信じられなかった。弱い自分を曝け出すことが出来るのは、今でも鉄朗の前だけだった。 「俺、今日バイト休もうかな。だってテツ、仕事休みだろ?ずっと一緒にいたい」 首に腕を回し、見下ろしてくる緑を抱きしめながら片手で髪を梳いてやる。緑は気持ちよさそうに目をとじて鉄朗にされるが侭になっている。 「俺だって一緒にいたいけど、バイトは休むな。やっと見つけたんだからしっかり働かないと」 「そうだけど、寂しかったんだもん。テツがいなかったあいだ俺ずっと一人だったんだよ?だから…」 緑はぴったりと鉄朗に抱きついて、離れようとしなかった。 「俺はずっと緑の傍にいるから安心しろ。だからバイトには行ってこい。俺がうまいもの作って待ってるから」 優しく宥めて、緑を抱え上げてベッドから出た。 緑はただ鉄朗をじっと見つめている。 「俺が体洗って綺麗にしてやるから、ちゃんとバイト行けよ」 「わかった…」 少し不満だったが、鉄朗がそう言うのなら仕方がない。 おとなしく抱かれて、浴室へと連れていかれた。 たっぷりと張った湯の中に下ろされて、後ろから抱き込まれる。 朝、風呂に入るときは大抵、一緒に入る。 緑は最初、行為のあと一緒に入る事を躊躇った。鉄朗のことは好きだが、一緒に入ってしかも身体を洗ってもらうなんて甘え過ぎだと思ったからだ。 しかし今はそれが当たり前になっている。 信じる事、頼る事を鉄朗から教えられた。 緑の中で少しずつ変化が現れている。 他人に依存するようになった。 空っぽだった心の中が埋まっていく―― 「夜、何食べたい?」 緑を抱きしめたまま、顔を覗き込んで尋ねる。気持ちよさそうにしていた緑は、だるい身体を反転させ、鉄朗と向い合った。 「テツが作ってくれるものならなんでもいいよ」 「食べたいもの、ないのか?」 「うん。これといったものは特に。テツが作ってくれる事が嬉しいから」 「緑より下手だぞ?」 「そんな事ないよ。俺、テツの料理が一番好きだもん」 上目使いでかわいいことを言ってくれる緑の頬を包み込んで、鉄朗はそっとキスをした。 愛しさが募る。 「家で待ってるから、頑張って働いてこい」 「うん…」 もう一度キスをして、二人は風呂をあとにした。 2 緑の新しいバイト先は駅前にあるコンビニだった。 場所が駅前だけあって客の数は半端じゃなく多い。特に朝のラッシュ時、正午の昼時、夕方の帰宅時などは忙しくて休む暇はない。 しかし緑は忙しい方が好きだった。時間があっという間に過ぎていき、気付くと帰る時間になっている。待っている人がいる今の緑にとって、その方が時間が短く感じてよかった。 バイトの時間は朝八時から夕方の五時までで、帰りに買い物をしていく。鉄朗のために何かを出来ることが嬉しくて、買い物も楽しいものだった。 緑はいつものとおり朝八時前に店に行き、接客をした。 通勤前のサラリーマンや通学前の学生、作業着を着た若い男など、店に来るのはさまざまな人がいた。忙しいので客の顔は憶えてはいない。それでも昼に来る常連客などは、次第に憶えるようになってきた。 やっと見つけたこの仕事を、緑はまじめにこなしていた。遅刻はしないし、今までなかった愛想も身に付けた。だから客からの評判はよく、店長も緑のことを気に入っていた。 「緑、冷蔵庫の補充に行って来てくれ」 店長の西野がレジをやっていた緑にそう告げた。 「わかりました」 素直に従い、冷蔵庫に向かう。 コンビニの冷蔵庫はジュースやお酒が所狭しと並んでいる。それを前の棚に並べるのが仕事だ。夏は涼しくて気持ちがいい。 「あーあ、早く帰りたいな…」 手を動かしながら、頭の中は鉄朗のことでいっぱいだ。 最近緑が考えている事は鉄朗のことばかりだった。 今何してるのかな、今日は鉄朗に何を食べさせてあげようか、そして鉄朗に捨てられたらどうしようか…。 他人の心が覗けなくてもどかしくなる。 「テツ、家で何やってるんだろう」 そんな事を考えて作業する事一時間、冷蔵庫の中の仕事がようやく終わり、再びカウンターに戻った。 昼のバイトは二人いて、レジをやったり、商品の補充をしたり、注文をしたりと忙しい。 「いらっしゃいませ」 緑ともう一人、一緒に働いている北原隆史が同時に入り口を振り返った。 そして緑の動きが止まった。 そこには以前、緑を無理やり犯した中谷繁利が立っていた。 (あいつは…!!) 瞬時に中谷と悟った緑は、奥の事務所に逃げ込んだ。 顔を見られればすぐにばれてしまう。 どうしても会いたくなかった。 思い出したくない事が頭の中にフラッシュバックする。 「鷺宮、どうしたんだ?」 急に事務所に引っ込んだ緑を不思議に思った隆史が訊いてきた。 「ん、ちょっと会いたくない人がいてさ…」 「店の中に?」 「そう」 視線を中谷に向けると、あちらも緑の方を向いていた。 (ばれたのか!?) 不安になり、その場に蹲ってしまった。 鉄朗に出会ってやっと幸せを掴んだと思った。 ずっと鉄朗といられるだけでよかった。他は何も望んでなんかいなかった。 (俺には幸せになる権利なんてないってこと?) 緑は無性に鉄朗に会いたくなった。 抱きしめて、キスをして、めちゃくちゃに抱いて欲しい――。 そうして自分の不安を拭って欲しかった。 「テツ…」 ポツリと呟き、もう一度外を見てみた。そこにはもう中谷の姿はなく、緑はまた仕事に戻った。 夕方五時、ようやく緑のバイトが終わった。 緑はとにかく急いで鉄朗が待つマンションへ戻った。見なれたいつものマンションへの道のりが、今日はとてつもなく長く感じた。 ガチャッと勢いよく玄関を開け、部屋に飛び込んだ。 「テツ!」 鉄朗は誰かと電話で話していた。 「………」 「ごめん」 「諦めて欲しい。じゃあもう切るから」 「テツ?」 会話を不思議に思い、怪訝な顔つきで鉄朗を見た。鉄朗はそんな緑に優しく微笑んで、抱きしめた。 「何でもないよ。それよりお疲れさま」 髪を撫でてやりながら顔を覗きこむと、不安そうに鉄朗を見つめる緑がいた。 「どうした?」 心配になり、訊いた。 「中谷が…」 一旦言葉を切って、俯きながら再び口を開いた。 「中谷が店に来たんだ」 「中谷って、まさかあの時の…!!」 「そうだよ。テツ、俺怖いよ。どうすればいい?」 緑は鉄朗に縋り付き、不安な心を吐露した。 やっと手に入れた今の生活を無くしたくなかった。もう一人では生きていけない。 鉄朗なしの人生なんて考えられなかった。 「まだ緑に気付いたかどうかわからないから、しばらくは様子を見よう」 「でも…」 「大丈夫だ。緑は指一本触れさせない。俺が守ってやるから安心しろ」 鉄朗は宥めるように、優しいキス顔中に降らせた。しばらくすると、緑の顔から薄っすらと笑みがこぼれるようになり、綺麗な顔が戻ってきた。 「腹減っただろ?約束通り作っておいたから食べよう」 「何作ってくれたの?」 「パスタ。カルボナーラなんだけど、ちゃんと卵をとくところから作ったんだぞ。どうだ、すごいだろ?」 胸を張って威張る鉄朗を見て、おかしくて吹き出してしまった。 (やっぱりテツだけだ、俺を安心させてくれるのは) 緑は改めて鉄朗の存在の大きさに気付いた。 短い時間の中で、鉄朗の存在だけがどんどん膨らみ、今では緑の心の全体を占めていた。 ずっといろんなものに裏切られて、信じる事を恐れていた緑を根底から変えてしまったのだ。 「ねえ、テツ」 「なんだ?」 一緒にテーブルに向い合って座り、フォークでパスタを巻いて口に運んだとき、緑が止まったまま鉄朗を呼んだ。 「このスパゲッティ、甘いんだけど…」 「うっそ」 慌ててカルボナーラを食べてみると確かに甘い。 「もしかしてパスタを茹でる時、砂糖入れなかった?」 「さ、砂糖!?」 (俺、間違えたっけ?) 思い出してみると、そんなような気がする。 最近、料理はずっと緑がしていた。だから久ぶりに台所に立ってみたら、どこに何があったのか、記憶が曖昧だった。砂糖は塩の隣に、同じ容器に入れてある。 「砂糖、入れたかも…」 情けない顔をしてうな垂れてしまった鉄朗を、緑はかわいいと思った。 そういうところも全部好きなのだ。 「大丈夫だよ。食べられるんだし」 「やっぱり緑が作ったほうがうまい。ずっと俺のために料理してくれるか?」 プロポーズともとれるこの言葉に、緑は驚いてまじまじと鉄朗を見つめた。 「ずっと…?」 「ああ。ずっと」 「テツの傍にいてもいいの?」 「俺が頼みたいぐらいだよ」 嬉しくて涙がこぼれた。 人に必要とされていると実感出来た事が嬉しかった。それが一番大切な鉄朗からだったので尚更だ。 「俺、テツのこと好きだよ。誰よりも好きだから」 「わかってるよ」 鉄朗がスッと手を伸ばすと、緑は立ち上がって縋りついた。 「好きだよ、緑」 「俺も…」 鉄朗は綺麗な顔を包み込んで、唇を重ねた。軽い口付けは次第に深くなっていく―― 薄く開いた口から舌を探り出し、絡める。 「ふっ…んん…」 首に腕を巻きつけ、離さないように鉄朗の舌を味わう。 「はぁ…んん…は…」 二人の間から、どちらのものかわからない吐息が洩れる。 「今はここまでにしよう」 肩に顔を埋めて、離れようとしない緑を驚かせないように離した。 「いやっ…」 離れるのが不安で抱き付く腕に力をこめた。 「緑、俺はここにいるから。どこにも行かないから安心しろって」 それでも不安そうに緑は鉄朗を見つめた。 いつも不安は付き纏っていた。たくさんの言葉を貰っても、確かなものは何もない。信じられるのは感じることが出来るものだけだ。 「緑、とりあえずご飯を食べよう」 「うん…」 ようやく鉄朗から離れた緑は、目に涙を溜めていた。 今日、店で中谷に会ったことが、思った以上に緑を不安にさせた。それまでの寂しい生活や、独りだったこと、強がって生きていたことすべてを思い出させた。 ふと、あるとき客に言われた言葉を思い出した。 「俺ね、薔薇みたいだって言われた事あったんだ」 「薔薇?」 「うん。ほら、薔薇ってすごく綺麗な花でしょ?でも周りにたくさんの棘をつけて、いろんなものを拒んでる。誰も寄せ付けない雰囲気が似てるんだって、俺に」 遠くに視線を向け、淡々と語る緑は確かに薔薇のように綺麗だった。赤い唇が動くたびに、ドキドキさせられる。 しかし今は棘は取り払われている。 「綺麗なところだけは似てるな」 指で赤い唇をなぞる。 緑は目を閉じて、顔を近づけ唇を押し付けた。 「さ、食べようか」 今度はあっさりと離れて、座っていた椅子に戻った。 3 ゆっくりと風呂に浸かってから、一緒にベッドに入った。 シーツは鉄朗が昼間洗濯したので、綺麗に伸ばされている。 「ねえ、テツ」 「ん?」 鉄朗の胸に頭を預けて縋りつく緑は、どうしても今日は抱いて欲しかった。確かな温もりが、愛が欲しくて堪らなかった。 「抱いて欲しい」 「緑!?」 「抱いて欲しい」 見つめてくる瞳の奥に、恥らいと不安が入り混じっていた。 「昨日もしただろ?体に負担がかかるからやめよう」 「負担なんてかからない。大丈夫だから。お願い」 「緑…」 今日はずっと変だった。鉄朗はどうしてなのかわかっていたが、心配になってきた。 今までも不安そうにしていたときはあった。それでも今日ほどではなかった。 「いいのか?」 「うん…」 恥ずかしそうに頷く緑をきつく抱きしめた。 「好きだよ、緑。愛してる」 この一言で心が安らぐ。 「テツ…。テツ…」 何度も名前を呼んで、背中に爪を立てる。 ゆっくり服を脱がされながら、鼓動が早まっていく。 深く、深く唇を重ねて、熱を与え合う。 「んんん…は…あぁ…」 触れ合う肌が気持ち良くて、甘い声が洩れる。 「ふっ…あぁ…っ…あ…」 胸の敏感なところを舐められ、感じている事を声で伝える。 緑の瞳から涙が流れた。 しかし顔は幸せそうに微笑んで、鉄朗に触れられている場所を憶え込む。 「ああっ…テツ…はや…く」 まだ服を脱がし終えていないのに、鉄朗を求めた。貫かれる痛みを考えると恐怖が甦る。でも今は恐怖よりも確かな痛みを感じたかった。 熱い鉄朗を感じたい。 「緑、やっぱりやめよう」 「どうして?俺がイヤ?嫌いになった?」 「嫌いなわけないだろう。でも今日はやめよう。ゆっくり眠った方がいい」 「嫌だっ!」 涙声で必死に抱き付いた。 「このままじゃ眠れないよ!俺を独りにしないで!離れたくない!」 「緑、落ち着け。大丈夫だよ。俺はここにいるから。離さないから。とにかく落ち着け」 「テツ…っ…テツ…」 中谷に再会したことが緑の精神状態を不安定にさせた。壊れてしまいそうな繊細な心が、揺らいでいた。 「な?俺、ここにいるだろ?」 冷えた緑の手を掴んで自分の頬に当てた。 冷たかった掌が熱を帯びていく。 「テツ…?」 「そうだよ」 軽いキスをして、細い身体を抱え込んだ。 「朝までこうしてるからゆっくり眠れ」 「うん。ねえ、もう一回キスして」 「何度でもしてやるよ」 目を閉じた綺麗な顔に、啄ばむように何度もキスをした。 そうしているうちに緑は落ち着きを取り戻し、深い眠りに引き込まれていった。 安らかな寝顔だった。 緑は疲れていた。 肉体的にではなく、精神的に。 やっと手に入れた幸せが壊れそうな気がした。怖くて仕方なかった。 もう、独りには戻れないから。 鉄朗の温もりを知った今は。 相変わらず綺麗な顔に、涙のあとが一筋残っていた。 鉄朗はそっと顔を近づけ、その跡を舐めて消した。 |