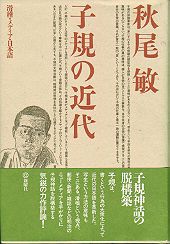
『子規の近代 -滑稽・メディア・日本語-』
秋尾敏 著 新曜社 ¥2,800(税別)
平成11年7月30日発行
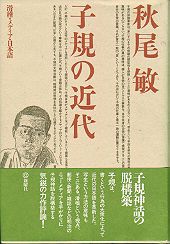 |
『子規の近代 -滑稽・メディア・日本語-』 |
各新聞・雑誌に、次の書評をいただきました。感謝いたします。
岸本尚毅氏 「個人の意識と歴史の関係」
共同通信配信(千葉日報・徳島新聞9/12・愛媛新聞9/12・京都新聞9/19 等)
嵐山光三郎氏 「俳諧革新進めた原動力さぐる」
読売新聞9/25
川名 大氏 「神話突き崩す深い洞察力」
読売新聞9/24夕
(羽)氏 「俳句の生成、縦横に展開」
千葉日報 99/8/24
無署名氏 中日新聞 99/9/19
産経新聞 99/8/28
川名 大氏 「2000年俳句研究年鑑」 富士見書房
宇多喜代子氏 「2000年俳句年鑑」 角川書店
虚子と碧梧桐を論じた部分が、平成12年度信州大学入学試験問題になりました。
| 期待していた以上の反響があって驚いている。かなり特殊な分野を扱った本だし、また内容も決して一般的とは言えない部分もあるので、なかなか読んではもらえないだろうと思っていた。しかし新聞や俳句総合誌の書評に数多く取り上げていただき、少しずつではあるが読者を広げているようなので、不思議な気がしている。やがて批判や反論を頂けるようになれば本物であろう。 『子規の近代』のテーマは、人間にとって文学とはどのようなものであるのかということと、近代という時代がどのような時代であったのかということを「俳句」という文化をとおして考えていくことである。 俳句とは何か、子規とはどのような人か、という問題は、いわばモチーフであり、表層の問題である。それは重要なことではあるがテーマとは言い難い。しかしモチーフであるということは、私の興味がそこにあるということで、決していいかげんなことではない。そのことにこだわり、こと細かに調べていくことによってしかテーマを解決する方法はない。 頂いた手紙の中に、「神は細部に宿る」という言葉があった。この本が、執拗に細部にこだわることによって、ものごとの本質に迫っていこうとしているという意味である。これは大変うれしい批評であった。私も、ものごとの本質は、細部にこそ宿っていると信じるものである。例えば書き出しの部分で、子規の「死はいやぞその如月の二日灸」という句の「ぞ」にこだわったのもそのためである。この「ぞ」には、明治という新しい時代の言葉の揺らぎや、その時代の青年の自意識のあり方などがはっきりと現れているのである。 また「回転するコンピュータグラフィック」という批評もあり、これも私が意図したことを見事に言い当てて下さっている。俳句とか子規とか近代とか文学とかいうものを、さまざまな角度から見てもらおうというのが、あの本の構成の意図だったのである。中には、章ごとに変化する書き方にとまどわれた読者がいらっしゃったかもしれないが。 明治以降、文学は、「純文学」と呼ばれる私小説を中心として語られていく。私小説には、時代を先取りする意識、すなわち「近代的自我」がとらえた「遅れた日本の状況」が記述されていた。その結果、「近代的自我」を読み、日本の遅れた状況を自分自身でどう超えていくかを考えることが、文学を理解するということの中心となってしまった。恋愛にしても社会問題にしても、遅れた日本の中で、未来のために若者がどう考えるかということが、文学のテーマのほとんであった。そのことを取り上げていない文学は、正統なものと見なされなかったといってもよい。その状況は、つい二十年ほど前まで続いていたのである。 しかし最近になってだいぶ様子が変わってきた。日本が遅れているなどと少しも思っていないらしい文学が現れ、また作品の中の主人公の悩みなどあまり問題にしない読者が増えてきたのだ。小説でワインを覚え、デート用のレストランを選ぶと言った現象である。それは今までの小説の読み方に慣れた人々の目には、かなり憂うべき状況と映ったようだ。 だがそれは、文学が堕落したのでも不真面目になったのでもなく、文学の多様な側面が認められるようになったということなのである。文学には、遅れた状況を告発するという機能もあるが、それがすべてではない。特に俳句という文芸は、そんな狭い文学の定義に収まるものではないのである。 さらに、文学というものが単に受容するものであるというような認識もいささか貧しい考え方である。すべての文化は行為することに意味があるので、自らが創造の側に立ち、表現できるような社会こそが豊かな文化を持つ社会だと言えよう。ギャラリーの存在も重要であるが、しかしプレイしないギャラリーというのもおかしな存在なのである。 今、人間一人一人の意識の価値が問われる時代にあって、俳句のような文芸の存在意義は大きい。普通の人々に表現の可能性を与え、世界観の基盤を与えるものとして俳句をとらえるとき、初めて俳句というものの意義の全貌が明らかになるはずである。 |
序
Ⅰ 子規の文学
一 近代のさざなみ
二 俳句の旅立ち -『桜句合せ』をめぐって-
1 『桜句合せ』
2 月並と伝統
3 露伴の目
4 『月の都』
5 『三人物語』
三 子規と「文学」
1 文学という概念
2 文学の機能
3 日本語の近代化と言文一致
4 子規の文学
Ⅱ 明治の俳諧
一 俳諧明倫講社から書生俳句へ 一新聞記事に見る明治中期の俳諧-
1 明治俳諧の評価
2 俳諧改良会員の決闘状
3 点取俳諧の流行
4 明倫講社の運営
5 新世代の意識
6 国民意識と近代的自我
二 明治の俳書
1 残された俳書
2 東京の俳諧
3 地方の俳書
4 明治の点取俳諧の価値
三 月並調の形成
四 月並俳諧の変容 -メディアの活用とリアリズムへの展開-
五 滑稽の伝統 -発句から俳句へ-
1 『人来鳥』
2 『雅の力競』
3 『花たら誌』
4 『風雅新誌』
5 『我楽多文庫』
6 雑俳と俳句
Ⅲ 風景と俳句
一 子規の近代 -俳句の成立を巡って-
1 言葉
2 子規の登場
3 明治二十八年 -状況の認識と内面の形成-
4 読者の生成
5 イメージ
二 癒すものとしての風景 -写生の成立-
Ⅳ 近代日本語と俳句
一 言葉とメディア
1 「文」の形成
2 標準語と言文一致
3 メディアとしての子規
二 解釈の座 -『蕪村句集講義』-
1 文学の解釈と俳句
2 『蕪村句集講義』
三 楕円の中心 -虚子と碧梧桐-
1 二人
2 子規の言葉
3 虚子の近代 ―非在の構造、あるいは関係性について―
4 碧梧桐の近代 -主体の形成-
5 楕円の中心
おわりに