|
|
今日の矢切地区の江戸川ぞいの水田、ねぎ畑地帯が農地等として開発されたのは、江戸時代に入ってからの慶長・元和(1605〜1613)以降のことで、それまでは、見渡す限り、広々とした野河原で、一面に”よし”が生い茂っていました。
また、1713年頃までは、江戸川沿いには民家、寺もあり村の中心地であったが、打続く水害で、寺も民家も高台へ移転した。
この湿地帯を農地等に開拓したのが外山忠兵衛という旗本でございました。その子孫には、幕末から没する明治33年まで、西欧文化移入による啓蒙活動をし、他分野にわたり欧風開花運動し、本邦初の東京帝国大学名誉教授になられた外山正一殿がいらした。
|
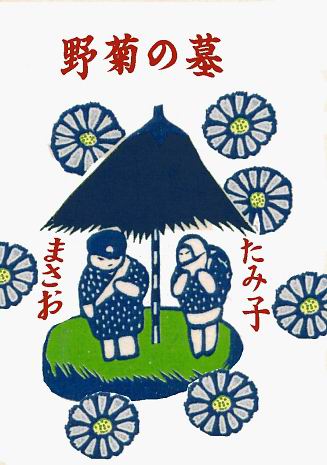
|