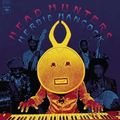
Produced by David Rubinson Recorded : 1973 Released : October, 1973 1.Chameleon, 2.Watermelon Man, 3.Sly, 4.Vein Melter
ここ数日のあいだ、ふと時間があるとファンクについて考えてしまう。というのも、自分 のなかでファンクというものに対して靄のようなものがかかってしまったからで、そうな ってしまうと靄をはらすためにいろいろと確かめたくなってしまうのである。ジャズ・ピ アニストとして有名なハービー・ハンコックという人がいる。近年では、ノラ・ジョーン ズやティナ・ターナーをゲストに迎えたジョニ・ミッチェルへのトリビュート作品が話題 となった人だが、この人が1973年に発表したアルバムに『ヘッド・ハンターズ』というア ルバムがある。ジャズやフュージョンのファンならば、聴いたことはなくても知らぬ人は まずいないだろう。ヒップ・ホッパーやDJの間では、サンプリングのネタ元としても有 名なアルバムだ。このアルバムに《カメレオン》という曲が入っているのだが、この曲を 聴いてファンクについて考えてしまったのである。 これまでぼくは、ハンコックの《カメレオン》について「これはファンクの傑作」だと思 ってきた。ぼくの手元にある音楽紹介本の『ヘッド・ハンターズ』について書かれた文章 をいくつか読んでみると、ファンク、エレクトリック、フュージョンなどの単語が、アル バムを紹介するキーワードになっているようである。それに対しては、いままではとくに なんの疑問も抱かなかった。エレクトリック楽器を使っていることは事実だし、後のフュ ージョンにつながる要素も確かにある。しかし、ふと”ファンク”という言葉には立ち止 まってしまったのである。『ヘッド・ハンターズ』や《カメレオン》のいったいなにが( あるいはどこが)、ファンクというキーワードと結び付くのだろう。そもそも、なにがフ ァンクなのか。そんなことを考えるうちに、よく見えていたと思っていたファンクに靄が かかってしまったのである。 ぼくが、《カメレオン》で一番ファンクを感じるところは、シンセサイザーを併用したヘ ヴィーなベース・ラインである。”グゥォン、グゥォン”と低音でなにかをえぐるような ベース・ラインは、メインのメロディ以上に印象に残る。ジャケットのイメージも手伝っ て、ヘヴィーなだけではなく無機質な印象も受けるベース・ラインである。しかし、その ヘヴィーで無機質なところに、ものすごくファンクを感じさせるのだ。そうなると、なぜ そう感じるのか、秘密を探りたくなってくる。ハンコック(あるいは作者としてクレジッ トされているメンバーのだれか)は、どのようにして、このベース・ラインを考え付いた のだろう。音楽においては、100%新しいものというのはない。かならずそれまでに創られ た音楽に、インスパイアされたものがあるとぼくは思っている。それを探せば、ファンク の正体がつかめるかもしれない。そんなことを考えてしまう今日この頃なのである。
| Head Hunters ( Herbie Hancock ) | |
|---|---|
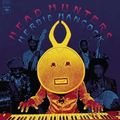
|
Produced by David Rubinson Recorded : 1973 Released : October, 1973 1.Chameleon, 2.Watermelon Man, 3.Sly, 4.Vein Melter |