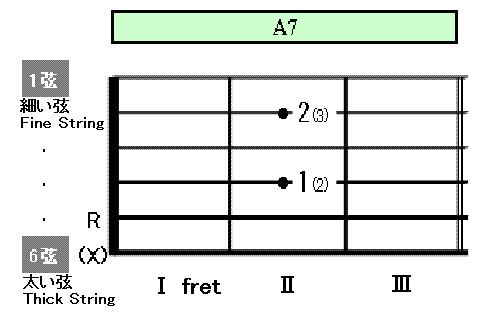

ベース弦(6,5,4弦等)を親指で弾いた直後、
その親指をとなりの弦(5,4,3弦等)に一旦乗せてからすみやかに離す。
この奏法をアポヤンド(スペイン語)と言う。
アポヤンドは強い音や長く響かせる音を出したいときに有効。
したがって指弾きの歌伴奏では、
ベーストーンを親指で弾くときアポヤンドにすると良い。
When you pick the bass string (6th, 5th or 4th) downward with thumb,
the thumb should rest on the next string(5th, 4th or 3rd)
just after picking.
And then it should be detached.
We call this way of picking “Apoyando”in Spanish.
The picking in the way of Apoyando can make the strong and long tone.
So we usually use Apoyando style
to play the bass note of the chord strumming when we sing.
弦を弾くときの通常使われる一般的な奏法。
弦を弾いた後の指は隣の弦には触れない。
アポヤンドと区別するために使われる言葉。
The ordinary finger picking of the string is called “Al Aire”in Spanish.
In this way, the finger dosen't touch any other string just after picking.
This is antonym of “Apoyando”.
イタリア語。語源的にはアルパすなわち楽器のハープから来ている。
ハープのいくつかの弦をいちどきに鳴らすときの
ボロロンッといった響きを表現している。
ギターのコードを弾くときには、
いく本かの弦を同時に弾かず分散させて弾き、
各音を綾なすように鳴り響かせる奏法を“アルペジオ”と呼んでいる。
したがって分散和音と呼ぶこともある。
歌伴奏ではフィンガー・ピッキングの最も基本的な奏法として良く使われており、
バリエーションとしてのアルペジオ・パターンは非常に多種多様。
ギター奏法としてのアルペジオは、
特に歌伴奏に際しては以下のように弾くのが一般的。
原則として6、5、4弦等低音弦を弾くには右手親指(T)で、
かつ比較的強音の出やすいアポヤンド奏法で弾き、
一方高音弦を弾くときは通常のアル・アイレ奏法だが、
それぞれの弦に受け持ちの指が次のように決まっている。
高音の
3弦は人差し指(I)、2弦は中指(M)、1弦は薬指(R)
を使って弾くのが原則。
This Italian music term come from the word arpa - harp.
The way of chord playing like a harp,
when its many strings are plucked at a time,
are called “Arpeggio”.
There are many kinds of arpeggio patterns.
And these arpeggio patterns are often played
as the accompaniment of the songs by many singers.
The way of playing is following.
Each bass string of 6th, 5th & 4th should be picked
with a thumb of the right hand in the "Apoyando" style.
The higher pitched strings like 1st, 2nd and 3rd
should be played with the other fingers.
Generally,
the 1st string is picked with the ring finger of the right hand
in the "al aire" picking way,
the 2nd string is picked with the middle finger in the "al aire",
and the 3rd string is picked with the index finger in the "al aire".
This is the traditional arpeggio picking style of the guitar.
今までに楽譜とかコードつきの歌詞などを読んで歌ったものの中で、
メロディーの高さが高すぎたりまたは低すぎたりして、
歌いづらかったという経験はありませんか?
それもそのはず声の音域(声域)は人それぞれ皆違うのです。
だから自分の声域に合った高さで歌えば全ての歌が無理なく楽にうたえますが、
書かれているコードやメロディーが
必ずしもあなたの声域に合っているとは限りません。
メロディーの高さを決定しているのはキー(調性)です。
キーは理論上12あります。
ならば12ある内の自分の声域にちょうど良いキーに、
曲のキーを勝手に変えてしまえば良いわけです。
曲のキーを変えること、すなわち別のキーに移し変えることを移調と言います。
この移調ができれば、
楽譜や歌本などに書かれている曲を全て自分の都合の良いキーに自由に変えて、
楽に気分よくうたえるのでとても便利です。
具体的な移調の仕方については
「阿部俊朗のテキスト解説092(番外レッスン2.)」を参照。
When you sing a song
while reading the words and the chords of some song book,
you may feel that
the pitch of the melody is too high or too low for you to sing.
If you feel so,
you had better to change the key to another
in which you can sing more comfortably.
The song is generally sung
depending on the individual vocal range of each one.
So it is not necessarily comfortable for you to sing in the key
in which key someone else feel good to sing.
We call the changing one key to another "Transposing".
For you as a performer,
it is very comvenient and useful
that you will become to know how to transpose from a key to another.
If you want to know the way of transposing practically,
See "AN EXTRA LESSON2. by Toshiro ABE"
歌いだす前やメイン・テーマの演奏が始まる前に、
通常楽器などで演奏される序奏部分のことを、
「イントロダクション」略して「イントロ」と呼ぶ。
イントロがあると、
曲のピッチ(音程)やテンポ(速度)が前もってわかるので歌いだしやすい。
The strumming or playing which is played before your start of singing
is called “Introduction”.
This introduction will give you the pitch of the first note
and the tempo in which you should sing.
一小節四拍の小節でダウン、アップ交互で8ストローク弾くと
“エイト・ビート”と呼ばれるリズムになる。
アクセントは四分音符刻みで考えれば通常通り2拍目、4拍目だが、
8ビートなので三つ目と七つ目の八分音符であるダウン・ストロークに置く。
実際に8ビート・リズムを弾く場合には、
ダウン・ストロークとアップ・ストロークの音の長さは
全く同じでなければならない。
エイトビート・リズムにはヴァリエーション(発展形)が多いが、
これらの発展形は全てダウン・アップのストロークと、
同じくダウン・アップの空ピックアクションの組み合わせでつくられている。
基本形と注意深く見比べて、
基本形のどの部分を空ピックにしているかを見つけることが重要。
If we play eight strums down and up alternately in one measure,
we call this rythm pattern “8-Beat Rythm.”
The accents are usually on the third down strum and the seventh down strum.
When you play the strums of 8-beat rythm pattern,
the time values of the down-stroke and the up-stroke
should be always the same.
All the variations of "8-Beats Rythm" are distinguished
by the distribution of down-up strums and down-up empty stroke actions.
It is very important to know the place of empty stroke;
compairing with the eight beats of the basic rythm pattern.
曲の最後には当然のことながら「あっ、終わりだな!」という感じが欲しい。
そのために様々に工夫された演奏の型がある。
これらの終止感を感じさせる演奏の型やフレーズ(楽句)を、
エンディング・パターン(終止形)と呼んでいる。
エンディング・パターン(終止形)としては大別して、
リズムによるもの、メロディーによるもの、
そしてコード進行によるものなどがある。
At the end of any music,
a better ending feeling should be produced by playing.
In order to produce a better ending feeling,
we know the various kind of playing patterns.
We call all these playing patterns "Ending Pattern".
Usually we play three kinds of ending patterns mainly;
rythmic ending patterns, melodic ending patterns
and ending patterns of chord progressions.
通常のメイジャー・コードは
ルート音に長3度(2.0)音程のサード音(第三音)を重ね、
さらにその音の上に短3度(1.5)音程のフィフス音(第五音)を重ねた、
ルート、サード、フィフスの三和音になっているが、
この場合のルートからフィフスまでの音程を完全5度(3.5)と言う。
さて、
フィフス音を重ねるときに、サード音から短3度ではなく長3度で重ねると、
こんどはルートからフィフスまでの音程が、完全5度より半音(0.5)高くなる。
この完全5度より高い5度音程を増5度(4.0)と言う。
「オーグメント」とは増大するの意味で、
オーグメント・コードとは、
ルート音に、長3度(2.0)音程のサード音、
そして増5度音程のフィフス音で構成された三和音で、
簡単に言えば、
メイジャー・コードのフィフス音が半音高くなっているコードと考えればよい。
たとえばCコードのコード・トーン(構成音)はC、E、Gの三音だが、
Cオーグメント・コードのコード・トーンはC、E、G# の三音となる。
The three factors of the triad are root, third and fifth.
As for a major chord,
the interval between root and third is major third (2.0),
the interval between third and fifth is minor third (1.5),
and then the interval between root and fifth is perfect fifth (3.5).
If the interval between third and fifth of major chord
is changed to major third (2.0),
the interval between root and fifth is increased
by a half tone to augmented fifth (4.0).
We call this type of chord "Augmented Chord".
So an augmented chord consists of
a root, the third of major third and the fifth of augmented fifth.
ギターの1フレットから3フレットまでを通常オープンポジションと言うが、
このオープンポジションで押さえるコードの中で、
その構成音に開放弦を含むコードを「オープン・コード」"Open Chord" と呼んでいる。
比較的に初心者でも知っている"G"、"C"、"D7"等のコードはその構成音に開放弦を含んでおり
オープンコード。
たとえオープンポジションではあっても、
"F"や"B♭"等の左手人差し指で6本全ての弦を押さえるタイプのコードは
バーコード
と言う。
ことアコースティックギターにおいてはその響きが良いため、
オープンコードが好まれ多用される。
コードのベース音として通常はルート音(根音)を弾くが、
コードの構成音ならば原則としてどの音をベース音として弾いても良い。
従ってルート音以外にも、
フィフス(ルートから数えて第5音)や、
サード(ルートから数えて第3音)、
さらには他のコード構成音もベース音として使われる。
ルートベースだけだと伴奏が単調になりやすいので、
よくベース音としてルート音と交互に他のコード音が弾かれることがあるが、
これらのケースでは、
交互に弾かれるルート音以外のベース音を「オルタネイト・ベース」と呼んでいる。
オルタネイト・ベースとしてはコードのフィフス音を弾くのが一般的。
We usually play a "root" as the basic bass note for each chord.
But you should realize that
any other note of each chord can be played as the bass note.
As the bass note,
we can play not only a "root"
but also the "fifth" or the "third" of each chord.
We call these other bass notes except for a root "alternating bass".
フラット・ピックを使ってのピッキングのダウン、アップには
以下のように一応の目安となるルールがあります。
その一、
四分音符と四分音符以上の長さの音符は全てダウン「弾き下ろし」で弾く。
その二、
四分音符以下の長さの音符は
全てダウン「弾き下ろし」、アップ「弾き上げ」交互に弾く。
弾きはしないが休止符にもこのルールは当てはまる。
その三、
タイのついた音符は、たとえそれがアップの位置にあっても、
全基本的にはダウン「弾き下ろし」で弾く。
(
シンコペーション syncopation
)。
When you play the melody of consecutive eighth notes with a flat pick,
you had better strike a string down and up alternately.
We call this picking style with a flat pick "Alternate picking".
Rule 1.
A quartwr note and the note whose time value is longer than a quarter note
should be played with downward picking.
Rule 2.
the note whose time value is shorter than a quarter note
should be played with downward and upward picking alternately.
Rule 3.
All the tied notes should be played with downward picking
(
syncopation
).
一般的に我々が良く耳にする音楽は音階上の音によって創られている。
さしあたり知っておく必要のある音階は三種類。
ひとつは
メージャー・スケール(長音階)
、
つぎに
マイナー・スケール(短音階)、
そしてクロマチック・スケール(半音階)である。
これらの音階はそれぞれの構成音間の
音程
配置の違いにより分けられる。
具体的に見てみよう。
たとえばDメージャー・スケール(ニ調長音階)をアルファベット文字で表し、
構成各音の主音からの度数(デグリー)をローマ数字で表すと次のようになる。
Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ(Ⅰ)
D, E, F#, G, A, B, C#, D
ド, レ, ミ, ファ, ソ, ラ, シ, ド
構成音は七音、
八音目で元に戻るが、この一回り音程をオクターブ(Octave)という。
さてここで隣り合った音と音の距離(音程)を調べてみると、
全音音程が五箇所(DEの間、EF#の間、GAの間、ABの間、BC#の間)、
半音音程が二箇所(F#Gの間とC#Dの間)あることが解る。
その配置は、全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音の順になっている。
これがメージャー・スケール(長音階)の音程配置である。
このようにスケール(音階)は
全音半音の音程配置によってその性格が決まり区別されている。
The tones which we use in the music are drawn from the scale.
Here we need to know at least three scales;
the major scale
,
the minor scale
with its harmonic and melodic forms,
and the chromatic scale.
If we visualize the scale tones of D malor scale
as an alphabetical series and the scale degrees by Roman numerals,
we get the following:
Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ(Ⅰ)
D, E, F#, G, A, B, C#, D
In this major scale we can find five whole-tone intervals
(the interval of D&E, E&F#, G&A, A&B, and B&C#),
and two half-tone intervals (the interval of F#&G and C#&D).
The distribution of whole-tone and half-tone intervals are:
Whole-tone, Whole-tone, Half-tone,
Whole-tone, Whole-tone, Whole-tone, Half-tone.
This is the distribution of the major scale.
The scales are distinguished
by the distribution of whole-tone and half-tone steps.
音程とは音階上の二つの音の間の高さの違い(距離)を表す。
二つの音が同時に鳴った場合の音程をハーモニック音程、
同時ではなく連続的に鳴った場合の音程をメロディック音程と言う。
ピアノ、ギター等の平均律楽器では音程の最少単位は「半音」(a half tone)となっている。
「半音」二つ分で「全音」と言う。
たとえばピアノ等の鍵盤(キーボード)を思い浮べてみよう。
白鍵と白鍵の間に黒鍵がはさまって配置されているところがある。
この場合左の白鍵と次の黒鍵をそれぞれ弾いた場合の音程差は「半音」音程、
黒鍵と次の白鍵すなはち右の白鍵をそれぞれ弾いた場合の音程差も「半音」音程である。
したがって左の白鍵と黒鍵を挟んだ右の白鍵との音程差は「全音」ということになる。
キーボードではオクターブの間で二か所黒鍵が無く白鍵の続いて配置されているところがある。
この二か所では、
白鍵と黒鍵を挟まないすぐ隣の白鍵をそれぞれ弾いた場合の音程差は「半音」音程となる。
ギター等フレットのある楽器では一フレットの差が「半音」音程差になっている。
The interval describes the “distance” between the two scale tones,
measured by their difference in pitch.
If the two tones are heard as the consecutive tones of one melodic line,
the interval is called the melodic interval,
as distinguished from the harmonic interval,
in which two tones are sounded together.
音(楽音)の長さと、高さを表す記号を音符と呼び、
音の休止している間の長さを表す記号を休符と呼ぶ。
休符は音符の一種。これらは通常五線譜に書き表される。
A note indicates the time value and the pitch of the musical tone.
And a rest indicates the time value of silence.
The notes and the rests are usually written on the staff.
一小節の四分の一にあたる時間的長さを表す音符。
通常の一拍はこの音符で表す。
A quarter note indicates the time value of a quarter of one measure.
It indicates the time value of one beat.
一小節の二分の一にあたる時間的長さを表す音符。
二分音符一つは四分音符二つ分の長さに相当する。
A half note indicates the time value of a half of one measure.
一小節分の時間的長さを表す音符。
A whole note indicates the time value of one measure.
一小節の八分の一にあたる時間的長さを表す音符。
一拍の二分の一すなわち半拍分になる。
An eighth note indicates the time value of a eighth of one measure.
It indicates the time value of a half beat.
音符の右に付点がつくと元の音符の1.5倍の長さになる。
A dot placed after the note increases the time value of it by one-half.
楽曲の
五線譜
冒頭によくあるト音記号 "a G clef"等、
五線上での音の高さを確定しておく記号を音部記号と言う。
ト音記号は「ト音」即ち「G音」別名固定ドでの「ソ音」の位置が
五線の下から二本目の線(第2線と言う)の線上にあることを示す。
ピアノ譜は二段譜になっているが下の五線譜冒頭にはへ音記号"an F clef"が使われる。
へ音記号は「へ音」即ち「F音」別名固定ドでの「ファ音」の位置が
五線の下から四本目の線(第4線と言う)の線上にあることを示す
これら以外にも良く使われるものにハ音部記号"a C clef"がある。
A "G" clef shows that the position of the note "G" is on the second line of the staff.
カーター・ファミリー・ピッキングは1930年代をピークに活躍した
アメリカン・トラディショナルの伝説的なフォーク・グループ
「カーター・ファミリー」の中心的ギタリストであった
メイベル・カーターが編み出した最も一般的なフォーク・ギター奏法で
ウッディー・ガスリーやボブ・ディランなど
その後のフォーク・ミュージシャンやカントリー・ミュージシャンに
多大な影響を与えている。
彼女のギター奏法の特徴は、
ベース弦でメロディーを弾きながら
その間隙を縫って高音弦のストロークを巧みに配するところにあり、
これによってメロディーと伴奏を同時に弾く
ギターのソロ演奏を可能にしている。
もともとは右手の親指でベースを弾き他の指でストロークを弾いたが
左手でのハンマーリングやプリング・オフ、
そして右手の方もアップ・ストロークが加わるなど、
変化に富んだバリエーションの多いフィンガー・ピッキングに発展した。
アップ・ストロークを多用する
ウッディー・ガスリーが言うところのチャーチ・リック奏法は、
本人の言によれば
すでに1930年代メイベル・カーターの弾いてたものだそうだが、
アップ・ストロークはフラット・ピックを使ったほうが
音もリズムもクリアーに表現できるため、
チャーチ・リック奏法以降でのカーター・ファミリー・ピッキングは、
フラット・ピックを使って弾くのが一般的になって来ている。
Carter Family Picking is an American traditional picking style
that was mainly played by Maybelle Carter
in the singing group called Carter Family.
Maybelle Carter's guitar-playing style
influenced most of the folk musicians who came afterward
like Woody Guthrie and Bob Dylan and ctc....
In her guitar-playing style,
the thumb of the right hand play the melody on the bass strings
and spaces between the notes of the melody
are filled in with the brushed chords.
Nowadays the most of the folk singers use a flat pick or a thumb pick
when they play Carter Family Picking.
楽譜は五本の横線とその間の四本の空白スペースからなり、
縦線によって小節に分けられる。
横線には一番下の線から順に
第1線、第2線、第3線、第4線、第5線、と番号が付され、
横線間の空白スペースにも同じく下から
第1間、第2間、第3間、第4間、と番号が付けられている。
The Staff consists of five lines and four spaces,
and is divided into measures by bar lines.
The five lines are numbered in sequence from the lowest horizontal line,
1st line, 2nd line, 3rd line, 4th line and 5th line.
The 5th line is the highest line.
In the same way,
The four spaces are also numbered in sequence from the lowest space,
1st space, 2nd space, 3rd space and 4th space.
カッティング(英語)
音をカットする、すなはち短めに切るということ。
一小節四拍のストローク奏法において2拍目、4拍目の弾き下ろし直後、
すみやかに右手の平小指側を弦に触れて消音する。
はや過ぎても遅すぎてもカッコわるい。
このことによりアフター・ビートのリズム感を歯切れ良く表現できる。
バーコードを押さえている場合はむしろもっと簡単で、
コードを押さえている左手の力を抜けばよい。
力を抜いた左手は結果的に全ての弦に触れている状態になり
消音(ミュート)してることになる。
もちろんこの場合も左手の力を抜くタイミングが重要。
いづれにしても歯切れよくリズムが聞こえてくるまでにはかなり練習が必要。
この演奏テクニックをカッティングという。
カッティングは通常音符の真上に記された点のスタッカート記号で表す。
When you play the rythm accompaniment with a guitar,
A better rithmic pulse is produced
if you mute the strings with the side of the right hand
just after the downward brush of the 2nd beat and the 4th beat;
in the music of four beats per measure.
And when you take the bar chords,
if you relax the left hand pressure just after the strumming,
you can also produce a better rythmic pulse.
This playing technique is called "Cutting".
Cutting is usually indicated with a "staccato" sign;
a dot over the note.
「カポタスト」はイタリア語、通常「カポ」と呼ぶ。
「フィンガー・ボードの頭」と言った意味で、
ギター本体のフィンガー・ボードの頭は「ナット」だが、
この道具を好みのフレットに装着することにより、
その装着されたフレットが実質的にフィンガー・ボードの頭になり、
ピッチが高くなるのに伴いキーを変えることができる。
ギターの初心者が使うコードはオープン・ポジションがほとんどで、
その数も限られるし歌うために弾けるキー(調性)も二三種類がせいぜい。
一方で自分の声域にぴったりのキーというのもやはり限られており、
気持ちよく歌えるキーが
歌によっては必ずしも"D"や"G"、"C"等の弾きやすいキーとは限らない。
人によって歌によって、
あまり弾き慣れていない"F"キーや、
"E♭"、"A♭"等フラット系のキーの方が歌いやすいこともママある。
移調すれば良いのだが、移調してもかえって伴奏が難しくなることが多い。
こういった場合に、知ってるキーのコードで弾きながら、
どんなキーでも好きなピッチの高さで歌えるという
きわめて手軽で便利かつスグレモノの道具がカポである。
"Capotasto" is Italian, usually we call "Capo".
The changing a song from one key to another is known as transposing.
But even if you don't know how to transpose a song,
you, a guitar player, can change the key easily by using "Capo".
A capo is a clamp which is placed across the strings of a guitar,
in order to raise them uniformly in pitch.
It can raise the pitch of the guitar one half-step for each fret.
If you clamp a capo across the 1st fret of your guitar
and finger a "D" chord ;
the position of the 1st & 2nd fingers of the left hand
must be on the third fret,
and the position of the 3rd finger must be on the fourth fret.
And then! you take now a "E♭" chord or a "D#" chord
which is a half-tone higher in pitch than "D" chord.
So, on this position using capo, you can sing a song of "E♭" key
by playing guitar accompanyment of "D" key.
Likely, if you can play the some chords of two or three kinds of key,
you can sing many songs of the various kinds of key.
空ピックとは、
弦を弾き下ろしたり引き上げたりするときのアクションだけを行うことを言う。
実際は弦を弾かないので新たに音を鳴らさないが、
直前に弾いた音がある場合はその音をそのまま響かせていることになる。
伴奏で正確なリズムを保つためには、
リズムをきざむアクションは止めないほうが良い。
従って二分音符の打弦後の二拍目や、付点二分音符の二、三拍目、
全音符の二、三、四拍目などは必ず空ピックするべきである。
空ピックのくせは身に付けておいたほうが良い。
The Empty Stroke means only the action of down stroke or up stroke
without picking and without sounding.
休止符とは「無音」状態を表す音符、
すなわち音の休止している長さを表す記号で、
音符同様五線譜上に書き表される。
その時間的長さは通常の音符と同様以下のようになる。
The Rests are the notes of silence.
The time value of the rests are like following;
一般的には三つ以上の音が同時に響いている状態を言う。
コードは通常三度音程の積み重ねによりできており、
最も基本的なコードは、
三つの音をそれぞれ三度音程で重ねて構成されている
三和音(トライアド)である。
四和音(セブンス・コード)や五和音(ナインス・コード)も良く使われる。
三和音の各音には名前が付されて、基本形の最低音はルート(根音)と言う。
ルート音はコードの基礎となる最重要な音なので
ファンダメンタルと呼ぶこともある。
つぎに、
ルートから三度音程の音をサード(文字通り三度)、
さらにこのサードから三度音程の音は、
ルートからすれば五度音程の音となるので、
この五度音程の音をフィフス(五度)と呼ぶ。
コードの各音は上下の位置がひっくり返ることはよくあるが(転回形)、
どの位置に転回していても
ルートはルート、サードはサード、フィフスはフィフスである。
The chord is the sonority
resulting from the simultaneous sounding of more than 3 tones.
And a chord is ordinarily built by superposing intervals of a third.
The simplest chord is the triad
which is a chord of the three scale-tones
obtained by the superposition of two thirds.
The names“root,”“third,”and “fifth”
are given to these scale-tones as the three factors of the triad.
The root is often called “fundamental.”
These terms are retained to identify the factors of the triad
in whatever order they may be arranged as an inversion.
The seventh chords are the chords of the four scale-tones
obtained by the superposition of three thirds.
ギターの
フィンガーボード
を図形化したもので、
縦の図形と横の図形の二通りがある。
いずれにしても
コード
の押え方が一目でわかるためギターの初心者にとっては便利。
コード・ダイアグラムとその読み方、
ここでは横図形で見てみよう。
具体的には以下の通り。
The chord diagram is an“aerial view”of the fingerboard of the guitar.
It is very convenient for beginners to know how to hold a chord like following.
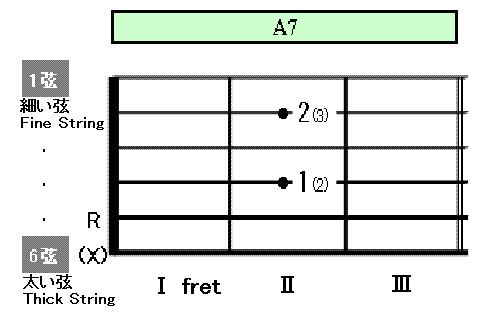
三和音
における第三音は、
ルート
からの音程差により、
メイジャー・コード
か
マイナー・コード
か、
そのコードの性格を決定する重要な音ですが、
このうちメイジャー・コードでの第三音すなわちルートから三度の音を、
言わば「吊り上げ」て四度の音に変化させた結果できたコードを、
サスペンディド・フォース・コードと呼んでいます。
コード・ネームの直後に"sus4"と記して表します。
三度の音を変化させたわけですから、本来の三度の音は無くなって、
サスペンディド・フォース・コードのコード構成音は三和音の場合、
ルート(根音)、フォース(第四音)、フィフス(第五音)となります。
例えばCコードで考えてみましよう。
Cコードの構成音はルートがC(ド)、
サード(第三音)がE(ミ)、
それにフィフス(第五音)がG(ソ)ですが、
ルートであるCとサードであるEの音程差は、
メイジャー・サードすなわち長3度(2.0)になるので、
これは正確にはCメイジャー・コードということになります。
しかしCメイジャー・コードは通常略してCコードと呼ぶのが一般的です。
このルートからメイジャー・サードすなわち長3度(2.0)のE(ミ)音を
半音(0.5)吊り上げるとF(ファ)音となり、
サードではなくフォースすなわち4度の音になります。
こうして出来たコードを、
3度の音が吊り上げられた結果4度の音に成ったという意味で、
サスペンディド・フォース・コードと呼んでいると理解しておきましょう。
通称は略して「サスフォー」と言っています。
そんなわけでCサスペンディド・フォース・コードは「Csus4」と記し、
その構成音はC(ド),F(ファ),G(ソ)となります。
Triad is a chord of three diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of two thirds.
A fundamental note of chord is called a root,
and the note that is superposed on root with a third interval
is called the third,
and the note that is superposed on the third with a third interval
is called the fifth.
If the third is superposed on root with an interval of major third,
and the other interval between third and fifth is minor third.
this chord is called "major chord".
And then, if the interval between root and third of a major chord
is changed from major third to perfect fourth,
this chord becomes an altered one
which is called "a suspended fourth" chord.
Practically explaining,
C major chord consists of C, E and G,
and the interval between C and E of this chord is a major third.
If the interval between C and E is changed to perfect fourth,
E is replaced by F and the chord becomes C suspended fourth chord
which is generally written "Csus4".
The chord tones of "Csus4" are C, F and G.
ダイアトニック・スケール
上の
サブドミナント音(Ⅳで表記される第4音)をベース音として、
その上に3度音程でさらに二つの音を重ねて、
合計三音で構成された和音(コード)を
「サブドミナント・コード」と言う。
たとえばCキーで考えてみよう。
Cキーで使われる音階はCメージャー・スケールだが、
Cメージャー・スケール上のサブドミナント音はF音。
F音(ファ)をベースにして3度上のA音(ラ)を重ね、
さらにそのA音(ラ)の3度上のC音(ド)を重ねると「三和音」となり、
全部でF(ファ), A(ラ), C(ド), の三音構成となる。
このコードがCキーのサブドミナント・コードであるFコード。
この場合の音程構成は、
FとAの音程差が長三度(2.0)、
AとCの音程差が短三度(1.5)でFからCでは完全五度(3.5)、
Cキーでのサブドミナント・コード"F"の音程構成は以上の通りだが、
同じ音程構成のFコードであっても、
たとえばFキーにおいて成立するFコードは、
トニック上に成立するのであってサブドミナント上に成立するのではないから、
それはトニック・コードでありサブドミナント・コードではない。
"Subdominant Chord" is a triad chord of three diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of two thirds
based on the subdominant note of a diatonic scale.
For example,
now we use C major scale in C key,
and the subdominant note of C major scale is "F".
As triad, "F" chord consists of F, A and C.
The interval of F and A is major third,
and the interval of A and C is also third but minor third.
So the interval of F and C is perfect fifth.
This "F" chord in "C" key is called "Subdominant chord".
最も広く使われているメイジャー・スケール(長音階)や、
ナチュラル・マイナー・スケール(自然短音階)などの、
ダイアトニック・スケール
上のある音をベースとして、
その上に3度音程でさらに二つの音を重ねて、
合計三つの音で構成された
和音(コード)
を
「三和音」すなはち「トライアド」と言う。
最初の基音となる音をルート(根音)、
その上に3度音程で重ねた音を、
ルートから3度音程の音と言う意味でサード(3音)、
さらにその上に3度音程で重ねた音を、
ルートから5度音程の音と言う意味でフィフス(5音)と言う。
たとえばCメージャー・スケールで考えてみよう。
C音(ド)をベースにして3度上のE音(ミ)を重ね、
さらにそのE音(ミ)の3度上のG音(ソ)を重ねると、
全部でC(ド), E(ミ), G(ソ)の三音構成のコードになる。
これがCの「三和音」すなはち「トライアド」である。
トライアドは最も基本的かつ古典的なコード(和音)で、
ルート(根音)、サード(3音)、フィフス(5音)で構成される。
All of the major scales and natural minor scales
are called diatonic scale.
And "Triad" is a chord of three diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of two thirds.
The names“root,”“third,”and “fifth”
are given to these scale notes as the three factors of the triad.
For example,
"C" chord consists of C, E and G which are the notes of C major scale,
and the interval of C and E is third,
and the interval of E and G is also third.
These three notes of C major scale are the three factors of the triad.
So we can call C chord "Triad".
Triad consists of root, third and fifth.
アウフ・タクト(ドイツ語)は弱拍のこと。
楽曲では小節の第1拍目(強拍)で始まらないことも多い。
第1拍目(強拍)以外の弱拍で曲が始まることを“弱起”と言う。
ちなみに曲の始めの弱起の部分の音符をピック・アップと呼ぶ。
Auftact (German) means Up beat.
In many cases,
the music doesn’t start from the 1st beat of the beginning measure,
but it starts from “Auftact”.
And the notes appearing before the beginning measure
are called “Pick-ups”.
“はずむ”ように聞こえるリズムを大ざっぱに「シャッフル」と言います。
8ビートでは、
一拍が2つの8分音符のダウン・アップで記されていますから、
ダウンとアップの音価は同等、すなわち同じ長さの音です。
しかしシャッフルのリズム表記では、
通常ダウンが付点8部音符でアップが16分音符になっています。
理論的にはダウンの音符がアップの音符の3倍の長さです。
しかし実際には、
ダウンとアップが厳密に3:1の長さで演奏されているわけではありません。
記譜としても一拍が三連音で書かれている例が多く見られますし、
音楽のジャンルによっても演奏者の感覚によってもとらえ方が微妙に違います。
要は一拍をダウンとアップの二つに分けた時に、
8ビートのように等価にならず、
前のダウンが長く後ろのアップが短い弾き方の”はずむ”感じのリズムを
このように表記します。
「スウィング」とか「ブギウギ」とか「シャッフル」とか・・・。
「スウィング」と言うと一般的にはジャズを意味するので、
ポップスで使われるこの種のリズムの総称を、
8ビートと区別する意味でよく「シャッフル」と呼びます。
The interpretation of dotted 8th and 16th notes produces
a "bluesy" or "boogie-woogie" rythm
which is also often noted divisible into thirds.
In the popular music,
they are usualy played more smoothly in a flowing manner,
although a dotted 8th note is
theoretically held 3 times longer than a 16th note.
Generally we call this type of rythm "Shuffle" or "Swing".
The word "Swing" is used in "Jazz" music.
So here we use the word "Shuffle" in the "Pop" music.
→ エンディング・パターン(終止形) Ending Pattern
オープン・コードの場合
一般的には右手てのひらで全ての弦に触れて音を止める。
バー・コードの場合は
押さえている左手の力をわずかにゆるめるだけで音は止まる。
はじめから音を出したくない弦がある場合は、
あらかじめ左手をその弦に触れておけばよい。
Touch all the strings with the side of the palm of your right hand,
Then you can stop the sound of the guitar strings.
Or if you relax the left hand pressure of the bar chord
just after the strumming,
you can also stop the sound of the guitar strings.
When you touch a string or some strings with your left hand before strumming,
you can mute the string or the strings which you don't want to make sound.
楽曲に書かれた音符にはそれぞれ強拍と意識されるものと弱拍と意識されるものがあります。
例えば4分の4拍で考えてみましょう。
1小節に4拍同じ高さの4分音符が書かれているとすると、
通常一拍目の4分音符は強拍として意識され、二拍目の4分音符は弱拍として意識されます。
さらに次の三拍目は一拍目に準ずる強拍として意識され、四拍目は弱拍と意識されます。
このように高さも長さも全く同一の四連4分音符でありながら、
それぞれに、「強」「弱」「中強」「弱」という風に強拍弱拍の意識分けがなされているのです。
さてここで二拍目と三拍目の4分音符を「
タイ
」Tie で結んでみましょう。
こうなると三拍目の音符は二拍目に吸収され、音としては二拍目の残響として聞こえます。
弾かれていた4つの音が弾かれている音としては3つになったのです。
聞く方の印象とすれば、元は「強、弱、中強、弱」であったものが「強、強、・、弱」に聞こえますから、
音やリズムの変化とともに面白さを感じることとなります。
この場合始め弱拍であった二拍目がタイの結果強拍に逆転しています。
この強拍弱拍の逆転を「シンコペーション」syncopationと言います。
シンコペーションは上記のように小節内でも起きますが、小節をまたいでも起きます。
さらに言えば一拍の中においてすら強弱は意識されます。
例えば僕らは口で拍を表現するとき、トン、トン、とか、タン、タン、タンとか言いますが、
この場合一拍をいわばオモテ(表)である強部の「タ」と、
ウラ(裏)に当たる弱部の「ン」の二つの音で表現しています。
英語の音楽用語ではこの前者強部を"Down beat"、後者弱部を"Up beat"と言います。
例えば四分音符二つ続けば、「タン、タン」となりますが、
この強弱部分を逆転させると、「ンタ、ンタ」になり、これもアクセントの移動即ち「シンコペーション」です。
音符で書けば四分音符二つが逆転の結果、
「8分休止、8分音符、8分休止、8分音符」となるかもしくは、
「8分休止、8分音符、8分音符、8分音符」となって、
初めの8分休止直後に並ぶ二つの8分音符は[タイ」でつなげられます。
さらにもう一つの書き方としてはこの二つの8分音符を一つの4分音符にまとめて、
「8分休止、4分音符、8分音符」と言う記し方もあります。
→ 音階(スケール) The scale
スタッカート(イタリア語)
音符の真上にある点は記号でスタッカートという。
スタッカートのある音は短めに切る。
実際の演奏では、
コード弾きの場合は弾きおろした直後に、または弾き上げた直後に、
返す右手の手のひらで全ての弦に触れて音を短めに止める。
Staccato (Italian)
A dot over the note is called "staccato".
It means to make the sound of a note shorter.
To make the sound of the note shorter,
Touch all the strings a little bit quickly with the side of the right hand
which moves upward or downward
just after the downward strumming or upward strumming of a beat.
高さの異なる二つ以上の音符の
最初と最後の音符をつなげるように描きこまれた弧線をスラー"Slur"と言う。
スラーでくくられた音符群は「レガート」"Legato"(イタリア語)、すなわち
音の切れ目がない様に滑らかに弾かれることを指示されている。
従ってスラーでくくられた音符群は一つのフレーズとして聞こえるので、
それが二つ続けばフレーズの切れ目を示すことにもなる。
また特に二つの音符間で良く使われるスラーには
ギター等の弦楽器において
ハマーリングオン
、
ブリングオフ
、スライド、グリッサンド等
弦楽器特有の奏法を示すためにも一般的に使われている。
弧線を使った音楽記号には他に「
タイ
」"Tie"があるが、
その機能も意味合いも全く別物なので要注意。
歌の伴奏に使われるコード(和音)は、
その歌のメロディーに使われているスケール(音階)を基礎として
構成されています。
そしてスケールはそれぞれの曲のキー(調性)により設定されています。
たとえばキーがDkey(ニ長調)に設定されている場合、
楽譜の最初ト音記号のとなりにはかならず♯記号が二つ書かれています。
したがってこれらの楽譜の歌のメロディーや楽曲は、
Dスケール(正確にはD メジャー。スケール ニ調長音階)で書かれています。
Dkeyでは主音(ドレミのドにあたる音)がDに設定されますので、
スケール(音階)の各音は次のようになります。
D(ド)、E(レ)、F#(ミ)、G(ファ)、A(ソ)、B(ラ)、C#(シ)、D(ド)
さてこれらのスケール上の各音には、
主音からの距離(度数で表す)により便宜上
それぞれの音に次のようなローマ数字が付されています。
D(ド)、E(レ)、F#(ミ)、G(ファ)、A(ソ)、B(ラ)、C#(シ)、D(ド)
Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ、 Ⅴ、 Ⅵ、 Ⅶ、 Ⅰ
主音Dは一度(Ⅰ)、E音は二度(Ⅱ)、F#音は三度(Ⅲ)・・・
と言った具合です。
歌の伴奏では、
このスケール上の一度Ⅰ(D), 四度Ⅳ(G), 五度Ⅴ(A)音を基礎として構成された
D (Ⅰ)chord, G (Ⅳ)chord, A7(Ⅴ7)chord, の三つのコードが
最も数多く頻繁につかわれます。
逆に言えば、
ほとんどの歌は
この三つのコードで伴奏してうたえるといっても過言ではありません。
われわれはこの便利で重要な三つのコードを「スリー・コード」と呼んでいます。
さらにはこれら三つには良く使われる正式名称があり、
一度Ⅰ(D)主音を「トニック」と言うので、
「トニック」を基礎として構成された和音を「トニックコード」、
四度Ⅳ(G)下属音を「サブドミナント」、
「サブドミナント」を基礎として構成された和音を「サブドミナントコード」、
五度Ⅴ(A)属音を「ドミナント」、
「ドミナント」を基礎として構成された和音を「ドミナントコード」、
またはこのコードはセブンスの形で使われることが多いので「ドミナントセブンスコード」、
とそれぞれを呼んでいます。
Let's see the music notes
which you have already played as the training materials.
Then you may find some sharp“#”signs or flat signs
beside the Clef Sign on the head of the music notes.
These signs means the “Key”in which the music is written.
For example, if you can find the two sharp“#”signs beside the Clef Sign,
generally this music is written in the “D”major key.
In the D key, we use the “D”Major Scale like the following.
D(do)、E(re)、F#(mi)、G(fa)、A(sol)、B(la)、C#(si)、D(do)
Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ、 Ⅴ、 Ⅵ、 Ⅶ、 Ⅰ
When we visualize the musical scale like this,
We will see that if D is the first note of this scale (Ⅰ),
Then G is the fourth ( Ⅳ),
And A is the fifth ( Ⅴ).
The chords D,G,A are based on these three scale tones of the D Key.
When we sing the song of D key,
we can sing most of the songs
with playing only these three chords as the accompaniment to the song.
We call these “The Three Chords”.
This Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ relationship occurs in all major keys,
And this is the very backbone of harmony in the Western Music.
If we can play The Three Chords we will be able to sing very many songs.
スリーフィンガー・ピッキングは日本では1960年代前半に、
アメリカのモダンフォークのグループ
「P.P.M」(ピーター、ポール アンド マリー)
の華麗な演奏と共に広まったフォーク・ギターのピッキング・スタイルです。
P.P.M の演奏自体は
実際のところトゥーフィンガー・ピッキングが基本になってもいますが、
スリーフィンガー・ピッキングは
トゥーフィンガー・ピッキングの進化した奏法と言えるでしょう。
特に歌伴奏の場合でのパターン・ピッキングは、
スローテンポでも軽快なテンポでもこちらの方が流麗で弾きやすいこともあり、
スリーフィンガー・ピッキングはカーターファミリー・ピッキングと共に、
日本では以後のフォーク・ギター二大奏法として定着しました。
通常のアルペジオ奏法では低音を親指で弾く一方、
高音弦を弾くのに人差し指、中指、薬指などを臨機応変に自由に使い、
右手四本の指を使って弾く
いわばフォーフィンガー・ピッキングとも呼べる弾き方ですが、
スリーフィンガー・ピッキングでは三本の指、
すなわち低音用の親指以外には
通常人差し指と中指を高音弦を弾くのに使い、
基本的には薬指を使わないのでこう呼ばれています。
トゥーフィンガー・ピッキングはもちろん、
低音を親指、
高音弦を人差し指、または中指のどちらかで弾きますので
二本の指しか使わないためこう呼ばれているわけです。
軽快で華麗なスリーフィンガー・ピッキングのスタイルは、
直接的にはギターのトゥーフィンガー・ピッキングよりはむしろ
1940年代白人系アングロアメリカン・ミュージックの中心にあった
「ブルー・グラス」の代表的バンジョー弾き
アール・スクラッグスの「スクラッグス奏法」と呼ばれる
バンジョーのスリーフィンガー・ピッキングの影響がかなり強いと考えられます。
ただしアール・スクラッグスのバンジョー奏法自体が
黒人の音楽であるブラックミュージックの影響を強く受けていると言われています。
一方でギターのトゥーフィンガー・ピッキングは
これもまた19世紀以来ブラックミュージックの中心にあった「
ブルース
」、
そのギター奏法にも原型が認められます。
ブルースの中でも
「ピードモント」スタイルと呼ばれる南東部のブルース・ギター奏法は
低音を右手親指で弾くと同時に、
高音弦を他の指で弾くフィンガー・ピッキング奏法で
奏法としての右手指使いの組み立ては
明らかに20世紀でのトゥーフィンガーや
スリーフィンガー・ピッキングにつながっています。
トゥーフィンガー・ピッキングの代表的奏者としては
エタ・ベイカーやエリザベス・コットン、
スリーフィンガー・ピッキングは、
旧くはミシシッピー・ジョン・ハートにより
その個性的な弾き方で印象付けられていますが、
歌伴奏やその付随的な演奏のみならず
インストルメンタルにおいても、
マール・トラビスやチェット・アトキンスのように、
さらに洗練されたかたちで使われています。
When you play the guitar,
it is possible to play a melody line and a bass line at once.
On one side,
you can play a bass line on the bass strings
with the thumb of the right hand.
and on the other side at the same time,
you can play a melody or fill-in notes on the treble strings
with the first finger and the second finger of the right hand.
In this picking style,
you play with only three fingers of the right hand;
thumb, index and middle.
We call this finger picking style "Three-Finger Picking".
Three-finger picking, especially the so-called "pattern picking"
consisting of a few right hand patterns
is very often used for accompaniment.
It can be thought that
three-finger picking is an improved picking style of Two-finger picking
using two fingers of the right hand; thumb and index or middle finger.
And moreover speaking,
the original style of these picking
might be the east coast, or "Piedmont", finger-picking style
of
"Blues"
music.
As players of two-finger picking,
Elizabeth Cotton and Etta Baker are well-known.
And on the other hand,
in "bluegrass" music,
the five-string banjo have been played in a paticular style
which is called "three-finger picking" or Scruggs' style.
Scruggs is the name of a great five-string banjo player.
The brilliant and exciting impressions produced by this guitar picking style
may come from Scruggs' picking.
As the traditional player of three-finger picking style,
Mississippi John Hurt was the big one,
and as the modern performers,
Merle Travis and Chet Atkins are well-known.
セーハはスペイン語の"Ceja"(セーハ)、英語の"Bar"や"Barre"にあたり、
人差し指で押さえるフレットの位置を示します。
"C.2"や"C.3"などと書き表わし、
スケールにしてもコードにしても左手指使いのポジションを指示します。
"C.2"は人差し指が2フレットにくるポジション、
"C.3"は人差し指が3フレットにくるポジションです。
Spanish word "Ceja" means "Bar" or "Barre".
The sign of "Ceja" is described like "C.2" or "C.3".
"C" is an abbreviation of "Ceja",
and its number indicates the number of fret
on which the index finger of the left hand
should be used to press a string or strings down.
So the sign "C.2" or "C.3" above the staff indicate
the fingering position of the left hand.
ダイアトニック・スケール上の音をルート(根音)として、
その上に3度音程でさらに三音を重ねて、
合計四音構成でできた「四和音」のコードを、
「ダイアトニック・セブンス・コード」と言いますが、
実はダイアトニック・スケール上には二種類のセブンス・コードが成立します。
そのひとつが普通に「セブンス・コード」と呼ばれているセブンス・コード。
ちなみにもう一つは、
「メイジャー・セブンス・コード」と呼ばれているセブンス・コードです。
ダイアトニック・セブンス・コードの構成音は、
ルート(root)、サード(third)、フィフス(fifth)、セブンス(seventh)の四音ですが、
ルートとサード間の音程が長3度(2.0)で、
サードとフィフス間の音程が短3度(1.5)になっているメイジャー・コードで、
ルートから七番目の音になるセブンスまでの音程が、
短7度(5.0)のダイアトニック・セブンス・コードを
「セブンス・コード」と呼びます。
ちなみにルートからセブンスまでの音程が、
長7度(5.5)のダイアトニック・セブンス・コードを
「メイジャー・セブンス・コード」と呼びます。
では具体的に見てみましょう。
例えば、
Cメイジャー・スケール上のG音(ソ)をルートとして3度上のB音(シ)を重ね、
さらにそのB音(シ)の3度上のD音(レ)を重ねると「三和音」となりますが、
そのD音(レ)の上にさらに3度上のF音(ファ)を重ねて、
全部でG(ソ), B(シ), D(レ), F(ファ), の四音構成とすると、
"G7"すなはちGの「セブンス・コード」が成立します。
この場合の音程構成は、
GとBの音程差が長3度(2.0)、
BとDの音程差が短3度(1.5)でGからDでは完全5度、
ここまでの音程配置で
このコードがメイジャー・コードであることが解ります。
さらにDとFの音程差が短3度(1.5)ですから、
GからFの音程差では短7度(5.0)になります。
すなわちGセブン・コードのセブンス音は、
ルートから短7度音程の音です。
従って、
メイジャー・コードの四和音で、
セブンス音のルートからの音程が短7度であるコードを
「セブンス・コード」と呼び、
"G7"、"C7"のように表記します。
間違いやすい例をここで一例、
同じCメイジャー・スケール上の音ですが、
C音(ド)をルートとして3度上のE音(ミ)を重ね、
さらにそのE音(ミ)の3度上のG音(ソ)を重ねると
やはり「三和音」となりますが、
そのG音(ソ)の上にさらに3度上にB音(シ)を重ねてしまい、
全部でC(ド),E(ミ),G(ソ), B(シ), の四音構成にすると、
この場合の音程構成は、
CとEの音程差が長3度(2.0)、
EとGの音程差が短3度(1.5)でCからGでは完全5度で、
ここまでは第一例の"G7"と同じですが、
次のGとBの音程差は長3度(2.0)になり、
CからBでは長7度(5.5)となって、
半音(0.5)高いセブンス音になってしまいます。
これをセブンス・コードにするためには、
セブンス音の"B"を半音下げて"B♭"にしなければなりません。
従って"C7"コードの構成音は、
C(ド),E(ミ),G(ソ), B♭(シのフラット)
となります。
Diatonic seventh chord is a chord of four diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of three thirds.
The names "root", "third", "fifth" and "seventh"
are given to these scale notes
as the four factors of diatonic seventh chord.
And there are two kinds of diatonic seventh chords.
One is "Seventh chord", and the other is "Major seventh chord".
And each must have major chord and minor chord respectively
as the triad part.
These chords are distinguished
by the distribution of major third and minor third intervals.
Then how is the seventh chord?
If the third note is superposed on root
with an interval of major third (2.0),
and the fifth note is superposed on the third
with an interval of minor third (1.5),
and at the same time
the interval between root and seventh is minor seventh(5.0),
it is the seventh chord of major chord.
Usually we call this type of chord just "Seventh Chord".
For example,
If we make a diatonic seventh chord based on G in C key,
the chord tones are like following;
Root is G, the third is B, the fifth is D
and the seventh is F.
How are the intervals of these chord tones?
The interval of G and B is major third (2.0),
and the interval of B and D is minor third (1.5).
Here we can know that this chord is a major chord.
Then the interval of D and F is minor third (1.5),
and so the interval of G and F is minor seventh (5.0).
Now we can understand that
this chord is definitely a seventh chord.
Seventh chords are generally written like "G7".
同じ高さ(音程)の二つの音符が、
弧線でつながって書かれていることがよくありますが、
この記号を「タイ」と呼んでいます。
タイで繋がっている二つの音符では、
前の音符は弾きますが、
後ろの音符はカウントするだけで、
弾かずに前の音符の音をそのまま響かせ続けます。
リズム・ギターではおおむね空ピックするのがふつうですが、
メロディー弾きの場合はカウントするだけで、
あまり空ピックはしません。
タイは同一小節内に限らず、二つの小節にまたがって使われることも良くあります。
タイが使われると結果的にアクセント(強拍)が移動することが多く、
このアクセントの移動を「
シンコペーション
」と呼んでいます。
なお、タイは同じ音程の二音をつなぐもので、
違う音程の二音をつなぐ記号は「スラー」と呼ばれ機能も意味合いも違っており区別されます。
混同されやすいので注意が必要。
When the two notes of the same pitch are tied together with a curved line,
pick or play the first note only,
and the second note should be merely held and counted.
We call this curved line "tie".
五つの全音
音程
と二つの半音音程から成る音階を、
ダイアトニック・スケールと呼んでいます。
いわゆる「ド・シ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」、
" Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do "、
で知られ、
最も広く使われているメージャー・スケール(長音階)や、
全音音程と半音音程の配置は異なっていますが、
マイナー・スケール(短音階)の中でも
ナチュラル・マイナー・スケール(自然的短音階)は
ダイアトニック・スケールと言うことができます。
The scale
which consists of five whole-tone intervals and two half-tone intervals
is called "Diatonic Scale".
The major scale and the natural minor scale are diatonic scale,
although the distribution of whole-tone intervals and half-tone intervals
are differant for each other.
ダイアトニック・スケール
上の音をルート(根音)として、
その上に3度音程でさらに二音を重ねて、
合計三つの音で構成された和音を「三和音」すなはち「トライアド」と言いますが、
この「トライアド」にさらにもう一つ3度上の音を重ねて、
四音構成でできた「四和音」のコードを、
「ダイアトニック・セブンス・コード」と言います。
従ってダイアトニック・セブンス・コードの構成音は、
ルート(root)、サード(third)、フィフス(fifth)、セブンス(seventh)の四音です。
たとえばG音をベースにして四和音を作れば、
その構成音はG(ソ), B(シ), D(レ), F(ファ)になり、G7コードが出来ます。
Gの「トライアド」にGから数えて七番目の音であるF音を加えているので、
この四和音を「ダイアトニック・セブンス・コード」と呼んでいるのです。
"Diatonic seventh chord" is a chord of four diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of three thirds.
For example,
"G seventh chord" consists of G, B, D and F
which are the notes of C major scale.
The interval of G and B is third,
and the interval of B and D is third.
So, as you know, the chord of G, B and D is "G Triad".
The interval of D and F is also third,
and "F" is the seventh note of "G".
We call this four notes chord "Diatonic seventh chord".
伴奏においてコードをピックなどで弾く場合、
弾き下ろすことをダウンストローク、弾き上げることをアップストロークという。
The down stroke means to pick or brush the strings downward,
and the up stroke means to pick or brush the strings upward.
通常音曲は音階上の音によって作曲されるが、
一般的によく使われる音階としては、
長音階(メイジャー・スケール)
とともに
短音階(マイナー・スケール)がある。
短音階(マイナー・スケール)はさらに次のような三種類がある。
自然的短音階(ナチュラル・マイナー・スケール);
長音階の主音(トニック)の短3度下の音を主音とする音階で、
音階内での構成音間の音程配置は、
第二音と第三音の間および第五音と第六音の間が半音音程となり、
長音階と異なってくるが、
構成音そのものは長音階とまったく同じで、
調号
も同じ。
和声的短音階(ハーモニック・マイナー・スケール);
自然的短音階での第七音が半音高くなる。
従って第六音と第七音間が全音半音程と成り、
第七音と第八音(オクターブ上の主音)の間が半音音程となる。
旋律的短音階(メロディック・マイナー・スケール);
自然的短音階での第六音と第七音が半音高くなる。
従って第五音と第六音および第六音と第七音間が全音音程と成り、
第七音と第八音(オクターブ上の主音)の間は半音音程となる。
具体的に考えてみると理解しやすい。
たとえばAマイナー・スケール(イ調短音階)の
自然的短音階をアルファベット文字で表し、
構成各音の主音からの度数(デグリー)をローマ数字で表すと次のようになる。
Ⅰ, Ⅱ,Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ,Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ(Ⅰ)
A, B,C, D, E,F, G, A,
ラ, シ,ド, レ, ミ,ファ, ソ, ラ,
構成音は七音、
八音目で元に戻るが、この一回り音程をオクターブ(Octave)という。
さてここで隣り合った音と音の距離(
音程
)を調べてみると、
全音音程が五箇所(ABの間、CDの間、DEの間、FGの間、GAの間)、
半音音程が二箇所(BCの間とEFの間)あることが解る。
その配置は、全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音、の順になっている。
僕はよくこれを略して、
「 全、半、全、全、半、全、全、」と口で唱えたりしてるが、
これがマイナー・スケール(短音階)の音程配置である。
このようにスケール(音階)は
全音半音の音程配置によってその性格が決まり区別されている。
短音階の中でも自然的短音階(ナチュラル・マイナー・スケール)は、
中世やルネッサンス期のヨーロッパで使われていた7つの教会旋法(Church modes)の一つ、
エオリアン(Aeorian)にその原型が認められる。
The tones which we use in the music are drawn from the scale.
We often find the songs which are composed using minor scale.
The tonic of minor scale is
a minor third lower than the tonic of major scale.
For example,
The tonic of A minor scale is A,
and it is a minor third lower than the tonic of C major scale.
And both of keys have no key signature.
We had better know that
the three kinds of minor scales are used in music.
These are natural minor scale, harmonic minor scale
and melodic minor scale.
Here let us study the natural minor scale precisely.
If we visualize the scale tones of A minor scale
as an alphabetical series and the scale degrees by Roman numerals,
we get the following:
Ⅰ, Ⅱ,Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ,Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ(Ⅰ)
A, B,C, D, E,F, G, A,
In this minor scale we can find five whole-tone intervals
(the interval of A&B, C&D, D&E, F&G and G&A),
and two half-tone intervals (the interval of B&C and E&F).
The distribution of whole-tone and half-tone intervals are:
Whole-tone, Half-tone, Whole-tone, Whole-tone,
Half-tone, Whole-tone, Whole-tone.
This is the distribution of the minor scale.
The scales are distinguished
by the distribution of whole-tone and half-tone steps.
Practicaly, the minor scale is played in music
as the variation of natural minor scale.
One is the harmonic minor scale.
In the harmonic minor scale, seventh tone (Ⅶ) is played as sharp note.
So in the harmonic minor scale,
the distribution of whole-tone and half-tone intervals are;
Whole, Half, Whole, Whole, Half, Whole and half, Half.
The other is the melodic minor scale.
In the melodic minor scale,
sixth tone (Ⅵ) and seventh tone (Ⅶ) are played as sharp notes.
So in the melodic minor scale,
the distribution of whole-tone and half-tone intervals are;
Whole, Half, Whole, Whole, Whole, Whole, Half.
通常音曲は音階上の音によって作曲されるが、
よく使われる音階には、
主として長音階(メイジャー・スケール)と短音階(マイナー・スケール)がある。
これらの内、
短音階(マイナー・スケール)で作曲された曲の調(キー)を
短調(マイナー・キー)と言う。
短音階(マイナー・スケール)それぞれの第一音(トニック)の高さにより
イ短調(Aマイナー・キー)、
嬰ヘ短調(Fシャープ・マイナー・キー)などと呼ばれる。
The key of music which is composed of the notes of minor scale
is called "minor key".
通常音曲は音階上の音によって作曲されるが、
一般的によく使われる音階としては、
長音階(メイジャー・スケール)と
短音階(マイナー・スケール)
がある。
長音階と短音階の違いは、
音階内での構成音間の音程配置により決まる。
長音階では第三音と第四音の間および第七音と第八音の間が半音音程となり、
短音階は長音階の主音の短3度下の音が主音と成る為、
構成音そのものは長音階とまったく同じで、
調号
も同じだが、
第二音と第三音の間および第五音と第六音の間が半音音程となる。
具体的に考えてみよう。
たとえばCメイジャー・スケール(ハ調長音階)をアルファベット文字で表し、
構成各音の主音からの度数(デグリー)をローマ数字で表すと次のようになる。
Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ,Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ,Ⅷ(Ⅰ)
C, D, E,F, G, A, B,C,
ド, レ, ミ,ファ, ソ, ラ, シ,ド,
構成音は七音、
八音目で元に戻るが、この一回り音程をオクターブ(Octave)という。
さてここで隣り合った音と音の距離(
音程
)を調べてみると、
全音音程が五箇所(CDの間、DEの間、FGの間、GAの間、ABの間)、
半音音程が二箇所(EFの間とBCの間)あることが解る。
その配置は、全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音、の順になっている。
僕はよくこれを略して、
「 全、全、半、全、全、全、半、」と口で唱えたりしてるが、
これがメイジャー・スケール(長音階)の音程配置である。
このようにスケール(音階)は
全音半音の音程配置によってその性格が決まり区別されている。
現代のメイジャー・スケール(長音階)は、
中世やルネッサンス期のヨーロッパで使われていた7つの教会旋法(Church modes)の一つ、
イオニアン(Ionian)にその原型が認められる。
The tones which we use in the music are drawn from the scale.
Probably the major scale is mostly used in the music of ours.
Now I explain the major scale here.
If we visualize the scale tones of C major scale
as an alphabetical series and the scale degrees by Roman numerals,
we get the following:
Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ,Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ,Ⅷ(Ⅰ)
C, D, E,F, G, A, B,C,
In this major scale, we can find five whole-tone intervals
(the interval of C&D, D&E, F&G, G&A and A&B),
and two half-tone intervals (the interval of E&F and B&C).
The distribution of whole-tone and half-tone intervals are:
Whole-tone, Whole-tone, Half-tone,
Whole-tone, Whole-tone, Whole-tone, Half-tone.
This is the distribution of major scale.
Like this, the scales are distinguished
by the distribution of whole-tone and half-tone steps.
1.一弦開放弦をピアノの一点ホ音(中央のミ音)に合わせるか、
または一弦5フレットを押さえて弾いた音をA音の音叉(440HZ)に合わせる。
Tune the open 1st string to the first E above middle C,
Or press the 1st string down at the 5th fret and tune this 1st string sound
until it sounds exactly the same as the A-sound of tuning fork(440hz).
2.二弦5フレットの音を一弦開放弦の音に合わせる。
Press the 2nd string down at the 5th fret,
And tune the 2nd string
until it sounds exactly the same as the open 1st string.
3.三弦4フレットの音を二弦開放弦に合わせる。
Press the 3rd string down at the 4th fret,
And tune the 3rd string
until it sounds exactly the same as the open 2nd string.
4.四弦5フレットの音を三弦開放弦に合わせる。
Press the 4th string at the 5th fret and tune to the open 3rd string.
5.五弦5フレットの音を四弦開放弦に合わせる。
Press the 5th string at the 5th fret and tune to the open 4th string.
6.六弦5フレットの音を五弦開放弦に合わせる。
Press the 6th string at the 5th fret and tune to the open 5th string.
●初心者には市販のギターチューナーを使うのが最も簡単で確実。
For the beginners,
It's the best to use the guitar-tuner
which you can buy in the instruments shop.
1. 五弦5フレットのハーモニックス音を440hzのA音に合わせる。
440hzのA音は市販の音叉、チューナー、
場合によってはピアノなど他の楽器からでも得られる。
Tune the harmonics sound of the 5th fret of the 5th string
to the first A above middle C.
until it sounds exactly the same as the A-sound of 440hz.
You can get the A-sound of 440hz from the tuning fork or the guitar-tuner
and also from some other instrument like the piano etc.
2. 一弦開放弦を五弦7フレットのハーモニックスに合わせる。
Tune the open 1st string
to the harmonics sound of the 7th fret of the 5th string.
3. 六弦5フレットのハーモニックス音を
五弦7フレットのハーモニックスに合わせる。
Tune the harmonics sound of the 5th fret of the 6th string
to the harmonics sound of the 7th fret of the 5th string.
4. 二弦開放弦を六弦7フレットのハーモニックスに合わせる。
Tune the open 2nd string
to the harmonics sound of the 7th fret of the 6th string.
5. 四弦7フレットのハーモニックス音を
五弦5フレットのハーモニックスに合わせる。
Tune the harmonics sound of the 7th fret of the 4th string
to the harmonics sound of the 5th fret of the 5th string.
6. 三弦7フレットのハーモニックス音を
四弦5フレットのハーモニックスに合わせる。
Tune the harmonics sound of the 7th fret of the 3rd string
to the harmonics sound of the 5th fret of the 4th string.
1. 五弦5フレットのハーモニックス音を440hzのA音に合わせる。
Tune the harmonics sound of the 5th fret of the 5th string
to the A-sound above middle C.
until it sounds exactly the same as the A-sound of 440hz.
2. 三弦3フレットの音を五弦開放弦にオクターブ違いで合わせる。
Tune the A sound of the 2nd fret of the 3rd string,
to the octave lower A sound of the open 5th string.
3. 六弦3フレットの音を三弦開放弦にオクターブ違いで合わせる。
Tune the G sound of the 3rd fret of the 6th string,
to the octave higher G sound of the open 3rd string.
4. 二弦開放弦を五弦2フレットの音にオクターブ違いで合わせる。
Tune the B sound of the open 2nd string,
to the octave lower B sound of the 2nd fret of the 5th string.
5. 四弦開放弦を二弦3フレットの音にオクターブ違いで合わせる。
Tune the D sound of the open 4th string,
to the octave higher D sound of the 3rd fret of the 2nd string.
6. 一弦開放弦を四弦2フレットの音にオクターブ違いで合わせる。
または一弦開放弦を六弦オープンに二オクターブ違いで合わせても良い。
Tune the E sound of the open 1st string,
to the octave lower E sound of the 2nd fret of the 4th string,
Or tune E sound of the open 1st string,
to the 2 octaves lower E sound of the open 6th string.
曲の五線譜の冒頭、ト音記号など音部記号の次に、
シャープ ”#” やフラット ”♭” が記されているのが良く見られる。
この位置に記されているシャープ ”#” やフラット ”♭”等の変化記号を
「調号」とか「調記号」などと呼んでいる。
その曲のキー(調)で使われている
スケール構成に必要なだけのシャープ ”#” やフラットが必要な音の場所に記されており、
臨時記号
の場合とは異なり、記された音に関しては
オクターブ
を含め全てに、
調号の効力は曲を通じて終わりまで及ぶ。
従って調号の効力を一時的に無効にするにはもう一つの変化記号のナチュラルを臨時記号的にそのつど使う。
なお調号の位置でナチュラルを使えば「転調」になる。
When you find sharp"#" or flat"♭" at the head of the staff,
between the clef sign and the time, we call it "Key Signature".
Key signature is effective throughout all the piece.
通常音曲は音階上の音によって作曲されるが、
よく使われる音階には、
主として長音階(メイジャー・スケール)と短音階(マイナー・スケール)がある。
これらの内、
長音階(メイジャー・スケール)で作曲された曲の調(キー)を
長調(メイジャー・キー)と言う。
長音階(メイジャー・スケール)それぞれの第一音(トニック)の高さにより
ハ長調(Cメイジャー・キー)、
変ホ長調(Eフラット・メイジャー・キー)などと呼ばれる。
The key of music which is composed of the notes of major scale
is called "major key".
ダイアトニック・スケール
上のある音をベースとして、
その上に3度音程でさらに二つの音を重ねて、
合計三つの音で構成された和音(コード)を
「三和音」すなはち「トライアド」と言い、
最初の基音となる音をルート(根音)、
その上に3度音程で重ねた音をサード(3音)、
さらにその上に3度音程で重ねた音を、
ルートから5度音程の音と言う意味でフィフス(5音)と言います。
さて、
同じ3度音程と言っても全音二つ(音間距離2.0)離れている長三度と、
全音一つに半音一つ加えた分だけ(音間距離1.5)離れている短三度があります。
ルートから長三度上の音(音間距離2.0)をサード音としていて、
さらにサードから短三度上の音(音間距離1.5)をフィフス音としているコードを
「メイジャー・コード」と呼ぶのに対して、
逆にルートから短三度上の音(1.5)をサード音としていて、
さらにサードから長三度上の音(2.0)をフィフス音としているコードを
「マイナー・コード」と呼んでいます。
ところでメイジャー・コード、マイナー・コード何れにしても、
長短3度音程の配置が異なるだけで、
ルートからフィフスまでの音程は同じであることが解ります。
この音程を完全5度(音間距離3.5)と言います。
ダイアトニック・スケール上に成立するコードの、
ほとんどのフィフス音は完全5度なのですが例外があります。
ルートから短三度上の音(1.5)をサード音としていて、
さらにサードからも短三度上の音(1.5)をフィフス音としているコード、
すなはちルートからフィフスまでの音程が、
完全5度に半音(0.5)足りない減5度(3.0)であるコードも、
ハーフ・ディミニッシュ・コードと呼ばれ実際に存在します。
さて、このルートから減5度(3.0)音程のフィフス音に、
さらに短三度(1.5)上のいわゆる「セブンス」音を加えると、
上下で接している構成音同士の音程が
全て短三度(1.5)になる四和音が成立します。
この特殊なセブンス・コードを、
「ディミニッシュ・セブンス・コード」と言い、
通常はさらに簡単に「ディミニッシュ・コード」と呼んでいます。
ちなみにディミニッシュ・コードのセブンス音は、
長7度(5.5)でも短7度(5.0)でもない減7度(4.5)の音です。
それでは具体的に、
ディミニッシュ・セブンス・コードを見てみましょう。
例えばCメイジャー・スケール上のB音をルートとして、
短3度(1.5)音程を次々に重ねて四和音を構成すると、
B(シ)、D(レ)、F(ファ)、G#(ソ#)のコードになります。
G#(ソ#)はA♭(ラ♭)と考えても同じことです。
それぞれの音程を見ていくと、
ルートBとサードDも短3度(1.5)、
サードDとフィフスFも短3度(1.5)、
ここまでで減5度(3.0)ですから、
このコードはここまでのところメイジャーでもマイナーでもない、
ハーフ・ディミニッシュであることが解ります。
つぎにフィフスFとセブンスG#も短3度(1.5)ですから、
ルートBからセブンスG#まで
全ての構成音が短3度(1.5)ずつで重ねられていますので、
このコードは「B・ディミニッシュ・セブンス・コード」
通称「B・ディミニッシュ・コード」ということになります。
表記としては「Bdim」または「B゚」と書きます。
A chord of three diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of two thirds
is called "triad".
The names "root", "third" and "fifth"
are given to these scale notes.
As for triad,
we mainly use two types of chords.
One is minor chord and the other is major chord.
The types of these chords are distinguished
by the distribution of a major third and a minor third intervals.
If the interval between root and third is a minor third (1.5),
and the interval between third and fifth is a major third (2.0),
this chord must be minor chord.
If the interval between root and third is a major third (2.0),
and the interval between third and fifth is a minor third (1.5),
this chord must be major chord.
And in both of them,
the interval between root and fifth is a perfect fifth (3.5).
Then,
If the interval between root and third is a minor third (1.5),
and the interval between third and fifth is also a minor third (1.5),
generally we call this chord "Half-diminished chord".
The interval between root and fifth of a half-diminished chord
is not perfect fifth (3.5) but diminished fifth (3.0).
And further,
if one more "seventh" note is superposed on the fifth of this chord
with the interval of a minor third (1.5) again,
How can we call this type of chord?
we call this type of chord
"Diminished seventh chord" or simply "Diminished chord".
The interval between root and seventh of a diminished seventh chord
is diminished seventh (4.5).
Now we know that
the diminished seventh chord is a chord of four scale notes
that are obtained by the superposition of three minor thirds.
For example,
If we make a triad based on B in C key,
the chord tones are like following;
Root is B, the third is D and the fifth is F.
How are the intervals of these chord tones?
The interval of B and D is a minor third (1.5),
and the interval of D and F is also a minor third (1.5).
So the interval between root and fifth is diminished fifth (3.0).
And if one more "seventh" note is superposed on the fifth of this triad
with the interval of a minor third (1.5) again,
this "seventh" note must be "G#"
which is the diminished seventh (4.5) note from root.
Now we can understand that
this chord is definitely a diminished seventh chord.
And this diminished seventh chord is written like
"Bdim" or "B゚".
二拍目と四拍目を強く弾くことでそこにアクセントが創出され、
2ビート(ツー・ビート)と呼ばれるリズム感を表せる。
一拍目と三拍目が弱音で弾ければさらに良い。
具体的には、ピックが弦に当たる深さが限りなく浅ければ弱音になり、
ある程度深ければ強音になる。
2拍目と4拍目をカッティングすればさらに効果的。
When we play the rythm accompaniment with 4 strums in a measure,
a better rhythmic feeling which is called “2 Beat ”can be produced
by putting the accents on the second beat and the fourth beat.
So play strong strokes on the 2nd & 4th beats,
and weakly on the 1st & 3rd beats.
And if you can use the playing technique which is called "cutting",
It would be better to cut the second beat strum and the fourth beat strum.
ダイアトニック・スケール
上の
トニック音(Ⅰで表記される主音)をベース音として、
その上に3度音程でさらに二つの音を重ねて、
合計三音で構成された和音(コード)を
「トニック・コード」と言う。
たとえばCキーで考えてみよう。
Cキーで使われる音階はCメージャー・スケールだが、
Cメージャー・スケール上のトニック音はC音。
C音(ド)をベースにして3度上のE音(ミ)を重ね、
さらにそのE音(ミ)の3度上のG音(ソ)を重ねると「三和音」となり、
全部でC(ド), E(ミ), G(ソ)の三和音構成としたコードが、
Cキーのトニック・コードである。
この場合の音程構成は、
CとEの音程差が長三度(2.0)、
EとGの音程差が短三度(1.5)でCからGでは完全五度。
Cトニック・コードの音程構成は以上の通りだが、
Cキーで書かれた曲は通常主和音のCにはじまり主和音のCで終わることが多い。
"Tonic Chord" is a chord of three diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of two thirds
based on the tonic note of a diatonic scale.
For example,
we use C major scale in C key,
and the tonic note of C major scale is "C".
As triad, "C" chord consists of C, E and G,
and the interval of C and E is major third,
and the interval of E and G is also third but minor third.
and now we can make the chord of three diatonic scale notes
that is called "Tonic chord" in C key.
ダイアトニック・スケール
上の
ドミナント音(Ⅴで表記される第5音)をベース音として、
その上に3度音程でさらに三つの音を重ねて、
合計四音で構成された和音(コード)を
「ドミナント・セブンス・コード」と言う。
たとえばCキーで考えてみよう。
Cキーで使われる音階はCメージャー・スケールだが、
Cメージャー・スケール上のドミナント音はG音。
G音(ソ)をベースにして3度上のB音(シ)を重ね、
さらにそのB音(シ)の3度上のD音(レ)を重ねると「三和音」となるが、
そのD音(レ)の上にさらに3度上のF音(ファ)を重ねて、
全部でG(ソ), B(シ), D(レ), F(ファ), の四音構成としたコードが、
Cキーのドミナント・セブンス・コードとしてのG7コードである。
この場合の音程構成は、
GとBの音程差が長三度(2.0)、
BとDの音程差が短三度(1.5)でGからDでは完全五度、
DとFの音程差が短三度(1.5)でGからFでは短七度。
Gドミナント・セブンス・コードの音程構成は以上の通りだが、
同じ音程構成のGコードであっても、
たとえばGキーにおいて成立するGコードは、
トニック上に成立するのであってドミナント上に成立するのではないから、
ドミナント・セブンス・コードとは呼ばない。
トニックのセブンス・コードまたはただのセブンス・コードである。
"Dominant Seventh Chord" is a chord of four diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of three thirds
based on the dominant note of a diatonic scale.
For example,
we use C major scale in C key,
and the dominant note of C major scale is "G".
As triad, "G" chord consists of G, B and D,
and the interval of G and B is major third,
and the interval of B and D is also third but minor third.
If we superpose a seventh note "F" on D,
the interval of D and F is also minor third,
and we can make the chord of four diatonic scale notes
that is called "G dominant seventh chord".
「バー・コード」とは、
左手人差し指で六本の弦全てを押さえている形のコードを言う。
一つのバー・コードを覚えると、
同じフォームでそのままフィンガー・ボード上を移動させるだけで、
実質十以上のコードを見つけ出して使うことができるので便利。
特にシャープ系やフラット系のコードを簡単に見つけられるのは利点。
バーコードはフィンガーボード上どこのポジションでも使われており場所を選ばないが、
オープンポジションで押さえられるコードのほとんどは
オープンコード
と呼ばれている。
バーコードは押さえが弱いときれいな音が出ないので、
どうしても無理に押さえがちになる。
指にそれ相応のパワーがついて来ないとどのみち良い音は出ない。
良い音を出すために最も重要なのはフォームと力のバランス。
たとえば"Bm"や"F"で言えば、
押さえの力の懸かるポイントが横方向としての三箇所のフレットにわたる。
とすればネックの裏側で支える親指の位置は、
左右三方から懸かってくるベクトルの中心でなければならない。
多くは人差し指でしっかり押さえなければいけないと思うあまり、
支えの親指の位置が人差し指のちょうど裏側になってしまう。
実際のベクトルの中心はむしろ中指の裏側に近いはず。
このように力のバランスがうまく取れていれば、
コードを押さえるフォームは無理のないきれいな形になるはず。
バー・コードのきれいなフォームとは、
人差し指が硬直せずに、ゆったりとした真直ぐになっているか・・・。
中指が横に傾いたり寝たりせず、垂直に押さえているか・・・。
薬指と小指の関節が逆反りせず、自然なアーチ状に曲がっているか・・・。
"Barre" is pronounced "bar".
To play the barre chord,
you must press down over all six strings at a particular fret
with your index finger (1st finger) of the left hand,
and remaining three fingers can be used freely to play a chord
And it is necessary for the index finger
to press down tightly across all the strings and remain relatively rigid.
ダイアトニック・スケール
上のある音をベースとして、
その上に3度音程でさらに二つの音を重ねて、
合計三つの音で構成された和音(コード)を
「三和音」すなはち「トライアド」と言い、
最初の基音となる音をルート(根音)、
その上に3度音程で重ねた音をサード(3音)、
さらにその上に3度音程で重ねた音を、
ルートから5度音程の音と言う意味でフィフス(5音)と言います。
さて、
同じ3度音程と言っても全音二つ(音間距離2)離れている長三度と、
全音一つに半音一つ加えた分だけ(音間距離1.5)離れている短三度があります。
ルートから長三度上の音(音間距離2)をサード音としていて、
さらにサードから短三度上の音(音間距離1.5)をフィフス音としているコードを
「メイジャー・コード」と呼ぶのに対して、
ルートから短三度上の音(音間距離1.5)をサード音としていて、
さらにサードから長三度上の音(音間距離2)をフィフス音としているコードを
「マイナー・コード」と呼んでいます。
ところでメイジャー・コード、マイナー・コード何れにしても、
長短3度音程の配置が異なるだけで、
ルートからフィフスまでの音程は同じであることが解ります。
この音程を完全5度(音間距離3.5)と言います。
ダイアトニック・スケール上に成立するコードの、
ほとんどのフィフス音は完全5度なのですが例外があります。
ルートから短三度上の音(音間距離1.5)をサード音としていて、
さらにサードからも短三度上の音(音間距離1.5)をフィフス音としているコード、
すなはちルートからフィフスまでの音程が、
完全5度に半音(0.5)足りない減5度(3.0)であるコードを、
ハーフ・ディミニッシュ・コードと言い、
通常は短7度(5.0)の音を加えた四和音構成で使われるので、
ハーフ・ディミニッシュ・セブンス・コードと呼んでいます。
ちなみにハーフ・ディミニッシュ・コードに、
減7度(4.5)の音を加えた四和音コードは、
ディミニッシュ・コードと呼ばれています。
ハーフ・ディミニッシュ・セブンス・コードは、
マイナー・セブンス・コードの第5音であるフィフスが、
半音下がったコードと考えると覚えやすく、
実際には表記上も、
たとえば"Bm7(♭5)"のように書き表されます。
それでは具体的に、
ハーフ・ディミニッシュ・セブンス・コードを見てみましょう。
Cメイジャー・スケール上のB音をルートとして、
3度音程を重ねて四和音を構成すると、
B(シ)、D(レ)、F(ファ)、A(ラ)のコードになります。
それぞれの音程を見ていくと、
ルートBとサードDは短3度(1.5)、
サードDとフィフスFも短3度(1.5)、
ここまでで減5度(3.0)ですから、
このコードはメイジャーでもマイナーでもない、
ハーフ・ディミニッシュであることが解ります。
つぎにフィフスFとセブンスAは長3度(2.0)ですから、
ルートBからセブンスAまでが短7度(5.0)なので、
このコードは「Bハーフ・ディミニッシュ・セブンス・コード」と言い、
Bm7(♭5)とかBm7(-5)と表記します。
A chord of three diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of two thirds
is called "triad".
The names "root", "third" and "fifth"
are given to these scale notes.
As for triad,
we mainly use two types of chords.
One is minor chord and the other is major chord.
The types of these chords are distinguished
by the distribution of major third and minor third intervals.
If the interval between root and third is minor third (1.5),
and the interval between third and fifth is major third (2.0),
this chord must be minor chord.
If the interval between root and third is major third (2.0),
and the interval between third and fifth is minor third (1.5),
this chord must be major chord.
And in both of them,
the interval between root and fifth is perfect fifth (3.5).
Then,
If the interval between root and third is minor third (1.5),
and the interval between third and fifth is also minor third (1.5),
How can we call this chord?
Generally we call this type of chord "Half-diminished chord".
The interval between root and fifth of a half-diminished chord
is not perfect fifth (3.5) but diminished fifth (3.0).
And further,
if the "seventh" note is superposed on the fifth of this chord
with the interval of minor seventh (5.0) from root,
we call this type of chord "Half-diminished seventh chord".
Half-diminished chord is usually played
as "Half-diminished seventh chord".
Let us see practically.
If we make a diatonic seventh chord based on B in C key,
the chord tones are like following;
Root is B, the third is D, the fifth is F
and the seventh is A.
How are the intervals of these chord tones?
The interval of B and D is minor third (1.5),
and the interval of D and F is also minor third (1.5).
Here we know that this chord is a half-diminished chord.
Then the interval of F and A is major third (2.0),
and so the interval of B and A is minor seventh (5.0).
Now we can understand that
this chord is definitely a half-diminished seventh chord.
A half-diminished seventh chords are generally written
like "Bm7♭5" or "Bm7-5".
異なる二つのコードそれぞれの構成音どうしをメロディックにつなげる技法を
パッシングと言う。
とくにルートなどのベース音どうしをつなげた場合はベース・ランと呼び、
コードの変わった小節の、直前の小節最後尾からニ、三拍において実行される。
歌伴奏の単調さに変化を与える効果が大。
The Passing is made up of the consecutive notes of the scale
connecting each other's chord tones of the two chords .
Especialy when the passing is played
as the bass progression on the bass strings,
it is also called“the Bass Runs”.
And it is usually played on the last one, two or three beats of the measure
just before the measure in which a new chord should be played.
It sounds like a bass melody.
ギターで音を出すには通常右手で弾弦するか、
右手で持ったピックなどにより弦を弾くわけだが、
右手で弾くことをせずに、
弦を押さえるのに使う左手の指先で弦を叩くことにより音を鳴らす奏法を、
ハンマーリングとかハンマーリング・オンと言う。
ハンマーリングによる音は右手で弾く音にくらべて弱くなりがちなので、
出来るだけ強めに叩くことがコツである。
When we play the guitar, we often use the special way of making sound
by striking a string with the finger tip of the left hand.
We call this way of playing "Hammering" or "Hammering-on".
Hammering is played not by picking the string with a finger of the right hand,
but by bringing the finger of the left hand down just behind the fret.
And the striking the string should be hard
so that the hammered note sounds out loud and clear.
フラット・ピック A Flat Pick、フィンガーピック Finger Picks、
そしてフィンガーピックの一種であるサムピックなどがあります。
コードのストローク弾きやリードギター用には通常フラット・ピックを使います。
フラット・ピックには三角形型とハート型があり、
硬さにもハード、ミーディアム、ソフトの三種類ぐらいあります。
初心者向きなのは三角型のミーディアム。
The Flat Pick is used for playing the chord strumming.
And for the beginners,
it is easy to play to use the triangle shape & medium- type pick.
五線譜冒頭は音部記号、その右隣には調号、
さらにその右隣に分数のように上下一組の数字で記されているのが拍子記号。
いわゆる4拍子、2拍子、3拍子などがある。
拍子は曲中で度々変わることも良くあり、その場合は変わる小節の冒頭にその都度書き込まれる。
四分音符を一拍として、四拍分を一小節とする。
上の数字は一小節の拍数、下の数字は単位となる音符の種類を示す。
この拍子に関しては数字ではなく、伝統的に使われてきた記号で記す場合も多い。
This means four beats per measure with a quarter note receiving one beat.
And the top number tells the beats in one measure,
and the bottom number indicates the kind of note which gets one beat.
二分音符を一拍として、二拍分を一小節とする。
この拍子に関しても数字ではなく、伝統的に使われてきたもう一つの記号で記す場合も多い。
This means two beats per measure with a half note receiving one beat.
四分音符を一拍として、三拍分を一小節とする。
This means three beats per measure with a quarter note receiving one beat.
歌の主旋律フレーズの末尾において、
音が希薄になったり空白になったりした部分で、
その不足感を埋めるように弾かれるフレーズを「フィル・イン」と呼んでいる。
ページの空白部分を埋める埋め草のようなもの。
「フィル・イン」には大別してリズム的なものとメロディー的なものがある。
いづれのフレーズでも
主旋律に対するある種の装飾効果を生み出すことができる。
When you sing a song with guitar accompaniment by yourself,
you may often feel dissatisfaction as music
at the last measures of each musical sentence
where there is no melody and no words exept for simple guitar strums.
A better ornamental phrase is produced
if you add a attractive melody or some rhythm variation
to your guitar accompaniment at these last measures.
This kind of instrumental melody or rhythm
which is ornamentally played at the last measure of each musical sentence
is called "Fill-in".
"Fill in" can enrich the monotonous measures.
ギター等の弦楽器は一見してヘッド、ネック、ボディの三パートから成るが、
ギターの場合このネック即ち三味線などで言う「棹」の部分表面には、
エボニー、ローズウッドなどの材質の板が張られており、
その表面には半音ごとに音が変わるように金属のフレットバーが打ち込まれている。
演奏時、左手により弦を押さえたりするフィンガリング(指使い)の場所となるため、
この板状の部分を「フィンガーボード」と呼ぶ。
ギターで音を出すには通常右手で弾弦するか、
右手で持ったピックなどにより弦を弾くわけだが、
右手で弾くことをせずに、
あらかじめ弦を押さえている左手の指を、
押さえたままの状態で一つ隣の高音弦側に引くようにずらすと、
弦がはじけて指から離れ音を鳴らすことができる。
この奏法をプリング・オフと呼んでいる。
プリング・オフはハンマーリングと同様右手で弾かずに、
弦を押さえるために使う左手の指の動きだけで音を鳴らす奏法である。
Beforehand press down the some string,
with the finger of the left hand.
And then remove this finger
by moving the finger to the side of the lower numberd string,
so that the string which was pressed before is sounded.
The finger of the left hand actually picks the open string.
We call this way of making sound with a finger of the left hand
"Pulling-off".
Picking called "Pulling-off" is the reverse of "Hammering-on".
Pulling-off is played
not by picking the string with a finger of the right hand,
but by removing the finger of the left hand
which pressed down the string beforehand.
ブルースは19世紀以来アメリカの黒人の間で歌われ続けてきた音楽で、
そのメランコリーな雰囲気と共に、
独特のリズムやスケール(音階)や音楽形式を持ち、
アメリカ音楽の主要なジャンルの一つとなっている。
一般的にはスローテンポなものが多く、
リズムは一拍三連の真ん中を抜いたようなリズムで、
重々しく引き摺るような感覚がある。
歌のメロディーを構成するスケールは、
通常の
メイジャー・スケール
の第3音や第5音等がフラット(♭)することが多く、
これらのフラット音をブルーノートと呼んでいる。
このブルーノート・スケールのメロディーが、
定型化された
スリー・コード
伴奏で
スローテンポのブルース・リズムにのせて歌われると、
魂を揺さぶるような独特でメランコリーな雰囲気をかもし出す。
歌詞の形式はスリーライン・フォームと呼ばれる三行詩。
一行が四小節で歌われるので十二小節で曲がつくられている。
一行目と二行目は同じ歌詞を繰り返すことが普通なので、
詩としてはきわめてシンプル。
このシンプルな詩の中に黒人たちは悲しみや苦しみや、
そして時には希望や祈りをこめて歌った。
"Blues" is a type of song
that has American Negro origin from 19th century,
and its tune is predominantly melancholy in character,
and is usually performed in slow tempo
with the characteristic rhythm of a triplet notes receiving one beat.
Its lyric has basicly a three line stanza
which is called "three line form",
and in most cases, first two lines have the same words,
and the only last line has the different words.
And a melody of each line is usually sung in four measures,
so a blues is sung in twelve measures long.
ブルースの歌詞の基本的な形式は
スリーライン・フォームと呼ばれる三行詩だが、
それぞれの一行には四小節が当てられて歌われる。
四小節といっても実際に歌われる部分はほぼ最初の二小節分で、
それに続く残りの二小節は伴奏だけとなるのが普通。
この伴奏だけの歌の無い空白部分が
ブルースの三行それぞれの終わりに三回発生するわけで、
この部分は聞いていても歌っていても多少物足りない感じがある。
そこで何か気の利いたフレーズで埋めたくなるのだが、
こういった埋め草のようなフレーズをフィルインと呼んでいて、
ブルースでは特に「ブレイク」という呼び方をする。
基本的なブルースでは使うコードはほぼ
スリーコード
、
コード進行もほぼ決まっており、
各調共通のローマ数字でコード表記すれば、
以下のようなコード進行になる。
一行目;Ⅰ,Ⅰ,Ⅰ,Ⅰ
二行目;Ⅳ,Ⅳ,Ⅰ,Ⅰ
三行目;Ⅴ,Ⅵ,Ⅰ,Ⅴ (ターン)
終止 ;Ⅴ,Ⅵ,Ⅰ,Ⅰ (エンディング)
一行目四小節はおおむね
トニックコード、
二行目四小節では最初二小節が
サブドミナントコードで、
後半二小節がトニックコード、
そして三行目四小節では初めがドミナントコードで、
次がサブドミナントコード、その次がトニックコードと続き、
「ターン」と呼ばれる最後の折り返し小節は
ドミナントコードで、
また最初から同じコード進行を
歌が終わるまで繰り返すことになる。
歌の終わり即ちエンディングはもちろんドミナントコードではなく、
トニックコードで終えるのが普通。
こうしてみると一行目後半のブレイクは
トニックコードに合ったフレーズで、
次のサブドミナントコードにつながるフレーズと言うことになる。
これに対し二行目後半のブレイクは
同じくトニックコードに合ったフレーズだが、
次のドミナントコードにつながるフレーズと言うことになり、
三行目最後の別名ターンと呼ばれるブレイクは、
トニックコードもしくは、
トニックコードからドミナントコードに変化するのに合わせたフレーズで、
繰り返し冒頭のトニックコードにつながるフレーズと言うことになる。
曲の終わりはもちろんブレイクではなくエンディングなので、
一般的にはトニックで終わりとなる。
Generally speaking,
the blues is the three lines form
consisting of twelve measures.
The chord progression of blues is basically like following.
1st line; Ⅰ,Ⅰ,Ⅰ,Ⅰ
2nd line; Ⅳ,Ⅳ,Ⅰ,Ⅰ
3rd line; Ⅴ,Ⅵ,Ⅰ,Ⅴ (turn)
Ending ; Ⅴ,Ⅵ,Ⅰ,Ⅰ
The first two measures of each line is usually vocalized,
and the last two measures of each line becomes
pause in the singing.
In these pauses,
the singing player of guitar can fill in
with his own instrumental passages
which are called "breaks".
In the typical three-line blues,
the first line of it's lyric is sung
in nearly first two measures out of four.
And the guitar accompaniment of those four measures are
played with "tonic" chords.
So the first break is played with tonic tune
at the end of first line.
And the second line of it's lyric,
mostly the same words as the first line, is sung
also in nearly first two measures out of four.
But this time the guitar accompaniment of those four measures are
played with "sub-dominant" chords of first two measures
and "tonic" chords of last two measures.
So the second break is also played with tonic tune
at the end of second line.
The third line of it's lyric is sung
also in nearly first two measures out of four.
And this time the guitar accompaniment of those four measures are
usually played with "dominant" chord of first measure,
"sub-dominant" chord of second measure,
"tonic" chords of third measure
and again "dominant" chord of the last measure as the turn.
Only at the ending, "tonic" chord is played in the last measure .
So the third break is played with dominant tune as the turn,
aithough the starting is played with tonic tune.
When the singing players sing blues,
they play three kinds of breaks in a blues.
歌をうたう、すなわち発声している時は必ず息を吐き出しています。
したがって発声する前にはあらかじめ息を吸い込んでおく必要があるわけです。
つまり歌をうたうということは、
息を吸い込むことと息を吐き出すことを交互に繰り返す、
呼吸行為そのものだと言えるのです。
この発声をする直前の息の吸い込みを「ブレス」と呼んでいます。
ブレス記号は「V」で表します。
ブレスが不十分だと、一つのフレーズをしっかり歌いきることができません。
逆にフレーズを歌っているあいだに十分に息を使いきらないと、
次のブレスがうまくできません。
ブレスは歌の基礎的技術なのです。
We usually breathe out when we sing some melody-phrase.
And we need to breathe in just before the vocalizing the melody-phrase.
So it can be said that
the singing is the repetition of breathing out and breathing in alternately.
In order to produce a better vocal expression and performance,
it is very important to breathe in fully
just before starting to sing a melody-phrase,
The sign "V" above the staff means "Breath".
"Breath" is the basic technique for singing.
二つの音が同じ音程を保ちながら進行することを並行音程と言うのですが、
よく使われるものとしては、
並行三度、並行六度、そしてオクターブなどがあります。
The progression of parallel scale notes
that are obtained by the superposition of a definite interval
is called "consecutive intervals".
As the consecutive intervals,
the third, sixth and octave are mostly played in the guitar music.
俗に分数コードとよく呼ばれているコードの表示がある。
二つのアルファベット文字が分数のように横線の上下に書かれていたり、
スラッシュを挟んで左右に書かれたりしているコード表示である。
上または左のアルファベット等は文字通りコード・ネームを表すが、
下または右に表示されているアルファベット文字はベース音を指定している。
基本としては通常コードの最低音すなわちベース音はルート(根音)である。
たとえばCコードのベース音はC音、
Amコードのベース音はA音といった風に・・・。
しかし必ずしもベース音がルートでなければならないとは限らない。
フィフス(五度)やサード(三度)などのコード構成音や、
さらにはスケール上の音ならどれでも一応はベース音とすることができる。
こういった場合に良く表記される指定ベース音付きのコード・ネームの例を、
下記に挙げておく。
C/G; G音をベース音とするCコード。
C/E; E音をベース音とするCコード。
C/D; D音をベース音とするCコード。
Am/G; G音をベース音とするAmコード。
A chord of the three scale-tones
is obtained by the superposition of two thirds.
For example;
A fundamental note of "C" chord is "C".
And this fundamental note is called "root".
And superpose "E" on "C".
The note "E" is the "third" of the fundamental note.
Then superpose "G" on "E". The note "G" is the third of "E",
and at the same time, the "fifth" of the fundamental note.
Likely "C" chord is consists of the three scale tones.
The names“root,”“third,”and “fifth” are given to these scale-tones
as the three factors of the triad.
When we play "C" chord, the bass note is usually a root note "C".
But we can also play
the "third","fifth and any other scale-tones as the bass note.
In these cases,
the bass note is specified beside the chord name as following,
C/G; C chord on the "G" note as the bass note.
C/E; C chord on the "E" note as the bass note.
C/D; C chord on the "D" note as the bass note.
Am/G; Am chord on the "G" note as the bass note.
etc.
The first alphabetical letter before slash represents chord name,
and the last alphabetical letter after slash represents bass note.
声もしくはヴァイオリン、チェロ等の擦弦楽器である音から別の音に移行する時、
階段状跳躍的にではなく、
坂を刷り上がるように、または滑り降りるように滑らかに移っていく演奏表現の事。
フレットのあるギターやピアノのような平均律楽器では厳密にはポルタメントな演奏は出来ない。
イタリア語で「運ぶ」と言った意味らしい。
ここでは最も基本的なコードである三和音(トライアド)で説明する。
三和音(トライアド)はルート(根音)、サード(ルートから三度音程の音)
そしてフィフス(ルートから五度音程の音)の三音で構成されるコードだが、
フィフスもサードから数えれば三度音程の音になり、
ルートから三度音程を二回重ねてつくられている。
さて、同じ三度音程と言っても全音二つ(音間距離2)離れている長三度と、
全音一つに半音一つ加えた分だけ(音間距離1.5)離れている短三度がある。
ルートから短三度上の音(音間距離1.5)をサード音としているコードを
「マイナー・コード」と呼ぶ。
基本的にルートからフィフスまでは完全五度(音間距離3.5)なので、
この場合、サードとフィフスの音程差は長三度(音間距離2)になる。
これにたいし、
ルートから長三度上の音(音間距離2)をサード音としているコードは
「メイジャー・コード」と呼び、
この場合では、サードとフィフスの音程差は短三度(音間距離1.5)になる。
たとえば、
具体的にAm コードで考えてみよう。
Am コードの構成音はルートがA(ラ)、サードがC(ド)、フィフスがE(ミ)。
AとCの音程は全音プラス半音で短三度(音間距離1.5)、
CとEの音程は全音プラス全音で長三度(音間距離2)になる。
従ってルートからサードまでが短三度上の音程(音間距離1.5)になっており、
Am コードは確かに「マイナー・コード」ということになる。
これにたいしAメイジャー・コードでは(通常Aコードと呼ぶ)、
サード音がルートから長三度音程で半音高いC#(ド#)になる。
このようにマイナー・コードとメイジャー・コードの違いは、
サード音のルートからの音程差の長短により決まる。
Here we think about the simplest chord which is called the triad.
The triad is a chord of the three scale-tones
obtained by the superposition of two thirds.
The names“root,”“third,”and “fifth”
are given to these scale-tones as the three factors of the triad.
Try to read the intervals of these three scale-tones.
If the third is superposed on root
with an interval of minor third (a whole tone and a half tone),
this chord is called "minor chord".
In this case, the other interval between third and fifth is
major third (two whole tones).
And if the third is superposed on root with an interval of major third,
this chord is called "major chord".
In this case, the other interval between third and fifth is minor third.
For example, let us think about Am chord practically.
The root of Am is "A", the third of Am is "C" and the fifth of Am is "E".
An interval between "A" and "C" is minor third.
Now you know that Am chord is definitely minor chord,
because the third of Am chord is superposed on its root
with an interval of minor third.
And in this case of Am chord,
the other interval between third and fifth is major third.
ダイアトニック・スケール上の音をルート(根音)として、
その上に3度音程でさらに三音を重ねて、
合計四音構成でできた「四和音」のコードを、
「ダイアトニック・セブンス・コード」と言いますが、
実はダイアトニック・スケール上には二種類の、
さらに細かく見れば四種類のセブンス・コードがあります。
「ダイアトニック・セブンス・コード」は、
ルート(root)、サード(third)、フィフス(fifth)、の三和音の上に、
さらに3度音程でセブンス音を重ねているわけですが、
元の三和音部分には、
メイジャー・コードとマイナー・コードがあります。
そして一方セブンス音と言っても、
ルートからの音程差により、
短7度の「セブンス」と長7度の「メイジャー・セブンス」があるので、
この組み合わせからすれば、
四つの「ダイアトニック・セブンス・コード」が考えられます。
この内、
マイナー・コードの上にルートから短7度のセブンス音を重ねてできるコードを、
「マイナー・セブンス・コード」と呼んでいます。
厳密に言えば、
ルートとサード間の音程が短3度(1.5)で、
サードとフィフス間の音程が長3度(2.0)になっているマイナー・コードで、
さらにフィフスとセブンス間の音程が短3度(1.5)、
すなはちルートからセブンスまでの音程が、
短7度(5.0)のダイアトニック・セブンス・コードを
「マイナー・セブンス・コード」と言います。
構成音間の音程配置を具体的に"Am7"コードで見てみましょう。
"Am7"コードの構成音はルートから順に、
A,C,E,G,となります。
この場合の音程構成は、
AとCの音程差が短三度(1.5)、
CとEの音程差が長三度(2.0)でAからEでは完全五度、
ここまででこのコードがマイナー・コードであることが確定です。
次にEとGの音程差が短三度(1.5)で、
AからGまでは短七度(5.0)ですから、
セブンス・コードになっています。
従ってこのコード"Am7"コードは、
たしかに「マイナー・セブンス・コード」です。
Diatonic seventh chord is a chord of four diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of three thirds.
The names "root", "third", "fifth" and "seventh"
are given to these scale notes
as the four factors of diatonic seventh chord.
And there are two kinds of diatonic seventh chords.
One is "Seventh chord", and the other is "Major seventh chord".
And each must have major chord and minor chord respectively.
These chords are distinguished
by the distribution of major third and minor third intervals.
Then how is the minor seventh chord?
If the third note is superposed on root
with an interval of minor third (1.5),
and the fifth note is superposed on the third
with an interval of major third (2.0),
and at the same time
the interval between root and seventh is minor seventh(5.0),
it is the seventh chord of minor chord.
Usually we call this type of chord "Minor Seventh Chord".
Practically,
let us see the distribution of major third and minor third intervals
in Am7 chord.
The interval of A and C is minor third (1.5),
the interval of C and E is major third (2.0).
Here we know that this chord is a minor chord.
And the interval of E and G is minor third (1.5).
So the interval of A and G is minor seventh (5.0).
Now we know that this chord is definitely a minor seventh chord.
Minor seventh chord is the minor chord
that has a seventh note of minor seventh interval(5.0) from its root.
ここでは最も基本的なコードである
三和音(トライアド)
で説明する。
三和音(トライアド)はルート(根音)、サード(ルートから三度音程の音)
そしてフィフス(ルートから五度音程の音)の三音で構成されるコードだが、
フィフスはサードから数えれば三度音程の音になる。
さて、同じ三度音程と言っても全音二つ(音間距離2)離れている長三度と、
全音一つに半音一つ加えた分だけ(音間距離1.5)離れている短三度がある。
ルートから長三度上の音(音間距離2)をサード音としているコードを
「メイジャー・コード」と呼ぶ。
基本的にルートからフィフスまでは完全五度(音間距離3.5)なので、
この場合、サードとフィフスの音程差は短三度(音間距離1.5)になる。
これにたいし、
ルートから短三度上の音(音間距離1.5)をサード音としているコードは
「マイナー・コード」と呼び、
この場合では、サードとフィフスの音程差は長三度(音間距離2)になる。
たとえば、
具体的にCコードで考えてみよう。
Cコードの構成音はルートがC(ド)、サードがE(ミ)、フィフスがG(ソ)。
CとEの音程は全音プラス全音で長三度(音間距離2)、
EとGの音程は半音プラス全音で短三度(音間距離1.5)になる。
従ってルートからサードまでが長三度上の音程(音間距離2)になっており、
Cコードは確かに「メイジャー・コード」ということになる。
メイジャー・コードを呼ぶ場合は通常メイジャーを省略するので、
Cメイジャー・コードと呼ばずにただCコードと呼ぶのが普通。
これにたいしてCマイナー・コードでは、
サード音がルートから短三度音程で半音低いE♭になる。
このようにマイナー・コードとメイジャー・コードの違いは、
サード音のルートからの音程差の長短により決まる。
Here we think about the simplest chord which is called the triad.
The triad is a chord of the three scale-tones
obtained by the superposition of two thirds.
The names“root,”“third,”and “fifth”
are given to these scale-tones as the three factors of the triad.
Try to read the intervals of these three scale-tones.
If the third is superposed on root with an interval of major third,
this chord is called "major chord".
In this case, the other interval between third and fifth is minor third.
And if the third is superposed on root with an interval of minor third,
this chord is called "minor chord".
In this case, the other interval between third and fifth is major third.
For example, let us think about C chord practically.
The root of C is "C", the third of C is "E" and the fifth of C is "G".
An interval between "C" and "E" is major third.
Now you know that C chord is definitely major chord,
because the third of C chord is superposed on its root
with an interval of major third.
And in this case of C chord,
the other interval between third and fifth is minor third.
ダイアトニック・スケール上の音をルート(根音)として、
その上に3度音程でさらに三音を重ねて、
合計四音構成でできた「四和音」のコードを、
「ダイアトニック・セブンス・コード」と言いますが、
実はダイアトニック・スケール上には二種類のセブンス・コードが成立します。
ひとつは普通に「セブンス・コード」と呼ばれているセブンス・コード。
もう一つは、
「メイジャー・セブンス・コード」と呼ばれているセブンス・コードです。
ダイアトニック・セブンス・コードの構成音は、
ルート(root)、サード(third)、フィフス(fifth)、セブンス(seventh)の四音ですが、
ルートから七番目の音になるセブンスまでの音程が、
短七度のダイアトニック・セブンス・コードを
「セブンス・コード」と呼び、
ルートから七番目の音になるセブンスまでの音程が、
長七度のダイアトニック・セブンス・コードを
「メイジャー・セブンス・コード」と呼びます。
どう違うのかを具体的に見てみましょう。
例えば、
Cメイジャー・スケール上のG音(ソ)をルートとして3度上のB音(シ)を重ね、
さらにそのB音(シ)の3度上のD音(レ)を重ねると「三和音」となりますが、
そのD音(レ)の上にさらに3度上のF音(ファ)を重ねて、
全部でG(ソ), B(シ), D(レ), F(ファ), の四音構成とすると、
"G7"すなはちGの「セブンス・コード」が成立します。
この場合の音程構成は、
GとBの音程差が長三度(2.0)、
BとDの音程差が短三度(1.5)でGからDでは完全五度、
DとFの音程差が短三度(1.5)でGからFでは短七度(5.0)。
すなわちGセブンス・コードのセブンス音は、
ルートから短七度音程の音であることがわかります。
そこでもう一例、
今度は同じCメイジャー・スケール上のC音(ド)をルートとして
3度上のE音(ミ)を重ね、
さらにそのE音(ミ)の3度上のG音(ソ)を重ねると
やはり「三和音」となりますが、
そのG音(ソ)の上にさらに3度上のB音(シ)を重ねて、
全部でC(ド),E(ミ),G(ソ), B(シ), の四音構成とすると、
この場合の音程構成は、
CとEの音程差が長三度(2.0)、
EとGの音程差が短三度(1.5)でCからGでは完全五度、
ここまでは第一例の"G7"と同じですが、
次のGとBの音程差は長三度(2.0)ですから、
CからBでは長七度(5.5)になります。
すなわちこの場合のセブンス音は、
"G7"での短七度音ではなく、
ルートから長七度音程の音であることがわかります。
従ってこちらのコードは
短七度音をセブンスとする「セブンス・コード」と区別して、
「メイジャー・セブンス・コード」と呼び、
"Cmaj7"とか"CM7"、または"C△7などと表記します。
Diatonic seventh chord is a chord of four diatonic scale notes
that are obtained by the superposition of three thirds.
The names "root", "third", "fifth" and "seventh"
are given to these scale notes
as the four factors of diatonic seventh chord.
And there are two kinds of diatonic seventh chords.
One is "Seventh chord", and the other is "Major seventh chord".
If the interval between root and seventh of the chord is minor seventh,
it is seventh chord.
And if the interval between root and seventh of the chord is major seventh,
it is major seventh chord.
For example,
If we make a diatonic seventh chord based on G,
the chord tones are like following;
Root is G, the third is B, the fifth is D
and maybe the seventh is F.
How are the intervals of these chord tones?
The interval of G and B is major third (2.0),
the interval of B and D is minor third (1.5),
the interval of D and F is minor third (1.5).
And the interval of G and F is minor seventh (5.0).
The diatonic seventh chord
whose interval between root and seventh is minor seventh
is called "Seventh chord",
so we call this chord "G Seventh chord".
Then let us see one more example.
If we make a diatonic seventh chord based on C,
the chord tones are like following;
Root is C, the third is E, the fifth is G
and maybe the seventh is B.
How are the intervals of these chord tones?
The interval of C and E is major third (2.0),
the interval of E and G is minor third (1.5),
the interval of G and B is major third (2.0) in this chord.
Then the interval of C and B is major seventh (5.5) in this chord.
So this chord based on C is obviously different kind chord from "G7",
and we call this chord "C Major seventh chord".
The diatonic seventh chord
whose interval between root and seventh is major seventh
is called "Major seventh chord".
The seventh note of "Major seventh chord" is
a half tone higher than the seventh note of "seventh chord".
Major seventh chords are generally written like
"Cmaj7", "CM7" or "C△7".
記号より前の部分を全て最初から繰り返して演奏する。
歌詞の多い歌などでは歌詞の回数分繰り返すこともある。
Play again all the music before the Repeat sign.
一度目は最初から後ろの繰り返し記号までを演奏。
二度目は、向かい合った前の記号と後の記号の間の部分を再び演奏する。
First time play the music from the beginning to the Repeat Sign,
And then play again between the repeat signs;
A preceding repeat sign and the repeat sign,
Those are facing opposite direction.
一回目の終わりは「1.カッコ」の小節を弾き、
リピート記号があるのでもう一度はじめから繰り返す。
演奏二回目の終わりでは「1.カッコ」を弾かずに飛び越して、
「2.カッコ」の小節を弾いて終わる。
The measure of 1st Ending is played in the 1st time,
and in the 2nd time it should be skipped.
The measure of 2nd Ending should be played in the 2nd time.
一度目は最初から「1.カッコ」の小節までを弾き、
リピート記号があるので、
二度目は前の記号(逆向きリピート記号)から繰り返し演奏して、
二度目の終わりでは「1.カッコ」を弾かずに飛び越して
「2.カッコ」の小節を弾いて終わる。
First time play the music from the beginning to the Repeat Sign;
the measure of 1st Ending.
In the second time,
play again from the preceding repeat sign (facing opposite direction)
to the measure before the 1st Ending.
And then skip to the 2nd Ending (the last measure) in this time.
一回目の終わりは「1.2.~ カッコ」の小節を弾き、
リピート記号があるので繰り返すのだが、今度は逆リピート記号から弾く。
唄う歌詞の回数により必要なだけ同じところを繰り返し、
最後の回では「1.2.~ カッコ」を飛び越して
「Last. カッコ」の小節を弾いて終わる。
The measure of 1st Ending is played in the 1st time,
and in the times which you need to play,
but in the last time it should be skipped.
The measure of the Last Ending should be played only in the last time.
まずリピート(繰り返し記号)があれば、
リピート記号より前の部分全て、
または二つのリピート記号に挟まれた部分を
2度または必要指定回数分演奏する。
次にD.C. al Codaとあるので、
もう一度最初から弾き(3度目または指定回数プラス1度目)、
To Coda の記号まできたら、そのうしろの部分を飛び越してCodaを弾いて終わる。
If the Repeat Sign is written,
first you should play all the music before this sign,
or the music between the two Repeat Signs,
the times which you need to play or to sing.
And then you’ll find “D.C. al Coda” sign,
This means to play once again from the beginning to the “To Coda” sign,
And then skip to the Coda.
●Da Capo al Coda (イタリア語 Italian):
ダ・カーポ・アル・コーダと読む。「最初からコーダへ」の意味。
This means to play again from the beginning and skip to the “Coda”.
●To Coda (al Coda)
トゥー・コーダと読む。コーダへ飛べという意味。
This means to skip here to the “Coda”.
●Coda
終止のこと。ふつう曲の終わりは最後の小節だが、
途中で終わるときには別途終止用の小節を用意する。
これをコーダという。
The Ending measures which is specially written.
セーニョ記号からもう一度演奏し、コーダへ飛んで終わる。
但しリピート記号がある場合はリピートの実行を優先する。
This means to play again from the “Segno” sign to the “al Coda”sign,
And then skip to the “Coda”.
●Dal Segno al Coda (イタリア語 Italian)
ダル・セーニョ・アル・コーダと読む。
音符を半音高くしたりその逆に半音低くしたり、
またそれらをもとの高さに戻したりするのに臨時記号が使われます。
良く使われる臨時記号として、
シャープ ♯、フラット ♭、ナチュラル ? の三つがあります。
これらの記号は音符の高さ(音程)に対して、次のように変化させます。
1)シャープは元の音符を半音高くする。
2)フラットは元の音符を半音低くする。
3)ナチュラルは、シャープまたはフラットで半音高くまたは低くした音符を、
元の高さにそれぞれ戻す。
シャープやフラットは
調記号(調号)
としても臨時記号としても使われますが、
ト音記号と拍子記号の間によく見られる
調号
は
その曲全体に効力を及ぼすのに対し、
臨時記号の効力は一時的なもので、
それが付けられた音符からその同一小節内に限り有効です。
ただし
オクターブ
違う音には同一小節内でも再度書き込みが必要。
なお次の小節では無論臨時記号の効力は無効になります。
ギターでは
フレット
が半音ずつ音が変わるように設定されていますので、
弦を押さえるポイントが同一弦上で
ブリッジ
方向に1フレットずらせばシャープしたことになり、
ヘッド
方向に1フレットずらせばフラットしたことになります。
In order to change the pitch of a note,
We use "Accidentals".
There are three accidentals; Sharp ♯, Flat ♭ & Natural ? .
1).Sharp raises a note a half tone.
2).Flat lowers a note a half tone.
3).Natural is used to cancel a sharp or flat
A sharp or flat is used both as the key signature and the accidental.
As an accidental,
a sharp or flat appears in a measure
in which there is no signature written,
and it is used only for the remainder of that measure,
and the next bar line cancels it out.
Natural is used to cancel out accidentals within the same measure,
and is also used to cancel a sharp or flat of the key signature
only in the remainder of that measure in which natural appeares.
コードは
音階
上のいくつかの音の集合体だが、
その中でもコードを構成するための基礎音となる音を
「ルート」(根音)と言う。
たとえば
トライアド(三和音)
で考えれば、
コードの基礎となる音、即ち基音が「ルート」で、
基音の上に基音から3度音程で重ねた音が
コード二つ目の構成音である「サード」(3度音)、
その「サード」音に更に3度音程で重ねた音、
即ち基音から見れば基音の上5度音程で重ねた音が
コード三つ目の構成音である「フィフス」(5度音)となり、
このタイプのコードはこれら三つの音階上の音で構成されている。
なおコード名はルート音名をもって呼ばれる。
具体的に見てみよう。
例えばCキーでのトニックコード "C" コード。
ルート音は"C"即ち固定ド音階での「ド」音。
「サード」(3度音)はルートの"C"「ド」音から3度音程で重ねた音だから"E"即ち「ミ」音。
「フィフス」(5度音)は「サード」(3度音)の"E"即ち「ミ」音に更に3度音程で重ねた音、
さらに言えば"C"「ド」音に5度の音程で重ねた音だから"G"即ち「ソ」音。
以上で"C"「ド」、"E"「ミ」、"G"「ソ」で構成される三和音"C" コードとなる。
"C"コードの「ルート」(根音)は"C"である。
A fundamental note of a chord is called "Root".
The simplest chord is a
triad
which consists of three scale notes.
And the names that are given to these scale notes are
"root", "third" and "fifth".
Root is the fundamental.
The third is a note
which is superposed on root with an interval of third,
and the fifth is a note
which is superposed on root with an interval of fifth.
 アベトシロー、阿部俊朗 Copyright Toshiro ABE, All right reserved 2000,2014.
アベトシロー、阿部俊朗 Copyright Toshiro ABE, All right reserved 2000,2014.