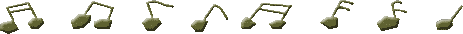
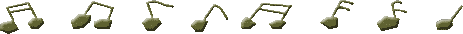
ジャズにおいてもそのメロディーが好んで演奏されるこの曲は 、
その元をたどればかなり古く、北アイルランドでの最初の採譜が19世紀中頃とされる。
現在では歌として有名なのだが、
採譜当時歌詞は無かったようなので歌であったかどうかはわからない。
一つの曲からいくつかの歌詞ヴァージョンが派生するのは
トラディショナル・フォーク・ソングでは良くあることだが、
この曲でも全くの同一メロディーながら
アイルランド民謡の「ロンドンデリーの歌」(Londonderry Air)としてのヴァージョンも
良く知られている。
「ロンドンデリーの歌」というタイトルとその王朝風の香りがするラブソングとしての歌詞は
1894年キャサリン・タイナン・ヒンクソンによるものだと言う。
ちなみにぼくの蔵書にある1963年版"Morton Downey's Collection of Favorite Irish Songs"には
この歌詞の「ロンドンデリーの歌」が掲載されている。
さて、「ダニー・ボーイ」のタイトルと歌詞は
1913年「ロンドンデリーの歌」のメロディーに合わせて
イングランドの弁護士フレデリック・ウエザリーにより作詞発表されたものだという。
とすれば「ロンドンデリーの歌」が元歌ということになる。
「ロンドンデリーの歌」はラブソングだが、「ダニー・ボーイ」は別離。
近い将来に予想される死によって、
再び会うことはかなわぬであろう恋人、友人、または家族である二人の、最後の別れの歌。
ぼくの歌っているのはハリー・ベラフォンテの歌詞ヴァージョンなので、
これから戦いに行く友とこの地に残らなければならない自分との別れの歌として、
僕自身の解釈においてイメージを膨らませながら歌っている。
ノルマン・コンクェストによりイングランドを統治したノルマン王朝が
十二世紀ヘンリー二世の時アイルランドに遠征、アイルランド諸侯の上に君臨する。
それ以来およそ八百年続いたイギリスの植民地状態から
アイルランド共和国として正式に独立したのは第二次大戦後1949年のことである。
独立の直接的契機となったのは第一次世界大戦中1916年に起きた復活祭蜂起の悲劇。
事前の蜂起計画失敗で何事も起こらなかった日曜日の翌日月曜日、
当然この日も何事も起こらないはずであったが、
不十分な数のライフルで武装した約千人ほどの男女がダブリン中央郵便局を占拠し、
なんとアイルランド共和国の設立宣言を発した。
一週間の抗戦により数千人の死傷者を出して後圧倒的なイギリス軍により鎮圧され、
その後二週間ほどの内に十数名の叛乱指導者たちが銃殺された。
この事件がアイルランド人の独立への意思を確固たるものにしたと言われている。
ウエザリーによる「ダニー・ボーイ」の作詞が発表された1913年は第一次世界大戦前夜。
復活祭蜂起のわずか三年前である。
当時のアイルランドでは
イギリスとの共存を希求するユニオニストと共和国独立を推進するナショナリスト双方が
それぞれの義勇軍を創設。
労働運動の高まりが独立運動と連動し
それにイギリス国教会を含むプロテスタントとカソリックの宗教的対立が複雑にからまり、
政治的にも社会的にも国内対立及びイングランドとの対立が先鋭化しつつあった。
他方イギリス議会においても、
グラッドストンの自由党は無論のこと、保守党でもアーサー・バルフォアなどのように、
アイルランド自治拡大の実現を認可すべきと考えていた政治勢力は少なくなかったようだ。
そんな中でイングランドの一弁護士であったウエザリーが
どのような想いでこの歌詞を書いたのかはとても興味深い。
「鑑賞室」へ戻る。
 To "Listening Room".
To "Listening Room".
トップ・ページへ戻る。
 Return to the TOP
Return to the TOP