皆さんは、3月に新宿三越であった、「不思議の国のアリス誕生の謎展」にいきましたか?
そこではアリス関係の展示と共に、アリスのパロディ・模倣出版を並べたコーナーがありました。そのなかに、「ごたごたの国のアドルフ」があったのです。チェンバレンのイモムシが世界地図を描いた茸をふまえてアドルフを威嚇している表紙しかそこでは見ることが出来ませんでした。
その後、やっと問題の原本を手に入れることができました。本来なら全訳を紹介すべきですが、私の語学力と時間的制約により、とりあえず面白そうな所を抄訳で紹介します。だんだんと後の箇所も訳していきますので、ご容赦下さい。
ごたごたの国のアドルフ
1・ユダヤの罠に落ちる
アドルフは、国会の中で、ヒンデンブルグに大統領令をおねだりするのが、とても退屈になってきました。おまけに、何もすることがないのです。一、二度、大統領の読んでいる憲法をのぞいてみたけれど、その本には、伝統もなければ誇りもありません。「へんなの」とアドルフは考えました。「指導者も軍備もないドイツなんて、何の役にもたちはしないわ」
そこでアドルフは心の中で、できるだけ考えようとしました――というのは、その日はとても暑かったので、眠くて頭がぼんやりしがちだったのです―ユダヤの商店を焼き討ちしたら面白いだろうけれど、外国の非難をかわしてそれをするだけの値打ちがあるだろうか?と、そのとき、一匹の眼鏡をかけた黄色い猿が、すぐそばを走っていきました。
それは、とくにおどろくほどのことではありませんでした。それにその猿―松岡―が「やれ、やれ、おそくなっちゃうぞ!バスに乗り遅れるな!」と独り言をいったのも、それほど不思議とは思いませんでした。(もっとも、あとでそのことを考えたときは、おかしいと思わなければならなかったのだ、アドルフはまだ三国同盟を持ちかけていないのだから、と思いましたが、そのときは、ごく普通のことのように感じたのです)けれども、松岡が、同志らしい猿を何人もつれて先を急ぐのを見たときには、さすがのアドルフも思わず立ち上がっていました。なぜといって、松岡が友達をつれているのは、まだ見たことがないのに気がついたからです。たちまち燃えるような好奇心にかられたアドルフは、猿を追いかけてはしりだし、ようやくのことで、松岡が、大きな穴に飛び込むところを見るのに間にあいました。
つぎの瞬間、アドルフもその穴にとびこんでいました。どうやってそこから出るということは、これっぽっちも考えていませんでした。
穴はしばらくのあいだ、互角のまままっすぐつづいていたのですが、とつぜんどーんと後ろから刺されたかと思ったとたん、がくんと落ち目になりました。それがあまり急だったので、止まろうと考えるひまもなく、アドルフは深い深いどん底へぐんぐんと落ちていきました。
穴がとても深かったのか、それとも落ち方がゆっくりだったのか、落ちていく途中でまわりを見まわしたり、これからどうなるのか考えたりする時間は十分ありました。まずどこまで落ちるのか下を見てたしかめようとしましたが、暗くてなにも見えません。つぎに井戸のまわりの壁を見ると、そこは戸棚や本棚でいっぱいでした。ところどころに、地図や絵が釘にかかっていました。アドルフは通りすぎながら、棚のひとつから壺をとりました。それには「マスタードガス」というラベルが貼ってあったのです。けれども、それは空っぽで、アドルフはがっかりしました。
「さあて」とアドルフは胸の中でいいました。「これだけ落ちるところまで落ちたんだから、今度は第一党から転がりおちたって平気だわ。党に戻ったら、みんなわたしが、すごく勇気があるってびっくりするだろうな! そうよ! たとえ銃殺刑になったって、ひとことも痛いなんていわないにきまってるわ!」(これは、たしかにそのとおりでしょう。銃殺されたのでは、口もきけません)
下へ―下へ―下へ。いったい、マルクの価値はどこまで下がるのか。「もう、どのくらい下落したのかしら?」と、アドルフは口に出していいました。「もうハンガリーのペンゴくらいになったのかしら? あそこじゃ、1該ペンゴ札というのが発行されたらしいわね」(アドルフは学校の授業で勉強したことをひけらかすのは、よい復習になると思って声にだしてみたのですが、じつはハンガリーのインフレは第二次大戦後のことで、アドルフの時代よりずっとあとのことでした。けれど、アドルフは、歴史がよくわかっていなかったのです)「1該ってのは、1京の一万倍で、1京は兆の一万倍で、兆は億の一万倍で、億は万の一万倍で、だから―1該って、いったい1ペンゴの何倍なのかしら?」(このように、アドルフは、計算もよくわかっていませんでした)
やがて、アドルフはまたしゃべりはじめました。「このまま落ちていくと、地球をつき抜けてしまうんじゃないかしら! 頭を下にして歩いている人たちのところに飛び出したら、おかしいだろうな!
2・涙のルール地方
「変てこりんなの、おかしいの!」と、アドルフは叫びました。「今度はマルクの価値がどんどんどんどん下がっていくわ。さよなら、1000マルク札!」(なぜかというと、とんでもないインフレのために、1万マルク以下の札は実質上使用不可能になったのです)「かわいそうなドイツの人たち!これからは誰がおまえたちにインフレに見合った給料をくれるのかしらね?社会民主党の政権じゃもうできないわ。これからは、自分で何とか考えなきゃね……でも、国防軍には、親切にしておかなきゃいけないわ」とアドルフは考えました。「でないと、政権獲得の時手伝ってくれなくなるわ!そうね……わたし、ウルグアイには、レームをプレゼントしよう」
アドルフは自分とおない年の子どもたちを一人一人思い出して、自分がそのうちのだれかに変わったのではないかと考えてみました。
「ゲッベルスじゃないことはたしかだわ」とアドルフは言いました。「ゲッベルスの脚はあんなに曲がっているけど、私は曲がってないもの。それに、レームでもあるはずないわ。だって、わたしは何でも知ってるけど、あの子は何にも知らないんだから!おまけに、レームはレームで、私はわたしだし……ああ、いやんなっちゃう!何もかもこんがらかってきたわ!わたしが前に覚えていたことを、いまも知ってるかどうか、ためしてみようかしら。ええと、1レンテンマルクは1兆マルクで、100レンテンマルクのパンは1兆の100倍で……あら、あら!桁があふれちゃったわ。地理をやってみよう。アルザスはドイツの領土である。ロレーヌもドイツの領土である。ラインラント全土もドイツの……だめだ、みんなまちがってるにきまってる!わたし、レームにかわっちゃったに違いないわ!そうだ、「すてきなホルスト・ヴェッセル」を暗唱してみよう」
ホルスト・ヴェッセルは 元気者
今日もナイフを 光らせて
ユダヤの血を ざあざあと
ベルリンの街で 流してるホルストは笑うよ 楽しげに
黒いブーツも 格好よく
にこにこ品よく 爆弾で
共産主義者を どかんどかん!
「確かにこの文句は事実と違うわ」とアドルフはうめきました。「わたし、レームになっちゃったんだわ。そして、あの汚らしい兵舎に住み、野蛮なSAと暮らし、男色もうんとしなきゃならないんだわ!いいえ、わたし、決心したわ。もしレームになっちゃったんなら、ずっと監獄にいることにするわ!みんなが外から、「さあ、出てらっしゃいよ!」といったってむだよ。外に向かって言ってやるわ。「それじゃ、ナチスを合法化してよ!そうじゃないとわたし、他の政権になるまでここにいるわ!」
3・狡猾レースと長い恨み
岸に集まってきたのは、まったくおかしな連中でした。びしょぬれのマントをまとった鳥たちや、重たい王冠を頭にくっつけたままの獣たちや――それが、みんなずぶぬれで、不機嫌そうな顔をして、いかにも心地悪そうにしているのです。
まず問題なのは、いうまでもなく、どうして王権を回復するかということでした。みんなでそのことを相談しましたが、数分のちにはアドルフは、ごく当たり前のようにみんなとうちとけて話をしていました。(たぶん鳥や獣たちは、アドルフを成り上がりの平民めと軽蔑していましたが)
とうとうしまいに、みんなの中でいちばん発言権を持っているように見える鼠が大声で言いました。「みんな、席について、私のいうことを聞いてくれ! 私がたちどころに諸君を再び王位につけてやろう!」みんなすぐに、鼠をまんなかにして輪になって座りました。アドルフは鼠を熱っぽい目つきで見つめました。王位がなくなってしまったら、世界は共産主義者に蹂躙されると思ったからです。
「えへん!」と鼠がもったいぶってはじめました。「よろしいか? これは私の知っているいちばん由緒正しい話です。『王権とは神により与えられたもの故、王は神にのみ責任を負う。人民の権利とは王権に従属すべきもの故、そは王権を侵すあたわず。すべて天上のものにつきては法王がしろしめし、地上につきては王がしろしめす。そは王権の根本原則にして――』さあ、どんなふうかね、あんた?」鼠はアドルフを振り向いてことばをつづけました。
「前とおなじびしょびしょよ」とアドルフは、さも憂鬱そうな口調で答えます。「皇帝はちっとも復位しないわ」
「それならば――」と、ドードー鳥がおごそかな口調でいいました。「私はこの会議を解散し、ただちにより効果的な方策を採用することを提案します」
「ラテン語でしゃべるな!」と、鷲の子はいいました。「そんな難しい言葉は半分もわからないぞ。それに、あんただって、わかってるとは思えないな!」そういうと、鷲の子はさっきと同じように斧で木を切りはじめました。
「私のいおうとしたのはだ」と、ドードーはむっとした口調でいい返します。「われわれが豊かになる最良の策は、昔やっていた植民地レースだということだ」
「植民地レースってなあに?」とアドルフはききました。べつだん、それほど知りたかったわけではないのですが、ドードーが、誰かが反対するはずだというように間を置いたのに、誰も反対しないようだからです。
「いや、やってみるのが何よりの説明になるんだ」とドードーはいいました。(みなさんも、いつかベトナムなどでやってみたいと思うかもしれないから、ドードーがどうやったかをここで説明しておきましょう)
ドードーはまず、レースのために十字架を大きく書きました。(布教の名目でやった方が、世間の通りがいいのだとドードーは言いました)そして、一同は後進国のあちこちに位置を定めました。「一、二、三、ゴー!」というような出発の合図もなく、みんな、好きなように非キリスト教徒を虐殺し、その国を略奪すればいいのです。だから、レースがいつ終わったか知るのは、必ずしもやさしくありません。とにかくみんなが三世紀も荒し回って、すっかり豊かになった頃に、ドードーがとつぜん「競争おわり!」と大声でどなりました。一同は輪になって集まると、はあはあ息を切らせながら聞きました。「でも、だれが勝ったんだ?」
この質問に、ドードーは、長いこと考えてからでなければ答えることができず、しばらく黙っていました。他のものも、黙り込んでまっていました。やがてドードーは口を開きました。
「正義が勝ったんだ。だから、みんな戦利品をもらわなきゃならない」
「でも、だれがその戦利品をくれるんだ?」とみんながいっせいにききました。
「そりゃ、もちろんこの子だよ」とドードーはいいながら、一本指でアドルフを指さしました。すると一同は、たちまちアドルフのまわりを取り囲みながら、大声で、「賠償金をくれ!領土を!」とわめきたてました。
アドルフはどうしていいかわからずに、必死でポケットに手をつっこみ、なけなしの領土やお金をみんなに渡しました。
つぎは植民地を消化することになりました。これは、ちょっとした騒ぎでした。大きな国からは小さすぎて何の意味もないと文句が出たし、小さな国は維持しきれずに手放さなければならなくなったのです。それでも、ともかく騒ぎが終わると、みんなはまた輪になって座り、鼠にもっと話をしてくれとせがみました。
「あなたは自分の身の上話をしてくれると約束したわ」とアドルフはいいました。「なぜあなたが――きの字としの字が嫌いになったか、その事情を教えてくれるって」名前を言えばまた怒り出すかと、おそるおそる、小さな声でいったのです。
「私の身の上話は長い悲しい話(テール)です」と鼠はアドルフに向き直り、ため息をつきながらいいました。
「もちろん長い両(テール)にはちがいないけど」と、アドルフは不思議そうにいいました。「でも、なんでルーブルでなくテールなの?」そして、鼠が話しているあいだ、ずっと、変だ変だと思いつづけていたので、アドルフには鼠の話が、こんなふうに聞こえていました。
こわいレーニンが
モスクワで
鼠に出くわし
言ったとさ
「ちょっと党本部へ
来てもらおう
お前に
階級的処分を
加えてやる
いいや、文句は
いわせない
どうでも裁判
しなけりゃ
ならぬ
なにしろ
白軍が不穏で
奪還されないかと
困ってるんだ」
鼠はレーニンに
言いました
「ソヴィエト政府に申し上げますが
判事も弁護士も
ない裁判なんて
やるだけ
無駄というもの
でしょう」
「ソヴィエトは一元的な
権力なのだ」
ずる賢いレーニンは
いいました。
「判事もわし
検事もわし
弁護はなし
どうでもおまえを
死刑にしてやる」
5・イギリスの忠告
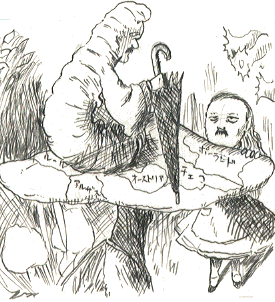 イモムシとアドルフとは、しばらくのあいだ黙ってお互い見つめあっていました。ややあってイモムシは、口から水ギセルをとり、だるそうな、眠そうな声でアドルフに話しかけました。
イモムシとアドルフとは、しばらくのあいだ黙ってお互い見つめあっていました。ややあってイモムシは、口から水ギセルをとり、だるそうな、眠そうな声でアドルフに話しかけました。
「おまえさんはだれだい?」と、イモムシがいいました。
これは、話のきっかけとしては、あまりいい兆しではありません。アドルフは、胸を張って答えました。「わたしはドイツ人であり、大ドイツ国家の理想を実現するため、神につかわされた者であります」
「それは侵略の言い訳か?」とイモムシが、言葉鋭く言いました。「はっきり分かるように説明しなさい!」
「このキノコはもともと、私のだったんです」とアドルフ。「おわかりでしょう、そのことは」
「わからんね」とイモムシは言います。
「おわかりになって然るべきかと存じます」とアドルフはますますていねいな言葉遣いで答えました。「同胞のドイツ住民がここで虐待されているのです。これを見過ごすことはできません」
「そんな事実はない」とイモムシ。
「いいえ、あなたはまだ知らないだけなのです」とアドルフ。「もし、あなたがわたしだったら、同じことをしたと思います」
「おまえだったらだと!」イモムシはさも軽蔑したように言いました。
アドルフはイモムシがあまりぶっきらぼうなので、少し腹が立ってきました。それで、きっとしてみせ、重々しい口調でいいました。「それでは、軍隊を送らねばなりませんね」
「なぜだ?」とイモムシが言いました。
これも、むずかしい問題でした。アドルフは、正当化するいい理由が思いつけなかったし、イモムシが恐ろしく不愉快そうに見えたので、くるりと身をひるがえすと、行ってしまおうとしました。
「もどってこい!」とイモムシが、アドルフを後ろから呼び止めました。「おまえに、大切な話がある!」
これは、かなりおもしろくなりそうでした。アドルフは振りかえって、戻っていきました。
「短気を起こすものではない」と、イモムシは言います。
「それだけなの?」アドルフは、こみ上げてくる癇癪を、精いっぱいに抑えながら言いました。
「ちがう」とイモムシ。
アドルフは待ってもいいだろう、と考えました。どうせすることはないのだし、それに、イモムシが妥協してくれれば軍隊を動かさずに領土が取れ、まる得になるからです。しばらくの間イモムシはタバコをぷかぷかふかして考え込んでいましたが、やがて腕組みをほどくと、口から水ギセルを取っていいました。「つまりドイツは、変わったというのだね?」
「そうじゃないかと思うのです」と、アドルフはいいました。「前にいたはずの皇帝がどこにもいないし、――それに、十年間も、同じ政権がないのですから!」
「どんなことが変わったのだ?」と、イモムシ。
「あのう……、わたし、『すてきなホルスト・ヴェッセル』を暗唱しようとしたのですけど、口に出すと、みんなちがった文句になるんです!」アドルフは、ひどく憂鬱そうな声でいいました。
「『ウィルソン父さん、年とった』をやってみろ」と、イモムシがいいました。
アドルフは両手を組んではじめました。
父さん、あんたももう年だ
髪も真っ白、それなのに
しょっちゅうヨーロッパ出かけてる
ちっとは年を考えなウィルソン父さん息子にいった
若い時分にゃ 身体に悪いと
思って大事をとってたが
車椅子暮らしになった今じゃ
何の心配あるもんか何度もいったが、年も年
おまけに国連提唱者
なのに意見が宙返り
いったい、それはなんのため?ウィルソン父さん、白髪頭ふって
地元じゃ議会が大騒ぎ
こっちじゃクレマンソーとロイドが騒ぐ
わしの試案はでんぐり返しさ父さん年だよ、身体も堅くなった
柔軟体操もできまいに
タコかと思うほどしなやかな身体
教えてくれよ、その秘訣世界によかれと思った案だが
財界は負債を返せとどなる
クレマンソーとロイドは賠償金ねだる
おかげですっかり骨抜きになった
「文句がちがっとる」とイモムシがいいました。
「少しちがってるでしょうね」とアドルフはおそるおそる「ことばがいくらか入れ替わってますね」
「始めから終わりまでちがっとる」と、イモムシは断言しました。また何分か、沈黙がつづきました。
先に口を開いたのはイモムシの方でした。「つまりおまえは、ズデーデン地方だけが欲しいと言うのだね?」
「そうだと思うのです」とアドルフ。「ドイツ人はドイツ国家に生きる権利があるし、それにわたし、植民地を作る趣味はないのです」
「いいや、全く申し分のない植民地だ!」
と、イモムシが怒ったようにいいながら、すっくと立ち上がりました。(イモムシの足元のキノコには、イモムシの植民地がいっぱいありました)
「でも、わたし植民地に馴れていないんですもの!」アドルフは哀れな口調で訴えました。そして、心の中で、「このじいさん、こんなに怒りっぽくなければいいのに!」と考えていました。
「そのうち馴れる」とイモムシは言って、水ギセルをくわえ、またぷかりぷかりやりだしました。一分か二分たつと、イモムシは口から水ギセルを取り、一、二度あくびをして、ぶるんと身震いしました。それから、キノコから降りて、ゆっくりと飛行機に乗り込みながら、行きがけに、
「東側なら許してやろう。西側は駄目だ」とだけいいました。
「東側って、何の?西ってなんの?」とアドルフはひとり考えました。
「キノコのだ」とイモムシは、まるでアドルフが声に出して聞いたみたいに答えました。そして、調印書を持って、飛行機で飛んで行ってしまいました。
アドルフはしばらくキノコを見つめて、どっちが東側か見定めようとしました。
「きっと、こっちが東だわ」とアドルフは考えました。「こっち側が赤くなっているもの」
*
「さあ、やっとヴェルサイユ条約から自由になったわ」とアドルフは嬉しそうにいいました。が、それも、一瞬のこと、手持ちの軍隊がどこにもないのに気づくと、たちまちおどろきの口調に変わってしまいました。
「あの緑色の旗はいったい何なのかしら?」とアドルフはいいました。「それに、あそこに住んでいた同胞はどこに行ってしまったのだろう?かわいそうなドイツ系住民、どうしておまえは圧迫されてるの?」アドルフは演説しながら手を振りましたが、はるか遠くの親衛隊がざわめくばかりで、まるきり何の反応もないみたいでした。
アドルフは首を、それまで自分の領土だったオーストリアの中に突っ込もうとしました。そのときです。いきなり、するどいひゅっという音がしたので、あわてて首を引っ込めました。一羽の大きな鳩が、アドルフの顔めがけて飛んできて、翼で乱暴に彼をたたいたのです。
「この植民地主義者め!」と、鳩は金切り声をあげました。
「わたし、植民地主義者じゃないわ」とアドルフは、腹を立てていいました。「ほっといてよ!」
「いいえ、植民地主義者よ。何度でもいうよ!」と鳩はくりかえしましたが、今度はおし殺したような口調でした。そして、泣き声になって、つけ加えました。「ありとあらゆることをやってみたんだ。それなのに、どうしてもうまくいかない!」
「何のことをいっているのか、さっぱりわからないわ」とアドルフ。
「国際連合にも頼ってみたし、イタリアにも庇護を求めた」と鳩はアドルフの言うことにはおかまいもせずにつづけました。「でも植民地主義者のやつは!まったく、あいつらは満足するということがないんだわ!」
アドルフはますますめんくらいましたが、鳩がしゃべり終わるまではそれ以上何をいっても無駄だと考えました。
「リンテレンを相手にするだけじゃ苦労が足りないというみたいに」と、鳩はさらにつづけます。
「夜も昼もなしに護国隊を動員しなきゃならないんだわ!」ええ、わたしゃもうここ三週間も、一睡もしていないんだ!」
「それはお困りでしょうね。同情するわ」とアドルフはいいました。ようやく、鳩のいう意味がわかってきたのです。
「そして、ようやく、社会民主党の赤色革命を封じ込めたと思ったら」と、鳩は金切り声をはりあげて続けました。「これでようやくロシアを心配せずにすむとおもったら、今度はドイツからにょろにょろおりてくるんだからね!ああ、植民地主義者ったら!」
「でも、わたしは植民地主義者じゃないんだってば!」とアドルフはいいました。「わたしはあの……わたしは……」
「ふん! さあおいい、あんたは何なの!」鳩がいいました。「いくら嘘をつこうったって、ちゃんとわかるんだから!」
「わたしは……わたしは民族主義者だわ」アドルフはなんとなくあやふやな口調でいいました。その日、何回も意見を変えたのを思い出したからでした。
「もっともらしいことをいって!」と鳩は腹の底から軽蔑した口調でいいました。
「あたしは、今までずいぶん民族主義者を見てきたけど、そんな変な言動の民族主義者なんて、一度もお目にかかったことがないわ!だめ、だめ、あんたは植民地主義者よ。いくらごまかしたって無駄だよ。そのうちには、領土なんて広げたこともないっていいだすんだろうけどね」
「もちろん、領土は広げたことあるわ」と、正直者のアドルフはいいました。「でも、民族主義者だって、植民地主義者と同じように、領土くらい広げるわよ」
「そうは思わないね」と鳩がいいます。「でももしそうなら、民族主義者だって植民地主義者の仲間ってことになるわ、あたしにいわせれば」
これは、アドルフにとっては、まったく初耳の考え方だったので、たっぷり一分か二分のあいだ黙って考え込みました。鳩はその間にまたしゃべるきっかけをつかみました。「あんたは領土を盗もうとしてるんだ。それぐらいわかっているわ。それさえわかれば、あんたが植民地主義者だろうと民族主義者だろうと、どっちでもいいんだ」
「わたしには、どっちでもよくはないわ」アドルフはあわてていいました。「でもとにかく、わたしは領土を探してたんじゃない。盗むにしたって、外国の領土はほしくないわ。ドイツ民族以外は嫌いだし」
「それじゃ行っちゃってよ!」と、鳩は巣に舞い下りて来ながら、ふくれっつらでいいました。
6・アカと陰謀
ドアをあけると、そこは国際共産主義陰謀団のアジトで、端から端まで陰謀だらけでした。公爵夫人は真ん中の3本脚の椅子に腰掛けて、赤ん坊をあやしていました。コックは火の上に身を乗り出して、各国に共産主義革命を起こす陰謀をこねまわしています。
 「この部屋には、ユダヤが多すぎるんだわ!」と、アドルフは一生懸命いいました。吐き気がして仕方がなかったのです。
「この部屋には、ユダヤが多すぎるんだわ!」と、アドルフは一生懸命いいました。吐き気がして仕方がなかったのです。
確かに、ユダヤは、この部屋に多すぎました。公爵夫人さえユダヤ人でした。そして社民党には、ユダヤ人が多数はいりこんでいるのです。料理女すらユダヤ人なのです。ユダヤ人でないのは部屋の隅でにやにや笑っている猫だけでした。
「おそれいりますが……」とアドルフは、おずおずと声をかけました。というのは、自分のほうから口をきくのが弱気のしるしと思われないか、自信がなかったのです。「あの猫は、どうしてあんなに笑っているのですか?」
「チェカーだからよ。だから笑うの。この豚!」
公爵夫人が最後の言葉をものすごい勢いで言ったので、アドルフは文字通り飛び上がりました。でもすぐに、その言葉は赤ん坊に言ったので、自分にではないことがわかったので、勇気をふるって、もう一度聞きました。
「わたし、チェカー猫が必ず笑うものだとは知りませんでした」
「あなたは秘密警察を知らないのです」と公爵夫人。「それは間違いありません」
アドルフは公爵夫人の言い方が気にくわなかったので、話題を変えたほうがいいなとおもいました。そのとき、コックが鍋を火からおろし、手の届くところにあるものを、手当たりしだいに公爵夫人と赤ん坊に向かって投げつけはじめたのです。まず敷石が飛んできました。続いて、火炎ビンや、手りゅう弾、ライフル弾などが雨のようにふってきます。公爵夫人は、平気な顔で、当たっても知らん顔をしています。赤ん坊は前から泣きわめいていたので、ぶつかっても痛かったのかどうか、とてもわかりませんでした。
「まあ、お願い、そんなことをしないで!」とアドルフは怖さのあまり飛び上がったりしゃがんだりしながら叫びました。
「世間の人がみんなよけいな妥協をしなければ」と、公爵夫人がしわがれたうなるような声でいいました。「世の中は、ずっと早く平等になるのに」
「それは世の中のためになりませんよ」とアドルフは言いました。自分の知識をちょっぴりひけらかす機会があったので、嬉しくなったのです。「だって考えてごらんなさい。そんなことをすれば、民族が劣化してしまいますわ!だって、劣等民族と優秀民族が交配すると、その二分の一は……」
「劣等といえば……」と、公爵夫人がいいました。「オットーを社民党の党首にしなさい!」
アドルフはコックを心配そうに見ました。本当に命令に従うか気になったのです。でもコックはせわしげに陰謀をこねまわしていて、聞いていないようだったので、アドルフは先を続けました。「二分の一だと思うけど……四分の一だったかしら……わたし……」
「うるさいよ!」と、公爵夫人は言いました。「私は数字にはだまされないんだから」そういって、また赤ん坊をあやしながら、子守歌らしいものを歌いだしました。そして、一節が終わるたびに、赤ん坊を乱暴にゆすぶるのです。
資本家、社長はどなりつけ
仕事をしたら ひっぱたけ
ひとが嫌がるのを知っていて
ゼネストやろうとするのだから合唱
(共産党と社会民主党が声をあわせて)
「ウラー! ウラー! ウラー!」
公爵夫人は、二番を歌いながら、社民党を乱暴に操ったり、放り出したりするので、可哀想に社民党は、激しく泣きわめき、そのためアドルフは、歌詞がほとんど聞きとれませんでした。
ファシスト達にゃ きびしくします
集会したら 殴り込み
暴力は いつでも革命の
最高の武器になるのだから合唱
「ウラー! ウラー! ウラー!」
「そら、お望みなら、すこしあやしてごらん!」公爵夫人は言うと、同時に社民党をアドルフに投げ出しました。「私は書記長様と中国革命の指導に行かなくちゃ」そして、さっさとアジトを出て行きました。
アドルフは赤ちゃんを危ないところで受けとめました。変な格好をした政党でみんながてんでに意見を言うので、とてもまとまりがないのです。「まるでヌエみたいだわ」
正しいあやし方がわかるとすぐに(それは右側を金でねじふせ、動けないように左側を突撃隊で押さえつけるのです)アドルフは赤ん坊を外へ連れ出しました。「もしわたしが赤ん坊をつれださなければ」とアドルフは考えました。「あの人達は赤ちゃんをすっかり洗脳して、どうしようもない劣等民族にしてしまうでしょう。とすれば、あそこに置き去りにするのは、人殺しみたいなものじゃなくって?」最後の言葉を口に出して言うと、赤ん坊はぶうぶうとうなって返事をしました。「ぶうぶういわないの」とアドルフはいいました、「そんなものの言い方はしちゃいけないのよ」
赤ん坊がまたぶうぶうとうなったので、アドルフはどうしたのだろうと思って、その顔を心配そうにのぞきこみました。するとー疑う余地はありません。赤んぼうは、ほんものの鼻より、ずっとユダヤの鼻に似た、ひどい鍵っ鼻をしていました。おまけに、その髪は、ゲルマンにしてはあまりにも黒すぎます。そんなこんなで、アドルフは、この赤んぼうの顔つきが気に入りませんでした。「もしこのままユダヤみたいになっちゃうなら」と、アドルフは真剣な顔でいいました。「もうわたし、あなたをドイツ人と認めないからね、わかった!」
アドルフは心の中で考えはじめました。「ところで、選挙になったら、この子をどうしたらいいかしら? おだてて支持を求めるか、それとも弾圧するか?」ちょうどそのとき赤んぼうがまた、すごくはげしくうなったので、はっとして顔をのぞきこみました。今度こそいよいよ疑いようもありませんでした−それは正真正銘のユダヤでした。アドルフは、これ以上こんなものを相手にするのはあんまりばかげている、と思いました。
そこでユダヤを地面に降ろすと、それはとことこ、静かにゲットーに入っていきます。アドルフは心からほっとしました。「ゲルマン民族として育ったら」とアドルフはひとりごとをいいました。「きっと、すごくおばかさんだったと思うわ。でも奴隷人種としてはなかなか役立つと思うわ」そして、自分の知っているほかの政治家で、奴隷になったほうがいいかもしれないもののことを考えたとき、チェカー猫が、ほんの二、三メートル先の木の枝にすわっているのを見つけて、ぎょっとしました。
猫はアドルフを見てにやりと笑っただけでした。性質のよさそうな猫に見えました。でも、すごくよくきく耳と、ものすごくたくさんのスパイをかかえているので、ちゃんと敬意を表したほうがいい、と考えました。
「ねえ、教えてくださらない、ここからどっちへ行ったらいいのかしら」
「それは、あんたがどこへ行きたいかによって違うさ」と猫がいいました。
「満州のほうには」と猫は右脚をふりまわして、「日蓮屋が住んでいる。それから日本のほうでは」といっても、もう一方の脚をふり、「松岡猿が住んでいる。どっちでもたずねてごらん。両方とも気違いだから」
「でも、わたし、気違いのところなんて行きたくないわ」と、アドルフはいいました。
「だってそれはしかたがないさ」と猫はいいました。「ここに住んでいるものはみんな気違いなんだから。俺も気違いだし、あんたも気違いさ」
「どうして、わたしが気違いなんていうんです?」と、アドルフがいいました。
「そうにきまってるさ」と猫。「でなきゃ、ここへ来たりしなかったろうからな」
アドルフは、そんな理屈はぜんぜんないと思いましたが、言葉をつづけました。「それじゃあなたが気違いだというのはどうしてわかるんですか?」
「まず第一にだ」と猫がいいました。「イギリスは気違いじゃない。これは認めるかい?」
「条件によってはね」とアドルフ。
「イギリスでは貴族は尊敬され、労働者は見下されるんだ。ところが、俺のとこでは貴族は首を切られ、労働者は尊敬されるんだ。だから、おれは気違いなんだ」
「それはたてまえだけで、尊敬されていないでしょう」と、アドルフはいいました。
「何とでもいうさ」と猫。「今日、書記長様とクローケーをやるかい?」
「それは、とってもしたいと思いますけど」とアドルフ。「でもわたし、まだご招待を受けていないんです」
「じゃ、そこで会おう」と猫はいって、消えてしまいました。
これには、アドルフはたいして驚きませんでした。チェカーだからゆくえをくらますのは得意だと思ったからです。アドルフが、今まで猫がいたところをながめていると、猫は突然また姿をあらわしました。
「ところで、あの赤ん坊はどうなった?」と猫がききました。「きくのを忘れるところだった」
「アカになってしまいました」とアドルフは、猫が普通の帰ってきかたをしたように、落ち着いていいました。
「そうだろうと思った」と猫はいって、また消えました。
アドルフは、猫がまた戻ってこないかと待っていましたが、もう現れませんでした。一分か二分して、日蓮屋が住んでるといわれた方角に歩きだしました。「松岡には会ったことあるけど」とアドルフはひとりごとをいいました。「日蓮屋のほうが面白そうだし、それに二・二六事件で上官をどなったくらいだから、松岡ほど狂ってはいないでしょう」こういってふと見上げると、れいの猫がまた現れて座っていました。
「さっきはアカといったのかい、それとも馬鹿といったのかい?」と猫はいいました。
「両方です」とアドルフは言いました。
7・気違い事変
 中国の中に租界がおいてあって、松岡猿と日蓮屋とが、お茶を飲んでいました。そのあいだにヤマネ(眠れる虎ともいう)がすわっていて、ぐっすり眠り込んでいました。ほかの二人はそのヤマネをクッションがわりにして、その身体を削り取ったり、頭越しに話をしていました。「ヤマネはずいぶんきゅうくつだろうな」とアドルフは思いました。「でも、ああして眠っているんだから、気にならないのかな」
中国の中に租界がおいてあって、松岡猿と日蓮屋とが、お茶を飲んでいました。そのあいだにヤマネ(眠れる虎ともいう)がすわっていて、ぐっすり眠り込んでいました。ほかの二人はそのヤマネをクッションがわりにして、その身体を削り取ったり、頭越しに話をしていました。「ヤマネはずいぶんきゅうくつだろうな」とアドルフは思いました。「でも、ああして眠っているんだから、気にならないのかな」
大きな大陸だったのに、三人は奉天あたりにごちゃごちゃとかたまっていました。アドルフが来たのを見ると、「領土はないよ! 領土はないよ!」と叫びました。
「いくらでもあるじゃないの」アドルフはむっとしていうと、大陸の一方の端にあったひじ掛け椅子に座りました。
「青島は要るかね?」と、松岡猿が、いかにもすすめたそうな顔でいいました。
アドルフは中国をぐるりと見渡しましたが、青島はとうに中国領でなくなっていました。「青島なんかないじゃない?」と、いいました。
「そんなものはないさ」と、松岡猿がいいました。
「ないものをすすめるなんて、ずいぶん礼儀知らずじゃないの」と、アドルフはむっとした口調でいいました。
「招待もされないのに、出兵するなんて、ずいぶん礼儀知らずじゃないか」と松岡猿がいいました。
「あなたの権益だとは知らなかったわ」とアドルフ。「三人にしては、ずいぶん広い領土じゃない」
「あんたの侵攻先は変えなきゃならんな」と日蓮屋はいいました。日蓮屋は、長いこと、非常な好奇心をこめてアドルフを見ていましたが、これが、はじめていった言葉でした。「でないと、最終戦争に参加できないぞ」
「人のことはとやかくいわないものよ」とアドルフは手きびしくいいました。「それより、あなたの跳ねっかえりの部下をなんとかしたら?」
日蓮屋はこれを聞くと大きく目を見はりました。でも、ただ、「海軍が軟弱になったのはなぜか?」といっただけでした。
「さあ、おもしろくなってきそうよ!」と、アドルフは考えました。「なぞなぞを始めたのはうれしいわ――その問題なら、私にも答えられそうだわ」アドルフは、声に出していいました。
「つまり、これを解決できるというのかね?」
「そのとおりよ」とアドルフ。
「それじゃ、言ってみるんだな」と松岡猿がつづけます。
「いうわよ」とアドルフは急いで答えました。「少なくとも……少なくとも私は考えてるとおりのことをいうのよ……それは元からでしょう」
「もとからじゃない!」と、日蓮屋はいいました。「それじゃなにかい、あんたは、東郷平八郎と岡田啓介を同じだというのかい?」
「おまえさんは……」と、松岡猿が、横からいいました。「末次信正と米内光政とが、おんなじだというのかい?」
「あんたはこういうのかい?」とヤマネが、寝言のようにいいました。「張学良と、汪兆銘がおなじだと?」
「おまえにとっちゃおなじことさ」と日蓮屋が言いました。そこで、交渉はとぎれ、一同は一分ほどだまりこみました。そのあいだアドルフは海軍の抵抗をかわす方法について、いろんなことを思い出そうとしましたが、たいしたことは思い出せませんでした。
日蓮屋が、最初に沈黙を破りました。「今は何年だい?」と、アドルフにむかっていったのです。彼はポケットから暦を取り出して、心配そうにながめ、ときどき振ってみたりしました。
アドルフはちょっと考えていいました。「1932年よ」
「5年くるってる!」といって、日蓮屋がため息をつきました。「だから、陛下に退位願って、高松宮に起っていただけといったんだ!」彼は、松岡猿を怒ったように見やりながらつけくわえました。
「いちばん優秀な戦力だったんだ」と松岡猿がおとなしく答えました。
「ああ、だけど、きっと宇垣が逃げたにちがいない」と日蓮屋がこぼしました。「岡山県人を入れたのがいけないんだよ」
松岡猿は暦を手にとって、陰気な顔でながめました。そして、自分のお茶のカップにじゃぼんとつけ、またながめました。しかしけっきょく、最初の言葉をくりかえすしかありませんでした。「あれは優秀な兵士だったんだがなあ」
アドルフは松岡猿の頭越しに、それを珍しそうにながめていました。「なんておかしな暦なの!」といいました。「これ、明治、大正、昭和って並んで、天皇の在位で年数を計っているけど、西暦で何年かわかりにくいじゃない!」
「なぜそれがいけないんだい?」と日蓮屋がつぶやくようにいいました。「あんたの暦は、人間を起点にしてないのかい?」
「もちろん、しているわ」とアドルフは待ってましたとばかりいいました。「でもわたしは、イエスという神様を起点に数えてるのよ」
「それなら、ぼくの場合もそうだ」と日蓮屋はいいました。
アドルフはひどく面くらいました。日蓮屋のことばは、まるで意味がないように聞こえたのです。けれども、それはちゃんとした論理に違いありません。
8・書記長のクローケー・グラウンド
お庭の入り口近くに、大きな農場がありました。その農場は白いのでしたが、それを、三人の人民委員が、せわしげに赤く塗っているのです。畑も、家も、農奴も、家畜も、みんな赤く塗っているのを、アドルフはおかしなことをするものだと思いながら、近くによって三人のすることを見守りました。ちょうど庭師たちのところへ来たとき、その一人がこんなことを言っているのが耳に入りました。「おい、気をつけろ、五! 輸送が貧弱なせいで、キャベツが全部途中で腐っちゃったじゃないか!」
「しかたないんだ」と、五がふくれっつらでいいました。「七が鉄をまわしてくれないんで、レールを増設できないんだ」
これを聞いて、七が顔を上げました。「鉄鉱石が少なすぎるし、それもほとんどは兵器製造に取られるのに、鉄道にまわす鉄があるもんか。二が鉄鉱石をくれないのが悪いんだ」
二は言い出しっぺの自分にお鉢がまわってきたので、びっくりしながらわめきました。「鉱山の人手不足を知らないのか! 囚人はぜんぶ兵隊にとられるもんで、だれもいなくなっちゃったんだ!」
「おまえ、しゃべらないほうが身のためだぜ」と、五がいいました。「きのう、女王様が、お前は銃殺されるだけのことはした、といったのを聞いたんだよ」
「なんて罪でだ?」と、七はいいました。
「お前の知ったことじゃないよ!」と二はいいました。
「いいや、あいつにも関係はあるさ」と、五がいいます。「聞かせてやろう――こいつは、革命のとき赤軍を指導していたのはスターリンじゃなく、トロツキーだなんていいやがったんだ」
二がはけをほうりだして、「いくらなんでもそんなひどいことを――」と言いかけたとき、彼の目は偶然そちらを見ているアドルフの上に落ち、きゅうに黙り込みました。ほかのものも、あたりを見回し、みんな、ひくく頭を下げました。
「すみませんが、教えていただけませんか」とアドルフが、ちょっとおずおずしながら、いいました。「あなたたちは、なぜこの農場にペンキを塗っているんですか?」
五と七はなにもいわずに、二をみつめました。二は低い声でいいました。「なに、それはね、実際のところ、ここにはコルホーズを建設していなきゃならなかったんだが、おれたちがレーニンの教えどおりクラークを連れてきてしまったんだ。それで、もし女王様に見つかったら、おれたちみんな銃殺されなきゃならないんだ。だから、一生懸命、女王様のいらっしゃる前に――」ここまでいったとき、庭の向こうを心配そうに見渡していた五が、「女王様だ! 女王様だぞ!」と叫びました。同時に三人の人民委員は、うつぶせになって、地面にはいつくばりました。そこへ、大勢の足音がしました。アドルフは女王様を見ようと、くるりと振り返りました。
最初に十人のハンマーを持った兵士がやってきました。次は十人の廷臣です。この廷臣たちの多くは、三人の人民委員と同じ、ユダヤ系で鉤鼻をしていて、鼻眼鏡をかけているのでした。鎌を持って、兵士と同じように、二人ずつ並んでいました。そのあとからは、女王様の子供たちがやってきました。ひとりは可愛い女の子でしたが、男の子のひとりは飲んだくれで、ひとりは捕虜になっていました。そのつぎにはお客さんたち――たいていは西欧の外交官でしたが、その中にアドルフは松岡猿がいるのを見つけました。松岡は早口の独断的な口調でしゃべっていて、アドルフには気づかぬふりで歩いていきました。そのあとに、ハートのキーロフが、女王様がパイプを持って微笑んでいる肖像画を掲げてつづいていました。そのあとに、女王様と王様がやってきました。
アドルフは、自分も人民委員のように地面に這いつくばって頭を下げるべきかどうかといくらか迷いましたが、共産主義にそんな規則があるなんて、聞いた覚えがありませんでした。「おまけに、それじゃせっかくのパレードが台無しになるわ」とアドルフは考えました。「みんなが平伏していて、パレードを見れないんじゃ」そこでアドルフは立ったままでいました。
パレードがアドルフの前にさしかかると、みんな立ち止まってアドルフを見ました。女王が、きびしい声で、「何者か?」といいました。女王様はハートのキーロフに向かっていわれたのですが、キーロフはただ頭を下げ、微笑みでこたえただけでした。
「西欧かぶれめが!」と女王はいって、じれったそうに髭をしごきました。そして、アドルフに向き直ると、ことばをつづけました。「そちの名は何という?」
「恐れながら閣下、わたくしめはアドルフにございます」とアドルフはうやうやしくいいましたが、心の中では、「なによ、たかが奴隷民族じゃないの。こわがることなんかないんだわ!」と思っていました。
「して、あの者たちは何者か?」と女王は、農場で平伏している三人の人民委員のほうを指さしていいました。というのも、顔を伏せて這いつくばっていると、この国民はほぼ例外なく飢えてやせこけているので、女王には、兵士だか元貴族だか、農奴だか富農だか、ぜんぜん見分けがつかなかったのです。
「そんなこと、知りません」アドルフは、自分の勇気にびっくりしながらも、いいました。「他の国家の内政に干渉する気はありませんから」
女王はたちまち真っ赤になって怒りだしました。というのも女王は、他の国の内政に干渉したり、よその国の共産主義者に指令を飛ばして組織を壊滅させることが、なによりも好きでしたから。「この者を人民裁判に! 強制収容所へ!」と金切り声で叫びました。
「ばかいうもんじゃないわ!」アドルフが、すごい声できっぱりというと、女王はぴたりと黙りました。
王様が、書記長の腕にふるえる手をかけようとしながら、まわらぬ舌でいっしょうけんめいに言いました。「寛容にするがよい。革命はまだ子どもなのだ!」
女王様は腹立たしげに王様を突き飛ばすと、キーロフの方を向いていいました。「レニングラードの組織をひっくり返せ!」
キーロフは片足で、用心深くそうしました。「被告席に立て!」と女王がするどい声で命ずると、たちまち容疑も罪状も証人も検事も裁判官もみんなそろい、あとは三人の人民委員に死刑を宣告すればいいだけになりました。
「おまえたちは、ここで何をしていたのじゃ?」女王がきびしい声で言うと、三人の人民委員はぺこぺこしながらあわれっぽい声でいいました。「恐れながら、女王様、わたくしどもは、革命のために、誠心をこめて……」
「よし、わかったぞ」それまでに農場を調べた女王はいいました。「この者どもは反革命トロツキストとして銃殺じゃ!」そして、パレードは進んでいきました。秘密警察が三人、かわいそうな人民委員を銃殺するために残りました。人民委員は、アドルフのところへ走っていって、助けてくれと頼みました。
「あなたたちを殺させはしないわ」アドルフはそういうと、三人を国外へ逃がそうとしました。しかし秘密警察の方が早く、人民委員のふたりは銃殺されてしまいました。のこりのひとりはメキシコまで逃げたのですが、そこで殺されてしまいました。
「反革命分子は根絶したか?」と、女王が叫びました。
「革命もろとも殲滅しました!」と、秘密警察が、叫び返しました。
「よろしい!」と女王は叫びました。
10・東欧のマルクス・ダンス
「あんたは東欧であまり暮らしたことはないだろう」(「ないわ」とアドルフは嘘をつきました)
「それに、たぶん共産主義も紹介されたことがないだろうな」(アドルフはまた口を開いて、『いちど殺したことは――』といおうとして、あわてて口をおさえ、『ないわ、もちろん』といいました)
「だから、あんたは、東欧のマルクス・ダンスがどんなにすばらしいものか、ぜんぜん分からないんだ!」
「そりゃ、わからないわ」とアドルフ。「それ、どんなダンスなの?」
「そりゃあんた」とグリフォンがいいました。「まず、国境にそって第三インターが並んで――」
「第二インターだよ」と、亀まがいがいいました。「スラブ人はじめ、グルジア人、アルメニア人、そのほかいろんな連中でね。それで、じゃまなコサックの連中をすっかりどけてしまうと――」
「ところが、いつもそれに、えらく時間がかかるんだ」と、グリフォンが口をはさみました。
「――まず二歩前に――」
「それぞれ、政治将校をパートナーにしてな!」と、グリフォンが叫びます。
「もちろんだよ」と、亀まがいがいいました。「一歩進んで、二歩後退して――」
「それから、つまり」と亀まがいがあとをつづけて「ほうりだされるんだ、あの――」
「収容所にさ!」グリフォンが大声で叫ぶと空中に飛びあがりました。
「――シベリアの、できるだけ奥地にほうって――」
「あとから秘密警察がおいかけるんだ!」とグリフォンが金切り声をあげました。
「シベリアで秘密裏に粛清!」と、亀まがいがめちゃめちゃにはねまわりながら叫びました。
「も一度政権をとりかえて!」と、グリフォンがせいいっぱいの声でわめきます。
「またモスクワに戻って――そして、ここまでが一区切りだよ。これで第二インターが第三インターになるんだ」亀まがいがきゅうに声を落としていいました。それまで狂ったようにとんだりはねたりしていた二匹は、またひどくおとなしく、悲しげにそこにすわりこんで、アドルフを見ました。
「さぞ、素敵なダンスなんでしょうね」とアドルフはおずおずといいました。
「ちょっとばかし、見てみるかい?」と亀まがいがいいました。
「それは、とっても見たいけど」とアドルフ。
「よし、一番だけやってみようや!」と、亀まがいが、グリフォンに向かっていいました。
「モスクワからの指令がなくても、やればやれるよ。どっちが歌う?」
「そりゃ、あんたが歌えよ」とグリフォン。「俺は歌を忘れちまった」
こうして、二匹は、しぐさもおごそかにアドルフのまわりをぐるぐる回りながら踊りはじめましたが、しょっちゅう、アドルフに近寄りすぎて、そのたびにナイフで攻撃されました。二匹は前足を振って拍子をとり、亀まがいは、つぎのような歌を、さも悲しげに、ゆっくりとした調子で歌いました。
チェコがオーストリアにいいました
「もすこし早く歩いてくれよ
ハンガリーが後ろから攻めてきて
領土をとるんで困ってるんだ
見てみろ、リトアニアやラトビアは
みんな真面目に共産化してるじゃないか
みんなモスクワで待ってるよ
あんたもどうだい、なかま入り?
来るか、来ないか、共産化?
来るか、来ないか、共産化?
そのすばらしさといったらば
とても想像できないよ
つかまえられて反動分子もろともに
はるかシベリアへざんぶりと
放り込まれるおそろしさ!」
けれどもオーストリアはいいました
「とっても、民意が遠すぎる」
そして横目でチェコを見て
ご親切はうれしいけれど
共産主義はけっこうといいました
行かない、行かない、共産化
やらない、できない、共産化
「民意なんかいいじゃないか」
コミンテルンがいいました
「むこう側には、理想社会が
ちゃんと待ってる理屈じゃないか
ベルリン遠く離れれば
モスクワそれだけ近くなる
褐色になることあるものか
どうだい、あんたもなかま入り?
来るか、来ないか、共産化?
来なけりゃ、攻めるぞ、共産化!」
「ありがとう、ほんとうに面白いダンスね」とアドルフはいいました。じつは、ようやく終わってくれたので、心の中でほっとしていたのです。
12・アドルフの証言
「だれがあんたたちのことなんか気にするもんですか」とアドルフは言いました。(そのときにはもう、もとの大きさに戻っていたのです)「あんたたちなんか、ただの帝国主義者じゃないの!」
そう言ったとたん、政治家たちは、いっせいに空にまいあがり、アドルフめがけてひらひらと落ちてきました。アドルフは怖いのと腹が立つのとで、小さな悲鳴をあげ、政治家を払いのけようとしました。
そして……大統領の膝に頭をのせて寝ていた自分に気がつきました。
「起きなさい、アドルフ!」大統領は言いました。「本当に、よく眠ったわねえ!」
「ああ、わたし、とってもおかしな夢を見たわ!」アドルフはそう言って、大統領に、思い出せるだけせいいっぱい、いまあなたがたが読んだ、彼女の不思議な冒険の話をして聞かせたのです。
アドルフが話し終わると、大統領はアドルフにキスしていいました。「ほんとに不思議な夢だったわね、でももうクルップの夜会にいきなさい、もうおそくなっているわ」
そこでアドルフは立ち上がり、駆け出しましたが、駆けながらも、なんて不思議な夢だったのかしらと思っていました。そう思っても、たしかにもっともでした。
最後に、大統領は、この小さなアドルフが、やがていつの日にか、一人前の指導者になったところを想像してみました。アドルフは、だんだん成熟していき、やがて自分の後を継ぐでしょうが、それでも理想や情熱を失わず、他の国の政治家を集めては、いろいろ不思議なお話をしてーおそらくは、はるか昔の不思議な国のおかしな政治家たちのお話もしてやって、各国の目を開かせるだろう。そして、あのおかしな政治家達が陥った過ちに学び、国々の素朴な苦しみをよくわかってやり、国々の素朴な喜びに共に喜びを見いだし、ドイツに千年王国を、世界に新秩序を創り出す指導者となっていくだろう……ヒンデンブルグは、そんなことを空想したのでした。