


|
 |
 星の町]:相原君の仙台通信(2000-10-20掲載)
星の町]:相原君の仙台通信(2000-10-20掲載)
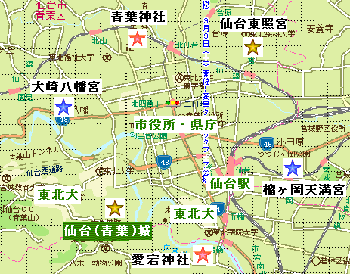
結ぶと星型になることに
気が付いた地元の
歴史研究家は、
仙台の町並みはかって星型
に整備されたのではないかと推測している。
六つの神社とは、 〈仙台城本丸〉とそれから
時計回りに 〈大崎八幡宮、〈青葉神社〉、
〈仙台東照宮〉、〈榴ケ岡天満宮〉、
〈愛宕神社〉
星の中心は国分町と定禅寺通の交差点で、
当時の城下町はこの六角の星にすっぽりと収まるのである。
(注:相原君の文により市内おおよその地点に★印をつけてみました。一寸ごちゃごちゃ過ぎましたね)
◆ これらの神社は城下から西へ抜ける作並街道や北へ抜ける七北街道などの主要道路を見渡せる高台
に造られており,政宗はこれらの 神社を有事の際の軍事上の拠点にするつもりであったのかもしれない。
◆そして、東北の方位には徳川家康の分霊を祭る仙台東照宮があるが、政宗は徳川を快く思って
いなかった のかもしれないと推測している。
それは、東北の方位は、「鬼門」と呼ばれ忌み嫌われていたからである。
京都の御所では、その東北の方位に延暦寺を建て「鬼門封じ」をするそのような風習があったことからも
類推できるというのである。
◆ところで、以上の新聞記事を呼んで「呼称と、方位としての東北の関連」が気になり、
私なりに調べてみた。
いにしえには、東北の呼び名は「みちのく」「みちのおく(道の奥)」で、「東北」ではなかった。
そしてここでいう「道」とは「国」を意味し「国の奥」すなわち「国の外・異国」を意味しており、
「みちのく」とは国内の地域を意味するものではなかった。
◆ 一方東北の呼称は、薩長政府の参与木戸孝允が、戊辰戦争での勝利を確信した後につけたもので、
「東夷北荻」をつづめたものといわれている。
なお、「西南の役」の西南という表現も、政府の「西戎南蛮」からの敗者に対する押し付けであると
考えられている。このように、方位の東北は古くから伝わったものであるが、地域の呼称である東北は
明治の始めに現れたものであり、「呼称東北」と鬼門である「方位東北」との間には、直接的関連は
無いものと私は思うのである。