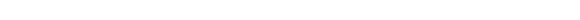常陸国風土記(ひたちのくにふどき)
常陸国風土記には、次のような記述が残されています。
平津(ひらつ)の駅屋(うまや)の西12里に岡あり。名を大櫛(おおくし)という。上古(いにしえ)人あり。体は究めて長大(たけたか)く、身は丘壟(おか)の上に居ながら、手は海浜の蜃(うむぎ)を摎(くじ)りぬ。その食(くら)いし貝、積聚(つも)りて岡と成りき、時の人、大朽(おおくち)の義を取りて、今は大櫛の岡という。その践(ふみ)し跡は、長さ40余歩、広さ20余歩なり、尿(ゆまり)の穴の径は、20余歩許なり。
古代、今の水戸市平戸町に、「平津の駅屋」があり、そこから見て西の方1,2里のあたりに岡がある、ここを 「大櫛」という。大昔、巨人がおり、岡の上にいながら手をのばして海浜の大蛤をほじくり出して取った。その巨人が取って食べた貝が積って岡となっている。このため、貝が「大朽」の意味から今は「大櫛の岡」というのである。また、巨人の踏んだ足跡は、長さ72メートル、広さ36メートル、小便のたまった穴の径は約36メートルもある。
風土記のふるさとパンフレット記載によるものです
トップ