『閉塞なんかブチ破れ!! 〜岡崎京子論』
I.はじめに
5年前、『リバーズ・エッジ』を読んで、主人公ハルナに対し、強く自分と同質のものを感じた。以後、岡崎作品を読みあさり、「同じもの」の正体を考えている。
その後作者は事故に遭い、現在闘病中である。読者として今の仕事は、作者がたどってきた道筋を追い、めざしていたものを探し求めることだと思っている。
まだ結論は遠いが、さし当たり現在まで気がついたものをまとめてみる。
II.作品の特徴
まず全体を眺める前に、作品の特徴と、作家としての姿勢について少し述べてみたい。
1.作画の軽視
作者の特徴としてまず挙げられるのが、作画のテキトーさである。トーンはずれているし、枠線もはみ出ている。ゴム掛けが不十分で、キメの絵でも線は伸びがなくへなへなであり、コマ割りも凡庸である。トーンはわざとずらしているのだが、それ以外は手抜きとしか言いようがない。デッサンも、上手くなろうという気配は微塵も見られない。
作画だけではなく、考証もいいかげんである。ドアのノブがコマによって反対についていたり、時計の時間があっていなかったりしていても、無頓着である。さらに時々資料なしで描いてしまう、登場人物の設定に矛盾がある、北海道でこたつを使っているなど、数え上げればきりがない。
これは、几帳面に描かなくてもOKという作者の姿勢によるものである。元々おおざっぱな性格と思われる作者は、そういう普通のマンガの作法とされている所を全部すっ飛ばすことで、初めてのびのびと自分のペースで描けるようだ。絵の巧さでの勝負をすっぱりあきらめている。作者にとって、絵は下手でいいもの、記号でしかない。手段は選ばないという、その腹のくくり方は見事に岡崎さんらしい。
2.テーマ性の重視
作画の軽視は、極端なほどのストーリー重視、内容偏重と対になっている。それがもう一つの特徴、テーマ性の強さである。最も作者の作品が読者を惹きつけるところである。
また、構成の特徴として、キャラクターの役割が露骨なことも挙げられる。そのキャラクターがあらわしているもの、担っている問題がはっきりしていて、作品自体をわかりやすくしている。
短編の多さも特徴的である。少しずつ違った視点で繰り返し描くことで、その時の作者のテーマをいろいろな角度から掘り下げているようである。複数の作品を関連づけて描くのも、同じ理由からと思われる。
常に時代の少し先をめざす、ということも言っている(1)。時代性も必要条件らしい。過去を描いた作品でも、それは現在を参照するために描かれている。作者にとっては常に「いま、ここで」が全てなのだろう。
ただし作品と作者は厳密には別物である。これは全ての創作に共通して言えることである。その差異を念頭に置きながら、考察を進めていく。
III.テーマの変遷
岡崎氏の作品は、年代によっていくつかに分けられる。まずそこから見てみたい。
年表も参考にして下さい。
1.第1期/半径5mの世界(1982-1988)
この時期は自分の身の回りのこと、自分の感性を、あたかも本能のおもむくままに描き散らしていた。日常の内部で、目標はまだ絞られることなく、ただ突っ走っていた。
セックスへの強い関心は持続して認められる。この時期に描かれるセックスは、まだそれほど深刻ではない。
2.第2期/家族(1989-1991)
1989年に大きな転換点を迎える。『pink』から内省・言語化へと向かうのである。それまでと違い、外から自分の作品を見る視点を獲得している。
この意味で、『pink』はエポックメイキングな作品と言えよう。
内面に目を向けた結果、80年代の少女マンガで多用された内言の増加が認められる。
この変化のきっかけは判らないが、1990年の結婚が関わっていると推測している。
それまでも作品の中には家族のテーマが繰り返し出てくる。作品に描かれる家族はどこかに欠落があり、離婚、崩壊、疎外、関係の希薄、父親の不在などとして描かれる。これらは、家庭の中に居場所がないということの表現と言えよう。
作者は血のつながりのある家族の中に、どこか居心地の悪さを感じていた(『ハッピイ・ハウス』の後書きより)。作者にとって家族とは親密であっても決してどこかそぐわないものだったようである。それが結婚という、契約による新しい家族を手に入れることで、新しい家族像を必要としたのかもしれない。結婚によって、自分の居場所を見つけたのかも知れない。
その意味で、『ROCK』『ハッピイ・ハウス』は新しい家族像の模索と見ることができる。「妹」と「ぬいぐるみ」の出現は、「家族」への関心の高まりと言えよう。また、母への愛着のテーマも見られる。
3.第3期/過去への決別(1990-1992)
その後『東京ガールズブラボー』で過去のふりかえりと再編を行っている。この作品は『くちびるから散弾銃』の3人の主人公の高校時代の話だが、テーマの流れとしては続編である。
作者はいくつかの作品のあとがきで「大人になりたくなかった」と語っており、大人としての自己像を保留してきた。『くちびるから散弾銃』も、そういう大人になり切れていない3人の話である。しかし『東京〜』では、ラスト近くで主人公の一人の夏美に「いつまでもいつまでもこうしていたいな」と言わせている。このせりふはこの作品の中で最も印象深く、この作品はこの言葉に集束すると考えられる。この言葉で作者は、自分の「子供時代」を距離をおいて眺めるに至る。
こうして作者は、自分の子供時代への決別を宣言し、楽園の喪失を認めるに至る。
ただし実際の作者の高校生活は、そんなに楽しかったわけではないらしい(1)。作品の中ではやりたいことをしきれないうちに北海道へ帰ったサカエが作者の実感であろう。あとがきでもサカエが最も作者の自己像に近いと言っている。
4.第4期/模索と掘り下げ(1990-1994)
第3期と重なって、作品づくりとテーマの模索の時期に入る。この頃作者はいろいろなことを試みながら、少しずつテーマを深めている。
a.作話法の模索
まず、他者との共作である。それまでも作者の活動範囲はマンガ以外にも広かったが、この時期には特に他者との共同作業を意識していたようだ。SF作家大原まり子との『マジック・ポイント』、しりあがり寿との共作、小説などへのイラスト、対談を数多くこなしている。
また、読み換えの試みもよく見られる。萩尾望都の『ポーの一族』の読み換えである『VAMPS』、原作ものとしてボリス・ヴィアンの『うたかたの日々』、自作『好き?好き?大好き?』の読み換えの『好き好き大嫌い』、『くちびるから散弾銃』が『東京ガールズブラボー』などである。
さらには、作話法の実験として、一つの話の終わりが次の話の始まりに続き、円環する日常とそこからの離脱のテーマを描いた『カトゥーンズ』が挙げられる。
いろいろな方法を試して、最も自分のテーマを表現できる方法を模索している時期と言っていいだろうか。
b.テーマの掘り下げ
この時期には、方法の模索と同時に、テーマを掘り下げる作業も行われている。
キーワード(3)を、ここでまとめてみたい。
「愛」は、作品の中にはあまり出てこない。より正確に言うと、愛の不在・欠如が繰り返し描かれている。
「セックス」は、第2期以降は体と心の解離、他者とのすれちがいとして描かれている。すなわち他者との交流を求めれば求めるほど、心理的距離は遠くなるというのである。
「死」は、実際の死というより、死んでいるようなこと、日常の閉塞として描かれる。
「暴力」は、殺すこととして繰り返し描かれる。それは破壊、憎悪、悪意に満ちており、何かの内圧が高まっている印象が強い。そしてこれは、第5期での閉塞を打ち破るパワーへとつながっていく。
「すれ違い、ディスコミュニケーション」。「おたく」や、『リバーズ〜』のカンナなど、自己愛的で他者との双方向的な交流が成立していない。まだ真の他者が存在していない。
これらを通して見られるテーマは、閉塞、自閉、他者との疎通不全、というようなものらしい。
しかし、閉塞とは何なのか、また作者にとってなぜそれが問題なのかも、今の所まだ私には判らない。
これらのテーマの総仕上げが『リバーズ・エッジ』である。この作品は、「死んでいる」日常を描いた、何も起きない物語である。すなわち、問いの完成、臨界点である。それだけ強い作品であり、多くの読者に支持されている。この作品でまとめをして、作者は次のステージへと進む。
5.第5期/戦闘開始(1995-)
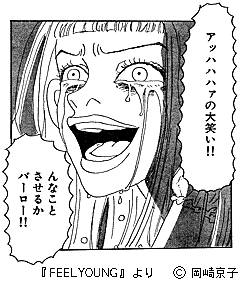 『ヘルター・スケルター』は、全身整形手術で造り上げられたモデルの主人公りりこが、迫り来る破綻に対して敢然と立ち向かう話である。3部作の予定だったが、途中で事故のため中断している。『リバーズ・エッジ』と同じ登場人物(吉川、狂言回し)を出すことで、『リバーズ〜』と対の作品(時間的には同時進行の物語)であることが明示され、『リバーズ〜』で立てた問いに対する答え(の始まり)と位置づけられる。
『ヘルター・スケルター』は、全身整形手術で造り上げられたモデルの主人公りりこが、迫り来る破綻に対して敢然と立ち向かう話である。3部作の予定だったが、途中で事故のため中断している。『リバーズ・エッジ』と同じ登場人物(吉川、狂言回し)を出すことで、『リバーズ〜』と対の作品(時間的には同時進行の物語)であることが明示され、『リバーズ〜』で立てた問いに対する答え(の始まり)と位置づけられる。
第1回は「んなことさせるかバーロー!!」という宣戦布告の雄叫びで締めくくられている(右図参照)。その明確さは照準が定まっていることを表している。作品自体は、ぼろぼろになった主人公が異国の地でそれでもしぶとく生き延びているラストで終わる。まだ回答は示されないが、決して負けを認めない力強さを感じる。
表情も変遷していく。第1期のおしゃれな顔から第4期の無表情へ、そしてこの第5期への攻撃的な笑いへと、代表的な顔が変わっていくのは、テーマの変遷の現れである。『ヘルター・スケルター』第1回では「笑いと叫びはよく似ている」とコピーが入っているが、これは上に挙げたせりふのあるコマのことである。
ここでモデルという役について見てみたい。
モデルの役は、それまでもたびたび登場する。『ROCK』『マジック・ポイント』『恋人はあなただけ』『リバーズエッジ』『3つ数えろ』『チワワちゃん』などである。それだけ重要な役割を担っていると言える。
その意味するところは、虚像、欺瞞である。外見を作ることでどんどん自分自身から疎外され、攻撃性が高まるイメージである。モデルは本質的に見られること(他者)によって成り立つが、作品の中でそれは主体性を奪われていることであり、同時に自ら主体性を放棄していることでもある。
モデルは作品の中では打破されるべきあり方の象徴として描かれている。ここで作者は、閉塞は欺瞞からと喝破していることが見て取れる。
そして高まる攻撃性は、虚偽を打破するパワーとして『ヘルター〜』では描かれている。それまでの作品で繰り返し描かれてきた暴力は、ここではっきりとその意味が認識される。
なお、虚偽をあばく役目として「浅田検事」が登場する。これについては次節で述べる。
IV.小沢健二とのシンクロ
ここで、作者にとってキーパーソンの一人である小沢健二に焦点を当ててみたい。小沢は作者にとって「王子様」であり、今まで見てきた作品の流れに強い関連が見られるからである。
小沢は性格は頑固で、基本的に前向きである。曲作りでは曲より詩に重点が置かれ、言葉の人である。歌からすると、自分にも人にも厳しいようである。しかし、100%前向きではなく、どこかシニカルな部分を残している。
小沢の軌跡を簡単にふりかえろう。パーフリの頃は、たとえば「いつも少しずつ死んでいく」(『スライド』)と歌うように、生への懐疑が認められる。やがて1989年?にパーフリを突然解散して小山田圭吾と決別し、ソロとして自分の問題に集中する。アルバム『犬は吠えるがキャラバンは進む』では決然とした歌声で、正面切ってそれに取り組む決意を表明する。またこの頃は友達(スチャダラ)と毎晩遊んでいた。そして1994年?の『ラブリー』(4)で一気に爆発し、生の確信を歌い上げる。
これは先に見てきた作品の流れと一致している。熱烈な小沢ファンで、ツアー『LIFE』の時はナミダとハナミズを流しながら声の限りに『lovery』を歌っていたはずの(会場では全員がそうだった)作者は、激しく勇気づけられたに違いない。
小沢は作者にとって、眠り姫を目覚めさせる「王子様」である。しかし目を覚ますとそこは戦場であり、地獄である。地獄を歩き抜ける覚悟をさせる者、閉塞した日常をあばく者、というのが作品の中での小沢の役どころである。「浅田検事」は小沢健二以外にはあり得ない。
V.終わりに
まだ全体像は見えていない。詰めも穴だらけだし、中核となる「閉塞」についてもまだよく判らない。しかし、とりあえずここまで来た。
そしてまた同時に繰り返し問う、読者とは何者なのかと。
作者には会ったことがないが、作品から見る限りあまり妥協はしない性格のようである。おそらく今も車いす上で、日常を闘っているのだろう。読者として今できることは、やはりあきらめないで復活を待ちながら、作品をていねいに読み、作者の替わりに歩き、そして自分を歩くことだと思う。
参考文献
(1)月刊『カドカワ』1990年8月号、角川書店
(3)キネ旬ムック『マンガ夜話』vol.2、キネマ旬報社、1998年
(4)小沢健二 アルバム『LIFE』1994年
1998年12月第一校、1999年12月と2004年2月一部改定
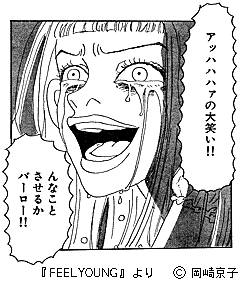 『ヘルター・スケルター』は、全身整形手術で造り上げられたモデルの主人公りりこが、迫り来る破綻に対して敢然と立ち向かう話である。3部作の予定だったが、途中で事故のため中断している。『リバーズ・エッジ』と同じ登場人物(吉川、狂言回し)を出すことで、『リバーズ〜』と対の作品(時間的には同時進行の物語)であることが明示され、『リバーズ〜』で立てた問いに対する答え(の始まり)と位置づけられる。
『ヘルター・スケルター』は、全身整形手術で造り上げられたモデルの主人公りりこが、迫り来る破綻に対して敢然と立ち向かう話である。3部作の予定だったが、途中で事故のため中断している。『リバーズ・エッジ』と同じ登場人物(吉川、狂言回し)を出すことで、『リバーズ〜』と対の作品(時間的には同時進行の物語)であることが明示され、『リバーズ〜』で立てた問いに対する答え(の始まり)と位置づけられる。