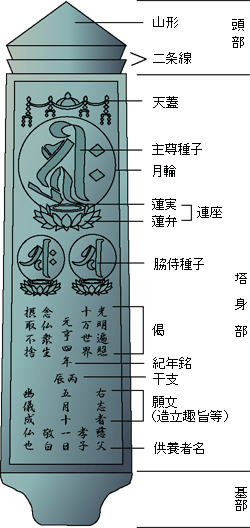|
|
鎌倉街道を探索していると、街道沿いのお寺や街道辻など人目につきやすい所によく板碑を見掛けます。 板碑の発生板碑の源流には幾つかの諸説があり定まったものが無いのでここでは説明しません。板碑と同形式のものは、平安時代の末期の絵巻である『餓鬼草子』『北野天神縁起』などに、木製と思われる板碑が見え、これら絵巻に見えるものは胎蔵界大日種子であるのが特徴であるそうです。 |
|||
|
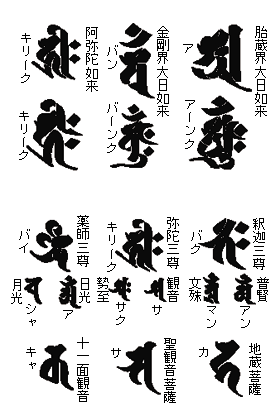
|
埼玉県の板碑の特徴埼玉県には現在2万基以上の板碑が確認されているそうです。これは質・量ともに全国一といわれています。板碑の石材は荒川上流の長瀞や槻川流域の小川町下里などから産出される緑泥片岩と呼ばれる石で、たがねなどで割ると板状に薄く割れる性質があります。この緑泥片岩は青色を帯びているために青石塔婆とも呼ばれていて武藏形板碑と分類します。板碑は日本全国に分布していますが、地域ごとに形や石材に特徴があり武藏形板碑は材質が柔らかく加工しやすいため、美術的にも美しいといわれます。 板碑はなんのために造られたのか板碑は大別すると追善供養塔と逆修作善塔に分けられます。 板碑の造られた時代板碑は鎌倉時代中期頃から造られ始め南北朝に全盛期を迎え、室町時代そして新しいものとして安土桃山時代のものもあり、そして江戸時代には造られなくなります。こうみてみると、ほぼ鎌倉街道と同じ時代に造られてきて、鎌倉街道が街道としての使命が終わる頃に板碑も造られなくなるのです。 現在の鎌倉街道跡周辺で見掛ける板碑は鎌倉街道とおおいに密接な関係にあるものといえましょう。 埼玉県内で最古の板碑は大里郡江南町須賀広の大沼公園所在の嘉禄3年(1227)銘阿弥陀三尊画像板石塔婆があげられ、上部は破損し画像も磨滅して明らかではありません。 最も新しいものとして戸田市新曽妙顕寺所在の慶長3年(1598)銘題目三尊板石塔婆があります。 その大きさの最大のものとして秩父郡長瀞町野上下郷所在の応安2年(1369)銘釈迦一尊種子板石塔婆で約5メートルの高さがあります。 反対に最小のものは在銘の確認できるものとして北埼玉郡川里村出土の永仁元年(1293)銘阿弥陀一尊種子板石塔婆で高さ22センチメートルです。 武士の間に広まった板碑は信仰と深い関係があり、貴族から武士の政権となった鎌倉時代から徳川家康が江戸幕府を開くまでのあいだは正に戦乱の続く時代でした。戦に直接参加する武士達は、常に死と直面していたのです。いつ死ぬかわからない不安、そして生きるためには人を殺さなくてはならない罪の意識、こうした生活感情と社会的背景が当時広まりつつある浄土教の思想と結び付いて武士の間で 盛んに板碑が立てられたと考えられるようです。その後豊臣秀吉の天下統一後は社会が比較的安定してきた為、仏に救いを求める意識が薄れ板碑は造られなくなったと考えられているようです。 石の証人としての板碑現在埼玉県立博物館(大宮公園内)には県内を代表する板碑の展示室があります。興味のある方は |