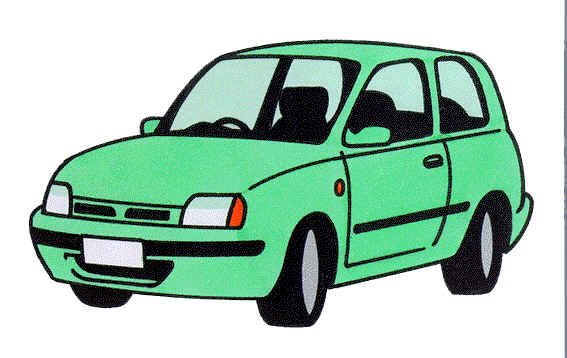プロローグ 

「支折です...うーん、ようやく暑さも峠を越えたのでしょうか。肌に受ける風に、秋
の香りを感じます...」支折は、紅茶のカップを口に当てた。
青木は、自分の志野焼の茶碗を片手で握り、窓の外の青空を見ていた。
「青木さん...日本の社会が、ここまで構造的に混乱してきて、いよいよ政治を当て
に出来なくなった観があります。もちろん、政治には、是非しっかりしてもらいたいわけ
ですが、もうそれを黙って見過ごしている訳にも行きません、」
「そうですね...」青木は、大きく息をつき、茶碗を見つめた。「いよいよ...私たち自
身の生活が苦しくなってきました。
しかし、マスコミは、その事を伝えていませんね。明るく豊な、バブルの頃のような話
ばかりをしています。まあ、“元気な話”というのは結構なのですが、社会の真実の姿
とは、ズレた所に位置しています。誰が、そんな事を操作しているのでしょうか...
いずれにしても、そうしている間にも、日本の社会の中で、構造的な貧富の差が拡
大して行く雲行きです。まさに、市民・国民が立ち上がらなければならない所に来て
います。ええ...新時代へのキーワードは...“情報公開”と“国民参加”ですね」
「はい!」
「ええ、それでは...さっそく、私たちがまとめた、“国民参加型・評価システム”のガ
イドラインを説明していきましょうか、」
「はい!」
≪3≫ 既存のグループや組織を活用する! 
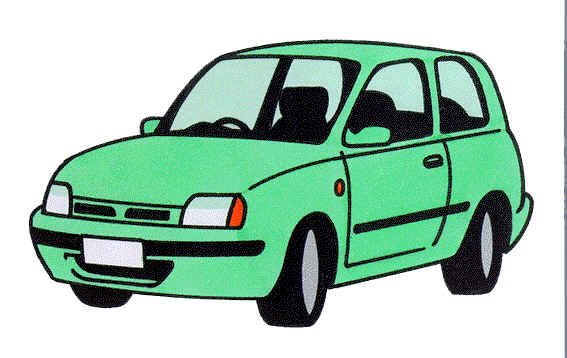
「ええ...
以上が、私たちがまとめた試案です。他にも、無数のアイデアがあると思います。そ
れらを、これからの活動の中で、どんどん提案して行って欲しいと思います」
「そうですね...
ともかく、最初は、無数の“評価グループ”を作る事だと思います。“新しい評価グル
ープ”の結成。“既存の様々なグループ”で、余技の文化活動として、“評価活動”を活
性化する。そして、相当数の、個人参加の窓口も必要ですね」
「あ...それは、“評価・NPO”で、直接管理するわけですね?」
「まあ、そんなあたりでいいと思います。ともかく、信頼性の高い、“全国民・全市民に
開かれている窓口”が必要です」
「はい、」
「それから、単に評価の結果だけをインプットするのではなく、“ディスカッションする場”
や、“評価対象のデータを分りやすく表示する場”なども必要ですね。それが、この国の
社会や、文化活動全体に、活力を与える事になると思います」
「はい...あの、“既存の様々なグループ”には、それぞれ本来の活動があるわけで
すよね。ここに、“評価活動”を加えてもらうということは、受け入れてもらえるものなの
でしょうか?」
「私は、十分に可能だと思っています...
もちろん、様々なケースがあると思います。しかし、これは、あまり負荷はかからな
いと思います。文化活動の一環として、是非、“評価活動の窓口”を設置して欲しいと
思いますね。ごく一般的な話題性を、信頼性の高い統計として、日常的に入力して欲
しいわけです。
旅行が近づいたら、旅行の話題でいいわけです。また、日頃スポーツや芸能の話題
が多いのなら、その方の評価活動に参加すればいいわけです。また、行政や政治に
注文があるなら、大いにその方面の評価活動に参加すればいいわけです。これは、
本来の活動を、それほど妨げるものではないと思います」
「はい...」
「それから、“企業”や“職場”、“各種団体”、“地域”にも、文化活動や話題性として、
是非、この“評価活動の窓口”を設置して欲しいと思います」
「はい。そして、これらの評価活動のデータを、“地域・評価NPO”が統括・処理して行
くという事ですね?」
「そうですね...
いずれにしても、これから膨大な試行錯誤をして行かなければならないと思いま
す。しかし、その試行錯誤や、新しい社会システムを作っていく行為そのものが、すで
に新しい文化なのです。そのプロセスそのものが、すでに社会を活性化しつつあると
いうことなのです」
「はい!」
「まあ、最初のテーマとしては、“地域社会のイベント”や、“地域の社会的問題”などを
取り上げ、それを評価システムに載せるのが分りやすいと思います。つまり、その結
果を、すぐに地域社会の中で反映させる事が出来るものにすることです。
“市民による、市民のための、市民の社会”を実現する、“共通認識を形成するツー
ル”になるという事です...そして、それを全国ネットワークへ拡大し、“国民による、
国民のための、国民の社会”を実現する“国民参加型・評価システム”にしていくわけ
です」
「はい!
そして、解放系システムとしては、さらに国際社会へ拡大していくわけですね。“世
界市民による、人類共通の認識”を形成する、“世界的・評価システム”につなが
っていくわけですね」
「そう願いたいものです...
ともかく、知恵を出し合い、“互いに競い合うような形の、2本か3本の評価システ
ム”を立ち上げ、“透明性”や“信頼性”を高めていくことが必要です」
「はい...あの、“評価システム”は、2本も、3本も必要なのでしょうか?」
「行政システムのように、1本の回線だと、“独占”になります。そうなると、“競争原理”
が機能しなくなり、やがて腐敗して行きます...まあ、初期段階は1本でいいのです
が、次のステージでは、そうした事でも、しっかりと知恵を出して行ってほしいという事
です...」
「はい!」支折は、コクリとうなづいた。
≪4≫
まず、郵便を使う、“簡単な評価システムの構築”!
小冊子や雑誌で、“評価ガイド・リスト”を作り、“評価集計データの発信”も!
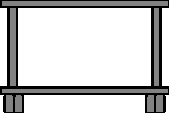





「ええ...」支折が、プラズマ・スクリーンに、次のデータを表示した。「これは、私たち
がまとめた試案ですが...ともかく、まず、身近な所から、手作りで活動を始めるとい
うことですね。
地域のイベントや、地域の社会問題など、自分達に見えるものから、すぐに“評価
活動”を始めて欲しいと思います。むろん、ディスカッションも、対策も、その“評価活
動”の延長線上に、必ず存在するものですね...
さて、地域の目に見える範囲の評価なら、“郵便システム”で十分です...まず、視
覚的にも分りやすい評価システムを、形の上でも示しておく事が大事だと思います。
また、郵便なら、デジタルディバイド(デジタルでの情報格差)もなく、初期段階においても、全
員参加がしやすいのではないでしょうか。パソコンは、最初のうちは、表計算でデータ
の整理に使う程度でいいと思います」
「まあ、そうですね...
郵便というのは、“時間をかけて、ゆっくりと集計するようなもの”に向いていると思
います。インターネットでの、高速・大容量システムが整備されたとしても、1つのシス
テムに1本化する必要はないのです。むしろ、郵便システム等の別の集計システム
があった方が、色々な人間的な楽しみが広がります。1つと言うのは、ともかく、行政
システムなどがそうですが、面白味がないですからねえ...」
「うーん...それでは、こうした郵便を使った評価システムなどは、将来的にはどのよ
うに拡大していくでしょうか?」
「うーむ...今後の展開は、どうなるかは分りません...
しかし、“郵便システム”で、当面考えられるのは、通信販売のカタログのような、“評
価ガイド・リスト”を、小冊子で、定期的に発行するような事が考えられます。それは、イ
ンターネットの“共通・評価ソフト”と“統一された内容”のものになると思います。とく
に、人気の高いものなどが、掲載されるようになるかも知れません...」
「はい、」
「一方、、“評価の結果”をガラス張りで“公開する仕事”...評価データを“加工する
仕事”...また評価データを応用する“膨大な裾野の仕事”も始まります。いずれにし
ても、小冊子には、これらの結果の方も、大いに掲載しなければなりません」
「あ、そうですよね...つまり、それが、デジタルディバイド(デジタルでの情報格差)を埋める
事になるわけですね」
「まあ、単にデジタルディバイドを埋めると言うよりも、各種の郵便物や、週刊誌なり月
刊誌なりの発行は、それは文化として強力な柱の1つになると思います」
「はい。電車の中や、公園のベンチでも読めますものね、」
「そういうことです...
まあ、ともかく、最初はまず、“国民参加型・評価システム”の全体を、分りやすい形
で定着させる事が先決です。それには、見える形の、手紙などによる“簡単な評価シス
テム”を提示し、ともかくそれを地域社会で“走らせて見る”という事ですね」
「はい。その素材として、地域のイベントや、地域の社会問題など、自分達にコントロー
ルできる範囲のものを、手がけてみるという事ですね」
「そうです。むろん、一方では、“インターネット・システム”の構築や、“共通・評価ソフ
ト”の開発なども、並行して行っていくという事になります」
「はい」


 出来る事から、スタート!
出来る事から、スタート!
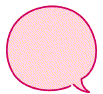


![]()
![]()