 <辛口時評・2002/No.4> .....(2002. 7. 6) <辛口時評・2002/No.4> .....(2002. 7. 6)
国家の混迷は、
“国民主権”と“情報公開”で突破を!
  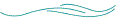   
津田・編集長 星野支折
〔1〕 武士道が完遂した明治維新
〔2〕 “白羽の槍”を喉元に当てて!
〔3〕 国会議員の、“全活動状況”の開示を!
新・民主主義社会への展開
〔4〕 地方政治の考察
〔5〕
政治、社会、文化の活力 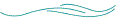
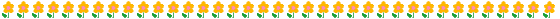
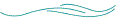  
支折は、テレビの大雨警報を見ていた。ひとしきり、激しい音のする窓の
方を眺める。窓ガラスにザーッ、ザーッ、と強い雨が吹きつけていた。彼女
は、カウチから立ち上がり、ゆっくりと窓の方へ歩いた。
雨飛沫(あめしぶき)で霞む窓の外に、紫陽花(あじさい)の花がボンヤリと見え
た。その先の方は、白い雨糸で何も見えない。薄暗い空の下で、雨だけが
激しく降っている...
「やあ...」津田が、部屋に入ってきた。「よく降るねえ...」
「はい...今年は、梅雨らしい梅雨ですわ」支折は、振り返って言った。「こ
れで、夏の渇水が乗り切れるんじゃないかしら、」
「うむ...まあ、これだけ雨が降れば、水が足りんということはないだろう」
二人は、雨音の響く窓辺のテーブルに席を取った。時折、ザーッ、と雨が
強く吹きつけてくる...
「さてと...前回はマスメディアについての考察だったな、」津田は、窓から
テーブルのノートパソコンに眼を落とした。
「はい...」
「今回は、政治の混迷について、全般的な考察をしようと思う」
「はい」
〔1〕
武士道が完遂した明治維新  
「ええ...まず...戦後、マッカーサー元帥がもたらした“民主主義”は、本
当に日本の社会に根付いていたのか...」
「はい、」
「まあ...ある意味では、大きな成果があった。これは間違いないがね。
“日本の第2の奇跡”と言われた、“経済大国”へのサクセスストーリイを描
いた時代だ。これを、否定するわけには行くまい...」
「はい、」
「また、“農地解放”、“財閥解体”、“教育の普及”等は、戦後の日本社会
に、維新革命のような劇的な変化をもたらした。そして、そこに、“民主主
義”という、新しい社会的パラダイムの種が蒔(ま)かれていったわけだ...
さあ...そこでその種は、立派な苗に育ち、鬱蒼とした成木に成長した
のだろうか?日本の民主主義は、古い社会の慣習を完全に打ち破り、真に
“国民主権”の国家となったのか?問題は、まさに、ここにある...」
「はい、」支折は、深くうなづいてから、やや首を横にした。「あの、津田・編
集長...すると、“日本の第1の奇跡”というのは、何なのでしょうか?」
 
「うむ...世界史の中で、最初に“日本の奇跡”と言われたのは、“明治維
新”だ。二百数十年の鎖国の惰眠(だみん)から目覚め、社会が大転回した時
代だ。日本の社会が、中世の江戸時代から、近代の明治時代へと大変身
した革命は、世界史的に見ても、非常にうまくいった革命だと言われてい
る。
明治維新というのは、支配階級であった、武士社会の革命だった。それ
も下級武士による革命だった。したがって、庶民はそれに、ほとんど巻き込
まれることはなかった。“サムライ”が、武士道精神のもとで、ある意味で整
然と完遂した革命だったわけだ。
しかし、その結果、日本は思いもよらぬほどの、強大な近代国家へと驀
進することになった...当時、アフリカやアジアの諸国は、西欧による植民
地化の辛酸をなめていた。だが、そうした中にあって、日本はうまく独立し、
近代社会へと脱皮できたわけだ」
「ふーん、そうかあ...それが、“明治維新”なのね、」
「まあ、日本の政治は、今でこそこんなロクでもない状態になっているが、
我々はあの、“明治維新”を完遂した国民なのだということだ!」
「はい!」
「それから、その維新革命から、三十数年後...日露戦争が勃発した。こ
の大国ロシアとの全面戦争で、新生の明治維新政府は、運命的な大勝利
をおさめたわけだ。
海軍は、当時世界最強といわれたバルチック艦隊を、日本海で迎え撃
ち、これを撃破した。この歴史的な大海戦のニュースは、たちまち世界中に
打電され、日本の予想外の大勝利は、世界を震撼させたという。
それ以後、日本は名実共に、世界の列強と肩を並べるようになって行く
わけだな...つまり、これが、最初に“日本の奇跡”といわれた時代だ」
「はい!」
「うーむ...明治は、私の最も好きな時代だねえ...開けっぴろげで、何も
かもが輝いていた時代だ...全てに、純朴で、真剣な時代だった...
そうそう、バルチック艦隊を撃破した日本艦隊の提督は、東郷平八郎
...そして、幕僚に秋山真之(さねゆき)がいた...
“舷々相摩す...”
“天気晴朗なれども波高し...”
などと、海戦の状況を打電したのは、幕僚の秋山真之と言われる...日本
中...いや世界中が、その快晴で波の高い日本海での激闘に、思いを馳
せた。それは、西欧を追いかけ、近代化途上の明治政府にとっては、まさ
に国家の命運を左右する大決戦だった...
乃木希典(のぎまれすけ)の率いた陸軍第三軍が、ロシア艦隊の軍港だった
旅順を陥落。東郷平八郎が率いた日本艦隊が、日本海においてバルチッ
ク艦隊を撃破。それからさらに、大陸の“奉天の会戦”においても、日本陸
軍は大勝利を収めた...」
「はい...」支折は、楽しそうに話している津田を眺め、頬を崩した。
「...そして、あの太平洋戦争の大敗北だ。それで、戦争は全て悪と決め
付けられてしまった。その時代の青春も、冒険も、男達のロマンも、全てま
とめてゴミ箱にブチ込まれてしまった。しかし、確かに、その時代はあった
のだ。むろん、私は、その敗戦の後に生まれた人間だがね...」
「はい...」
「しかし、男の子というのは、いつの時代でも、戦争ごっこが好きなものさ。
そして、それが生きる力にもなる。将来、それが正義のための戦いになる
かも知れないし、スポーツになるかもしれない...あるいは、もっと違う形
の、生きるための力になるのかも知れない...
そうした人生の戦いの中から、ロマンが生まれる。苦しい状況の中から、
豊な芸術や文学が生まれてくる...
人生とは、その中で、もがき苦しむのではない...一歩引いて、自分を
も含めて、その全体を観察するのが楽しいものだ...首を2センチほど引
き、斜め上あたりから見下ろすのがいい...
...」
「はい...」支折は、あごを引いて、津田の顔を見上げた。
「はっはっ...おっと...脱線してしまったな...
ええと、つまり...戦後の民主主義が、本当に日本の社会に根付いた
のかどうかということだったな...まあ、確かに、日本の国力は見事に復
活し、社会は再び安定し、民主主義も定着した...
しかし、真の意味で、日本の社会は、民主主義というものを理解していた
のかどうかが問題なわけだ...」
「はい...どうだったのでしょうか?」
「うーむ...経済分野で大成功を収めただけに、民主主義の本質が無視さ
れ、見落とされ、ひたすら突っ走ってきたような感じがする...政治や官僚
機構のギアチェンジも、あのバブルの狂乱の中で押し流されてしまったよう
だ...」
支折は、テーブルの上に目を落とし、強くうなづいた。
〔2〕
“白羽の槍”を喉元に当てて!
 
<国家再生のカギは・・・
国民の怒り!>
「ええと...それで、津田・編集長...まず、私たちは、何をしたらいいの
でしょうか?」
「そうだねえ...それで、みんな悩んでいるわけだ...
かって、細川・元首相が、日本新党を率いた総選挙で、“政治家総とっか
え!”と訴えたものだった。これは、今でも的を射た言葉だと、私は思って
いる。その細川・内閣から、すでにだいぶたつわけだが、自民党に政権が
戻ってしまったからねえ...すっかり、元の木阿弥になった...」
「はい...」支折は、静かにうなづいた。「そして、とうとう行き詰まってしま
いました...」
「うむ...まあ、分かっていたことだが、そうなったな、」
「はい、」
「公明党も、保守党も、かっては自民党政治を批判し、国民に向かって大改
革を訴えていたのだがねえ...その、彼等は今、旧体制の自民党を支え
る側に回っている...何故なのか...これが、国家や国民のためになると
は思えないのだが...」
「あ、でも...今は、小泉内閣を支えているし、」
「彼らが、与党に参加したのは、その前の橋本・内閣の時からさ」
「はい...うーん...その時、
この2党からは、ちゃんと説明はあったので
しょうか?」
「まあ、多分、説明はあったのだと思う。無いはずはない。しかし、何を言っ
たのか、覚えてないな。ともかく、私はいまだに、納得のできる説明を聞い
た覚えが無い」
「うーん...」
「今、この時点からでも、公明党と保守党が、国家大改造の方向に舵を切
れば、“新世紀・維新”は大車輪で動き始めるんだがね。むろん、これは小
泉改革の方向でもあるわけだし、」
「はい...でも、編集長、この2党の真意は、いったい何なのでしょうか?
“利権”が欲しかったということなのでしょうか?」
「うーむ...まあ、それが知りたいわけだ。納得のできる説明というヤツを
ね。今まで、自民党政治を批判してきたわけだし...」
「はい、」
「それにしても国民は、これからはこうした問題で、もっと真剣な“白羽の
槍”を、各政党の喉元に突きつけるべきです。最後まで、ごまかしたり、お
茶を濁したりするのではなく、膝詰で、本音で話し合うべきです。
また、政治家や政党も、自分たちの言動が、著しく社会的信用度が低い
ということを、もっと自覚すべきです。政治家が嘘つきだという事は、残念な
がら、小学生でも知っているのではないでしょうか...こんなことで、いい
はずがないのです!
また自分の支持する政党であるなしにかかわらず、“抜き身の刀”、“白
羽の槍”を持って、私たちは真剣な話し合いをする時に来ているのではな
いでしょうか。これは、“政治”に対してばかりでなく、行政である“官僚機
構”に対しても、また文化を担う“マスメディア”に対しても同じだと思いま
す。何事に対しても、本音で、真剣に話しを詰めて行かなければ、この国の
再生は不可能なのではないでしょうか。
...」
「はい。まさに、私もそう思います!」支折は、強くうなづいた。「政治も、官
僚機構も、マスメディアも、この現実を真剣に受け止めるべきだと思いま
す。そもそも、こうした国家の動脈が硬化したから、国全体が循環器系の
重病にかかってしまったわけですから、」
「うーむ。そのとおりだ。まさに、支折さんの言うとおりですね」
「はい! 族議員の跋扈する自民党に対しては、利益代表の考えは排除し
て欲しいと思います。国会議員として、国民全体の利益と国家運営の観点
から、議論すべき課題は山ほどあると思います」
「うーむ...自民党も、そういう政党になってくれれば、魅力はあるんだが
ねえ。民主党は、どうかな?」
「はい。民主党は、何をやっているのかしら、と思います...それから、社
会民主党は、“机上の空理空論”で、さまよっている感じがします」
「うーむ...これも、いつまでもこんなことを放置しておくわけには行かない
ねえ。“白羽の槍”を前にした、真剣な議論の末、不要なものは始末しない
といけない。ま、最終的には、以下のような、実力行使が必要になると思う。
【1】メディアや集会で、徹底的に議論する。
【2】デモ行進等で、直接圧力をかける。
【3】選挙権による“主権”の行使で、完全に排除する。
まあ...選挙権を行使できない“官僚機構”や“公団”に対しては、マス
メディアやデモ行進等で、直接圧力をかける手段を発掘していくことが必要
だね。つまり、農水省や厚生省や道路公団の体質が、一新されないのな
ら、そのつど、デモ行進や集会等で、国民が直接圧力をかけていくべきだと
いうことです」
「インターネットは、利用できないかしら?」
「ああ、それも、いいかも知れませんね」
〔3〕
国会議員の、“全活動状況”の開示を! 
新・民主主義社会への展開
インターネットによって、議員活動/政治状況を詳細
に開示して行けば、政治にお金はかかりません。今こそ、
21世紀型の、“新・民主主義社会”へ移行する時
...
「さて、次は、国会議員全員の活動状況を、インターネットで公開することで
す。これは、各政党・各議員が、責任を持って行うべきだと思います。また、
衆議院と参議院も責任を持って公開し、NPOがそうした情報を再構成し、
国民にわかりやすいデータを作り上げていくことも必要だと思います。
また、各選挙区ごとに、こうしたデータを並べ替え、日常的に検索できる
ことも必要ですね。私たちが選出した議員が、日ごろ何をやっているのかを
知ることは、政治意識を高めるという観点からも、非常に重要です。
むろん、ガラス張りにするということは、プラスとマイナスの両面があると
思います。しかし、原則開示が民主主義の基本だと思います。すでに、イン
ターネット時代が進行し、少しづつこうした流れは始まっていると思うのです
が、しっかりとした信頼の出来るフレームを構築して行くことが望まれます。
こうした、しっかりとしたデータが常時公開されていれば、各議員は選挙
区のことは気にせずに、本来の政治の仕事に没頭できるのではないでしょ
うか。また、こうした確かなシステムが確立されて行けば、いわゆる“金集
め”に奔走する苦労もなくなると思います...
どの議員が、どのような政策に対し、どんな意見をもって活動しているの
か...すべて国民にわかるようにすることが大事です。そうすれば、本来、
“ねじれ現象”などは無いはずなのです。また、いつ、何処で、何をしていた
のかも、原則としてキッチリと公開すべきだと思います。
したがって、こうした全面ガラス張りの情報公開に応じられない議員であ
れば、国民はそうした議員は必要ないということにしたいですね。評判の良
くない“族議員”は監視できるし、仕事をしない議員も、能力の欠ける議員も
不要だということです。また、国会は国家の最高意思決定機関であり、これ
からボツボツ勉強しますというような人物も、当然いらないわけです。国会
は、国家が必要とする、最高の人格が求められている場なのですから...
...」
「うーん...はい...非常に厳しい内容ですが、実現できるでしょうか?」
「NPOを組織し、まず民間で出来ることから、フレームを作っていくべきだと
思います。それから、各政党や各議員の協力も得られると思います。また、
各ホームページともリンクさせればいいわけです。さらに、衆議院と参議院
でも、院としてのシステムを作って行くことが不可欠の時代が来ると思いま
す。まあ、難しいことは、何も無いですね...
溢れるほどの情報があれば、あえて大金をかけて宣伝する必要も無い
わけですし、真意というものも、この場で伝えていけるはずです。国民は、
それが例えば、NPOのデータだけだとしても、それを信じて選挙をすると思
います。金を集めてパーティーをするのと、どっちがいいのか、それは国民
が選択して行くのではないでしょうか...
もちろん、議員にも基本的なプライバシーはありますし、その部分まで公
表する必要は無いわけですが、一般の人よりも、その領域は狭くなるのは
確かでしょう。
また、私はかって、あえて言ったことがあるのですが...国会議員は、
希に見る犯罪発生率の非常に高い集団です。こうした観点からも、あえて
ガラス張りにしておくことは、盛り場に監視カメラを置くようなものであり、非
常に有効だと思います。是非、犯罪の発生を、ゼロにして欲しいものです。
何しろ、あの辻本清美・議員でさえ、形はどうあれ、犯罪性を問われたわ
けです。鈴木宗男・議員が疑惑の総合商社(辻本清美・議員の言葉)なら、辻本清
美・議員は、祭りの出店での、“疑惑の金魚すくい”のようなものですかね。
しかし、まあ、タモの紙が破れてしまい、金魚が落ちてしまったわけですか
ら...」
「はい。でも、私は辻本さんの気持ちは良くわかります!」支折は、髪を撫
で上げた。「本当にお気の毒だと重います。あれは、手違いだったのだと思
います...」
「うむ...まあ、いずれにしても、今までのままでは、ダメだということです。
今、ここで述べたような、“新・民主主義の胎動”が始まってこないと、“地球
社会のパラダイムとしての民主主義”が、今後、閉塞状況に陥って行きま
す。インターネット時代の到来が、“新・民主主義の時代”を招来する事を、
私は強く期待しています」
「うーん...いいかも知れませんね!」
「私は、このホームページのトップで、こう主張してきました...
国家大改造は、 “国民主権” がキーワードです!
司法・立法・行政/マスメディア・文化 の大改造は、“国民主権”のスタンスで!
まさに、立法府である政治の改革も、“国民主権”がキーワードだと思い
ます。そして、これと連動するわけですが、次に重要なのは、国民に対する
“情報公開”です。情報がしっかりと公開されれば、次のステップは、おの
ずと見えて来るのではないでしょうか。
ま、このぐらいの意気込みでやらないと、日本の政治は浄化できないの
ではないでしょうか。いずれにしても、ひとこと言っておきますが、お金儲け
をしたいのなら、官僚や政治家になるべきではないのです。そういう人は、
最初から民間で事業を起こせばいいのです。また、現在の日本のように、
大混乱に陥っている国家の運営では、これは権力闘争の場と考えるべきで
はないと思います。ここは、
聖域における聖職...聖職における聖断!
...と考えて行動して欲しいですね。抵抗のための抵抗勢力などは、言語
道断です!」
「ええと...はい!」
〔4〕
地方政治の考察 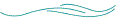   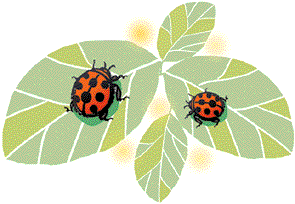
「ええ、津田・編集長...それでは、地方政治の方は、どうなのでしょう
か?」
「そうですねえ...地方政治も、状況は中央とそれほど変わらないと思い
ます。したがって、ここでも、NPOによるインターネットの場での公開がい
いと思います。
まあ、地方政治の場合、中央よりも、さらに“泥臭いもの”が残っています
からねえ...NPOと政党と議会等が連携し、しっかりとしたフレームを作っ
て行くことが大事だと思います。これが、21世紀の民主主義の、新しい形
を作っていくことになると思います。
“ムラ社会”や、“仲良しクラブ”的な、明らかに“ヘンな意見”は、こうした
公開フレームの中で明らかにし、排除して行くべきです。こうした民主主義
の原則が、21世紀型の透明・公正な法治国家を作り上げていく上で重要
です」
「はい、」
「したがって、地方政治でも大事なことは、“国民主権”と、“情報公開”で
すね。それが、社会の活力を生み出します。不正や偏見や独断専行の中
からは、活力は生まれてこないですからねえ、」
「はい!」支折は、テーブルに両手をついた。「今回の、日韓共催のワール
ドカップが、私たちにそれを教えてくれたのではないでしょうか!」
「うむ。これは今後、若い世代に引き継いでいってもらいたいね。これから
の若い人たちが、スキンシップの中で、理屈抜きに、一緒にやって行って欲
しい」
「はい」
〔5〕
政治、社会、文化の活力   
「さて、そのワールドカップも、ついに終わってしまった...」
「はい。まだ、その余韻が残っていますけど...」
「うーむ...しかし、よくあれほど国民が一体になり、盛り上がったものだと
思う...政治も、あれぐらい盛り上がってくれればねえ...」
「サッカーが盛り上がるのは、共通のルールがしっかりと守られているらだ
と思います!」支折は、テーブルの上で、両手を固く握り締めた。「日本の
政治や、社会や、文化が、活力をなくしているのは、そのルールが消えてし
まい、見えなくなり、国民の支持を失ってってしまっているからではないで
しょうか?」
「うむ! まさに、そのとおりだと思う!
国民の支持を失った政治や文化と
いうのも、何処か間の抜けた、寂しいものだねえ...」
「はい。でも、何故、それが壊れないのでしょうか?私は、それが不思議で
す」
「まあ、既得権を主張する者が居るからだろう。北朝鮮の体制がぶっ壊れな
いのと同じだ。しかし、こんなことでは、日本という国が、ちっとも面白くない
ね。それに、活力も出てこないし、衰退の一途だ...」
「はい」
「まあ、こっちの方も、何とかしないとね」
「はい!」

「ええ...今回は、ここまでとします!
あ、それから...煮え切らない国会や政党に、デモ行進をかけると言う
のなら、私も是非参加してみるつもりです...」 ...星野 支折...
  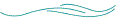   
|
辛
口 時 評

![]()
2002年
![]()


INDEX
![]()

![]()