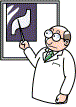アディポネクチン (脂肪細胞が分泌する、“生理活性物質”の1つ)
・・・・・・・・・
アディポネクチン (脂肪細胞が分泌する、“生理活性物質”の1つ)
・・・・・・・・・ 
<肥満による、アディポネクチンの分泌量低下が、
生活習慣病のリスクを増大させます...>

「響子です...ええと、さっそく始めます。マチコ...いいかしら?」
「あ、うん!」マチコは、ミケの頭をおさえた。ミケは首を縮め、目を細めた。
「さ、では...ええ...肥満が生活習慣病を招く、もうひとつのルートを説明します。
それは、アディポサイトカイン(脂肪細胞が分泌する、“生理活性物質”の総称)のひとつ、“アディ
ポネクチン”の減少によって起こります。一口に言うと、そういうことです...」
「ふうん...」マチコが、ミケの頭をひと撫でした。「それだけ?」
「まさか、」弥生が笑った。
「はい。もちろん、説明します...
ええ...他の生理活性物質では、分泌量の増加によって病気が発症することが
多いのですが、この“アディポネクチン”ではその逆になります。
後で詳しく考察しますが、この“アディポネクチン”は、どうやら諸々の“病気の火消
し役のタンパク質”らしいのです。したがって、この分泌量が減少することによって、
病気の方のリスクが増大するというわけですね。そこで、何故、分泌量が減少するの
かというと、脂肪細胞が増大することによって、減少することが観測されています。そ
れも、特に内臓脂肪が指摘されています」
「あ、それじゃあ、肥満になると、分泌量が減少するわけね...」マチコが言った。
「そのとおりです!」響子はうなづいた。「ええ...それじゃ、アディポサイトカインの
ひとつ、アディポネクチンについて、さらに詳しく説明します」
【アディポネクチン】

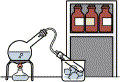


「うーん...何から話したらいいかしら...
最近...大阪大学/細胞工学センターで、脂肪細胞で発現している、遺伝子の
検索が行われました。これは、“ボディーマップ解析”と呼ばれるプロジェクトの一環
で、人体の臓器や細胞で発現している遺伝子を調査・比較し、細胞の種類ごとの機
能を探る研究でした...」
「あのさあ、響子、」マチコが言った。「同じ遺伝子でも、臓器細胞が違うと、違う働き
になるわけ?」
「そうねえ...最初10万個といわれていたヒトゲノムの遺伝子が、3万個ぐらいって
ことになっちゃったわけだし、そういうことかもね。今度、注意して見ていてよ。私も確
認してみるから、」
「あ、うん」
「弥生もね」
「ええ」
「それで...脂肪細胞で発現している遺伝子のうち、約1500個をランダムに調査し
たそうです...その結果、脂肪細胞は、エネルギーを備蓄して飢餓に備える他に、
多彩な生理活性物質を分泌していることが分かりました。これは、すでに述べたこと
ですね」
弥生が、小さくうなづいた。
「さて、こうした研究の中で、脂肪細胞のみで発現している、“未知の遺伝子”に注目
が集まりました...
ええ...こうした研究では、しばしば遺伝子という言葉が使われますが、要はそ
の遺伝子の設計図によって作り出される、タンパク質が存在するということです。これ
は、分かるでしょう?」
「遺伝子と、タンパク質は、同じではないということね?」マチコが聞き返した。
「もちろん!遺伝子は、設計図です。タンパク質は、その図面によって作られた製品
です。つまり、その細胞で当該の遺伝子が発現しているという事は、DNAライブラリ
ーの中から、その遺伝子がピックアップされて、mRNA(メッセンジャーRNA)に転写され、
その細胞のタンパク質製造工場であるリボソームで作られたということです。
今回は、脂肪細胞で発現している遺伝子のうち、約1500個をランダムに調査した
ということですね。マチコ、この意味は分かる?」
「うん」
「はい...
ええ、したがって、そうした特異なタンパク質よりも、そのプロセスの源流にある遺
伝子として扱ったほうが、理解されやすい場合が多いわけですね」
「うーん...そっかあ...」
「それで...ええ、その問題の“未知の遺伝子”ですが、それがアディポネクチンと命
名されたわけです。“アディポ”というのは、前にも言ったように、脂肪のことです。そ
して“ネクチン”とは、代表的な細胞間タンパク質ネクチンからもらったそうです。
さて、この“未知の遺伝子”が、何故それほど注目を集めたかというと、脂肪細胞
の既知・未知の全遺伝子の中で、最も強く発現していたからだといいます。
そこで、色々調べたところ、このアディポネクチンの血中濃度が低下すると、イン
シュリンの効きが悪くなり、“糖尿病”の発症へとつながることが分かったのです。こ
のことは、アメリカのアリゾナ州に住むピマ族についても調査されています。つまり、
肥満と糖尿病患者の多いことで知られるピマ族においても、アディポネクチンの血中
濃度の低い人の方が、糖尿病を発症する例が多かったわけです...」
「うーん...糖尿病ね、」マチコが言った。「そんな風に調べるわけね」
「それと...“動脈硬化”につながる、諸々の細胞現象を抑える働きも確認されてい
ます。つまりこれは、アディポネクチンの血中濃度が低いと、動脈硬化の危険因子と
なるということです。動脈硬化の火消し役が不在だと、動脈硬化になるリスクが非常
に高くなるということですね。それから、このアディポネクチンの血中濃度というのは、
1dl(デシリットル)あたり
0.5mg 〜 1.0mg
と、きわめて高濃度なことも判明しました」
「その、メカニズムはどうなのかしら、」弥生が、ポツリと口を開いた。「火消し役の、」
「ええと...はい...
動脈硬化の初期現象として、炎症をきっかけに、“単球(/炎症の主役)”が血管内皮細
胞に接着するの...この時、“単球”が出す生理活性物質の働きを受けて、血管内
皮細胞が“接着分子”を作り出すわけね...アディポネクチンは、この“接着分子”の
発現を、強力に抑制することによって、この初期現象のプロセスを阻害していくわけで
す...」
「うーん、すると、邪魔をするわけね?」マチコが言った。
「そう!だけど、これだけじゃあないの...
動脈硬化の次の段階では、血管内皮細胞に接着した“単球”が、血管内膜に入り
込み、そこで“マクロファージ(貪食細胞)”へと分化するの...」
「マクロファージというのは、聞いたことがあるわね」マチコが言った。「それは、細菌
の1種かしら?」
「いえ、“マクロファージ”というのは、細菌・異物・細胞の残骸などを、その自分の細
胞内に取り込み、消化する力があるの...風邪をひいた時なんか、初期の段階で、
その菌を食べちゃうわけよ...」
「それでさあ、マクロファージは、細菌じゃないの?」マチコが聞いた。
「そうねえ...別な言い方をすれば、“マクロファージ”というのは、強力な、大型の、
単核細胞ね。仕事としては、炎症の修復や、免疫に寄与するわけ...だから、“貪
食細胞”と言うわけなの。
さっき、“単球”という言葉があったでしょう。これは、“白血球の一種”なんだけど、
細胞組織の中に入ると、この“単球”が、マクロファージになるわけよ。だから、動脈
硬化の次の段階では、“単球”が、血管内膜に入り込み、そこでマクロファージへ分
化すると言ったわけよ...」
「うーん、はい...」
「ええと...何処だったかしら...
あ、そうそう...マクロファージは、その自らの細胞内に、酸化したLDL(/悪玉コ
レステロール)を取り込んで膨れ上がり、プラーク(塊)を形成するわけね。これは、悪
いやつよ。そこで、またまた火消し役のアディポネクチンが登場するわけ...」
「うーん...ややこしいわねえ、」
「もう少しよ!ええ、つまり、こういうことなの...
アディポネクチンは、マクロファージが悪玉コレステロールを取り込む時に使う特殊
な受容体、“スカベンジャー受容体タイプA”の発現を抑制する働きがあるの。これが
うまくいけば、マクロファージは悪玉コレステロールを取り込めなくなり、プラークの形
成もおきにくくなる...つまり、動脈硬化も抑えられるわけ...これでおしまい、」
「つまり、アディポネクチンは、マクロファージの仕事の邪魔をするわけね?」マチコが
言った。
「そういうこと!」
「ここでは、マクロファージは、悪役ですのね」弥生が言った。「正義の味方だと思って
いたのに、」
「そう。ここでは、そういう役回りね」
「うーん...」マチコが言った。「簡単には、納得のできない話よね」
「そうね。私たちとしては、とりあえず全体的な風景が理解できればいいと思います。
“β3-アドレナリン受容体遺伝子”の所でも言いましたが、私たち自身がそのことを
理解しているということは、治療効果が上がるということです。まだ、発症していない
人の場合は、予防効果があがるということですね」
「うーん、そうかしら?」マチコが首を横にした。
「マチコ、ここは大事な所よ」響子は、ゆっくりとマチコと弥生の方に体を向けた。「私
たち人類が、様々な病原菌を克服したり、様々な病気を克服してきたのは、それを
“理解した時”からなの...それを文明の力で“理解した時”、人類は、それを克服す
ることができたの...ペストも赤痢も、」
「うん」
「病気でも、その病気を理解できた人は、その病気を乗り越える時なのよ...エイ
ズ、インフルエンザ、BSE(狂牛病)...どれも今でも怖い病気だけど、私たちはそれを
理解し、日常生活の中で回避できるわけ...もちろん、個人、社会、国家のレベル
で、それぞれ対応できる深度は違うわけですけどね...でも、知るということは、大
事なの...」
「うん!」マチコは、コクリとうなづいた。
「でも、」と、弥生が言った。「ガンはどうかしら?」
「そう...だから、ガンが問題になるわけよ。でも、それを理解することによって、私
たちも発癌物質を回避したり、喫煙をやめたりするわけよ。それから、様々な治療法
が開発されたり、やがては遺伝子レベルでの回避などへも進んで行くと思います」
「うん!」
「さあ、話を進めます...いいマチコ?」
「はい」弥生が答えた。
「この、動脈硬化の火消し役であるアディポネクチンには、実は、さらに他の能力もあ
るのです。例えば、血管の内膜が厚くなる一因として、“平滑筋細胞の過剰増殖”が
あります。アディポネクチンは、この細胞の増殖因子“PDGF”の働きを抑制する作用
があるのです」
「“平滑筋細胞”の...“過剰増殖”ねえ...」マチコが言った。「そんなんで、動脈硬
化になるんだあ...」
弥生は、黙ってうなづいた。ミケが、マチコの足をチョイチョイと引っ掻いた。マチコ
は、ミケの腹を優しく踏みつけ、ぐるぐると振り回した。
「マチコ!」ミミちゃんが、インフォメーション・スクリーンの方で呼んだ。「ボスの車をキ
ャッチしたよ!」
「あら、そう。じゃ、追跡して、」
「うん!」
「しっかりね」
「大丈夫だもん!」
「ええ...いいかしら...」響子が、ミミちゃんの方から目を戻した。
「はい」マチコがうなづいた。
「ええ...このアディポネクチンは...高濃度で血中を流れ、全身を巡っています。
そして、血管壁が傷つくと、血管壁の中(血管内膜)に取り込まれます。そして、そこ
で生じる動脈硬化への病変を、効率よく防いでいるようです...
ところが、内臓脂肪型の肥満になると、脂肪細胞のアディポネクチンの分泌量が
低下し、当然ながら血中濃度も下がります。すると、インシュリンの効きが悪くなって
糖尿病を誘発します。また、動脈硬化の火消し役がいないために、動脈硬化もまた
進行するという次第です...」響子は、マチコと弥生を見、パン、と両手を合わせた。
「それは、要するに、内臓脂肪型の肥満が、よくないということよね」マチコが言った。
「そういうことです!」
<ボス=岡田>
「どう?」マチコが、ミミちゃんに聞いた。
「うん!ずっと、GPSで追跡してきたの!まっすぐ基地の方に来るもん!」
「そう、」
「デジタルマップを解析したら、もうすぐ基地の監視カメラに入るもん!」
「そう...」マチコは、モザイク画像のインフォメーション・スクリーンを眺めた。
「カメラに入ったよ、マチコ...」ミミちゃんが、モザイク画像の中から、基地へ続く雑
木林の画像を拡大した。
「あ、ボスが運転してるよ!窓を開けて、景色を見てる!」
3人は、テラスからガレージの方へ回った。そこへ、ボスの車がのんびりと入って
来た。ボスは、砂利敷きのカーポートの端に車を止めた。あたりに、大量の落葉が吹
き寄せてきている。
「ボス!おはようございます!」マチコが言った。
「おはようございます!」響子と弥生も言った。
「ああ、おはよう!今日は、よろしく頼む!」
「はい!」響子が言った。「ボスがサイバースペースへ来られるなんて、本当に珍しい
ですわ」
「うむ。今回は、私も関心のあるテーマなんでね」岡田は、助手席の手荷物を引き寄
せた。「一応、自分自身の体の管理もあるし...勉強しておきたいわけさ...」
「ボスも、そろそろ体には気をつけて欲しいわね」マチコが言った。
「ああ。それと、たまには外へも出てみたい。晩秋の軽井沢も、悪くないね」
「はい。素敵ですわ」響子が言った。「私は騒々しい夏よりも、秋の軽井沢が好きです
わ」
「ふむ、」岡田は、ゆっくりと車から落葉の舞う地面に降りた。「皇后様の御実家の、
旧正田邸がこの町へ移築になるそうだな?」
「はい!予定地のあたりを、後でご案内しますわ」
「あ、お持ちします、ボス」弥生が、岡田の手から手提げ袋を取った。
「おう、すまんな」
岡田は、みんなに案内され、広い作業ルームに入った。南側に、大きなガラス窓
があった。そこから、部屋全体に外の明かりが入っていた。その右手の西の壁に
は、大型液晶スクリーンがある。電源は入っていなかった。
部屋は小奇麗で、秋の草花の花瓶が幾つもあり、出窓の花器にはカラス瓜が活け
てあった。作業ルームではあったが、いかにも女性が管理している基地だった。
「あの、ボス、」マチコが言った。「今までの講義は見ていたんですか?」
「ああ。一応見ていたよ。君等の、元気な様子も見ていた」
「どうでしたか?」響子が聞いた。
「良かったよ。マチコも、弥生も、なかなか良かった」
「わーい!」マチコは、両手を上げた。
弥生は、微笑して、口に手をやった。
「ところで、車庫にあるグレーの車は、響子さんのかな?」
「あ、はい。そうです」
「私の車とよく似ているな。私の車は、もう10年も乗っているんだが、」
「あ、多分、同じだと思います。トヨタのコロナ。同じ型です」
「そうか...私も新車にしたいんだが、今年もまた無理だな、」
「私も今度は、四輪駆動にしようかと思ってます」
「そうか。冬の軽井沢は、四輪駆動がいいか、」
「はい。みんなで、現在、物色中です」
「うむ。今年は、鹿村へは行かないのかな?」
「まだ、分かりません。清安寺の良安さんから、待っているとメールが来ていますけ
ど、今の仕事がまだ少しかかりますし...」
「そうだなあ、」
「でも、12月には入れば、いけると思います」
「うむ、」








【アディポネクチン遺伝子の変異】 

「ええ...」響子は、ボスの方を向いて言った。「アディポネクチンの分泌量が低下す
ると...インシュリンの効きが悪くなり、糖尿病を誘発します。また、動脈硬化の火消
し役がいなくなるため、動脈硬化も進行します。これは、先ほど説明した通りです。
そこで、では、このアディポネクチンというのは何者なのかということで、内臓肥満
とは関係なく起こる、アディポネクチンの低下を調べてみました。つまり、肥満ではな
い、アディポネクチンの低下で、糖尿病や動脈硬化が起きやすくなるかどうかというこ
とです...
この調査は...話が少し飛躍しますが...具体的には、アディポネクチン遺伝子
の変異を探すことから始めました。そして、4種類の変異(/アミノ酸配列の変わる変
異)を発見しました...あの...この説明で分かるでしょうか?」響子は、ボスに聞
いた。
「うむ...遺伝子変異の調査ということだね...」岡田は言った。「ともかく、話を進
めよう」
「はい...ええ、その見つかった4種類の変異のうち、2種類では、アディポネクチン
の血中濃度が著しく低下していました...」
「うむ...つまり、そのアディポネクチン遺伝子の変異を持った人では、肥満に関係
なく、アディポネクチンの血中濃度が低かったということかな?」
「はい。そう理解していいと思います」
「うーむ...」岡田は、ゆっくりと、マチコと弥生の方を見た。「私が加わると、ペース
が乱れるかな?」
「いえ、」弥生が言った。「ボスにも質問してもらった方が、よく分かると思います」
「しかし、まあ、今までのペースがあるだろう。私は、黙って聞いているとしよう」
「どうぞ!どんどん質問して下さっていいですわ!」響子が言った。「私に分からない
所は、ちゃんと分からないと言いますから、」
「女性だけでやるのは、今回が初めてなのよね」マチコが、腕組みをして言った。「だ
から、大変なのよ」
「そうか...たいしたものだ!」岡田は、全員を見回していった。「いや、君たちも、立
派になったものだ。もう、一人前だな、」
「そうよね」マチコが言った。「私は最初に、ボスと一緒に、尾瀬へ行ったのよね、」
「うむ。あれから何度も、至仏山へ登る計画を立ててみたりしたが、とうとう行かずじ
まいになってるな、」
「あの時は、EPSONのCP-500だったわね、デジタルカメラは。81万画素だった
かしら。あれは、当時、ピッカピカの最新鋭機種だったのよ。81万画素も、当時最大
だったわ」
「うーむ...そうだったな...まだ、35万画素が主流の頃だった。それに、メモリー
も小さかったし、ともかく連射速度がノロかった」
「はい。今は早くなったわねえ。そして、少し重かったわよね、CP-500は、」
「うむ。登山には少々重かったな。軽い機種もあったんだが」
「あの、ボス...」響子が言った。「講義を進めていいかしら?」
「ああ。すまん、すまん。こんな話は、後にしよう」
「はーい!」マチコが言った。「あ、ボス!ポンちゃんに、パーティーの準備を頼んであ
りますから、」
「うむ、ポン助は何処かね?」
「ええと...Pちゃんと、キノコとりに行っています!」


「さあ...いいかしら...」響子が言った。
「うむ、」
「ええと...アディポネクチン遺伝子の変異を持った人では、肥満に関係なく、アディ
ポネクチンの血中濃度が低かった...ということでしたね。4種類の変異のうち、2種
類の変異の人では...と、ここまででしたわね?」
「はい」弥生がうなづいた。
「さあ...この調査では、最も頻度の高かった異変は、約700例中の9例とあります
...このケースでは、アディポネクチンのアミノ酸配列で、169番目のイソロイシンが
スレオニンに変わっていました...これらはいずれも、“必須アミノ酸”ですね...」
「必須アミノ酸て?」マチコが、首を傾げた。
「あ、はい...“必須アミノ酸”というのは、体内で合成できないか、合成が困難なア
ミノ酸を言います。したがって、これは、食物として取り込まなければならないわけで
すね。人間の場合は、8種類あります...」
「響子さん、」弥生が言った。「すると、アディポネクチンは、アミノ酸でできているとい
うことかしら?」
「そういうことです。タンパク質ですから。アディポネクチン遺伝子が、アディポネクチン
という生理活性タンパク質を作るのです。こうしたタンパク質は、20種類ほどの、アミ
ノ酸の直鎖構造で作られています...ただし、必須アミノ酸は、食物として取り入れ
たものを使うわけね。これらの必須アミノ酸が不足すると、ストレスを起こすわけ、」
「うーん...響子、アミノ酸というのは、何よ?」マチコが聞いた。
「あ、アミノ酸というのはね...ともかく、これは、自然界には80種以上が確認され
ています。このうち、人体のタンパク質の合成に使われているのは約20種類ね。細
かいことは、まだ確定できないわけ、」
「ふーん、」マチコが言った。
「分かりました」弥生が言った。「マチコ、このぐらいにしておきましょう」
「うん」
「ええ...じゃ、いいわね...」
「はーい」
「ええと...このケースのアディポネクチン遺伝子を持つ人では、アディポネクチンの
血中濃度が、明らかに低くなっています。この700中の9例の全員が、糖尿病か、も
しくは耐糖能異常となっています。さらに、この9人では、高脂血症、高血圧の合併
率も高く、9人中6人が、すでに冠動脈疾患を発症しています...
これは、肥満とは関係なしに、アディポネクチン遺伝子の変異が引き起こした疾患
です...」
「するとこの人たちは、さあ、」マチコが言った。「肥満とは関係なく、遺伝子の変異
で、肥満症と同じような症状が出たということかしら?」
「まさに、そのとおりです!そうだと思います!ただし、私も、確信を持ってそう言い
切れるわけではありません。このあたりは、まだ最先端の研究領域でしょうし、参考
文献では、こう言っているということですね...これは、SNP(スニップ)といって、
“単
一塩基変異多型”からくるものです。
“単一塩基変異多型”というのは、遺伝子の“個人差”のことを言います。どの人
でも、ゲノムの配列は、ホモサピエンスとして99.9%が一致します。しかし、残り
0.1%が、各個人によって異なるのです...これが、いわゆる“個性”なのです。
そのメカニズムは、まだよく分からないのでしょうが、この“個性”の中に、親の顔
の形の伝承や、遺伝子疾患や、気質や、才能なども含まれるのでしょう...良いも
のも、悪いものも...でも、“良い悪い”は、生物進化の巨大な流れから見れば、そ
れは関係のないことかも知れません...どうでしょうか、ボス?」
「うーむ...響子の言う通りだろう...“進化の袋小路”のようなものも、確かにある
にはある...しかし、それも“進化の旅路”の貴重な1つの事象ということができる。
つまり、この世には、“良し悪し”はなく、切り捨てていいものは何もないのだというこ
とだな...リアリティー(真実)とは、本来そういうものだ」
「はい。ボス、ありがとうございました」響子は、岡田の方に、小さく頭を下げた。「良
い説明をいただきました...
ええと...さて、この参考文献の研究者たちは、“アディポネクチン欠損マウス”を
つくるのに成功しています。そして、アディポネクチンの効果もこのマウスで確認して
います。でも、研究は、さらに続いているわけですね。そして、むろん、今後も多くの
発見があると思います...」
「大変よねえ」マチコが言った。「なるほどね、」
「この“アディポネクチン欠損マウス”というのは、人間の生活習慣病の、いいモデル
マウスになるようですね...
ええ...いずれにしてもですね、遺伝子要因で起こった低アディポネクチンの状態
でも、≪ 糖尿病+高脂血症+高血圧
≫という状況が起こりうるということです...」
「でもさあ、響子、」マチコが言った。「内臓脂肪が肥大化して、蓄積すると、どうして
アディポネクチンの分泌量が低下するわけよ?」
「うーん...実は、そのメカニズムは、まだよく分かっていないようです。ただ、アディ
ポサイトカインの1つに、“TNF-α(腫瘍壊死因子α)”というのがあるんだけど、こ
れがアディポネクチンの分泌量低下の一因と言われています...」
「ふーん...」
「あ、それからね、インシュリンの効き目を良くする薬に、“チアゾリジン系薬剤”という
薬があるの。これを投与すると、アディポネクチンの血中濃度が、4〜5倍も上昇する
というわね...
これらはいずれも、アディポネクチン遺伝子の発現調節部位(プロモーター)に作用
するようです...“TNF-α”は、プロモーター活性を強く抑制
し、“チアゾリジン系薬
剤”では、プロモーター活性を強く促進するということですね...」
「アディポネクチンは、私たちの体には、ジャンジャンあった方がいいわけよね、」マチ
コが言った。
「うーん...でも、私たちの体というのは、総合的なバランスが問題なのよ。善玉と悪
玉は、表裏一体でもあるのよ。お酒だって、飲み過ぎれば、体に害があるわけよ、」
「うーむ...なるほど...」岡田は腕組みをした。「西洋医学的な対処療法と、総合
的なバランスを考える漢方医学があるわけか...面白いな、」


肥満 と
病気の方程式


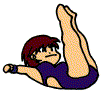

![]()



 INDEX
INDEX
![]()
![]()