|
(2000. 9. 4)
<2>
エントロピー増大宇宙と、生命進化のベクトル
 
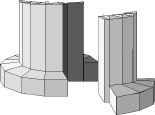 


「あ、高杉塾長、」里中響子は、インフォメーション・スクリーンに映った高杉を見て、軽
く頭を下げた。「お忙しいでしょうか?」
「いや、かまわんよ。何かね?」高杉は、My Work Station
のロビーで立ち止まって
言った。。
「今、“大戦略DNAの攻防”に居るのですが、外山さんがちょっと高杉さんにお聞き
たいことがあるそうです。よろしいかしら?」
「うむ、かまわんよ」高杉は、片手をズボンのポケットに突っ込み、コンソールに手を
伸ばした。「そっちの方も、いよいよ動き出したようだな、」
「はい。私もここを担当するようになると、当分忙しくなりそうですわ」
「うむ。まあ、忙しいのはいいことだ」
「はい」
「高杉塾長!」外山が、スクリーンの正面に顔を出した。「先日はどうも、」
「ああ、外山さん、こちらこそ。それで、聞きたい事というのは何でしょうか?」
「はい。実は、高杉さんがこのページに付けたタイトルのことです」
「ほう...」
「このページの、“大戦略・DNAの攻防”というタイトルです。このタイトルの、意味を
知りたいのですが、」
「ああ、なるほど...」高杉は、天井を見上げた。「もっともなことです...そのタイト
ルを付けた頃、思っていた事は、こういうことでた...DNAの攻防の相手とは、この
宇宙のエントロピー増大そのものだったのです。つまり、熱力学の第2法則/“エントロ
ピー増大”のことです。ご承知でしょうが、この“エントロピー増大”というのは、放って
おくと熱的平衡が進むということで、最終的には宇宙の熱的な死を意味します。熱的
な死とは、あらゆる粒子の熱運動量がゼロになり、極限まで冷えることです。
仮に、この宇宙に死がおとずれるとすれば、それはこの“熱的な死”か、“ブラック
ホールによる死”と言われています。ブラックホールによる死とは、“重力的な死”に
なりますね。これは、宇宙にできた無数のブラックホールが、重力的に共食いを始
め、最後には巨大なたった1つのブラックホールが残るという風景です。もっとも、こ
の最後のブラックホールも、実は蒸発してしまうようです。まあ、いずれにしても、天
文学的スケールでの理論であり、計算ですが...
一方、この熱力学の第2法則“エントロピー増大”は、あらゆる構造や秩序というも
のを破壊し、かき混ぜ、均一化します。つまり、形あるものは、必ず壊れ、滅びて行く
という、あの行程です。もっとも、熱運動量を完全にゼロにすると言うのも、科学技術
的に非常に難しいものがあります。絶対零度は、摂氏零下273.15度ですが、現在
到達しているのは、この絶対零度へ10万分の1ぐらいと言われています。素粒子は
熱運動量を失い飛び回らなくなっても、実は“ゼロ点運動”という振動は続けているの
です。しかし、この振動さえも無くなった時、素粒子は素粒子であるという保証は無
いのかも知れません...
ええ...というわけで、つまりこの“大戦略・DNAの攻防”というタイトルはです
ね...DNAシステムに於ける増殖と構造化と進化という巨大なベクトルは、宇宙の
“エントロピー増大”と拮抗する位置にあるということです」
<ちなみに...熱力学の第1法則は、“質量保存の法則”です...>
「ははあ、すると、“大戦略”というのも、やはりこのエントロピー増大宇宙に拮抗す
る、DNAの進化、構造化、マイナスのエントロピーということですか?」
「はい。そういうことでした。DNAは、進化と構造化の強大なベクトル(力と方向)
を内包
しています。むろん、ビッグバンのかすかな揺らぎから、宇宙の構造化が始まったと
いう宇宙論の考えを、否定するつもりはありません。しかし、生命の発現を“宇宙の
初期条件”に入れると、もう少し違った宇宙のバリエーションが出てくるのではないで
しょうか。例えば、宇宙自体が生命化していく力と、エントロピー増大の拮抗のよう
な、」
「すると、その“宇宙の初期条件”に入ってくる生命の発現とは、どのようなものなの
でしょうか。つまり、具体的に、」
「うーん...私はその方面が専門ではありませんし、そこまで深く考えたこともありま
せん。ただ、これまでの素粒子論的なアナロジーでいけば、生命微粒子、生命波動
のようなものが別にあることになるのでしょうか。しかも、ビッグバン宇宙論と整合性
のとれた形で...」
「なるほど...」
「もっとも、その生命波動とはどのようなものかといわれても、答えは用意していませ
んがね...ただ、“生命”や“意識”や“意思”が宇宙の初期条件に入ってくると、物
理科学はどうなりますかねえ...面白いとは思いませんか?」
「はあ、」
「私は科学者ではないから、こんな気楽なことが言えるのでしょうか、」
「と言うより、難しい問題です...私は、進化とは単純に、この地球生態系という巨
大複雑系が生み出す力、基本的には“学習”と考えていますが...」
「システム進化論のエリッヒ・ヤンツは、“進化の自己超越”と言っています。つまり、
進化とは自らの中で発生し、さらに自分自身をも超えていくものだと、」
「なるほど、“進化の自己超越”ですか...」
「生命の発現を、“宇宙の初期条件”に入れるのは、単純で、明快で、完璧な答えで
す。ただし、いたって安易かも知れません...」高杉は、楽しそうに微笑んだ。
「すると、宇宙開闢(
かいびゃく )の設定段階で、すでに生命の発現がインプットされたとい
うわけですね?」
「ええ、偶然による生命の発現は無しということです...いずれにしても、ビッグバン
をマイナス時間まで遡った物理学というのは、まだ確立されていません。つまり、こ
の我々の“宇宙の初期条件”というのは、まさに我々にはまったくの未知の領域なわ
けです。
したがって、この現世の最大の謎...生命の発現、そして認識の発現、さらに自
己の発現は、宇宙の初期条件にまで還元されても、不都合は無いと思いますね」
「すると、今あるこの宇宙は、“場”として、生命の発現が条件だったと言えるわけで
すか?」
「そういうことになりますねえ...それというのも、波動関数だけでは、この宇宙はお
ろか、物理空間さえも描けないからです。何故なら、その波動方程式を認識し、観察
する意識が必要だからです。それが発見され、観察されなければ、存在しないのと
同じですから、」
「うーむ、哲学ですねえ、これは、」
「しかし、量子力学では、あの“参与者”という概念を導入せざるを得なかったわけで
す」
「なるほど、」
 <計算時間が爆発するアルゴリズム> <計算時間が爆発するアルゴリズム>
<アルゴリズムとは、プログラムを作成する時の解法の手順のこと...>
「ところで、話を戻しますが、外山さんは先日、ヒトを“10万個の変数”(ヒトの全遺伝子数)
を持つシステムと言っておられましたね。そして、計算時間が爆発(計算が膨大になり、実質
的な意味を失ってしまうこと)してしまうと、」
「はい。それは、タンパク質の構造解析においても同様ですね」
「うーむ...何故、計算時間が爆発してしまうような生命システムが、この地球には
溢れ返っているのでしょうか?動物ばかりでなく、雑草や地中の微生物にしても、そ
の総量は膨大なものです。そしておそらく、実際の生物界においては、そんな途方も
無い計算は全く行われていないはずです。それでも、全てがきわめてダイナミック
に、スムーズに流れている...これは何故でしょうか?」
「私も、同感ですですが、そこが難しい...」外山は、インフォメーション・スクリーンの
中の高杉を見つめた。「実質的にどのようなことが行われているのか?そこが知りた
いですね」
「私は先ほども言ったように、それをスムーズにさせている要因は、“意識”、あるい
は“意思”だと思いますね。計算時間が爆発してしまう膨大な情報量の中に、“意識”
を流すのはきわめて有効です。例えば、我々だって普通、目の前に流れている小川
の水を、流体力学やコンピューター・シミュレーションで認識しているわけではありま
せん。人間にとって、小川はサラサラ流れ、キラキラ陽光が輝き、気持ちよく冷たい。
ただ、それだけでいいのではないでしょうか。
つまり、10万の変数を持つシステムをスムーズにコントロールしているのは、“個
体”や“種”や“生態系”に流れる、“意識”ではないかということです」
「うーむ...」外山は両手を組み、口の上へ持っていった。
「私は、このホームページで、“36億年の彼”という概念を考察しています。これは読
んで字のとおり、地球生命圏の時空を越えた全体であり、この生命圏の人格とも言
えるものです。最終的には、この超越的な意識が、地球生命圏全体を覆っているの
ではないかと、」
「なるほど、」
「むろん、私の思いつきの意見に、賛成していただけなくてもけっこうですがね。しか
し、計算時間が爆発してしまうのも事実でしょう」
「はい、」
「どうなのでしょうか...外山さん。生命体の発現というものは、DNAの情報だけで
可能なのでしょうか?」
「と、言われますと?」
「例えば、イカやイワシ。これらは、いくら食べられても“種”を残していけるように、大
量の卵を産みます」
「ええ、」
「一方、有袋類のカンガルーなどは、子供をかなり長い期間お腹の袋の中に入れて
います。あるいはある種のアメーバなどは、乾燥等の危機に直面すると、自らが犠
牲になってカプセルを作り、わずかな仲間をその中に入れて“種”を守ります。このよ
うに、全ての生物種において、個体を越えた“種”としての戦略というものを持ってい
ます。また、このように、多種多様であるために、“種”があるといってもいいのかも知
れません」
「はい、確かに、」
「つまり、そこに、“種”としての共同意識体”があり、時間軸を超えた“形態形成場”
が展開していると考えます」
「形態形成場理論ですか」
「つまり...“種”の共同意識体や、形態形成場、生態系...その上位ステージに
ある“36億年の彼”も、個体の発生や進化に深く関与していないかということです。
DNAの遺伝子発現の光景も、それがDNAコードだけで作用するだけでなく、上位ス
テージや下位ステージの情報系と深く共鳴している戦略的部分があるのではないか
と...」
「否定できない部分はありますね。しかし、そこにどのようにアルゴリズムを求めるの
ですか?」
高杉は、黙ってスクリーンの中でうなづいた。
「具体的にどうでしょうかねえ...」外山は、首をかしげた。「二元的・二進法のコン
ピューター言語とは、およそ対極的な位置にあるような気がしますが、」
「ここは、生命情報科学(バイオインフォマティックス)の外山さんに、是非うかがいたい所で
もあるわけです」
「まあ、私個人としては、色々と考える所はあります...例えば、“生命単位”のよう
なものを考えて、それで生命を因数分解できないかとか、」
「具体的には?」
「コンピューター内に作る、最小単位の生命プログラムのようなものでしょうかね。生
物体の形態的特徴は、まず有機物であり、アミノ酸であり、タンパク質です。それか
ら、増殖と呼吸、食物やエネルギーの吸収、そしてエントロピーの排泄...ま、呼吸
をしないウイルスのようなものでも、増殖はするわけですが...」
「それなら、現在のスタイルのコンピューターでも、何とかなるわけですか...」
「まあ、考えるのは自由ですからねえ...」外山は、眼鏡の縁を押さえた。「それにし
ても、生命は複雑です...しかもそれが、局所生態系、地球生命圏、そして銀河宇
宙へ開いている開放系システムになっているわけですから...」
「確かに、複雑です。しかし、その膨大な関係性を単純化させているのが、“意識”と
“ストーリイ性”ではないでしょうか」
「高杉さんが先日言っておられた、超個性についても、同じベースでしょうか?」
「はい。生物体には個としての振る舞いと、種としての振る舞いがあります。個体を
超える超個的(トランスパーソナル)な部分は、確かにあります。最も分りやすいのは、私た
ちがそれぞれ男性だということですね。これは個体を越えて、目に見えない情報力学
で、女性と対になっている部分です。これが、私たちの持つ超個的な部分の一端で
す。もっとも、雌雄で分かれる生殖細胞などは、DNAの中ではっきりと認識できま
すがね。しかし、問題なのは、もう少し上の、“種の共同意識体”です。もっとも、人類
のそれは、巨大な人類文明を形成しているわけですが、」
「どうも、高杉さんの視点というのは、私などよりもだいぶ広い範囲を見ておられるよ
うですねえ、」
「そうかも知れません。私は専門分野を持ちませんから」
  
「あの、この辺でよろしいかしら?」里中響子が、インフォメーション・スクリーンに体を
入れて言った。「そろそろ本題の方に移りたいと思いますが、」
「ああ、うむ」高杉は言った。「よろしく頼みます」
「はい」
「高杉さん、どうもありがとうございました。また、ゆっくりと話したいですねえ」
「私の方も、聞きたいことが山ほどあります」
「あの、高杉塾長、後でいらっしゃいませんか?」響子が言った。「今日の休憩は、ポ
ンちゃんにビヤガーデンの出前を頼んであります。おそらく、ビヤガーデンはこれが今
年最後になるのじゃないかしら」
「おう、じゃあ、ぜひ行かなくちゃならんな」
「はい。お待ちしてますわ」
「それじゃ」外山は、手を上げた。
「これからが大変だね」
「はい」


|
![]()
![]()
![]()

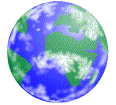
![]()

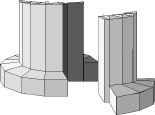

![]() INDEX
<新体制スタート・・・対話形式/2000.8.21>
INDEX
<新体制スタート・・・対話形式/2000.8.21> ![]()
![]()

![]()