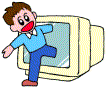

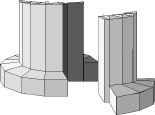

「ええと...」高杉が、窓の方から視線を戻して言った。「それでは...
響子さんの要望に従いまして...量子情報科学における、“量子もつれ”について、
その周辺のことを、事前に簡単に説明しましょう。“量子もつれ”という現象については、
それから説明します」
「あの、」響子が言った。「高杉さん...
量子力学と...量子情報科学は、同じ系列のものと考えていいのでしょうか?」
「同じステージの上にあるものです...
しかし、量子力学は、20世紀初頭のものであり、量子情報科学は21世紀初頭のもの
ですね。約1世紀/100年の開きがあるわけです。今、まさに、新たに量子情報科学と
いう名前を冠し、新しい飛躍の段階にあるわけです。
特に、情報テクノロジーとしての、全く新しいステージの開拓が期待されています。こ
の原動力になっているのが、これから話す“量子もつれ”という現象の、科学的確証と、
そのテクノロジーの革新的展開だということでしょう...
本来の量子力学そのものは、現在、“標準モデル”と重力理論の一般相対性理論の
統合を進めています。自然界に観測される4つの力のうち、“電磁気力”、“弱い相互作
用の力”、“強い相互作用の力”は、“標準モデル”で統合されています。最後に残ってい
るのが“重力”なのです。
そうした中で、最も有力視されているのが、“ひも理論”とか、“超ひも理論”とか呼ば
れているものですね。当ホームページで取り上げている《M理論の窓》もその1つです」
「はい...量子情報科学は、そうした量子力学とは別に、報科学の方に特化した領域と
いうことですね」
「そういうことです...
さて...この“量子もつれ”という現象ですが...量子力学における、“基本的な奇妙
な性質の1つ”として、最近、正式にカウントされたようです。粒子と波の“相補性”や、
“不確定性原理”や、“参与者の導入”といった、量子力学独特の奇妙な現象の1つとい
うことです。
したがって、“何故だ?”、と聞かれても困ります。つまり、こうした現象が、まさに、私
たちの眼前に展開する世界で、“観測されている”と、科学的に確証されたと解釈してく
ださい。つまり、“この世の風景”で展開している、“理屈抜きの事象”...“物理的解釈
の1つ”として...カウントされたということでしょう...」
「理屈抜き...ということですね?」
「まあ...
理屈があるなら、それを追求するのが、物理学者の仕事です。しかし、全てが、理屈で
割り切れるものではないし、説明しきれるものではないのです。
例えば、“私”というものを、全て説明することなど、およそ不可能でしょう。しかし、この
相互主体性の世界では、それぞれの“私という存在”を、原則的にOKと認め合っている
ことによって、社会性が成立しているわけです...つまり、そういうレベルの話です」
「ふーん...つまり、“量子もつれ”とは、量子力学における“不確定性原理”などと、同
じレベルの話だということですね、」
「そうです...
しかし、実際のところ、“量子もつれ”の情報は、一般的にはまだあまり出回ってはい
ません。私も参考文献で、始めてこの言葉を知った程度です。その推理の上で話してい
ます」
「はい、」
「そうですねえ...
“不確定性原理”と非常によく似た言葉で、“不完全性の定理”というのがあります。
“不確定性原理”は、ご存知のように、ハイゼンベルクが提唱したものです。一方、この
“不完全性の定理”というのは、数学者のクルト・ゲーデルが提唱したものです。
この“不完全性の定理”によると...“いかなる包括的な論理体系も、自己矛盾せず
には証明できない前提を、必ず1つ以上は持っている”、ということです...彼は、この
定理の中で、それを数学的に証明したわけです。これもまた、量子力学に、大きな衝撃
を与えたようです」
「うーん...」響子が、口に拳を当てた。
「まあ、それが具体的にどのようなことを証明したのか、私は知りません...
しかし、当時の学会では、支持されています。したがってここでもまた、デカルト/ニュ
ートンの“絶対性”というものが崩れ...科学哲学においても、“相対性”の時代に入っ
たと言われています」
「それは、何時のことかしら?」
「クルト・ゲーデルが、この論文を発表したのは、1931年です。まさに、あの量子力学の
黎明期においてです。まあ、これは数学的な証明だけに、大きな衝撃だったと思います
ね...」
「はい、」
「“この世の風景”というものは...私たちの認識の鏡に、時間軸上に展開されて、スト
ーリイ性に解釈され、認識されるわけですが...それが真の姿というわけではないので
す...
第一に、時間を超越した、直接的認識というものもあるわけです。明らかな予知や、過
去知などがそうですね。また、空間を超越した、直接的認識というのも、確かに存在しま
す。透視などがそれです...
すると、それでは、“この世の時空構造”とは、どうなっているのか、という問題になり
ます...謹厳な物理学者は、こうした問題は避けたいところでしょうが...さて、何時ま
でそんなことを言っていられるでしょうか...」
「そうですね、」
「また、“私”という主体性について...また、相互主体性世界の成立についても、完全
に説明されているわけではありません。リアリティーは、何故、“巨大な、唯一絶対の全
体性”なのか...
こうした“認識主体”と物理空間との矛盾が...具体的に、“量子もつれ”というような
奇妙な現象として、素粒子の世界に析出してくるのでしょう...“相補性”や“不確定性
原理”も、そうなのかも知れません...
つまり、物理空間も、一種の人間的なバイアス(偏向)のかかった仮想空間であり、1つ
の人間的な解釈にすぎないということです...」
「うーん...はい...」
「さて...肝心の、“量子もつれ”の説明をしましょう...」高杉は、椅子をずらし、両手を
組み合わせた。「いつまでも、脱線しているわけにはいきません」
「はい、お願いします」
≪量子もつれ≫

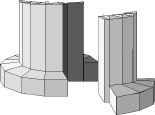



「例えば...」高杉が言った。「“量子もつれの関係”にある、2個で1組のサイコロが、何
組かあると考えて下さい...それから、その各組のサイコロを、1個づつに分断し、2つ
のグループに分けます。ここまでは、いいですか?」
「はい...
つまり、磁石のように、S極とN極でくっついたサイコロのペアが、何組かあり...その
ペアを、別々にして、2つのグループに分けたということで、いいでしょうか?」
「そうですね、いい説明です...
ただし、それは磁石でペアになっている関係性ではなくて、“量子もつれ”でペアになっ
ている関係性です...それを、切り離し、別々の2つのグループに分けたというアナロジ
ー(類比)です...」
「はい...」
「さて、そこで...
その2つのグループのサイコロを、それぞれ別の場所で振るわけです...すると、どう
いう現象が起こるか...いいですか、ここが肝心な所です...
<“量子もつれの関係にあるサイコロ”では、“同じ組のサイコロ” は、
別々の場所において、何度振っても、同じ目が出るのです...>
まあ、もしこんなことを、マジックで見せられたら、実に不思議なわけです...“量子
もつれのサイコロ”を両手に分けて持ち、一方のサイコロを振っていく。それから、もう
一方のサイコロを振りながら、その目をどんどん当てていくことが出来るわけです。しか
も、科学的に、厳密に、正確に言い当てて行けるわけです...」
「ほんとかしら?何故、そんなことが起こるのかしら?同じ組みのサイコロは、同じ目
が出るわけですね?」
「そうです。そして、量子情報科学というのは、この性質を応用して、新展開していくこと
になります。基礎科学から、量子コンピューターのデバイス上へ、新展開していくことにな
ります」
「ふーん...でも、そんなことが、本当にあるのかしら?」
「まあ、“何故か?”とはは聞かないでください...
つまり、それが、“量子もつれ”なのです。もし、マジックで、タネ明しをするとすれば、そ
れらのサイコロは、実は“量子もつれの関係”にあるんですよ、という説明になるわけで
す」
「うーん...」響子は、両手を組み、首を斜めにした。「何故かしら...?あ、ごめん
なさい...この質問は、ナシですわね...」
「いいですか...
最初に振ったサイコロは、これはまあ1/6の確率で、ランダムに目が出ます。次に、
残った方を振ってみる。すると今度は、何度振っても、同じ目になる。と、まあ...こうし
た現象が、“量子もつれ”というわけですね...
しかも、この現象は...もし一方が、約4億光年も離れた、アルファ・ケンタウリ星に
あったとしても、“しっかりと成立する”と言い切っています。ここが、基礎科学のすごい所
です。空間に影響されないのです。距離に影響されないのです。そこに介在する相互作
用の、力学が無いわけです...」
「あ...基礎科学において、そうだというわけですね...」
「そうです...だから、すごいのです。これが、つまり、“量子テレポーテーション”につな
がるのでしょう...」
「うーん...」
「では、何故、そんなことが断言できるのか...
それは、基礎物理学における長年の研究成果から、“それは正しい”と証明されたか
らです。むろん、現在の量子力学における話です。それが、“量子もつれ”という現象なの
です...電磁波が、“粒子”であり、“波”でもあるというのと同じように、それが事実とし
て観測されているということです。
理屈ではなく、こうした現象が、キッチリと観測されていているということなのです。そし
て、それが、すでに“量子コンピューター”への応用の段階に入っている、ということなの
です...」
「はい...」響子が、唇にコブシを当てた。
「とは言っても...これは量子世界での話です...
実際には、このような大きなサイコロで、観測されているわけではありません。つまり、
“量子もつれ”は、あくまでも“量子世界の風景”なのです。ただし、量子の世界が、ナノ・
スケールや人間・スケール、マクロ・スケールに、全く影響を及ぼさないかというと、そん
なことはありません...
粒子加速器などの高エネルギー物理学は、素粒子を極限まで加速し、マクロの宇宙
物理学と密接に関係しています。宇宙物理学のビッグバン理論などは、宇宙線やこうし
た粒子加速器から、検証が進んでいるわけですから、」
「はい、」
「つまり、こうしたミクロの世界は、マクロの世界とは、全く別の世界というわけではない
のです」
「うーん...」

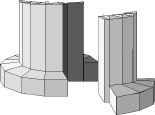



「余談ですが...
現代物理学は、量子力学と一般相対性理論のダブル・スタンダードだと言われます。
一般相対性理論は重力理論なのですが...“標準モデル”に、この重力理論がうまく“く
りこみ”がてきないのです。
したがって、ミクロ世界は量子力学が支配し、マクロ世界は一般相対性理論が支配的
だと言われています...それから、このミクロ世界とマクロ世界の中間にあるのが、今
話題のナノ・スケールの領域です。これは、生物でいえば、DNAやタンパク質のスケー
ルですね。
ちょうどこのあたりが、量子力学と一般相対性理論の揺らいでいる、“境界領域”とい
うことらしいですね、」
「はい...」
「私は、専門家ではありませんが...
面白いのは...ここはちょうど、“命のスケール”だということです。実際、今、応用分
野で話題になっているのは、“カーボン・ナノチューブ”などの実用化ですが、やがて膨大
な有機物がこの領域の研究分野に入ってくるでしょう。
タンパク質や、糖鎖などの膨大な情報が、ナノ・テクノロジーに合流してくるでしょう。本
当の意味での、生物体の解明が始まることになります...」




「高杉さん...」響子が言った。「このサイコロの話は、それでは量子世界では、実際に
起こっていることなのですね?」
「もちろんです...実際に起こっていることが、観測されているのです...
原子やイオンや光子など、量子世界においては、“量子もつれ”は現実に起こっていま
す。それが、実験などで突き止められているわけです。こうしたことが実体化し、定量的
に観測され、それが体系化されてきたことで...“量子情報科学”という、1つのエキサ
イティングな学問分野が、立ち上がって来たのでしょう」
「はい...でも、世界観まで変わって来ますわ」
「その通りです...
しかし、“そんなバカなことがあるか”と思う人は、まず、真剣に考えてもらいたいと思
います。そう言っている...“私とは、いったい何者なのか...いったい、ここは何処で
あり...なぜ私は、ここに存在しているのか...”と...」
「そうですね...」
「私たちにとっては...
“自分自身の存在”こそが、まず、この世界における最大の謎なのです。その、“自分
という不思議な座標”から、あらためて、21世紀の基礎科学のステージを眺めてみても
らいたいと思います。不思議といえば、全てが不思議な世界です。そうした不思議さに比
べたら、“量子もつれ”など、どれほどのものでしょうか...」
「はい...」
≪量子テレポーテーション≫


「さて、」高杉が言った。「つぎに、“量子テレポーテーション”ですが、これは“量子もつ
れ”という基本的な性質を応用します。色々なバリエーションが考えられるようですが、こ
のことについては、今後考察していきます...これには、時間的熟成が必要です...」
「はい...」
≪量子テコンピューター≫
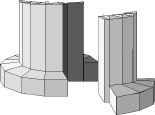
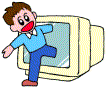


「“量子テレポーテーション”技術の応用で、最も実現性が高いのが、“量子コンピュー
ター”です。
これは、“量子もつれ”の“光子の偏光”が、縦偏光と横偏光の“重ね合わせ”で表現
でき、“量子ビット(キュービット)”といいます。現在考えられているは、“量子コンピューター”
における、この“重ね合わせ”が、1つのポイントのようです...」
「うーん...よく分りませんわ...」
「まあ...これだけ言っても、何のことか分からないと思います...
これも後で、詳しく考察していくことにします。また、今後の量子情報科学の展開で、
少しづつニュースのような形で、私たちの耳にも入ってくると思います...」
「はい、」
「これからは、社会のあちこちで、今言ったような耳慣れない言葉を聞く機会が増えてくる
と思います。しかし、一度に全てが理解できるわけではありませんし。少しづつ、21世紀
の基礎科学として、未来の科学文化として、量子情報科学を吸収していって欲しいと思
います」
「はい!
今、まさに、新しい科学時代が動き出そうとしています。どうぞ、今後の展開に、ご期
待ください...」







 量子情報科学のスタート
量子情報科学のスタート 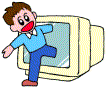
![]() INDEX
完全リニューアル
・・・・・
推敲
(2007. 6.14)
INDEX
完全リニューアル
・・・・・
推敲
(2007. 6.14) 