 Twitter
仏教/雑学
Twitter
仏教/雑学 
【 道元 ・ 芭蕉 ・ 達磨 ・・・ 藤原俊成 】 (1~ 162)
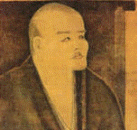
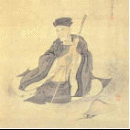


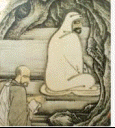
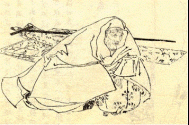
| MENU/ボスの展望台/ボスのTwitter/(仏道)/仏教・雑学/【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】 |
|
【 道元 ・ 芭蕉 ・ 達磨 ・・・ 藤原俊成 】 (1~ 162)
|
| トップページ/New Page Wave/Hot Spot/Menu/最新のアップロード/ 担当: ボス= 岡田 健吉 |
|
2016年 ~2017年 |
|
| 11月25日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(3) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(1) に詠んでいます。
《仏教/・・・雑学》・・・(4) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(2) いです。仏道を修行する道元禅師にとって、<思へばくやし>となるわけです。 一方、藤原俊成は…還暦の頃に大病して出家し…
|
| 11月26日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(5) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(3)
おそらく道元禅師は、平安王朝末期の大歌人である、藤原俊成のこの歌に接した事が あったのかも知れません。 そして… 江戸時代/元禄の頃の俳人/松尾芭蕉は…逆に、その風雅の中に没入し…
《仏教/・・・雑学》・・・(6) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(4)
仏道の立場から見れば、これは<風雅への妄執(もうしゅう/悟りきれず、心の迷いによってあくまで 離さないでいる執念)>であり、<限りない執着(しゅうちゃく/ある物・事に強くひかれ、深く思い込んでどうし ても忘れ切れないこと)>であり、<悟りとは対極>にあるものです。 芭蕉は…四季の風雅に<深く・・・恋焦がれ>、ある意味で、苦しい風狂(ふうきょう/風雅 に徹し他を顧みないこと)の旅をしていたのです。 辞世(じせい/この世に別れを告げること)の句は次のようなものです…
《仏教/・・・雑学》・・・(7) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(5)
までも<生前最後の句>と言います。 芭蕉は…元禄 7年9月29日の夜、突如、下痢を発病し、病床に就きます。 10月5日に、大阪蕉門(/大阪における蕉門・・・松尾芭蕉の一門)の重鎮の1人/之道亭(しどうてい/ 槐本之道(えもと・しどう/大坂道修町の薬種問屋の主人。伏見屋久右衛門。芭蕉の最期を看取った1人。)の<亭>/宿 所・・・眺望や休憩のために高台や庭園に設けた小さな建物。)が、手狭なため…
《仏教/・・・雑学》・・・(8) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(6)
8日深更(しんこう/夜ふけ、深夜)、呑舟(どんしゅう/蕉門の1人)に墨を摺らせてこれを作句した、と いいます。 芭蕉といえば…江戸日本橋や、 江戸深川の芭蕉庵などを想起しますが、元々は忍者の 里/三重県伊賀市の生まれです。『奥の細道』の終点も…
|
| 11月28日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(9) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(7)
に近いわけです。 芭蕉を深く尊敬していた俳人/与謝蕪村もまた…摂津/大阪の生まれですが、江戸日 本橋あたりに出て来て、やがて西へ流れ、京都に居住します。 芭蕉は…どちらかと言えば<崇高(すうこう/気高く偉大なこと)>…
《仏教/・・・雑学》・・・(10) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(8)
さて… 道元禅師の話にもどりますが、道元は…
《仏教/・・・雑学》・・・(11) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(9)
風に乗せて歌っています。
芭蕉坐像図/白鴎画 (江東区芭蕉記念館所蔵) ネットより画像借用 《仏教/・・・雑学》・・・(12) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(10)
仏頂和尚が、江戸深川の芭蕉庵を訪ねた折の句で、これにはよく知られたエピソードが あります。 この句の<水の音>は…『無門関(むもんかん)・第一則/趙州狗子(じょうしゅうくし)』の… < ・・・・・・・・・・・・『無門関』 は、こちらへどうぞ>
芭蕉坐像図/白鴎画 (江東区芭蕉記念館所蔵) ネットより画像借用 《仏教/・・・雑学》・・・(13) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(11)
この公案/『無門関・第1則』 は、こういうものです… 「犬には仏性が有るでしょうか、それとも無いでしょうか」
「無!」と趙州は答えた。>
芭蕉坐像図/白鴎画 (江東区芭蕉記念館所蔵) ネットより画像借用 《仏教/・・・雑学》・・・(14) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(12)
・・・今も響き続けて>…います。 さて… それ程の芭蕉ですが…何故、深い心境の分水嶺から、<風雅への妄執(もうしゅう)>へ と、<身を沈めて行った>のか。それは、おそらく…
芭蕉坐像図/白鴎画 (江東区芭蕉記念館所蔵) ネットより画像借用 《仏教/・・・雑学》・・・(15) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(13)
た、留学した)沙門(しゃもん/仏教の修行僧、サマナ)/道元>とは、違う所なのでしょう。 芭蕉は… 俳人であり、<衆生救済(しゅうじょうきゅうさい)>などのテーマはなく、旅を終生の友とし、各 地に存在する蕉門(しょうもん/芭蕉門下の俳諧の弟子)を巡り、俳諧道を究める人生だったので しょう。<四季の風雅に殉じるのも・・・覚悟の上>…と。
|
| 12月 2日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(16) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(14)
<風雅への妄執(もうしゅう)/風雅への・・・苦しいほどの恋>ですから…その深淵は見 えずとも、ある程度の理解は可能です。 では…道元禅師の、 <思えばくやし 色にめでけり>という心象風景(しんしょうふうけい/現実の風景ではなく、心の中で 思い描いている風景)は…どう理解すべきでしょうか。全く、逆の立ち位置の主張が…<仏道 への邁進(まいしん/まっしぐらに突き進むこと )>と、言います。
《仏教/・・・雑学》・・・(17) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(15)
平安王朝末期の大歌人/藤原俊成も、鎌倉時代の道元禅師より以前に、歌に詠んでい るわけですから…これは間違いのない、<仏道の・・・王道>と言えるものです。 若輩者/私…に言えることは… 理解できることではないから…修行が必要となり…悟りに至る道が示されている…という 事です。 『無門関・第41則/達磨安心』 では… 禅宗の初祖/…菩提達磨(ボダイ・ダルマ)/…壁観(へきかん/壁を見る)バラモン(バラモン教の僧侶) は…
《仏教/・・・雑学》・・・(18) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(16)
<九年面壁(くねん・めんぺき/9年間にわたる面壁座禅)といわれる・・・壁面座禅(へきめん・ざぜん/ 壁に向かって座禅すること)>をしています。 その初祖/達磨は、<花・紅葉・冬の白雪>を見ていたわけではなく、<尾上の桜> を見ていたわけでも、ありません。 つまり、9年間も… 藤原俊成や道元禅師の言う所の、<色>…を愛(め)でていたわけではないのです。で は、何を見ていたのか?
《仏教/・・・雑学》・・・(19) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(17)
一言でいえば、<空(くう)>なのでしょう。 しかし…その<空>を説明するのは、非常に難しいのです。 <一切皆空(いっさい・かいくう)>とも…仏教では言います。 これは… <一切の存在は・・・すべて固定した実体ではなく・・・空である>…と言います。これ が、【仏教の根本教理】 なのです。
|
| 12月 4日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(20) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(18)
<色即是空(しき・そく・ぜ・くう)>とあり…<色/しき>は<即/すなわち>、<是/これ >、<空/くう>である…とあります。 さらに、<空即是色>(くう・そく・ぜ・しき)と、逆さにしてくり返しています。 その前文には…<舎利子(しゃ・り・し) 色不異空(くう・ふ・い・くう) 空不異色(くう・ふ・い・しき)> とあるわけですから、何度も何度も…
《仏教/・・・雑学》・・・(21) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(19)
色は空に異らず、空は色に異らず・・・
色はすなわちこれ空にして、空すなわちこれ色なり・・・> 釈尊/お釈迦様/仏陀が…弟子/舎利弗(しゃりほつ/釈迦10大弟子の1人。特に、舎利弗と目連を、 釈迦2大弟子と呼ぶ。)に<空>を説いている、くだりです。道元禅師が、<思へばくやし・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(22) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(20)
これを、さらに具体的に言えば… <あらゆる迷妄の無くなった・・・空の境地>に至れば…<一切の仮の姿の現象/ 色(しき)が・・・実相/仏の世界の真実の存在・・・> …として見えて来る、ということです。 それにしても… これは、単に言葉として理解しただけです。それで済むなら、修行は不要なのです。道元 禅師の 『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)/画餅(がびょう)』 に、こんなくだりがあります…
《仏教/・・・雑学》・・・(23) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(21)
そのようにして、一枚の仏を描くのであるから、一切の仏は、みな画仏(がぶつ)であ
る。一切の画仏は、みな仏である・・・〉 <色や空の・・・相・・・>も、長い修行によって、見えて来るわけです。しかし禅宗には、 <頓悟(とんご/修行の階梯(かいてい)を経ず、ただちに悟りを開くこと。)・漸悟(ぜんご/順を追って次第に悟りに 近づくこと)>がある様に…
|
| 12月10日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(24) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(22) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (1)
【無門関・第41則/達磨安心】 が取り上げられたので…それについて、簡単に考察し て置きましょう。 室町時代の…禅僧/水墨画家/雪舟(せっしゅう/備中(/岡山県の西部)に生まれ、京都/相国寺で修 行した後、大内氏の庇護のもと周防(すおう/山口県東南半分)に移る。その後、遣明船に同乗して中国(/明)に渡り、李 在より中国の画法を学んだ。)が… その場面を描いた有名な絵/『慧可断臂図(えかだんぴず)』(/国宝)があります。
(『慧可断臂図』(えかだんぴず)/国宝 (重要文化財から・・・2004年に国宝に指定。) 禅宗の初祖・達磨が少林寺において面壁座禅中、慧可という僧が彼に参禅を請うたが許されず、自ら左腕を切り落 として決意のほどを示したところ、ようやく入門を許されたという有名な禅機の一場面である。リアルにあらわされた 面貌と一点を凝視する鋭いまなざし、そして動きの少ない構図が、画面全体に息苦しいまでの緊張感を生み出し ている。) 《仏教/・・・雑学》・・・(25) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(23) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (2)
<-- 菩提達磨は壁に向かって坐禅していた。雪の中に立ちつくしていた二祖は、腕を切 って言った。 「私の心はまだ安らかではありません。師よ、願わくば安心させて下さい。」 達磨は言った。 「心を持って来なさい。安らかにしてあげよう。」
《仏教/・・・雑学》・・・(26) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(24) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (3)
「心を求めましたが、ついに得る事ができませんでした。」 達磨が言った。 「お前のために、安心し終わった。」 -->
二祖/慧可(えか/・・・はじめは神光と呼ばれていた)が、長年の血のにじむ様な苦行の末、洛陽 郊外の嵩山(すうざん)少林寺の、菩提達磨(ぼだいだるま)/壁観バラモンに見(まみ)えた時の 経緯です。
|
| 12月11日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(27) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(25) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (4)
言います。 長年の決死の求道も虚しく…壁観バラモンに参禅を求めて立ち尽くすという、絶望感を味 わった者でなければ、容易には理解できないのかも知れません。 釈尊/釈迦牟尼尊者も…<6年余の・・・空前絶後の苦行>の中で…
《仏教/・・・雑学》・・・(28) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(26) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (5)
絶望の姿で、慧可/神光は昼も夜も、菩提達磨に教示を請うて、立ち続けていました。 一方…<九年面壁>の達磨は、それを許さず、意に介しません。冬/十二月九日の夜、 嵩山(すうざん/・・・中国の河南省鄭州市登封にある )に大雪が降りました。
|
| 12月12日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(29) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(27) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (6)
に、達磨も哀れに思い、声を掛けました…
「師よ、願わくば慈悲(じひ)をもって法の門を開き、われら衆生を救って下さい」
《仏教/・・・雑学》・・・(30) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(28) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (7)
「諸仏無上の妙道は、行じ難いところをよく行じ、忍び難いところをよく忍んで、永く 精進して初めて得られる。 小徳小智の身で軽心慢心をもって、真の教えを得たいなどと願うは、おこがましい。 労しても、甲斐(かい)のないことだ。」
《仏教/・・・雑学》・・・(31) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(29) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (8)
斬り落し、これを師の前に置いた。 師は彼の法にかなった素質を認め・・・ 「諸仏は最初に道を求める時、法のために身体のことは顧(かえり)みない。今、お前 は私の前で自分の臂を断った。お前の求道の真はよく分かった。」
《仏教/・・・雑学》・・・(32) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(30) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (9)
神光が尋ねた。 「諸仏の法を聞くことができましょうか、」 「諸仏の法は、人に従って得られるものではない」 「私の心はいまだ安らかではありません。師よ、どうか安らぎをお与え下さい」
の伝記を収録している。多くの禅僧の伝記を収録しているため、俗に<1700人の公案>と呼ばれているが、実際に伝の あるものは965人です。現在も、禅宗を研究する上で代表的な資料。)にあり…
|
| 12月13日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(33) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(31) ★ 【無門関・第41則/達磨安心】 (10)
鋭く、求道の真を伝えています。 菩提達磨は面壁座禅で<空>を見ていたわけですが…【無門関・第41則】はこういう 次第で、<空>と直接的な意味での関係はありません。究極的には、<悟る>というこ とですが。
|
| 12月16日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(34) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(32)
芭蕉の<風雅への妄執(もうしゅう/悟りきれず、心の迷いによってあくまで離さないでいる執念。)/魔心 (ましん/・・・魔: 一般に、人の心を惑わす悪鬼や災いをもたらす魑魅魍魎、人を一事に熱中させるもの/心魔: 仏教で 心の内部の障害)>とはどう解釈すればいいのか。 <風雅の・・・限りない肯定/共感>は、<限りない・・・現実肯定>であり…それは 禅道とも共通するものです。 芭蕉は仏頂和尚(ぶっちょう・おしょう)に師事しましたが、鎌倉/円覚寺(/臨済宗円覚寺派の大本
山。鎌倉五山第二位に列せられる。)/大顚和尚(だいてん・おしょう)とも親しかった様です。 ★ 仏頂和尚(ぶっちょう・おしょう/ 根本寺・第21世住職の仏頂和尚は、鹿島神宮との間で領地争いがあって、その訴訟のため江戸に滞在することが多かっ たようです。その時は、根本寺の末寺であった江戸深川の臨川庵(/18年後に臨川寺)を使った。芭蕉の有名な句/ <古池や かわず飛び込む 水の音>は、仏頂和尚が深川の芭蕉庵を訪ねた時のもの、とされています。) ★ 大顚和尚(だいてん・おしょう/ 鎌倉/円覚寺の第163世住職/・・・芭蕉の代表的な門人に、杉山杉風(すぎやま・さんぷう)と並ぶ宝井其角(たからい・ きかく)がいますが、 <其角/きかく>の号を与えたのが大顚和尚です。)
《仏教/・・・雑学》・・・(35) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(33)
咲いていた梅の花も… 今はもう散って… 卯の花の季節になってしまった… その卯の花を拝み… 涙を流していることだ…
《仏教/・・・雑学》・・・(36) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(34)
良しとはせず…
|
| 12月17日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(37) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(35)
もっとも、この句は芭蕉の句集には無いらしく、後世の作り話かも知れません。しかし、芭 蕉が悟りをひらいた逸話としては、非常によく出来た話です。
《仏教/・・・雑学》・・・(38) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(36)
<散れば散れ>…と、万物の流転を肯定する<悟リ/空へ至る飛躍/・・・頓悟の示 唆>を…芭蕉は豁然(かつぜん/ぱっと打ちひらけるさま。突然迷いや疑いが晴れるさま)と、見事に受け 止める、力量があったということです。山道を登り続け、突然、広々とした海の視界が開 けた時の様です。
《仏教/・・・雑学》・・・(39) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(37)
前にも言った様に、芭蕉は<幾重にも悟りを重ね>ながらも、<風雅への愛着/愛惜 (あいせき/大切にし、手放したり損ねたりするのを惜しむこと)/妄執>は捨てなかった様です。 それは、出家者/藤原俊成や、入宋沙門(にっそう・しゃもん)/道元とは、人生の立ち位置が 異なるという事です。芭蕉は俳諧師であり、芸術家であり、蕉門の総帥/元禄の大スター なのです。
《仏教/・・・雑学》・・・(40) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(38)
蕉門/蕉風(しょうふう/芭蕉の誹風・・・蕉門俳人は、自分たちの俳風を<正風>と称した。)は江戸の文化の 風として、奥州にも届いてた様です。 芭蕉と曽良(『奥の細道』の同行者)はそうした俳句の知己や知人の紹介を頼り、各地で句会を 催(もよお)しながら路銀(ろぎん/旅に必要な金銭)を集め、奥州平泉、尾花沢、立石寺(りっしゃくじ)、 象潟(きさかた)、直江津(なおえつ)と…当時の日本を、庶民がヒッチハイク/探検して歩いた わけです。
《仏教/・・・雑学》・・・(41) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(39)
諸大名の参勤交代の副産物として、緩やかに日本全国に伝播(でんぱ/伝わり広がって行くこと) していた様です。他に、勤番侍(きんばんざむらい/国もとから出て、江戸や大坂の藩邸詰めとなっている侍。) の旅や商人の旅が多かったと思われますが…<文化の伝達者>としての旅人は、俳 諧師(はいかいし)などです。絵師や僧侶などもそうだったのでしょう。そうした文化や各地の 情報を得るため…
《仏教/・・・雑学》・・・(42) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(40)
したわけです。 特に… 各地に散在する俳諧門下を巡回している俳諧師は、今風の新聞や週刊誌の様な知識 階層の情報源です。各地に関所などもあり、僧衣が何かと便利だったようです。 元禄時代の芭蕉をよりやや下り(/近代に近く)ますが、小林一茶の句に、こんなの旅のエピ ソードの句が有ります…
おそらく、実体験の句でしょう。
|
| 12月23日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(43) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(41)
これは、中国/宋の、蘇東坡(そとうば/・・・蘇 軾(そしょく): 中国北宋時代の政治家、詩人、書家。東坡居士 と号したので、蘇東坡とも呼ばれる)・居士(こじ/在家の禅の修行者)の詩が、踏襲(とうしゅう/それまでのやり方
を受け継いで、その通りにやること)されています。 山色豈非清浄身 (さんしき・あに・しょうじょうしんに・あらざらんや) 夜来八萬四千偈 (やらい・はちまんしせんの・げ)
他日如何挙似人 (たじつ・いかんか・ひとに・こじせん) ★ 七言絶句/渓声便是広長舌 中国/北宋時代の詩人/蘇東坡は… 文学者であり役人でもありましたが、皇帝そしった罪で湖北省/黄州へ左遷されました。その罪がと かれ、しばらく弟のいる州へ行こうと旅立ちます。その時に立ち寄ったのが廬山・恵林寺であり、照 覚常総禅師に参禅します。 そして、そのとき与えられたのが、【無情説法の公案】といわれます。これは、山川草木など情のない
ものの説法の声を聞け、というものでした。 総禅師のもとを辞し、再び州へ向かいます。しかし【無情説法の公案】は、彼の脳裏を離れず、馬に
揺られながらも、全身全霊で公案に取り組んでいました。 豁然と心境が開けます。その心境を、詩にしたのが…この<広長舌の七言絶句(しちごんぜっく/漢詩で、 七言の句が4句からなる近体詩)>です。
《仏教/・・・雑学》・・・(44) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(42)
<風雅への妄執/風雅への魔心>に身を沈めて行きながらも、<禅的な悟り>を纏 (まと)っている様に… 道元も… <思えばくやし 色にめでけり>と詠みながらも、多くの<色>を愛でる歌を残していま す。その言い訳ではないのでしょうが、こんな歌があります…
《仏教/・・・雑学》・・・(45) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(43)
浅い所で、衆生(しゅじょう)に教示(きょうじ)しているわけです。 我々衆生は、その浅い所を住処(すみか)とし、ウロウロしているわけですから。
|
| 12月24日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(46) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(44)
ええと、くり返しますが… 俊成は…平安時代後期~鎌倉時代初期の公家で、歌人です。この時代に90歳まで生き ていますから、まさに歌人の妖怪といったところでしょうか。 藤原北家御子左流(ふじわらきたけ・みこひだりりゅう)の…権中納言/藤原俊忠の子で、養子に 出ますが、再び実家/御子左家(みこひだりけ)に戻っています。
《仏教/・・・雑学》・・・(47) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(45)
にわたり克明に記録した日記。国宝。) 『小倉百人一首』を編集した…藤原定家がいて… 養子/寂蓮法師は…弟/僧・俊海/…醍醐寺阿闍梨の子がいます。
『小倉百人一首』 の寂蓮法師の歌/【87番 →
寂蓮法師】は、次のものです…
《仏教/・・・雑学》・・・(48) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(46)
ます…
|
| 12月26日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(49) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(47)
あの…栄華を極めた、藤原道長(/長女の中宮彰子は、紫式部や和泉式部、赤染衛門を女房とし、華 麗な文芸サロンを形成しました。同じ一条天皇の中宮には定子がいて、清少納言が仕えていたが、中宮定子は出産時に 薨去し、清少納言も宮廷を去りました。)の系譜を引く家系です。 俊成は… 晩年の藤原基俊(ふじわらの・もととし/『小倉百人一首』/【75番→藤原基俊】)に入門し…<承久の乱 >で隠岐に配流となった後鳥羽院、佐渡に配流となった順徳院の時代の、歌人です。 90歳という長命で、子/藤原定家の時代とも、重なるわけです。
《仏教/・・・雑学》・・・(50) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(48)
六条藤家(ろくじょう・とうけ/・・・藤原北家末茂流庶流。藤原隆経の子/顕季(あきすえ)を家祖とする歌道の家。単に 六条家とも言う。その跡を継いだ清輔(きよすけ/藤原清輔)・顕昭(けんしょう/亮阿闍梨/すけのあじゃり)は実践のみな らず、歌論においても才能を示し、御子左家の歌道の家/藤原俊成・寂蓮らに対抗する。)の藤原清輔の勢力に 圧倒されつつも、しだいに、力を付けて行った様です。 清輔/藤原清輔が没すると…政界の実力者/九条兼実(くじょう・かねざね/九条家の祖)に迎え られ、歌壇の重鎮となります。 後白河院の下命で勅撰和歌集/『千載和歌集』(せんざい・わかしゅう/勅撰和歌集の第7で、『詞 花和歌集』の後、『新古今和歌集』の前 )を…そして、子内親王(しきし・ないしんのう)の下命で歌論書/ 『古来風躰抄』(こらい・ふうていしょう/和歌観、和歌の歴史を述べ、『万葉集』以下の『千載和歌集』にいたる、8 撰集の秀歌を例示しつつ、ところどころ評を加えている。)を編集・献上しました。
《仏教/・・・雑学》・・・(51) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(49)
出家後は、<釈阿(しゃくあ)>と号しますが…<釈教(しゃくきょう/)>に分類(/・・・春・夏・秋 ・冬・旅・悲傷・祝・恋・雑・神祇・釈教・・・に分類 )される歌に、次の様なものがあります。
げん・しつどでい、けつじょう・ちこんすい/・・・漸く湿(うるほ)へる土泥を見ては、決定(けつじょう)して水に近づきたりと知 るがごとし)の心をよみ侍(はべ)りける (意味は・・・ 井戸を掘る時、湿った土や泥を見て水脈が近いことを知るように、法華経を深く学ぶほどに真の仏智に近づくことを知る・・・ といった意味。)
《仏教/・・・雑学》・・・(52) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(50)
武蔵野の堀兼の井のように… 掘るのが困難な井もあるものを… 私が掘ってゆくと、嬉しいことに… 水脈が近づいてきたのだった… “堀兼(ほりかね)”に、“土が固くて掘りかねる”の意を掛けています。<水の近づき> の<水>は…仏智のことです。
《仏教/・・・雑学》・・・(53) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(51)
康治年間(1142年~1144年)、待賢門院(たいけんもんいん)中納言(/待賢門院・璋子に仕えた女房。藤 原定実の娘)が人々に法華経28品の歌を詠むよう勧めた時、それに応じて作った歌と言わ れます。 出家者/釈阿(しゃくあ)として…その心境を吐露(とろ/気持・意見などを、隠さずに他人に打ち明け述べ ること)した…という事になるのでしょうか。
|
| 12月27日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(54) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(52)
到達したことが、<うれしく水の 近づきにける>という事から分かります。 当時の人々は… <神・仏・仏教>は身近な生活の中にあり、出家する前も信仰心や知識はあったわけ です。
《仏教/・・・雑学》・・・(55) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(53)
その真剣な眼差しは、現代人の私達よりもはるかに深く、人生や物事を考えていたと思 われます。死は身近にあり、野性の闘争と<一期一会>(いちごいちえ/一生に一度だけの機会。 生涯に一度限りであることから、その一瞬一瞬を自覚を持って大切に生きること。)が混在していた人生です。 しかし… 貴族社会/知識階級にも、仏教は奥が深く、経典は難解を極めたものだったのでしょう。 現代のように、瞬時に翻訳ソフトが解説してくれる時代ではなかったのです。
《仏教/・・・雑学》・・・(56) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(54)
俊成自身も出家者となり、一身を投じたわけです。還暦(かんれき/60年生きて干支(えと)が生まれ た年に戻る(=還)数え年で61歳のこと。)の頃に大病し、出家した様です。 さすがに… 歌道の家/御子左流の初祖であり…大地に水が染み込む様に、仏智を吸収していく事 が出来たのでしょう。その喜びが、<うれしく水の 近づきにける>という句から読み取 れます。 ちなみに… 栄西禅師/明菴栄西(みょうあん・えいさい、ようさい)が入宋(にっそう/栄西は2度入宋。彼の地で、インド渡 航を願い出るが許可されず・・・天台山万年寺の虚庵懐敞に師事。虚庵懐敞より臨済宗黄龍派の嗣法の印可を受ける。)し、 京都に建仁寺(/臨済宗建仁寺派大本山の寺院)を建立したのは、1202年であり、俊成が没した のは1204年ですから…禅宗とは、わずかに重なる程度です。 明菴栄西は… 日本臨済宗の開祖ですが…日本曹洞宗の開祖/永平道元(えいへい・どうげん)/道元禅師 は、入宋前に建仁寺で修行していて、師/明全を通じて栄西とは孫弟子(/最新の研究では、 直接には、会っていないとされる。)の関係になります。
|
| 1月 23日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(57) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(55)
菩提達磨(ぼだい・だるま)が3年近い航海の末… インドから中国/広州にたどり着いたのは、梁(りょう/中国の南北朝時代に江南に存在した王朝)の 武帝の時代/普通元年(520年)9月21日と伝えられます。 当時中国では…仏教とは人々の吉凶禍福(きっきょうかふく)を占い、金の光り輝く仏像を礼 拝することによって…
《仏教/・・・雑学》・・・(58) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(56)
中国/シナに入国した外国人は、善人悪人を問わず都の武帝に一報が届きます。仏教 を国是(こくぜ/一国の政治の基本的な方針)とする武帝は、達磨を都に招待し、<有名な武帝と
達磨の問答>が行われます。 「わしは・・・多くの寺を建て、経文を書写し、多くの僧侶僧尼を育てた。このわしに、 どの様な・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(59) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(57)
「その様なものは、功徳(くどく)にはなりませんぞ」 「無功徳だと!どうしてか?」 「その様なことは、それが出来る人なら、やって当たり前のことです。やらなければ 人間のクズです」 「では、真の功徳とは何を指すのじゃ?」
《仏教/・・・雑学》・・・(60) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(58)
「お前は、悟りを開いた僧と聞いているが、それはウソか!」
「そんな事は、わたしは知らない」 帝は、この会見を生涯悔(く)いたと言います。
|
| 1月 24日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(61) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(59)
アレクサンドロス大王・・・アレクサンドロス3世のこと)の東征によるギリシア彫刻の影響を受け、仏像 彫刻が誕生します。 中国/唐時代の訳経僧(やっきょうそう/経典の翻訳に従事する僧で、鳩摩羅什(くまらじゅう)や玄奘三蔵など が代表格・・・三蔵法師という)/玄奘三蔵(げんじょう・さんぞう/インドへの旅を地誌/『大唐西域記』として著し、こ れが後に伝奇小説/『西遊記』の基ともなった。)がチベットを越え、インドのナーランダ大学(/インドビ ハール州、ナーランダ中部にある・・・427年に建てられた世界最古の大学の1つ。北部インド仏教の最重要拠点。)に学 んだ頃には、仏教はそのピークを過ぎようとしていた…と言われます。
現在のアフガニスタン東部からパキスタン北西部にかけて存在した古代王国。カーブル川北岸に位置し、その東端はインダ ス川を越えてカシミール渓谷の境界部まで達していた。 ガンダーラ王国は紀元前6世紀~11世紀間存続し、1世紀~5世紀には仏教を信奉したクシャーナ朝のもとで最盛期を迎 えた。 ガンダーラ美術は、ギリシャ、シリア、ペルシャ、インドの様々な美術様式を取り入れた仏教美術として有名。)
《仏教/・・・雑学》・・・(62) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(60)
海路でシナ/中国に入ったのは…梁(りょう)の武帝の時代/520年であり… 玄奘三蔵が… 密出国から16年の修行の旅を終えて…657部の経典を都/長安に持ち帰ったのは… 唐王朝/第2代皇帝/太宗の時代の645年です。 つまり… 中国で禅宗が開花して125年後であり、まさにその黎明期(れいめいき/新しい時代・文化などが 起ころうとする時期)でした。 そこに、天竺(てんじく/インドをさす中国での古称)から大量の仏典が持ち込まれたわけです。これ らの仏典は、はるか日本にまで伝わるわけです。 いずれにしても… インドでは、再びヒンズー教が台頭しつつあり…
《仏教/・・・雑学》・・・(63) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(61)
大乗仏教は、北方のガンダーラ・チベット・中国へを経て日本へ。小乗仏教/上座部仏 教は、南方のスリランカを経て、東南アジアに広がって行きます。 この、大きな仏教の流れの中で…インドでは仏教の衰微(すいび/衰えて勢いが弱ること)の風が 吹き始めていたわけです。 菩提達磨の伝説では…その真実性はともかく…達磨は南天竺国(みなみ・てんじくこく)/…
《仏教/・・・雑学》・・・(64) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(62)
第28祖/菩提達磨>になった…という事です。 達磨は…師/般若多羅のいまわ(今際/臨終の)の言葉に従います。
低い南方に止まらず・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(65) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(63)
梁(りょう)の武帝との対談に絶望し…師の言葉に従い北を目指し、密かに梁の国を去りま す。葦(あし)を分けて揚子江(ようすこう)を渡り、魏(ぎ)/北魏(ほくぎ/後魏)の国に入り、都/洛 陽(らくよう)に到着します。そこで、嵩山(すうざん)少林寺に留まり、終日、壁面端坐(へきめん・た んざ)しました。
|
| 1月 25日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(66) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(64)
<壁観バラモン>と呼ばれるわけですね。達磨はその後<九年面壁>し、160余歳 の長寿を全うしたと伝えられます。 これから逆算すると… <真の仏法>を伝えるために、達磨が南天竺を発った時は、すでに150歳を越えてい たのでしょうか。そして、この奇跡がなければ…
《仏教/・・・雑学》・・・(67) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(65)
かせる事もなかったのです。また、榮西禅師(/日本臨済宗の開祖)がそれを日本に伝える事 も、道元禅師(/日本曹洞宗の開祖)がそれを求め、入宋(にっそう)する事もなかったわけです。 <仏教・第28祖/菩提達磨>が…中国の大地に<真の仏法/・・・禅宗の種>を 運んだ功績は、はかり知れません。
《仏教/・・・雑学》・・・(68) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(66)
中国の大地で、その種がまかれ、芽吹き、開花したために…異文化/インド臭さ/イン ド大陸の体臭がありません。 自力本願的な坐禅修行は… 原始仏教(/釈尊の存命時代を含めて、初期の150年~200年の期間。)や上座部仏教(/インド南部のセイ ロン島/スリランカから、東南アジアに広がった仏教。かっては、小乗仏教と呼ばれていた。)に近いわけですが、 禅宗は大乗仏教の範疇に入ります。 ともかく… <禅宗によって・・・仏教が真に中国文化に溶け込み・・・そして中国文化圏でもあっ た日本にも・・・スムーズに溶け込んだ・・・>…わけです。
|
| 1月 26日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(69) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(67)
<奈良仏教>は… 聖徳太子の法隆寺、渡来僧/鑑真と唐招提寺、聖武天皇の東大寺が…代表格でしょう か。 <平安仏教>は… 同じ遣唐使船に乗った学僧空海と最澄…後の弘法大師/高野山金剛峯寺/真言密教 と、後の伝教大師/比叡山延暦寺/天台宗が…代表格でしょうか。規模も大きく、仏典 などの内容も進化しています。
《仏教/・・・雑学》・・・(70) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(68)
禅宗の移入の時代であり…栄西の臨済宗と道元の曹洞宗が展開し…また、蘭渓道隆 (/らんけい・どうりゅう/鎌倉時代中期の南宋から渡来した禅僧・大覚派の祖。無明慧性の法嗣、建長寺の開山。)な どの渡来僧も、かなり来朝しています。 中国に騒乱がった事と、船の発達もあり、入宋も容易になります。騒乱は元/ジンギス・ カンの、人類史上最大規模のモンゴル帝国の建設で、その矛先が元寇(げんこう)となって 鎌倉幕府を襲います。 一方、<禅宗や念仏(法然・親鸞(しんらん)の浄土宗・浄土真宗/・・・南無阿弥陀仏ととなえる)>により… まさに、日本文化の中に…<日本土着の仏教が育ち・・・民衆の中に根を下ろした> …様子です。
|
| 2月 5日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(71) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(69)
『正法眼蔵/現成公案』の1節を見てみましょうか。 あるから、生死(しょうじ)を解脱(げだつ/俗世の束縛・迷い・苦しみから離脱し、悟りを開くこと)した所に 生死があり、迷悟(めいご/迷いと悟り)を解脱した所に迷悟があり、解脱の有る無しを問 題としない所に解脱がある。
道元禅師開祖の永平寺/大広間の天井絵・・・230枚の花鳥色彩画 /ネットより画像借用 《仏教/・・・雑学》・・・(72) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(70)
り、迷いを離れようとすれば、迷いは広がるばかりである。 > 中国/宋/天童山・景徳寺(/現在の浙江省寧波地区)/天童如浄の元で<悟り>を開いた 道元は、帰朝して『正法眼蔵』を…
道元禅師開祖の永平寺/大広間の天井絵・・・230枚の花鳥色彩画 /ネットより画像借用 《仏教/・・・雑学》・・・(73) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(71)
これは…若く楽しく、希望に満ち、心踊る作業…だったと思われます。 中国/宋から帰朝して…京都/建仁寺(けんにんじ/臨済宗建仁寺派大本山の寺院。開山は栄西で、道 元はここで栄西の弟子/明全に師事・・・明全と共に南宋に渡り、曹洞宗禅師/天童如浄より<印可>を受けます。)に 入りますが、やがて建仁寺を出て…京都/深草に草案(/・・・興聖寺)を結んだ頃からでしょ うか。 その頃… まず…日本曹洞宗・第2祖/懐奘(えじょう)を、弟子になる事を許します。2歳年上の孤雲 懐奘(こうん・えじょう)ですが、帰朝後、建仁寺に滞在していた折に論破した経緯があります。 その時から師事(しじ/師として仕えること)する事を懇願(こんがん)されていましたが、建仁寺に 身を寄せている身分であり、断っていたものです。
|
| 2月 6日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(74) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(72)
のが迷いである。ものごとの真実が自然に明らかになるのが、悟りである。> <真実が自然に明らかになるのが・・・悟り>と言われても…<迷いの真っ只中> にあっては、まさにそれが体現できないわけです。
《仏教/・・・雑学》・・・(75) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(73)
悟りの上に悟る人があり、迷いの上に迷う人もいる。悟った人が本当に悟った人で あるならば、自分が悟っている事すら、自覚しない。 >
《仏教/・・・雑学》・・・(76) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(74)
ここまで、書けるということは… <覚醒の翼>はそのはるか先まで、見渡していたという事でしょう。釈尊は無論、若い 道元も、その深淵を照らす光ははかり知れません。 しかし… さいわい道元禅師は、『正法眼蔵』(/(仮名記述/道元著)・・・75巻+12巻+拾遺4巻(現在の研究結果 による)の中に、膨大な言葉を残してくれています。
|
| 2月 7日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(77) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(75)
る事ができるが、その有様は鏡に影が映るようでも、水に月が映るようでもない。 主観と客観は一体であるから、その一方だけを知ろうとするならば、あとの一方は 消えてしまう。>
《仏教/・・・雑学》・・・(78) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(76)
<心身を一体として、ものごとを見聞きするならば・・・>とありますが… 意識して、その様にするという事ではないでしょう。その事を知りつつ、坐禅修行で身に つくものと思います。 <主観/主体と・・・客観/客体・・・は一体>であり…その間に<境界>はなく… <巨大な1つの全体・・・唯心世界>…なのです。
《仏教/・・・雑学》・・・(79) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(77)
を忘れることである。自己を忘れるということは、すべての物事が自然に明らかに
なることである。 > 含蓄(がんちく/深い意味がひそんでいる、表現の味)のある言葉ですが、日常的な知識では理解は できません。禅の修行が必要なのだと思います。
|
| 2月 8日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(80) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(78)
離れてしまっている。真実がもともと自己の内にあることが、正しく理解されれば、
すぐさま “本当の人” になる。> る事であり…
《仏教/・・・雑学》・・・(81) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(79)
しかし、それをいちがいに、薪は初めにあるものであり、灰がそれに続くものであ ると考えてはならない。薪は薪になりきっていて、初めから終わりまで薪である。
《仏教/・・・雑学》・・・(82) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(80)
薪である。灰もまた灰になりきっていて、初めから終わりまで灰である。> 私が、初めて『正法眼蔵』 に接した若い頃から…難解で、理解できないものでした。
《仏教/・・・雑学》・・・(83) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(81)
【量子力学】のコペンハーゲン解釈に出会った時、<波束の収束>(はそくのしゅうそく)の 概念と似ている…と気付きました。 <薪の一瞬一瞬> <灰の一瞬一瞬>は…それぞれ<重ね合わせ>になっている というアナロジー(/類推、類比)で…その<一瞬一瞬が・・・重ねあわせで・・・世界を究め つくしていると>、と解釈しました。
きないと解釈し、観測すると観測値に対応する状態に変化する<波束の収縮>が起こると解釈する。) する。)
《仏教/・・・雑学》・・・(84) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(82)
の、解釈の一端を垣間見た思いでした。<人間的な・・・過去・現在・未来にわたる ・・・“今の広がり”・・・>の考察の…側面になるでしょうか。 現代物理学は… その深い所で、東洋的思想とよく一致すると聞きますが、鎌倉時代初期の道元禅師の 思想に、量子力学の<重ね合わせの概念>があるとは…まさに驚きでした。
|
| 2月 9日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(85) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(83)
ら、再び生に戻ることはない。このように、生といえば生になりきっていて、生が死
に移り変わると言わないのが、仏道において定められた教えである。> <重ね合わせ>に存在して…
《仏教/・・・雑学》・・・(86) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(84)
でしょうか。
て、死が生に移り変わると言わないのが、仏道において定められた教えである。従 ってそれを・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(87) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(85)
<無数の・・・一瞬一瞬の生>が、それぞれ<一切世界を・・・究めつくし>…<重 ね合わせ>になっている…と解釈できます。 しかし… <相互主体性世界を・・・結晶化>させている…<この世の風景/・・・人間原理スト ーリー>は…さらに途方もなく複雑です。 あるいは… ある意識/宇宙意識が…<ホモサピエンスの・・・種の共同意識体の超座標>に、 <壮大な落書き・・・人類文明社会の興亡>を、描き出しているのかも知れません。
|
| 2月 10日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(88) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(86)
て死になりきっている。それは例えば冬と春のようなものである。人は、冬そのもの
が春に変わるとは思わず、春そのものが夏になるとは言わない。> 言葉だけで理解するのではなく…
《仏教/・・・雑学》・・・(89) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(87)
があります。 は破れない。広く大きな光ではあるが、寸尺の水にも宿る。月全体が草の露にも宿
り、一滴の水にも宿る。> 人間/人格に…
《仏教/・・・雑学》・・・(90) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(88)
妨げないのは、一滴の露が天の月を妨げないようなものである。一滴の水の深さ は、天の月の高さを宿している。>
《仏教/・・・雑学》・・・(91) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(89)
うーむ… 21世紀の私達が接しても…新鮮な言葉の数々を、鎌倉時代初期の道元禅師が創作し ていたのですから、驚くばかりです。 同様に… 紀元前5世紀の土埃(つちぼこり)のインドの大地を、裸足で歩んでいた…釈尊の真理探 究の深さと、その直観力に…2500年後の私達が、遠く及ばないわけです。釈尊の<覚 醒の・・・深淵>は、はかり知れません。
|
| 2月 16日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(92) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(90)
芭蕉は… 旅の難儀(なんぎ)も全て<風雅>とし…<大いなる・・・現実肯定・・・の世界観>…の 中で生きた人の様です。 その<風雅>に、恋い焦がれ、<風雅の妄執(もうしゅう)/風雅の魔(/人の心を迷わし、悪に 引き入れる悪霊)心>に取り憑(つ)かれていたとも言われます。<無我無心で・・・飄々(ひょう ひょう)と生きる禅僧>とは、また別の…
《仏教/・・・雑学》・・・(93) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(91)
《当/ホームページ》の…文芸/俳句担当/星野支折の言葉をかりれば… <そうした深い芸術的・深淵を・・・恋い焦がれて歩み進んだ・・・“芭蕉独特の風雅 の結晶世界”・・・が、芭蕉と共に確かに存在していた・・・>…ということですね。
《仏教/・・・雑学》・・・(94) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(92)
山形県の出羽三山(でわさんざん/・・・山形県の村山地方・庄内地方に広がる月山・羽黒山・湯殿山の総称。修 験道を中心とした山岳信仰の場として現在も多くの修験者、参拝者を集めている。)を訪れています。 『奥の細道』の記述では… <6月3日、羽黒山に登る>…とあり、さらに、<羽黒山の別当代(べっとうだい/別当とは 一山の法務を統括する長のことです。そして、代とありますが、これは代わりの意味で、50代別当・天宥が流罪になり、 東叡山(とうえいざん/東京都台東区上野にある寛永寺の山号。 京都の叡山/比叡山に対していう )から代理が置かれ ていたもの。)/会覚(えかく)・阿闍梨(あじゃり/模範となる高僧の敬称ですが、密教で伝法潅頂(でんぽうかん じょう/菩薩が仏位に上る時、法王の職を受ける証として、諸仏が智水を頭に注ぐ儀式)を受けた僧のことです。また、天 台宗と真言宗では、伝法潅頂の職位を受けた僧を、このように呼ぶようです。)にお目にかかる>…とあり、 南谷の別院に宿泊していますが、芭蕉の名声が知れ渡っていて、懇(ねんご)ろにもてなし て下さった、という事です。
|
| 2月 17日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(95) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(93)
ここ羽黒山/南谷では… 残雪の香りをのせて… 心地よい風が吹き寄せてくる… 旅で疲労したこの身には… この上なく有難く… 清らかな空気であり、風である事だ…
《仏教/・・・雑学》・・・(96) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(94)
中で、しばしの静養の時を過ごした様です。残雪の谷あいから吹き寄せてくる薫風(くんぷ う/若葉の香りを漂わせて吹く、初夏の風。)に、長旅の疲れも癒(いや)されたのでしょう。
けい)する・・・>、 <8日、月山(がっさん)に登る・・・>と…『奥の細道』にあります。旧暦/6月8日ですか ら、まさに、江戸時代の夏山登山です。
《仏教/・・・雑学》・・・(97) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(95)
会覚・阿闍梨(えかく・あじゃり)がお世話をして下さったのでしょうか。木綿注連(ゆうしめ)を首に 掛け、宝冠(ほうかん)で頭を包み、身支度も準備万端に整えての、月山登山です。 月山に登る者は、登山前の潔斎(けっさい/神事・仏事の前に、飲食その他の行為をつつしみ、水浴などして 心身を清めること)の時から下山するまで、修験袈裟(しゅげんけさ)として木綿注連(ゆうしめ)を首に 掛けるのが習わしの様です。宝冠は、防寒対策にもなる頭巾ですね。
|
| 2月 18日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(98) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(96)
強力(ごうりき/登山者の荷物を背負って案内する人)という山ガイドに先導され… 雲や霧の立ちこめる冷え冷えした山の中を、氷雪を踏みながら8里ばかり登った…とあ ります。1里は4km程ですから、約32kmですね。 さらに… 息も絶え絶えに…冷え切った体で、月山頂上に上り詰めています。
《仏教/・・・雑学》・・・(99) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(97)
折から、日も暮れて….<既に出ていた月が鮮明になった・・・>とあります。俳人が 2人、さすがに月への関心は深く、観察が鋭いですね。 それから… <頂上付近の小屋で、笹を敷き、まとめた篠竹(しのだけ/)を枕にして、横になって夜 が明けるのを待った・・・>…とあります。
《仏教/・・・雑学》・・・(100) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(98)
朝日が出、雲が消えていたので、さらに、湯殿山(ゆどのさん)の方へ向って下った様です。 前日は… 雲や霧が立ち込める天候でしたが、翌日は朝日が出て雲も消え、好天だった様です。 旧暦/6月9日ですから、新暦/7月25日…まさに梅雨明けだったのでしょうか。
《仏教/・・・雑学》・・・(101) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(99)
現在の登山装備ならともかく…霧の中の氷雪登山です。そして山頂の小屋で食事をと り、一夜を過ごすとういのは、強力/山案内が無しでは不可能だと思います。 旅慣れた芭蕉でも… 月山は標高1984mの残雪のある高山です。この強力/山案内も、羽黒山別当が手配 してくれたのでしょうか。どのみち芭蕉と曽良は、支援者を当てにしての冒険旅です。
|
| 2月 19日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(102) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(100)
<谷の傍に鍛冶小屋があった・・・>と記されています。さらに、<この地方の刀鍛冶 (かたなかじ)/月山という人が、霊験のある水をこの地に選び、身を清めて剣を打ち、 ついに“月山”と銘(めい)を刻んで世に賞せられた様だ・・・>…とあります。芭蕉は南 谷で静養中に…
《仏教/・・・雑学》・・・(103) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(101)
それから、岩に腰掛けてしばし休んでいると… <三尺ばかりなる桜のつぼみ、半ばひらけるあり・・・>と、あります。 芭蕉は… <降り積もった雪の下に埋れて、春を忘れぬおそ桜の花の、心わりなし・・・>と、 感嘆しています。まあ、非常に…
《仏教/・・・雑学》・・・(104) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(102)
<炎天の梅花が、ここに香るが如しであり・・・行尊・僧正の歌の情も思い出される が、むしろこの花の方がまさりて覚ゆ・・・>と、記しています。 芭蕉は…可憐で穢(けが)れの無い花に目を細め、花へのお世辞を込め、記している様 です。
《仏教/・・・雑学》・・・(105) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(103)
『小倉百人一首』/【66番→大僧正行尊】であり、詞書(ことばがき)は…
<大峰にておもひかけず桜の花の咲きたりけるをみてよめる 僧正行尊>
《仏教/・・・雑学》・・・(106) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(104)
大峰山は現在も女人禁制です。 行尊は… その大峰山で厳しい修行中に、ふと山中にひとり可憐に咲く山桜に目が止まります。穢 れを振り払った行尊の清浄な心と、穢れのない花が共鳴したのでしょう。
月山、湯殿山は明治10年に解禁され、羽黒山は一部を除いて女人禁制ではなかった様です。一部というのは荒沢寺な どの奥の院で、それも仏像の移動などにより解禁された様です。羽黒山が女人禁制でなかったのは、山の神が玉依姫命 (たまよりひめ)という女性の神とされており、女性の参詣が盛んだったためと思われています。ただ、女性の山伏修行は 禁じられていたようで、昭和25年に初めて許されたようです。)
|
| 2月 20日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(107) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(105)
山桜の花を、同等の人格として、語りかけています。ふーむ…優しいですね。 それにしても、芭蕉は… 数え年/51歳の生涯ですが、芭蕉翁(おう/おきな・・・男の老人を慕って言う言葉)などと呼ばれて いました。それ程に、かなり若い内から、その風格があり…<徹底した悟りを究め・・・ 深く風雅の中に没入>…していた人の様です。それゆえ、仏教界にも名が知れ渡り、 江戸/元禄のスーパースターだったわけです。
《仏教/・・・雑学》・・・(108) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(106)
芭蕉翁を深く慕い、その生き様に深く憧れていました。むろん、当時も今も、俳句を詠む 人は、みな芭蕉に憧れていたわけで、蕪村や一茶の様に自由人/俳人になれたのも、 また人々の憧れでした。
蕪村(俳人、画家)は… 江戸中期の人(1716~1784年/享保元年~天明3年)で、芭蕉(1644~11694年/寛永21年~元禄7 年)が他界して22年後に… 現在の、大阪市都島区毛馬町で生まれました。それから、20歳頃に江戸へ出て、日本 橋石町の界隈(かいわい/あたり)で活躍し、晩年は西へ向かい京都で暮すわけですが、元々 が、芭蕉と同様に関西の人(芭蕉は・・・三重県伊賀の人)でした。 母親が、京都/丹後の人だったからでしょうか、丹後でも暮らしていますね。母親は、毛 馬村の名主の家に奉公に上がっていた時、主人の子を身ごもり、生まれたのが蕪村だっ た様です。毛馬村には名主の一家/一族があるわけであり、自由人の蕪村は母の出身 の地/丹後にアイデンティティを感じていたのでしょうか。
《仏教/・・・雑学》・・・(109) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(107)
江戸中期から末期にかけての人(1763~1828年/宝暦13年~文政10年)です。継母(ままはは、 けいぼ/父の後妻)と折り合いが悪く、14歳の時に長野県北部/信濃町柏原から奉公のた めに江戸へ出、奉公先で俳句を覚えた様です。 蕪村の生涯とは21年間重なり…〔明治維新〕が1868年ですから、一茶が他界し40年 後の事です。
この地から北側の渓谷の向こうに、越後富士といわれる妙高山があります。渓谷を流れる谷川が関川で、信濃/長野県 と越後/新潟県の県境になっています。ボス/(岡田)は、この渓谷の向こう側/妙高山の麓で、少年時代をおくりました。 それで、一茶の1字を拝借し、俳号を <一風> としています。)
|
| 2月 21日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(110) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(108)
湯殿山の細かな事については、修験者の決まり事として他言することは禁じられていま す。芭蕉も<筆を止めて記さない事にする>…と、筆を止めています。 芭蕉一行/芭蕉・曽良・強力は下山し… 羽黒山/南谷の宿坊に帰った後…会覚・阿闍梨(えかく・あじゃり)の求めに応じて…
《仏教/・・・雑学》・・・(111) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(109)
《仏教/・・・雑学》・・・(112) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(110)
落ちた物を拾うことが禁じられ… 参道はお賽銭(さいせん)を散り敷いた様だ… そこを踏み行くのはかたじけなく… 泪が滲んでくる事だ…
『奥の細道』の原文を掲載しておきます。 『奥の細道』/出羽三山 元禄2年(1689年) 6月3日~6月10日(新暦/太陽暦 7月19~7月26日) 出羽三山(山形県鶴岡市/磐梯朝日国立公園の一角 月山、羽黒山、湯殿山の総称)
《 六月三日、羽黒山に登る。 図司左吉と云者を尋て、別当代会覚阿闍利に謁す。 南谷の別院に舎して憐愍の情こまやかにあるじせらる。 四日、本坊にをゐて誹諧興行。
有難や雪をかほらす南谷
人と云事をしらず。延喜式に「羽州里山の神社」と有。書 写、「黒」の字を「里山」となせるにや。 「羽州黒山」を中略して「羽黒山」と云にや。「出羽」とい へるは、「鳥の毛羽を此国の貢に献る」と風土記に侍と やらん。月山・湯殿を合て三山とす。 当寺武江東叡に属して天台止観の月明らかに、円頓 融通の法の灯かゝげそひて、僧坊棟をならべ、修験行 法を励し、霊山霊地の験効、人貴且恐る。繁栄長にし
て、めで度御山と謂つべし.....》 《 八日、月山にのぼる。木綿しめ身に引かけ、宝冠に 頭を包、強力と云ものに道びかれて、雲霧山気の中に 氷雪を踏てのぼる事八里、更に日月行道の雲関に入か とあやしまれ、息絶身こゞえて頂上に至れば、日没て月 顕る。笹を鋪、篠を枕として、臥て明るを待。日出て雲消 れば湯殿に下る。 谷の傍に鍛治小屋と云有。此国の鍛治、霊水を撰て 爰に潔斎して劔を打、終月山と銘を切て世に賞せらる。 彼龍泉に剣を淬とかや。干将・莫耶のむかしをしたふ。 道に堪能の執あさからぬ事しられたり。 岩に腰かけてしばしやすらふほど、三尺ばかりなる桜 のつぼみ半ばひらけるあり。ふり積雪の下に埋て、春を 忘れぬ遅ざくらの花の心わりなし。炎天の梅花爰にかほ るがごとし。行尊僧正の哥の哀も爰に思ひ出て、猶まさ りて覚ゆ。 惣而此山中の微細、行者の法式として他言する事を 禁ず。仍て筆をとゞめて記さず。坊に帰れば、阿闍利の 需に依て、三山順礼の句々短冊に書。
涼しさやほの三か月の羽黒山 (芭蕉) 雲の峯幾つ崩て月の山 (芭蕉) 語られぬ湯殿にぬらす袂かな (芭蕉) 湯殿山銭ふむ道の泪かな (曽良)
|
| 3月 15日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(113) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(111)
前は…俊成の<釈教>(しゃっきょう/釈教歌・・・仏教に関する題材を詠んだ句や歌。)に分類されてい る歌を取り上げました。ええと…次の歌でした。もう一度、掲載しておきます…
掘るのが困難な井もあるものを… 私が掘ってゆくと、嬉しいことに… 水脈が近づいてきたのだった… “堀兼(ほりかね)”に、“土が固くて掘りかねる”の意を掛けています。<水の近づき> の<水>は…仏智のことです。
《仏教/・・・雑学》・・・(114) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(112)
のものです。
東方からやって来る時… 通った諸国では…
《仏教/・・・雑学》・・・(115) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(113)
再びまた、蓮華の花が降りしくのだ… 釈迦が説法する…
霊鷲山(りょうじゅせん)の暮れかかる空から… <理/理論>からではなく、<研ぎ澄まされた感性>から、仏道の奥義(おうぎ、おくぎ/ 最も奥深い大切な事柄)に迫ったのでしょうか…ふーむ…
《仏教/・・・雑学》・・・(116) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(114)
<勧発品>(くわんぼつほん)というのは…『法華経の最終章/第二十八品』です。 それから、歌の方の… <花ぞ降りしく>とは…普賢菩薩が東方からやって来る時に、通った諸国では、天から 蓮華の花が、雨のように降ったという…言い伝えです。 <鷲の山>は…霊鷲山(りょうじゅせん)の事ですね。マガダ国の都/王舎城の近くにある 仏教聖地の1つです。 <法のむしろ(筵/むしろ・・・ワラやイグサなどの草で編んだ簡素な敷物。菰(こも)とも呼ばれる。)>は、釈尊 の説法の場というほどの意味です。
《仏教/・・・雑学》・・・(117) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(115)
歌人の…<研ぎ澄まされた感性>から、仏道の奥義に迫るというのは… 例えば、行尊(ぎょうそん/【66番→大僧正行尊】/★ もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに 知る人もなし ) の様に…<吉野の山奥での・・・回峰修行>をするのとは、まるで異なるアプローチで す。 が、しかし… 逆に行尊も…若い頃、厳しい死を賭すほどの、<吉野の山々の・・・回峰修行>の最中 に、<ふと・・・可憐な山桜に・・・心を引き寄せられた・・・>、わけですね。
|
| 3月 16日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(118) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(116)
<可憐な山桜>に心引かれたのは…<感性の世界>であり…これは不覚ではなかっ た…という事でしょう。回峰修行の中での<花との出会>は、<仏縁>であり、<覚醒 >だったのかも知れません。 それが、どの様な<覚醒>であったかは、むろん、行尊のみの知る所ですが…
《仏教/・・・雑学》・・・(119) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(117)
侶の人格>が…芭蕉の時代にも、現代の人々にも、快く親しまれ、存在感を示していま す。 しかし…話を、大きく戻しますが… 道元禅師は…<★ 花紅葉 冬の白雪 見しことも 思へばしやし 色にめでけり>と 詠み…藤原俊成も、道元禅師よりも少し前の歌人ですが… <★ 高砂の 尾上の桜 見しことも 思えば悲し 色にめでける>と…
《仏教/・・・雑学》・・・(120) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(118)
そして、行尊もまた… 厳しい回峰修行から…一瞬、<心が離反し・・・浮き上がった所の感性で・・・桜の花 に心を寄せ・・・>て…<仏道の奥義>を、物語っているのでしょうか。 行尊のそれは…<奥義>とは言えないかも知れませんが…私は、<意外に深い・・・ 仏縁>…と思っています。
《仏教/・・・雑学》・・・(121) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(119)
<覚醒/悟り>とは…<この世の・・・どの様な座標>にあるのでしょうか。『無門関』 (むもんかん/中国・宋時代に・・・無門慧開によって編集された禅の公案集。)の冒頭には、次のような無門 禅師の<偈頌(げじゅ)/偈(げ/禅宗で、悟りの境地などの宗教的内容を表現する漢詩)>があります。 つまり仏道の<覚醒/悟り>の場所を…指し示しています… 千差路(せんさ・みち)あり この関を透得(とうとく)せば
乾坤(けんこん)に独歩(どっぽ)せん
そこには幾千もの道がある…
《仏教/・・・雑学》・・・(122) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(120)
宇宙を闊歩(かっぽ)する者となろう… 無論…これは… <物理的/数学的な・・・座標系>にはなく、<広大無辺な・・・心の領域>にありま す。仏道の説く<空/・・・色即是空>とは…<人の・・・無意識世界//ホモサピエ ンスの種の共同意識体の・・・無意識世界>と…深く関係する様です。
|
| 3月 17日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(123) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(121)
<美福門院(びふくもんいん)に、極楽六時讃(ごくらく・ろくじ・さん)の絵にかかるべき歌奉(たて まつ)るべきよし侍(はべ)りけるに、よみ侍りける、時に大衆法を聞きて弥(いよいよ)歓喜 瞻仰(かんき・せんがう)せむ>
《仏教/・・・雑学》・・・(124) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(122)
目の当たりにしているのが… まさに、それなのだ… 入り日を眺めては… 思い憧れてきた… 阿弥陀如来の御国… 極楽浄土の…
夕暮れの空よ… 今回、初めて接してみたのですが…まさに、仏教の教えそのものを指す様です。
《仏教/・・・雑学》・・・(125) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(123)
<★ 高砂の 尾上の桜 見しことも 思えば悲し 色にめでける>は… <釈教>の歌には分類されていないのです。まあ、歌の世界ですから、厳格な決まりは 無いと思うのですが、この次は、俊成の他の歌も見てみましょう。
|
| 4月 12日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(126) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(124)
ここでは…『正法眼蔵/画餅』の章を、少し覗いて見ましょうか。 <画餅(がびょう/画に描いた餅)・・・は飢えを満たさない>という、有名な一節にまつ わる法話(ほうわ/仏法を説き聞かせる話)です。
《仏教/・・・雑学》・・・(127) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(125)
するとき、各の体験が、互いに妨げあうことなく実現するのである。それを、諸仏と 万物が同一であるか異なっているかという、分別によって学んではならない。 そのため・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(128) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(126)
・・・というのである。 一つのことを体験するということは、一つのことが本来具えている姿を奪うことでは ない。一つのことを他のことと対立させることでも、対立をなくしてしまうことでもない。 強いて対立をなくそうと・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(129) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(127)
体験することが、体験することにこだわらないとき、一つの体験は、すべての体験に 通ずる。このように一つのことを体験するということは、そのものになりきることであ る。そのものになりきるとは、すべてのものになりきることである。>
《仏教/・・・雑学》・・・(130) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(128)
一言一句…非常に、含蓄(がんちく/表面に直接現れない意味・内容)のある言葉です。 まあ…『正法眼蔵』ですから当然です。私(/岡田)も、言葉では理解していたつもりですが、 改めて痩(や)せた言葉に自然な肉付きを感じます。が、この体験も、さらに深い肉付きや 骨格があるのでしょう。私に、どこまで極められるかは、分かりませんが。
|
| 4月 13日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(131) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(129)
て、その名や地位や姿も様々であるが、みな、間に合わせの解答に満足している。 従ってこの言葉を・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(132) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(130)
にかいた餅というのである」 る」
《仏教/・・・雑学》・・・(133) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(131)
およそ、彼らの言うように、経典による教えが仮のものであって、真実を知るのに役 立たないということを言おうとして、それを「画餅」と呼ぶと考えるのは、大きな誤り である。そのような者達は、仏道を正しく伝えず、覚者の言葉に、暗い者達である。
《仏教/・・・雑学》・・・(134) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(132)
「常に、そのものを究め尽くしている」
《仏教/・・・雑学》・・・(135) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(133)
る。 いる者は全くいない。そのような者達が、どうして真のことを知っていようか。
《仏教/・・・雑学》・・・(136) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(134)
ず、自ら学ぼうともせず、人の話に耳をそばだてようともせず、そのような事には全 く無関心な様子であった。 >
《仏教/・・・雑学》・・・(137) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(135)
<諸悪をなさない・・・諸々の善を行う・・・何ものかが、ここに眼前している・・・常に、
そのものを究め尽くしている>
|
4月 14日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(138) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(136)
餅米を用いて作られる餅そのものは、必ずしも生滅するとも言えず、不滅であると も言えないが、今はそれを画餅即(すなわ)ち解脱の境地として悟る時である。それが 来たり去ったりするものであると・・・考えてはならない。>
|
| 4月 15日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(139) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(137)
<解脱>とは…個々の体験であるばかりでなく…<人間の普遍的本質>を貫く、不滅 の体験だと…言っています。 そもそも… <人間・・・一人称/私とは>…一体、何でしょうか? そして、<人間・・・二人称/あ なた、三人称/彼>…の、真の構造的意味とは、一体、何なのか?
《仏教/・・・雑学》・・・(140) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(138)
ホモサピエンスの…<種の共同意識体・・・の中で成立>している…<無数の個々 の意識の・・・重ね合わせから析出して来る・・・ホログラムの様なもの>…なので しょうか? さて… あえて、こんな言い方/ややこしい存在哲学の藪に、山刀(やまがたな)で切り込んだのか といえば…道元禅師がそこに踏み込んで、その辺りの事を言及しているからです。 <この世/・・・この迫真世界>もまた…
《仏教/・・・雑学》・・・(141) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(139)
の、側面を持つからです。 現代物理学は…つい最近… <巨大ブラックホール連星合体の・・・重力波/GW150914>を、捕捉しました。 重力波とブラックホールを、同時に科学的に確認し…<新たな天文学の窓/重力波 天文学>は…
《仏教/・・・雑学》・・・(142) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(140)
に欠けているもの、があります。 それは… 物理的宇宙を、まさに今、解き明かしつつある、<観測者の座標・・・のインプット/入 力>です。現状は、<一人称のパラダイム/・・・私という人格>は…その外側で佇 (たたず)んでいるという事です。では、<私/観測者は・・・宇宙の中の何なのか?>… という事になります。
《仏教/・・・雑学》・・・(143) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(141)
<私/・・・一人称的な窓/・・・命と意識による、この世の走査体>…は、この世の 外では、ありえないわけです。 では… <物の領域>と<心の領域>を統合する<人間/・・・私という人格>とは…<神 の側面>を持つ…という事なのでしょうか? 道元禅師は…そうした答えを、<画餅/・・・解脱の境地/ ・・・空(くう)・・・>…
|
| 4月 16日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(144) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(142)
ほめたたえる詩。四句から成る・・・頌(じゅ)。偈頌(げじゅ)。)を掲載して置きましょうか。<悟り>に至る 道を示しています。 千差路(みち)あり 此(こ)の関を透得(とうとく)せば 乾坤(けんこん)に独歩せん
そこには幾千もの道がある この関を通り得るならば 宇宙を闊歩 (かっぽ)する者となろ…つまり、仏法の立場からの、<究尽(ぐじん/究め尽くすこと)であり・・・悟りの浄土>です。 <餅を描く絵具は、山水を描く絵具に等しい。 いわゆる山水を描くには、青絵具を用いる。・・・
《仏教/・・・雑学》・・・(145) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(143)
むきは等しく、働きは等しい。 したがって、今ここに「画餅」と名づける解脱の有様は、一切のごま餅、菜餅、乳餅、 焼餅、きび餅などが、悉(ことごと)く画によって実現することである。
《仏教/・・・雑学》・・・(146) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(144)
ことを、知るべきである。 したがって、現実の餅はみな画餅である。この外に画餅を求めるならば、未だに画 餅にあわず、画餅のことを悟らないのである。 画餅は、ある時には実現し…
《仏教/・・・雑学》・・・(147) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(145)
しかし、そうではありながら、それは古今の姿を超えている。生滅の相を超えている。 そのような所に、画餅の国土が現れ、成立するのである。>
《仏教/・・・雑学》・・・(148) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(146)
<一枚の画餅>が…餅一般を現しているように… <我の解脱>が…<山水の解脱>、<世界の解脱>を、実現していると言います。 まあ、同じ意味ですが… <山水の解脱>のことは…『正法眼蔵/…山水経』の章に…詳しく書かれています。
|
| 4月 17日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(149) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(147)
う飢えの事ではない。 腹の中に一物もない解脱の境地を言うのである。そのような境地は、画餅の解脱の 境地と対立するものではない。したがって画餅を食べても、飢えはやまない。
《仏教/・・・雑学》・・・(150) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(148)
理がないのである。 飢えは飢えで、一切世界を究め尽くしており、餅は餅で、一切世界を究め尽くしてい るのである。>
《仏教/・・・雑学》・・・(151) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(149)
<画餅飢えに充たず>という言葉を… <解脱の境地においては・・・対立はない! >…という様に解釈するのだと言います。 <対立>…とは、あらゆる意味での対立であり、比較であり、優劣です。 <長い苦行の末>…その高峰/峰頂に立ち、見渡して見れは、<解脱/悟り>とは、 その様なものだという事です。 しかし、まあ… <その一言/言葉の概念>ですむなら…<長い修行の時>も、必要ないく、<修行 の喜び>もなく、<崇高なる頂>を拝することも、無くなります。
|
| 5月 13日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(152) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(150)
【道元・芭蕉・達磨…藤原俊成】のシリーズを、終了しようと思います。 最後に、俊成の<釈教>(しゃっきょう/和歌・連歌・俳諧で、仏教に関係のある題材を詠んだ歌や句)では ない、普通の季節の歌も考察すると約束していましたので、それらを幾つか拾って見て みましょうか。
《仏教/・・・雑学》・・・(153) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(151)
せ侍りけるに、立春の心を 皇太后宮大夫俊成 (新古今集 巻1/春歌上 0005)
《仏教/・・・雑学》・・・(154) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(152)
立春であるというので… 唐土(もろこし/・・・唐時代の中国)まで行き渡る… 春であるのに… 都にばかりと…
思っていたことよ… <詞書>にある…<入道前関白太政大臣>とは、九条兼実(くじょう・かねざね)です。治 承二年(1178年)五月、兼実に詠進(えいしん/詩歌を作って、宮中や神社などに差し出すこと)した百首 歌(ひゃくしゅうた/数を定めて詠う和歌(定数歌))ということです。
鎌倉前期の公卿。摂政・関白。従一位。藤原忠通の三男。 京都九条殿に住み、九条家を創設。月輪殿・法性寺殿と言われる。源頼朝の信任を得て摂政・関白となり、後白河法皇 歿後の朝勢を掌握、頼朝の征夷大将軍宣下を実現させた。)
《仏教/・・・雑学》・・・(155) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(153)
西海の彼方、遥かな唐土まで行き渡る… 季節の運行を、空間的に大きく捉えて詠み… 丈高い立春歌…” ふーむ…これが俊成の歌ですか。<詞書>に…皇太后宮大夫俊成とありますから、還 暦(かんれき/・・・干支(えと/十干十二支)が一巡し、誕生年の干支に還ること。人の年齢について言う場合が多く、数 え年61歳(誕生年に60を加えた年)を指す。)の前後に大病を患(わずら)い、出家して…
|
| 5月 14日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(156) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(154)
(千載集/183)
《仏教/・・・雑学》・・・(157) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(155) 須磨(すま)の浦人は… 日頃から涙がちなのに… 五月雨の頃は… 焼いて塩を取る藻も… 湿めりがちで… いちだんと…
濡れぼそていることだ… めに藻を焼く、その煙です。
《仏教/・・・雑学》・・・(158) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(156) <須磨の浦人(うらびと)>の<須磨(すま/神戸市須磨区)>は…摂津国の歌枕。また、ここ は…流謫地(るたくち/罪により、遠地に流される場所)でもあり、浦人というのは罪を得て遠地に流 された貴人を連想させます。そして<須磨の浦人>は…『源氏物語/須磨巻』を…
|
| 5月 15日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(159) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(157)
春・夏と来たので…次は、俊成の秋の歌を見てみましょう。 (千載集259)
《仏教/・・・雑学》・・・(160) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(158)
野辺を吹き渡って来る秋風が… 身にしみて感じられ… 心細げに鳴く鶉の声が… 聞こえてくる…
この深草の里では… 去られた女が、鶉の身に化身して寂しげに鳴く…
《仏教/・・・雑学》・・・(161) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(159)
<深草の里>は…地名の深草/京都深草に草深い里の意を掛けています。 <鶉鳴くなり>は…『伊勢物語/百二十三段』の、男に捨てられ、鶉に化身して野で鳴 いていよう…と詠んだ、女を暗示していると言います。これは有名な歌で、俊成の自信作 の様です。
|
| 5月 16日 |
《仏教/・・・雑学》・・・(162) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(160)
<須磨の関の千鳥>を詠んだものと思いましたが、季節感がはっきりする、雪の朝の 歌にしました。
の許に遣はしける (新古今集/664)
《仏教/・・・雑学》・・・(163) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(161)
あなたが訪ねて来るかと… 眺めるけれど… まだ足跡もない…
庭の雪であるよ… <詞書/・・・極月(ごくげつ/12月のこと)の十日あまり雪のいとたかうふりたる朝に、左 大将実、新大納言ときこえし時おくりし>…とあります。
《仏教/・・・雑学》・・・(164) 【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】/(162)
これで、《仏教/雑学》/【道元・芭蕉・達磨・・・藤原俊成】のシリーズを、終了します。
|