 ボス のTwitter
=2014年
ボス のTwitter
=2014年 
<正法眼蔵/・・・現成公案> (げんじょうこうあん/真理を実現すること)
(97~126/・・・3~32/完)





| Community Space /ボスの展望台/ボスのTwitter/仏道/正法眼蔵/現状公案 |
|
<正法眼蔵/・・・現成公案> (げんじょうこうあん/真理を実現すること) (97~126/・・・3~32/完) |
| トップページ/New Page Wave/Hot Spot/Menu/最新のアップロード/ 担当: ボス= 岡田 健吉 |

 ツイート の
記 録
ツイート の
記 録 

|
|
|
12月 20日 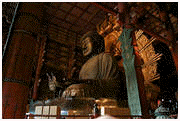 東大寺盧舎那仏像 (とうだいじ・るしゃな仏像) 一般的には奈良の大仏 (国宝) |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(97) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(3) ここでは、幾つかの巻の全文/冒頭部分を紹介する…
★ 《 現 成 公 案 》 の巻 全ての物事を、仏道の立場から見る時… 迷いと悟り、修行の有る無し、生と死、 解脱した人とそうでない人の、違いが明らかになる。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(98) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(4) 全ての物事を、無我の立場から見る時…迷いもなく悟りもなく、解脱した人もなく 解脱しない人もなく、生もなく死もない。 元々仏道は…有るという立場にも、無いという立場にも捉(とら)われないものであ るから…
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(99) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(5) …生死を解脱した所に生死があり、迷悟を解脱した所に迷悟があり、解脱を問題 としない所に解脱がある。しかし、そのことが分かっていながら、解脱を愛し求め れば、解脱は遠ざかり、迷いを離れようとすれば、迷いは広がる。
|
| 12月 21日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(100) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(6) 自己の立場から思案して…物事の真実を明らかにしようとするのが、迷いである。 物事の真実が、自然に明らかになるのが、悟りである。 迷いを迷いと知るのが悟った人であり、悟りに執するのが悟っていない人である。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(101) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(7) 悟りの上に悟る人があり、迷いの上に迷う人もいる。悟った人が本当に悟った人 ならば、自分の悟りすらも自覚しない。しかしその人は、本当に悟った人であり、悟 りからも迷いからも自由な、解脱の境地を行い現してゆく。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(102) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(8) 身心を一体として、物事を見聞するならば…事物を直接に知ることが出来る。そ の有様は鏡に影が映るようでも、水に月が映るようでもない。主観と客観は一体 であり…一方だけを知ろうとすれば、他方は消えてしまう。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(103) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(9) 仏道を学ぶということは、自己を学ぶこと。自己を学ぶとは、自己を忘れること。 自己を忘れるとは、全ての物事が、自然に明らかになることである。全ての物事 が自然に明らかになるとは、自分をも他人をも解脱させる。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(104) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(10) 悟りの跡形さえ残さず…その事を行い現して行く… 人が初めて真理を求める時…それを自己の外に求めるから、遥かに離れてしま う。真理が元々、自分の内にあることを理解していれば、すぐに <本当の人> となる。
|
| 12月 23日 (天皇誕生日)  鎌倉大仏/長谷の大仏 阿弥陀如来像 (国宝)  鎌倉大仏の後部 左下の穴から中に入れる |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(105) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(11) 人が舟に乗って岸を見れば、岸が動いていると思い、目を下に向けて舟を見れ ば、舟の進行を知る。 そのように、自己の身心を動揺させて物事の真実を知ろうとすれば、自分の心 や本質が永遠不変であると思い誤る。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(106) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(12) 自分の行いを正しくし…事実を直視すれば、物事が永遠不変でない事が分かる 筈(はず)である。 薪(たきぎ、まき)は燃えて灰となり、それが薪に戻ることはない。しかし、一概に、薪 は初めにあり、灰はそれに続くものと考えてはならない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(107) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(13) 薪は薪になり切っていて…初めから終わりまで薪である。見かけの上では前後 があるが、それは、つながりのない前後であり、薪はどこまでも薪である。灰もま た灰になりきっていて…初めから終わりまで灰である。(/このことをよく理解し・・・このよう に見るのが仏道である)
|
| 12月 24日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(108) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(14) 薪が灰になった後、再び薪に戻らないように…人も死んでから、再び生に戻るこ とはない。 生といえば生になりきり、生が死に移り変わると言わないのが、仏道で定められ た教えである。それを <生死を超えた生> と言う。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(109) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(15) 死といえば死になりきり、死が生に移り変わると言わないのが、仏道で定められ た教えである。それを <生死を超えた死> と言う。 生といえば、一瞬一瞬、生になり切り…死といえば、一瞬一瞬、死になり切って いる。
|
12月 25日 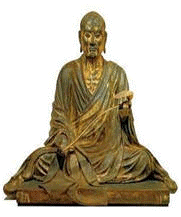 行基菩薩坐像 唐招提寺蔵 (重要文化財) 聖武天皇に招聘され奈良 の大仏建立の実質上の責 任者となる。日本における 最初の、仏教界最高位であ る大僧正を贈られた。 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(110) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(16) それは冬と春のようなものである。人は、冬そのものが春に変わるとは思わず、 春そのものが夏になるとは言わない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(111) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(17) 人が悟りを得るのは、水に月が宿るようなものである。月は濡れず、水は破れな い。広く大きな光ではあるが、寸尺の水にも宿る。月全体が草の露にも宿り、1滴 の水にも宿る。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(112) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(18) 悟りが人を破らないのは、月が水に穴を開けないようなものである。人が悟りを 妨げないのは、1滴の露が天の月を妨げないようなものである。1滴の水の深さ は、天の月の高さを宿している。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(113) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(19) 月影が宿る時の長短にかかわらず、それが大水にも小水にも宿ることを学び、 天の月の大きさを知りなさい。 真理が本当に体得されていない時には、かえってそれが十分であると思う。
|
12月 26日 釈迦三尊像 (法隆寺金堂/国宝) 中央が釈迦如来 脇侍には文殊・普賢の二菩 薩が多いが、ここでは、左 に薬王菩薩、右に薬上菩薩 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(114) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(20) もしそれが、本当に体得されていれば、どこか一方は足りないと思う。船に乗って 海に出て四方を眺める時、海は円く見えるばかり。その外の形には見えない。し かし、海は円くも四角くもなく、様々な姿形がある。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(115) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(21) 海は魚が見れば宮殿、天人が見れば玉飾り。それが我々の目には円く見えるに 過ぎない。 全ての物事がそうである。常識の立場にも仏道の立場にも様々あるが、人は自 分の能力の範囲内でしか、それを知ることはできない。
|
12月 27日  円空仏/如来立像 (東京国立博物館蔵) 円空は、江戸時代前期の 行脚僧。全国に円空仏と呼 ばれる独特の作風を持った 木彫りの仏像を残したこと で知られる。 生涯に約12万体の仏像を 彫ったと推定され、現在ま でに約5350体発見されて いる |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(116) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(22) 物事の真実を知るには、海山が円や四角く見える他に、姿形が極まりなく、無限 の世界があることを知るべきである。自分の周りや自分自身の内にも、無限の 世界がある事を知るべきである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(117) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(23) 魚が水を行く時、水には限りがなく…鳥が空を飛ぶ時、空には限りがない。魚や 鳥は昔から水や空を離れず、広く行く必要があれば広く行き、狭く行く必要があ れば狭く行く。しかし鳥や魚も、そこを離れればたちまち死ぬ。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(118) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(24) 魚が水を命とし、鳥が空を命としていることを、人は知っている。その上は、鳥の 無いところに空は無く、魚の無いところに海は無い事を知りなさい。命は鳥におい て実現し、魚において実現するのである。
|
12月 28日 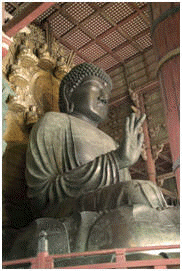 奈良/東大寺 毘盧舎那仏 (国宝) (びるしゃなぶつ) 真言宗では大日如来 天台宗では法身仏 華厳宗では報身仏 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(119) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(25) この事を進んで行い現しなさい。 修行の内に悟りがあり、長短を超えた命が実現される。水を究め尽くし、空を究 め尽くした後に、水や空を行こうとする鳥魚があれば、水にも空にも行くべき道 を得ず、安住する所も無い。
|
12月 29日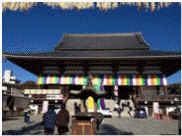 足立区/西新井大師 師走の西新井大師  西新井大師の 弘法大師像 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(120) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(26) 今、自分の居る所に気づけば…自ずから修行ができ、真理が実現する。今、自 分の行くべき道に気づけば…自ずから修行ができ、真理が実現する。 真理を実現するための道や処(ところ)は…大小、自他、時を超え…常に実現され る。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(121) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(27) 以上の例えのごとく… 仏道の修行とは、1つの事に会えばその事を究め、1つの行いを成せばその行 いを貫く。 そこに…真理を実現する境地があり、真理を実現する道があるが…なかなか、 その事を悟ることができない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(122) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(28) つまり… その事を悟ることが…仏道の究極だからである。 悟った事が…必ず知識となり、論理的に理解されるとは限らない。悟りの究極 は、修行によって体験されるものであるが、それが自分で気づくとは限らない。
|
|
1月 1日 元 旦  阿修羅像 (国宝) 奈良/興福寺 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(123) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(29) 麻谷山(まよくざん/中国の山西省永済県にある山)の宝徹禅師(ほうてつ・ぜんじ/馬祖に嗣法。丹霞禅師 と共に遊行し、麻谷山を通りかかると、丹霞禅師と別れ、そこに住したと言う)が、扇を使っていた。 僧が問うた。 「風の本質は変わらず・・・行き渡らない所は無いのに、どうして扇を使っておら れるのか」 「お前は・・・風が行き渡らない所は無いという、本当の意味を知らないようだ」
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(124) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(30) 僧が再び問うた。 「それは、どういうことですか」 師は黙って、扇を使うばかりであった。僧は深く感じ、礼拝した。 真理を知るという事…正しく伝えられた教えを生かすとは…このような事である。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(125) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(31) <風の本質は変わらないから、扇を使わなくてもよい・・・ 扇を使わなくても、風を 感じることができる> というのは… 風の本質を知らず、その本質が変わらないという事も、知らない者の言う事である。
|
| 1月 2日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(126) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(32) 風の本質が…変わらないからこそ、仏道を行なう者の風が、大地の黄金であるこ とを実現し、長河の水を酪乳に成熟させたのである。
|